萩原朔太郎 1
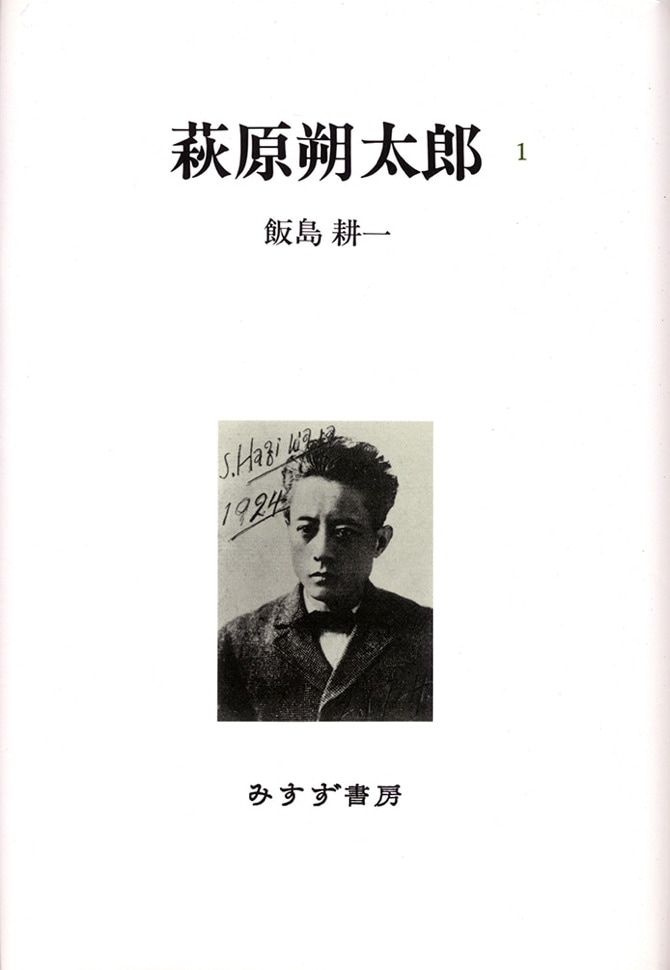
| 判型 | 四六判 |
|---|---|
| 頁数 | 272頁 |
| 定価 | 3,850円 (本体:3,500円) |
| ISBN | 978-4-622-07079-5 |
| Cコード | C1095 |
| 発行日 | 2004年1月5日 |
| 備考 | 現在品切 |
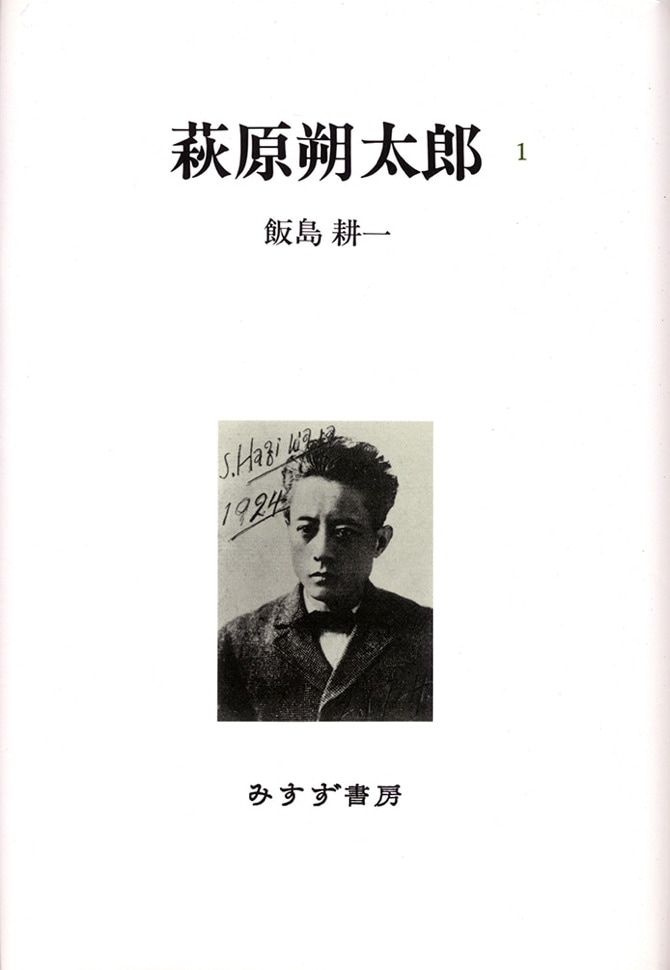
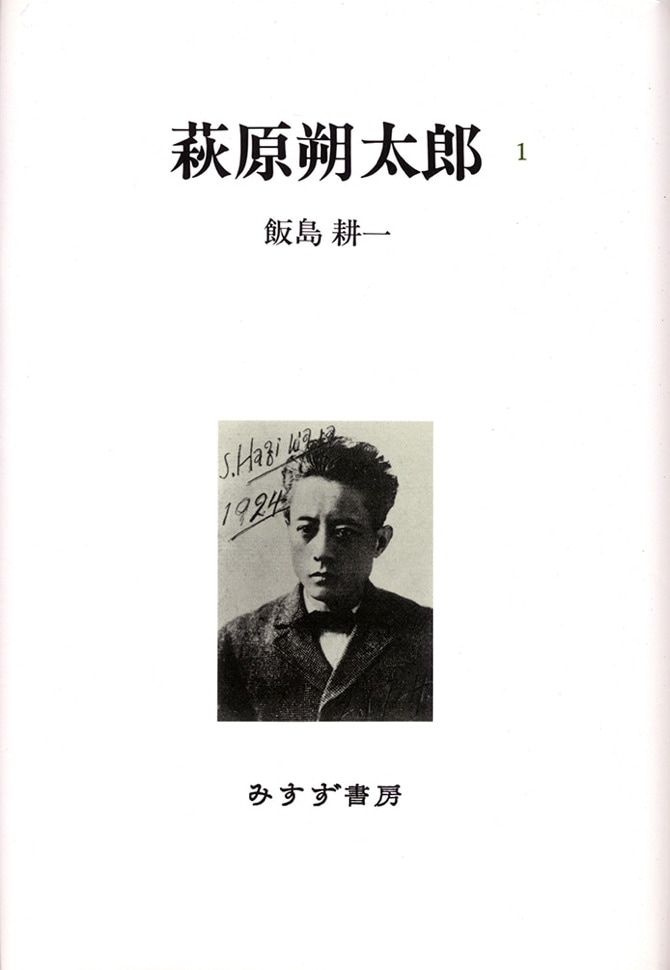
| 判型 | 四六判 |
|---|---|
| 頁数 | 272頁 |
| 定価 | 3,850円 (本体:3,500円) |
| ISBN | 978-4-622-07079-5 |
| Cコード | C1095 |
| 発行日 | 2004年1月5日 |
| 備考 | 現在品切 |
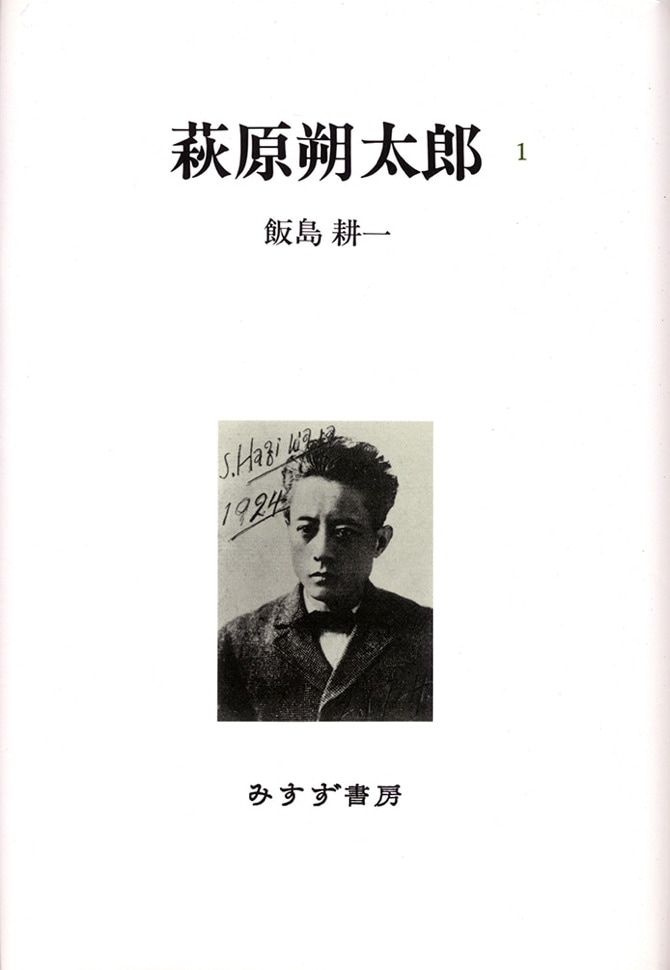
「白秋からやってきた象徴詩、それを受けつぐべき者として朔太郎は決定的な位置に立っていた。その時期に朔太郎が立たされたのだとしてもよい。その時期が朔太郎を必要としたとしてもよいかもしれない。朔太郎の変容があり、新しくレールが敷設されて今日の詩というものがあるとさえ言えるのではないか。白秋までと、朔太郎以後はそれほどに変わったとも言えるのである。白秋が〈のうのう〉として朔太郎が〈いらいら〉していたことの指摘は、単なる外見的なことではなくて、意外に近代というものの本質に触れていた……」(白秋と朔太郎)。
中野重治著『室生犀星』への辛辣な批評によって始まる本書は、生き生きとした詩人論として卓れているだけでなく、より大きく日本の近現代史の問題と深くかかわっている。著者は蕪村や子規・漱石から日夏耿之介・蒲原有明・辻潤へ、またキュビスムやシュルレアリスムなど、文学空間を自在に往来し、かつ詩的言語の深部を探りつつ、朔太郎という存在を歴史のなかに位置づけてゆく。ゆっくりと姿を現わしてくる等身大の詩人と歴史との関係はまことにスリリングである。全2巻