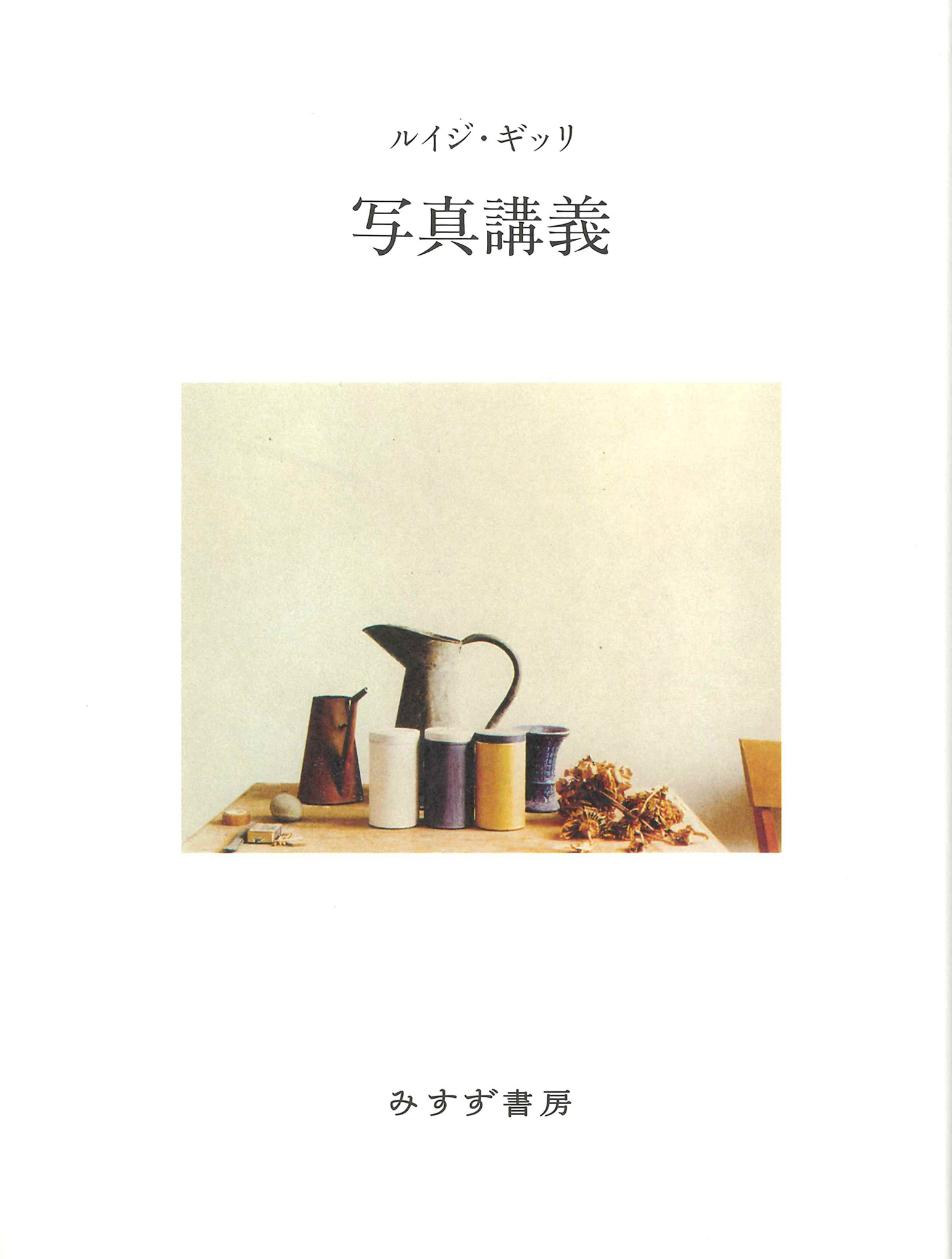
2014.06.25
ルイジ・ギッリ『写真講義』
萱野有美訳
2014.06.25
本書カバーを飾るのは「物質試行54 フィガロ計画」である。当初「DUBHOUSE」シリーズの第3作目に位置づけられ、ストレートに「SACROPHAGUS」と銘打たれていた福島第1原発石棺化計画だが、震災直後から始められ、徐々に図面、ドローイング、模型が増殖、現時点での著者の「物質試行」最新ナンバーとなった。
ここに提示されているのは平面図(本文巻末にパース)で、上から順に1号炉、2号炉と描き込まれている(海は右手)から、常識的な地図づくりに即して整合的ではある。よってタイトルを立てたまま文字を横組みにする必要はなかったかもしれないが、装丁担当者は絵の強度につられてつい寝そべらせてしまった。ただ頭を傾けるか逆に本を傾けるかして絵本来の向きで見てほしい、というのがまず第一にある。
けれどもこのような90度回転、縦横変換は内容がそうさせたというべきか、本書の主題に通底した意味をもつとも思っている。ウロボロスの蛇さながらの縦組みと横組み、立ち技と寝技との内在的なせめぎあい(むろん、「猪木アリ状態」――ウィキペディアに項目あり――ではない)。それは建築の根幹そのもの、そして結局のところ3・11が建築に何を開きだしたか、という問題に答えようとするものなのだから。
表題作の立原道造論ははじめ「建築‐非建築の荒野で」と題され、「みすず」2008年12月号に掲載された。昨年の梅雨時にはすでに初校が出ていたものの、年明けに著者校が戻ってきたさいは3倍弱のヴォリューム(400字原稿用紙換算で150枚弱)にふくれあがっていた。以下、著者「あとがき」に直接語ってもらうことにしよう。
「2008年にこの文章を書いたときと、それを読む現在とのあいだには、東日本大震災と原発事故がある。そのあとの目で読みなおしたとき、立原道造の「背中」が、いつもの親しみ深さをこえて、急に間近に迫っていた。震災のあとでこそ、立原道造の建築にたいする考え方がまさに現代につながっており、いまの建築の置かれている問題のどまんなかにまっすぐ届いているように感じられはじめたのだ。
立原の存在はそんなに大きかったのか。
大幅に書き加えておきたいことが見えてきた。
それは立原道造の建築を、建築のなかだけではなく立原の詩の世界にも見いだすことにもなった。そして大胆にも、建築家・立原道造の存在のつかまえ方次第では、日本はもちろんのこと、世界における近代建築史全体にたいする認識のあり方をさえ根本から変えてしまうのではないかという予感すらめばえてきた。
さて、こうして手直しをやり終え、いまあらためてこの本の全体を見なおすと、驚いたことに、それぞれの章はまるで最初から計画されて書かれたかのように構成され、あるいはそのプロセスを例証しているようにさえ感じられるではないか。
巻頭の立原論に続く「ル・コルビュジエのメディア戦略」をはじめとする「近代主義」批判として書いた第Ⅰ章、近代建築の前夜をおもに集めた第Ⅱ章、私自身の携わった近作に関する第Ⅲ章、そして巻末の「〈建屋〉と瓦礫と」にいたるまで、それらは私の知らぬまにあらかじめ思考の地層深く整然と埋め込まれ、静かにいままで発掘を待っていたかのようである。(…)
私は21世紀のはじめに「建築零年」というタイトルの本を出しているが、そのとき以来、では「零年以後」はいったいどうなるのかというそのことが、まるで遠い蝉の鳴き声か、あるいは低い耳鳴りのようにずっと気になりつづけてきた。
本書は、そんな「零年以後」にたいする私の応答でもあるし、また、そうでありたい」



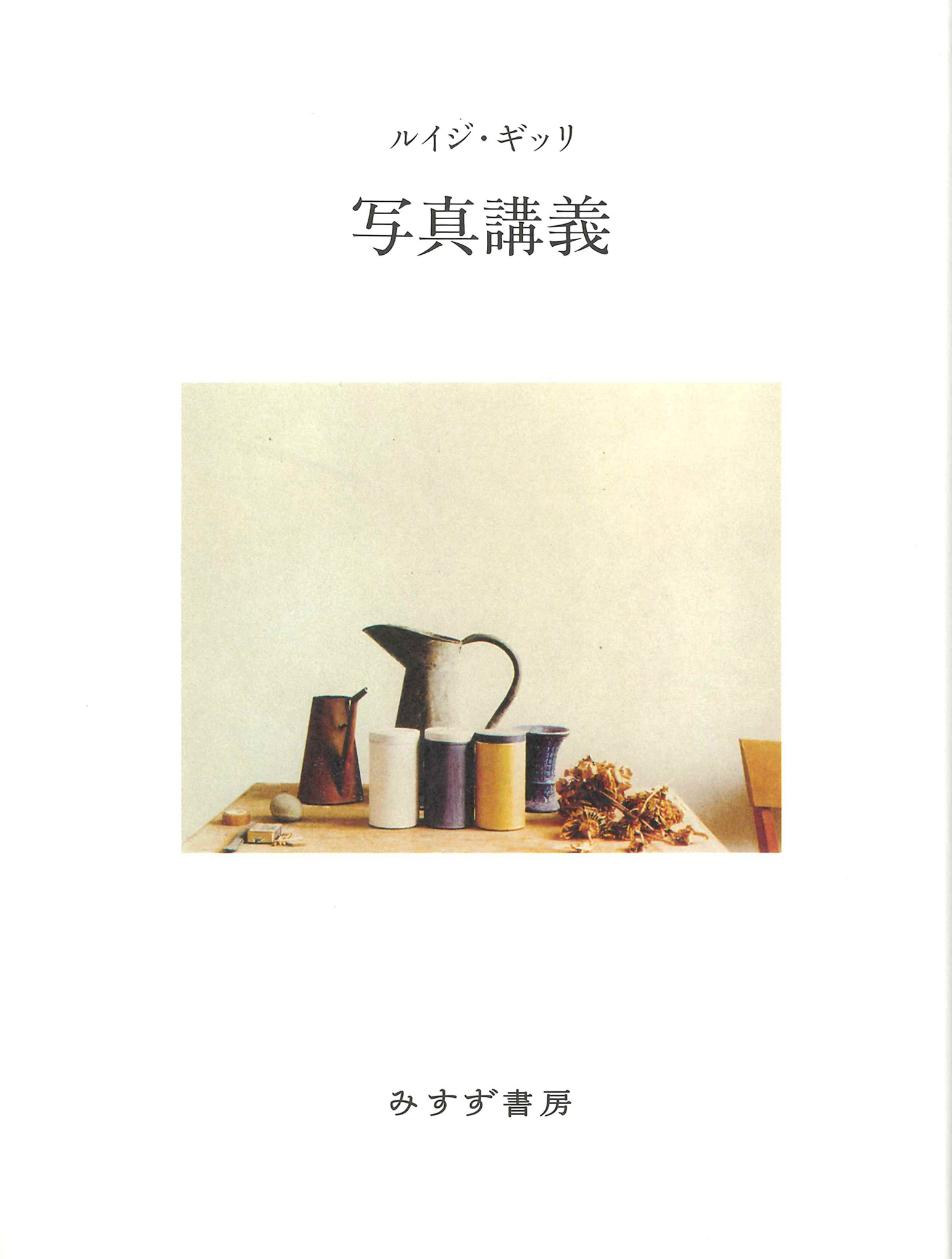
2014.06.25
萱野有美訳

2014.06.19