
2015.12.24
中村隆文『不合理性の哲学』
利己的なわれわれはなぜ協調できるのか
高田ゆみ子訳
2015.12.22
今年87歳にして現役の作家であるパウゼヴァングの百冊目にあたる長編のテーマは、〈戦争の日常〉。舞台は、都会からの疎開者を受け入れるようなドイツの深奥の小さな山村――しかし、国じゅうを浸した戦争の不安、恐怖はこの地にも襲いかかり、ナチス・ドイツの敗色が濃くなるとともに、人びとの心のすみずみまで、疲弊と、愛する者をうしなう悲しみに覆われていきました。そんな1944年夏から翌年5月までの物語です。
主人公は、間に合わせの訓練を受けただけでロシア戦線に送り込まれて左手を失い、故郷の山あいの村で郵便配達人として働く17歳のヨハン。夫や息子からの便りを待ちわびる家族に戦地からの手紙を届ける一方、彼らの死を報せる「黒い手紙」をもたらすのもヨハンの仕事でした。
臨月のおなかをかかえて夫を待つ妻、意気揚々と出征していった十代の息子を案じる母、総統が最終勝利をもたらしてくれると熱狂的に信じる少女。戦争に、ヒトラーに批判的な者。収容所から脱走してきたロシア人捕虜をかくまう娘。ウクライナやポーランドから連れてこられた強制労働者や、ヨハンとおなじく傷病兵として帰郷した青年たち。そして、ヒトラー・ユーゲントのリーダーからSS隊員になった孫の戦死を受け入れられず、訪れてくるヨハンを孫オットーだと思い込むようになる老女……登場人物のひとりひとりが、狂気に翻弄された「あの時代」の姿を鮮烈に伝えながら、物語は思わぬ結末へ――
おなじ作者の既刊短編集『そこに僕らは居合わせた』がそれ自体完成された20枚の素描だとするなら、『片手の郵便配達人』はそれらのモチーフを背景に描き込んだ大きな油絵といえそうです。あらすじからはこぼれ落ちてしまうこれらの人びとのエピソードこそが、じつは、作者が本当に書こうとしたことであり、それを束ねるために、物語の主人公はかならず郵便配達人でなければならなかったのでしょう。
ヒトラー自殺の報に涙を流して泣き、17歳で敗戦を経験したかつての軍国少女。ナチス・ドイツ下の日常をとおして刷り込まれた価値観を問い直す作業を続けた娘時代。作家としてかずかずの作品を書きながら、「あの時代」をみつめつづけてきた作者が、70年をかけて熟成されたすべてを投げ入れ、渾身の力をこめて描く、戦争の本当の姿。戦争が本当はどういうものであったかが忘れ去られようとしている今、そのメッセージをお届けします。

2015.12.24
利己的なわれわれはなぜ協調できるのか
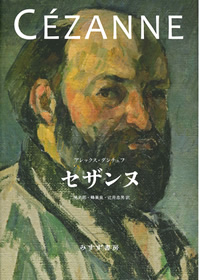
2015.12.11
二見史郎・蜂巣泉・辻井忠男訳