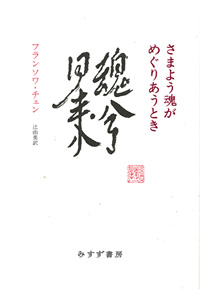
2013.05.27
フランソワ・チェン『さまよう魂がめぐりあうとき』
辻由美訳
〈大人の本棚〉 富山英俊訳
2013.05.27
ホイットマンは『草の葉』初版を1855年7月に、36歳のとき出版した。解題に記したような、不思議な本だった。どの文学史も述べるようにそれはエマソンの認知を受けて、詩人はつぎの版へと活動を継続した。その後の『草の葉』(基本的に「全詩集」であり続けた)の増補改訂の経過はかなり複雑だが、実質的には初版以降に、56年、60年、67年、71年、81年版があると考えればよい。その81年版に晩年の作品が追加された「臨終版」(91-92年)は長く流布し、日本での翻訳も概ねそれによってきた。アメリカでも初版自体は忘れられたが、20世紀の半ばすぎからその価値は再発見され、容易に入手できる形で出版されてきた。現在では各版はすべて、ネット上で読める(http://www.whitmanarchive.org/)。この翻訳は数種の版本によったが、最終的にはサイト上の各ページ画像を確認した。
最終版が初版中の重要作品をまるで違うものに変えた、ということはない。だが初版中の行や節の抹消・変更はかなりあり、その多くは、後年の詩人がおもに性と宗教について一般読者の強い拒否反応を避けようとしたからだ、と理解できる。説明的な詩行の付加もあり、また一部には、自分のすでに書いたものにとまどい合理化と整理を試みるホイットマンの姿も見てとれる。初版での性急な熱気を伝える句読法は、後には抑制され標準化された。長篇の詩はセクションへと分けられ、それは主題の展開を見やすくするが、全体の流れを分断してしまう(本書では、後からの分割箇所をとくに表示していない)。現在では、初版をより好むひとは少なくない。
(中略)
ホイットマンは、信ずるものを得て知らせを伝える宗教者のように語る。だがかれは、ある名前をもつ神的存在に関する特定のお話や教えを語らず、むしろ「永遠を序章と結末のある芝居として見ない」(13頁)、「特別の安息日も裁きの日ももたない」、「いかなる赦しも代理の贖罪も知らない」(31頁)などと、否定の形で自分の考えは違うことを告げる。なにと違うかといえば、もちろんキリスト教ないし啓示宗教一般である。だれもの常識を確認するなら、近代科学の発達が教える宇宙の巨大や生物の進化などは(両者とも当時の理解が「〔ぼくは、ぼくを祝福する、〕」に現れる)、神の世界創造やアダムの堕罪や神の子キリストの十字架の贖罪や、来世での神の裁きや天国や地獄や、キリスト再臨による世界の終末などの物語を信じにくくさせる。すなわち「特殊で超自然なものにかんする全理論……は、夢のように姿を消」し、「特定の事態や人物におけるいかなる奇跡も……受け入れられない」事態に至る(22頁)。だがホイットマンにおいてそれは、宗教の解消でなく、その力の自由で平等で無差別な一般化に向かう――「そこではあらゆる動きとあらゆる草の葉と……すべてはことばにできない完璧な奇跡であり、すべてはすべてを指し示してそれぞれが個別でその場にある」(同)。
ホイットマンがそれを感じ考え信じる状態を経験したことは、確かだろう。それを、宇宙のすべての存在者の「聖性」の認識と呼び、その経験をある種の「神秘体験」と呼ぶことはできる。だがそれは、一個人の心的状態であっただけでなく、ある観念の運動を含むものであり、それゆえその言語による表出が可能になった。その運動とは、二元論の階層関係の転倒であり、魂と肉体、生と死、救いと罪、救う神と救われる人、贖われる未来と罪ある現在、また善と悪、法とその外、といった種々の二元論は揺るがされ、覆される。ホイットマンの詩には、その転倒を示す逆説的表現が頻出する。
あるがままの世界は奇跡であり啓示であり救済であるという直観を得て、その力ないし光を感じ熱中したひとりの男が、この本を出版した。かれは、各人がおのれの司祭となる新しい宗教形態の構想は、合衆国の民主主義の自由と平等の価値を再確立し、南北戦争に向かう絶望的な政治状況を救済できると考えていた。
(中略)
ホイットマンが直観したものは、宇宙の全体を貫く命の力と呼ぶべきものであり、それは生殖の力でもあったが、またキリストの贖罪の力をも包含したようだ。それは、詩人の専有物でなく、重力や光のように遍在して、万人が、というよりあらゆる存在者が分有する。――ただしそれは、穏健な常識をもつ読者(とくにキリスト者)には「ありえない」考えであり、ありえないものは考えられず読みとられないことも多い。
「〔ぼくは、ぼくを祝福する、〕」の中盤は、その直観の力を世界の悲惨と悪に直面して維持できるか、という試練の実演であると言えるが、その後の展開は一方向には向かわない。一方で「ぼく」の力は無際限の宇宙の果てまで拡散して「神」との出会いが約束されるが(その「神」の性格や「ぼく」はどんな個体としてどう存続するかは明らかでない)、他方で地上の人間たちと土地の現実に戻る。ひとつの個体の消耗と損傷、力の衰えは感知され、そして夕暮れどきに自然の諸力へと哀切に帰還して作品は終わる。いずれ同じことになる読者は、それに共感する。またその終わり近くで「ぼくのなかにそれがある……それがなにかわからない」(1299行)と、直観の対象が正直にただ「それ」とだけ示されることも、同じく読者の共感を誘うだろう。「それは永遠のいのちだ……それは幸せだ」(1308行)と言われても、やはり手探りであるに違いない。さらにすこし前では「それ」は、さまざまな死と悲惨を被る人間たちと、地中から宇宙の果ての天体上に至る存在者のすべてを「裏切らない」と言われていた(1122-32行)。つまり「救う」のだろう。
(後略)


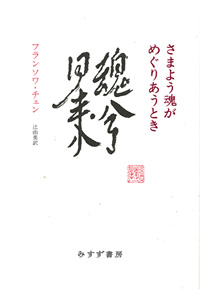
2013.05.27
辻由美訳

2013.05.10
当世「公立無料貸本屋」事情