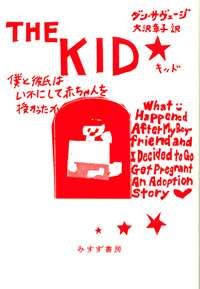
2016.08.16
社会はちょっぴり変わるかもしれない
ダン・サヴェージ『キッド――僕と彼氏はいかにして赤ちゃんを授かったか』 大沢章子訳
ツヴェタン・トドロフ『民主主義の内なる敵』 大谷尚文訳
2016.08.01
本書はTzvetan Todorov, Les ennemis intimes de la démocratie, Robert Laffont | Versilio, Paris, 2012の全訳である。
ロラン・バルトの指導を受け、文学の構造批評の若手の旗手とみなされていたツヴェタン・トドロフが、一般人類学と呼ばれる分野に足を踏み入れたのは『他者の記号学――アメリカ大陸の征服』(La conquête de l’Amérique. La question de l’autre, Seuil, 1982)からである。トドロフのいう一般人類学は、ふつうに実践されている人類学の根底にある「人間とは何かの定義」の探求の意味でもちいられている。そして、トドロフにとっては、彼が本書でくり返し述べているように、新自由主義経済がベースとしている人間観とは逆に、社会は個人に先行し、共存は自己の存在に先行する。つまり、トドロフの「人間とは何かの定義」には「他者の問題」は本質的な要素として組み込まれているのである。
共産主義ブルガリアで育ったトドロフにとって、理想化した言い方をすれば、留学で訪れたフランスもまた他者であった。民主主義に出会ったときの感動は本書の冒頭で明快に語られている。実際に語られているのは、かつてのブルガリアの不自由さであるが、知る(connaître)とは共に‐生まれる(co-naître)ことだとするポール・クローデルの言に従えば、故国の不自由さはフランスで目の当たりにした自由と同時に誕生したとも言えるだろう。このときの政治的で文化的なコントラストの体験は今なお残存していると、自分がフランス共和国市民として帰化したことについて触れながら、トドロフはつぎのように述べている。
私の私的なアイデンティティについては、それは確かに少しはフランス的になったが、無条件にではなかった。私は人生の最初の24年を忘れることはできない。そのおかげで、私はまだ私の内部にフランスに対する外的な眼差しをつねに保持している。あるいは、私はある種の土着のフランス人にとって自然(人間的)に属するものをこの国の文化のせいだと考えている。〔……〕しかしながら、私が確信しているのは、一つの内閣やその役人が、私が考え、信じ、あるいは愛さなければならないものを私に代わって決めることを私が望まないということである。(本書、182-183ページ)
「外的な眼差し」は冷ややかな眼差しを意味しない。それは他者が無自覚である他者自身の値打ちを認める力でもあるだろう。訳者はたまたまインターネットでフランス・キュルチュールの番組の見出しを見る機会があった。そこに「民主主義はたんなる観念か」とあった。「観念」とは、実体に対応しないことばだけのものを意味するだろうか。トドロフは民主主義に対するこうした類の軽口は断固、拒否するだろう。民主主義は、あるいはその凋落は、私たちの力では左右できない人間的自然なのではない。それはフランス革命以来、築き上げてきた「この国の文化」であり、個人の内面まで支配しようとする全体主義体制下での生活を思うとき、絶対に守るべき価値なのである。本書はこうした確信のもとに書かれている。トドロフは「反共産主義者のなかでもっとも好戦的なのは、転向した旧共産主義者である」(214ページ)と述べているが、言い換えれば、旧共産主義者こそが民主主義のありがたみをよく認識しているということになるだろう。
そう思いつつ世界のほうを振り向いたとき、私たちの目に飛び込んで来るのは、シリアの内戦、ISイスラム国、パレスティナ問題、頻発するテロ、中東の難民問題である。さらにサブプライム・ローンの破綻に端を発しリーマン・ショックにいたる金融危機はいまだ記憶に新しく、資本主義の不安定さは、いわば私たちのトラウマになっている。トドロフが本書で記述しているのは、こうした世界の政治・経済・文化の現在時であり、それらの出来事がもつ意味である。ただし本書における現在時とは2012年の現在時であり、2016年とは目に見える風景は異なっているが、本訳書が出版される2016年は本質的に2012年の延長、あるいは――残念なことに――悪化であり(ISイスラム国は「政治的なメシア信仰」「新自由主義」の残酷さに相応する出来事だと言えなくもないし、アメリカ大統領予備選は「ポピュリズム」の華々しい実例を示してくれた。本書第6章「ポピュリズムと外国人嫌い」を逆の意味で読んでから戦略を練り上げたのではないかとさえ思わせる)、本書の意義そのものは変わらない。そしてこれらもろもろの出来事の発端に、トドロフは民主主義の危機を見るのである。本書の冒頭で、キリスト教の原罪をめぐるペラギウスとアウグスティヌスの過去の論争を引き合いに出すのも、ゆえなしとはしない。この論争を暗号解読格子として使えば、冷戦終結後にその全貌をあらわした新自由主義、ウルトラ自由主義、さらには「政治的なメシア信仰」なるものが根拠としている人間理解の特徴が、いかなるものかが浮き彫りになるからである。
本書の書名である「民主主義の内なる敵」が、危機がどこにあるかを端的に物語っている。フランス革命によって誕生した民主主義は、20世紀に入ってからはベルリンの壁が崩壊するまで、全体主義(ナチズムと共産主義)との競合のなかで形づくられてきた。民主主義の敵は外部にあったのである。そしてその間、民主主義はあらゆる美徳を身につけたと言っていいだろう。だが全体主義が瓦解した瞬間から、民主主義の変質が始まった、とトドロフは言う。民主主義の暴走にブレーキの役を果たしていた全体主義国家が崩壊したがゆえに、それまでは「相互に制限し合い、補い合って」(本書、12ページ)民主主義を形成していたそれぞれの要素が、美徳の仮面をかなぐり捨てて、ばらばらに肥大化しはじめ、民主主義そのものに敵対するようになったと言うのである。「内なる敵」ennemis intimesとはこのことである。intimesとは「内的に一体化した」というような意味である。トドロフはこの肥大化を、トドロフと同じ国立科学研究所(CNRS)内部の芸術・言語研究センターに所属するフランソワ・フラオーの用語を借りて「行き過ぎ」démesureと呼んでいる(François Flahault, Le crépuscule de Prométhée. Contribution à une histoire de la démesure humaine, Mille et une nuits, 2008を参照)。トドロフが行き過ぎを見出す民主主義の構成要素とは、進歩、自由、人民である。
(中略)
たとえば、第5章「新自由主義の結果」は、2011年の東日本大震災による福島の原発事故への言及から始まっている。トドロフは、ここで何より深刻なのは、「カタストロフが故意に惹起された爆発〔原子爆弾のことを指している〕の結果ではもはやなく、共通の幸福に役立つと見なされている平和的な計画の結果」(129ページ)だったことだと述べ、「爆発は自然的カタストロフの結果ではなく(自然はカタストロフという概念を知らない)、一連の人間的決定の結果である。爆発は結局、民間の大株主と行政官僚の癒着から生じ」たのだと指摘している。私たちは福島の原発事故にもっと絶望し、もっと怒るべきなのかもしれない。
(中略)
新自由主義においては、労働の管理そのものでさえ人道に対する罪であることを知ったからには、私たちはこのような事態に対して何らかのアクションを起こさなければならないのだろうか。実際、トドロフ自身、「これに対していかなる抵抗も対置しなければ、これらの敵〔民主主義自体によって産み出された内なる敵〕はしまいには、いつの日かこの政治体制からその実質を排除することになるだろう。それらは人間の自己喪失と人間生活の非人間化へとみちびくのである」(221ページ)と指摘している。つまり、本書はまた民主主義の現状分析であるとともに、「民主主義」を作り直すためのレジスタンスへの呼びかけでもあることをつけ加えておきたい。
トドロフはまた、「ヨーロッパの政治に関心をもつ男女」について「政治的操作のプロの言ったことをわかりもせずにそのままくり返しているような印象をしばしばもつ」(195ページ)と述べ、「自分たちが生きている社会をしかるべく理解しなければ、間違って行動する恐れがある」(226ページ)と書いているが、政治操作のプロに操作されるのは「ヨーロッパの政治に関心をもつ男女」ばかりではないだろう。日本の「政治に関心をもつ男女」もそうである。私たちが「間違って行動」しないためには現代日本の民主主義の現状について「しかるべく理解」する必要があるが、本書はまさしく私たちにとって現代日本の政治・文化の現状を認識するための格好のモデルになるのではないだろうか。(後略)
copyright Otani Naofumi 2016
(訳者のご同意を得て抜粋転載しています)
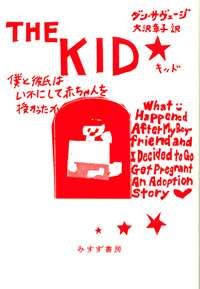
2016.08.16
ダン・サヴェージ『キッド――僕と彼氏はいかにして赤ちゃんを授かったか』 大沢章子訳

2016.07.29
メイ・サートン『70歳の日記』 幾島幸子訳