幸福への意志
〈文明化〉のエクリチュール
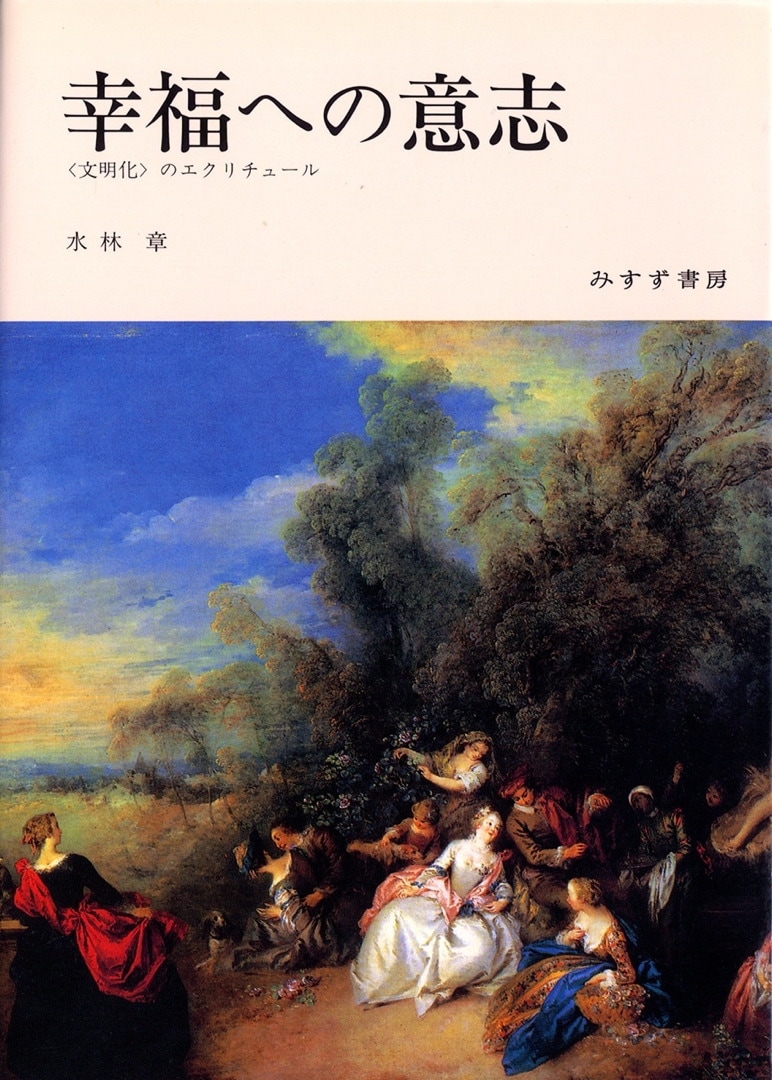
| 判型 | A5判 |
|---|---|
| 定価 | 7,150円 (本体:6,500円) |
| ISBN | 978-4-622-03497-1 |
| Cコード | C1022 |
| 発行日 | 1994年11月9日 |
| 備考 | 現在品切 |
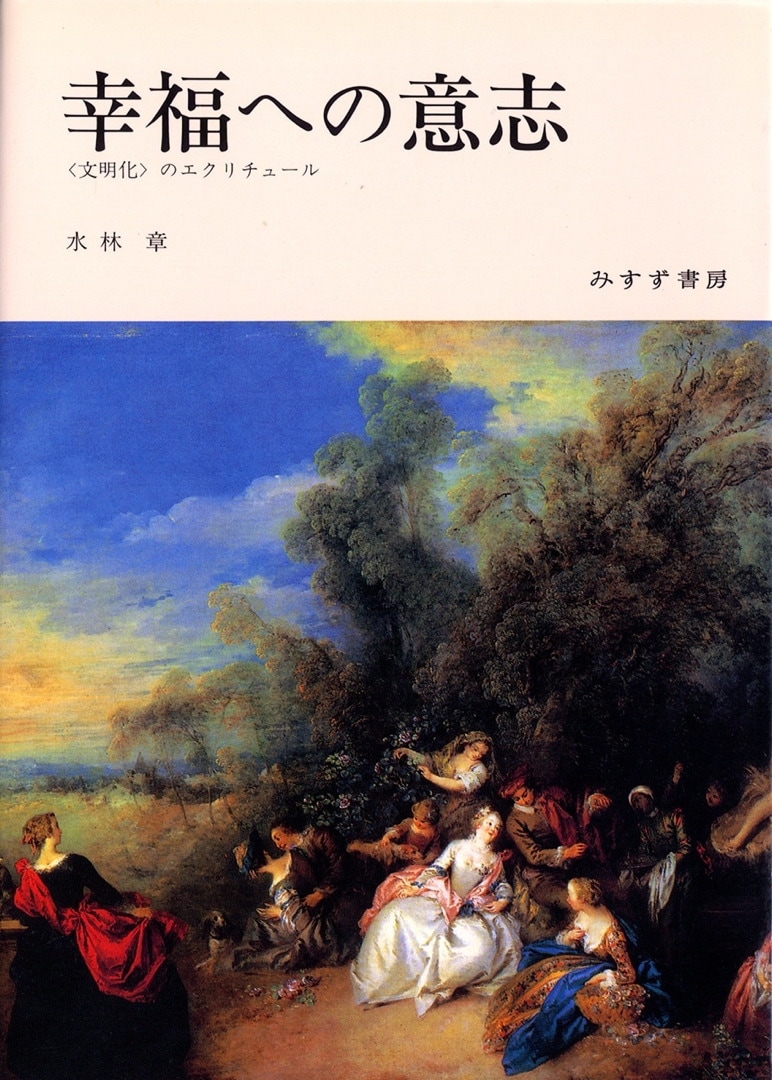
幸福への意志
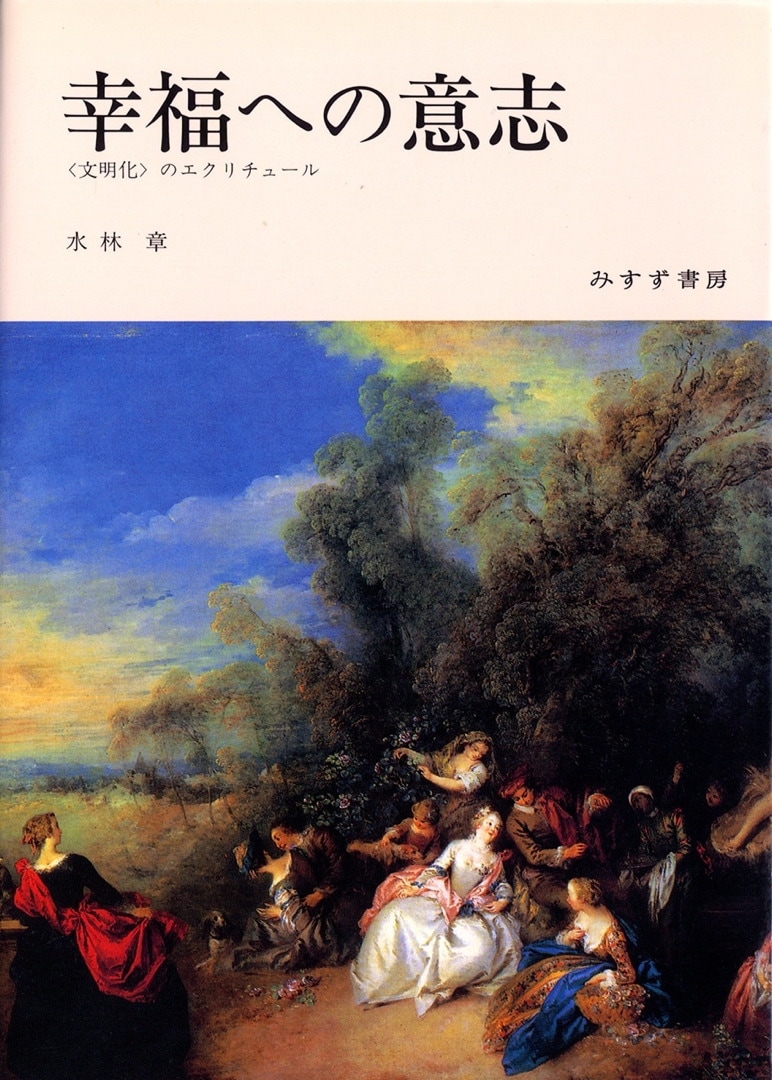
| 判型 | A5判 |
|---|---|
| 定価 | 7,150円 (本体:6,500円) |
| ISBN | 978-4-622-03497-1 |
| Cコード | C1022 |
| 発行日 | 1994年11月9日 |
| 備考 | 現在品切 |
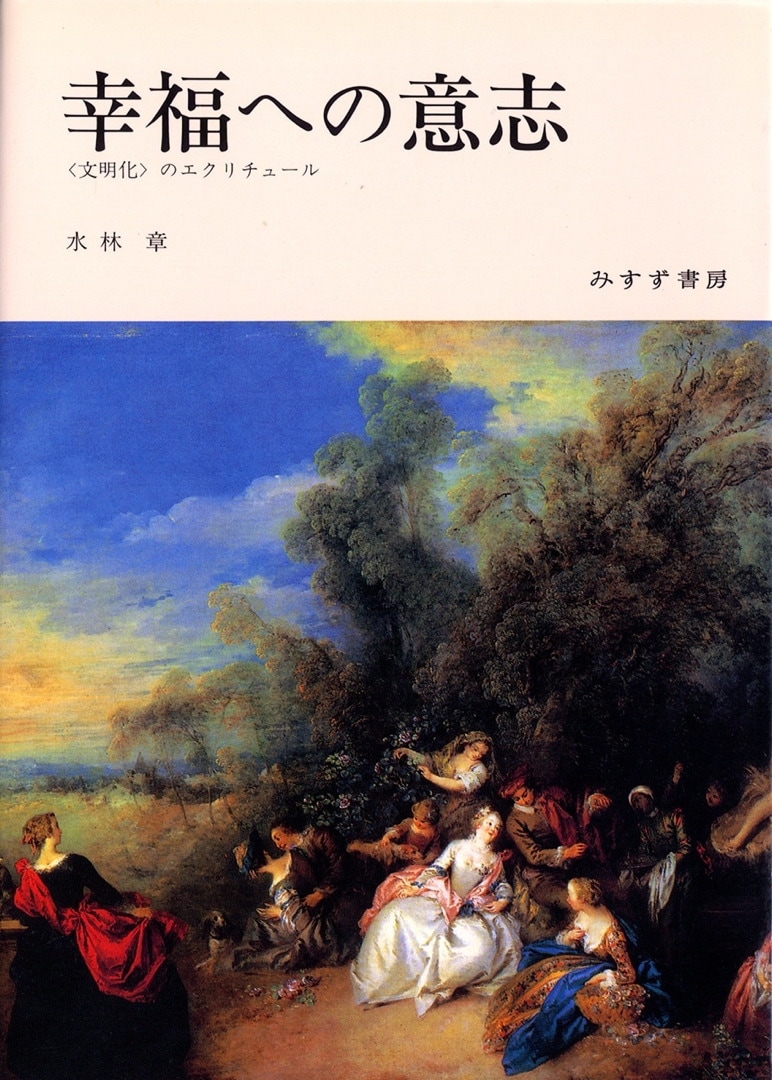
モーツァルトは走る。宮廷の豪奢には目もくれず、しかもいまだ近代人の苦悩とも無縁に、彼はただ一度限りの傷つきやすい瞬間を呼吸する。
18世紀の歴史は、このモーツァルト的な中間性の主題を秘めて展開したのではなかったか。封建社会の遺制と、市民社会の兆候が重なり合うなかで、そのいずれの悲惨からも自由であろうとする意志が、限りなくあやうい均衡のうえに、つかのまのきらめきを見せる。
ディドロ、ボーマルシェ、そしてとりわけルソー。進行する〈文明化〉の過程の刻印は、テクストにどのように押されているか。文学と歴史の交差する地点に視座を置き、両方の文脈を重ねることを通じて、著者はこの世紀の深みへと読み進む。
市場経済の波濤を目の前にして発せられた最後の問い。〈自然〉と〈社会〉のはざまにルソーが見ようとした「世界の真の青年期」とは何か。そして〈家族〉の幸福のゆくえは……?
「現代のあらゆる企て、あらゆる問題の背後には、18世紀の存在が控えている」(J.スタロバンスキー)。