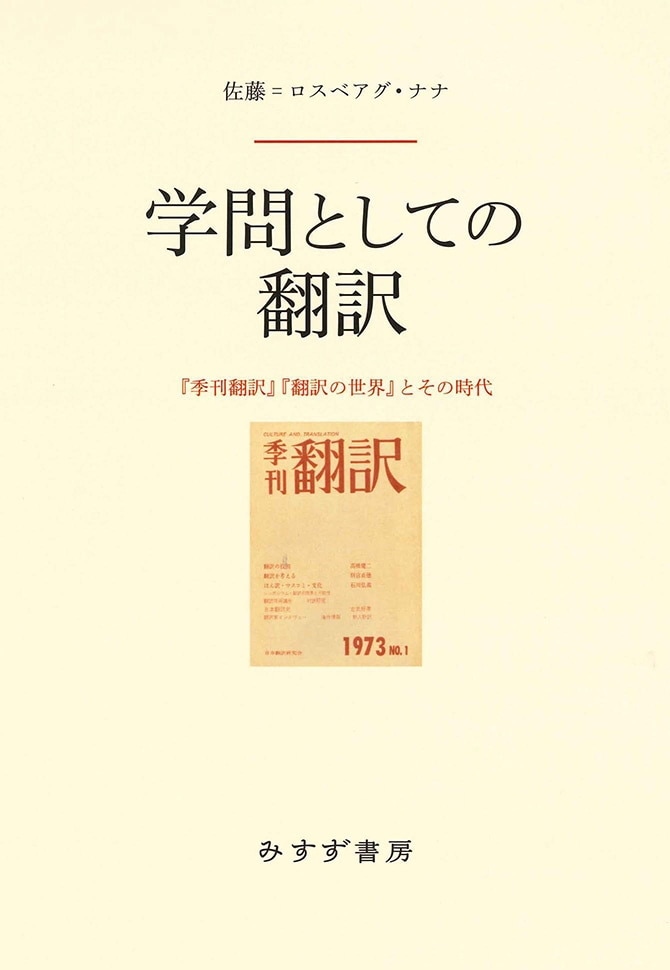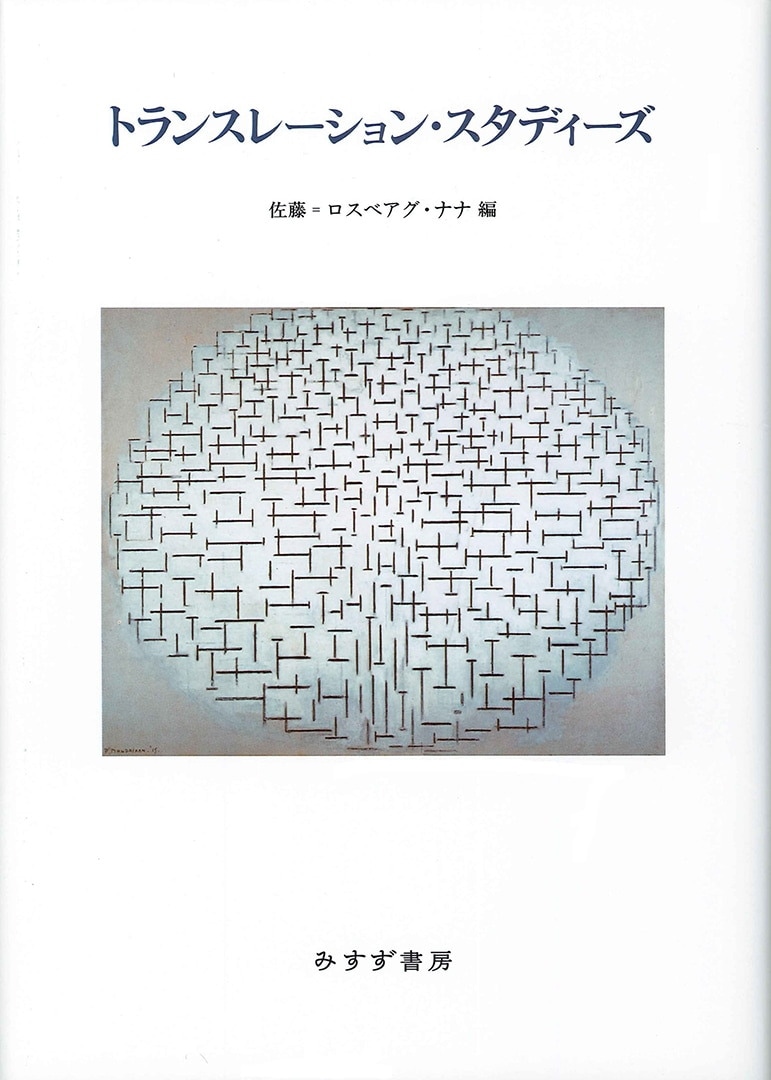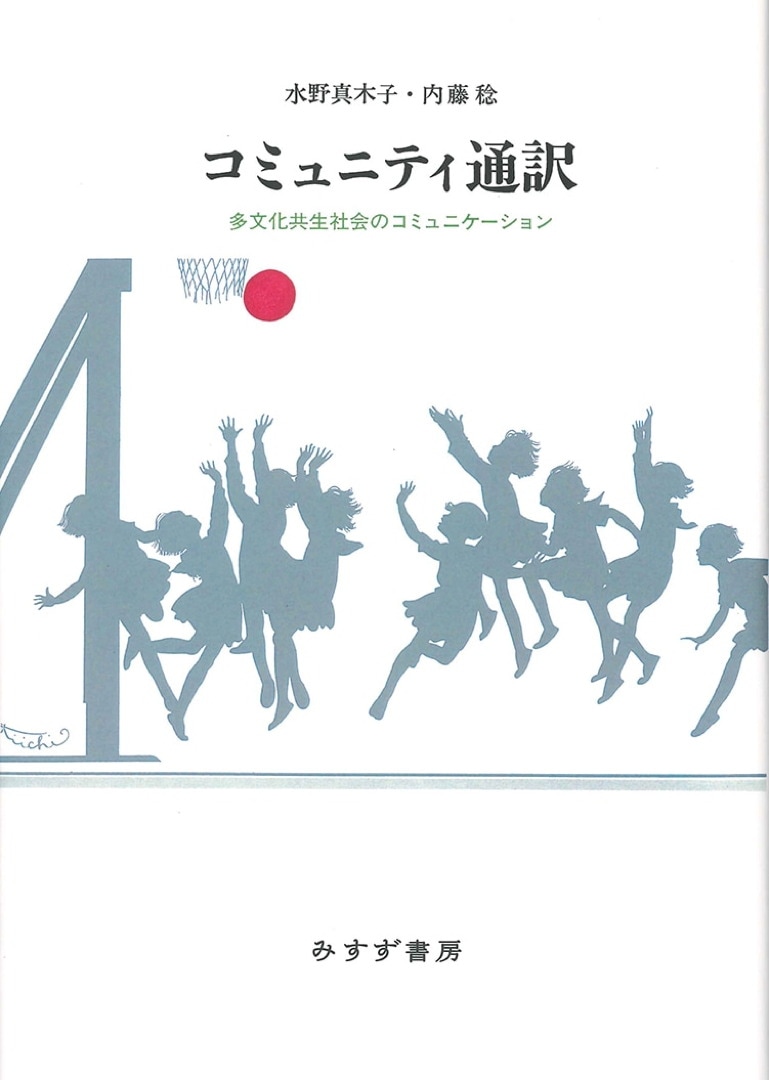『季刊翻訳』1973年創刊。発行は、みき書房。編集方針に「〈広い意味の翻訳〉について、多角的な研究と情報の伝達を目指す専門誌」「翻訳を通じて、文学や文化を、さらには政治を、経済を、そして社会を考えていく共通の広場としたいわけです」。誌上に磯谷孝、別宮貞徳、成瀬武史、武富紀雄、高橋泰邦、小笠原豊樹、鶴見俊輔、五木寛之、西山千ら錚々たる論客。7号で姿を消した。
忘れられた雑誌に偶然出会って、著者は驚く。もっとちゃんと足もとを見なくては。翻訳大国ともいわれるほどの日本で、蓄積されてきた翻訳史や、翻訳について考え論じられてきたさまざまの言説、翻訳や翻訳論にかかわってきたたくさんの人々のことを、知らなくては始まらないと思うんですよね、そう目をまるくしながら語ってくれる著者は、トランスレーション・スタディーズという学問の学際性に魅了されて、海外で開かれる研究発表の場に大学院生のときから参加してきた。イギリスの大学で教えるようになって十年がたつ。この間、特定の学会を母体としないオープンな国際学術会議を何度も組織して世界各地で実現するなど、行動力のきわだつ著者の、素直な驚きと謙虚な気持ちとが終始この研究を駆動している。
『季刊翻訳』の後継のように創刊された『翻訳の世界』(1976-2000)を、続いて著者は追っていく。1980年代中頃から90年代初頭、黄金期の『翻訳の世界』を、第3章のインタビュー(辻由美、鴻巣友季子、伊藤比呂美、西成彦、井上健、管啓次郎、沼野充義、丸山哲郎、今野哲男)は時代背景の中に豊かに肉づける。インタビュアーの飾らない人柄が引き出したものだろう、率直な証言が多面から相貌を浮かび上がらせる。
たとえば、「出版翻訳家の職業倫理規範」を1990年代初めに誌上で紹介していた辻由美が感じていたこと。「「みなさんに知ってほしかった。日本では下訳が当たり前だと思っていることに対して疑問だった。ペアで(またはチームで)翻訳を行うのは否定しないが、下訳を使うことには賛成できない」という気持ちがあった」。 鴻巣友季子は、「翻訳は精神修養の場で、高度な趣味やたしなみ」だったという。「外国文学はそれ自体が高尚なもの」で「翻訳を手掛ける大学の先生は知識層のトップ。とてもたてつくことができない」。そこに切り込んだのが、賛否あってもきわめて反響の大きかった別宮貞徳の連載「欠陥翻訳時評」で、鴻巣は「象牙の塔が崩れること」と当時のさまを表現する。 伊藤比呂美は「みみで聞いたように読める翻訳を目指していた」。 西成彦は、1993年以降『翻訳の世界』が編集方針を転換する時期について、大学の教養部解体が進み第二外国語が力を失っていく、大学統廃合のさきがけとなった状況を指摘する。 翻訳学校バベルで講師歴のある井上健は内部事情を語る。また幻に終わったという「翻訳大学院」構想にふれる。 管啓次郎は「「たとえばアフリカ英語文学の翻訳の文体をつかって、フランス思想を翻訳したい」と考えた」。「70年代は、60年代のラディカリズムの挫折の時代と考えられがちだが、その時代が用意してくれていた何かがあっての80年代だった」という。 沼野充義は、同時期の『ユリイカ』や『現代思想』や『海』と『翻訳の世界』を並べて「欧米のアカデミックなジャーナルでは考えられないような早いテンポで仕事を進め」「越境的な分野を軽いフットワークで開拓することができた」「特に既成の学会になかなか居場所が見つからない若手」に「活躍する場を提供した」と評価する。
そして編集の立場から丸山哲郎は「すごく困りました。翻訳をテーマとする雑誌ってこういう内容のものだという共通了解などありませんから」「その時、自分用に四象限で時間軸もつけたマトリックスみたいな絵を作って持っていました」。 後をうけた今野哲男は、女性のためのキャリアアップマガジンへという会社の決めた路線変更にともなって「本来なら丸山から女性編集長にとすべきところを」「「つなぎ」の編集長を務めたわけです」。——
翻訳論、翻訳家の職業倫理から、アカデミズム、翻訳産業、大学と専門学校と通信教育、教育カリキュラム、世界文学、あるいは編集、出版、読者、と広がる地平をこの断片的紹介ではうまく伝えきれない。それにインタビュー以外にも、例をあげれば、聖書新共同訳のために1966年という早い時期に東京の八王子でユージン・ナイダ指揮のもと国際セミナーが開かれていたといった史実の発掘や、まず最初の章で、これまで欧米のトランスレーション・スタディーズの解説書の多くにも単に「誕生し、発展した」としか書かれてこなかった、英国を中心とする欧州のトランスレーション・スタディーズ誕生の過程を、そこに働く力学を丹念に明かして跡づけた功績、また、日本で一般に考えられがちな学会や学術会議のありようが欧州のそれと必ずしも同じでないこと、また、欧州では学術雑誌の果たす役割の一部分を、日本の雑誌文化では『季刊翻訳』や『翻訳の世界』のような商業雑誌でもある独特の雑誌群が担ってきたのではないかという問題提起、など、読みどころは読み手の側の興味関心によって各所にみいだされること間違いない。書名に込めた著者の思いを読了後に納得していただけるとおもう。