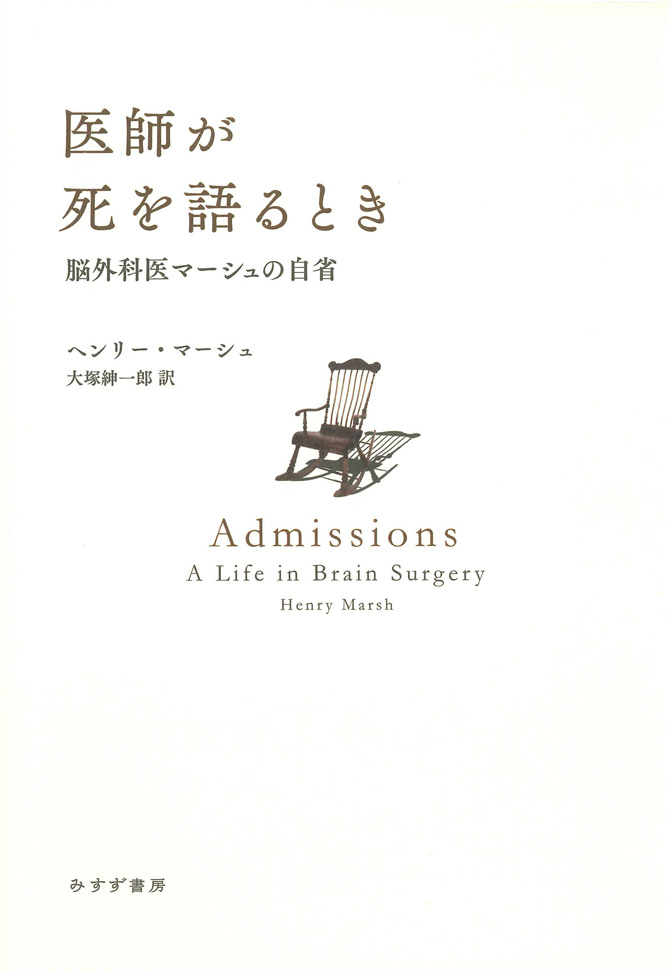(「訳者あとがき」の抜粋を以下ウェブでお読みになれます)
大塚紳一郎
ここにお届けするのはHenry Marsh, Admissions: A Life in Brain Surgeryの全文を訳出したものです。無事に訳出が終了し、本書をお届けできることは訳者として感無量の一言に尽きます。本書は他に類を見ない、正真正銘の名著だからです。
*
著者のヘンリー・マーシュはイギリスの脳外科医(神経外科医)。彼の名を一躍世界的に有名にしたのが前作のDo No Harm: Stories of Death, Life and Brain Surgeryでした。
世界中でベストセラーになった同書の愛読者の中には(出版当時の)イギリス首相デイヴィッド・キャメロンも含まれています。在職中のクリスマス休暇に同書を読み耽ったというキャメロン首相は、そこで描かれている脳外科手術の現場で苦闘する脳外科医や医療スタッフたちの、そして残酷な運命を辿った患者やその家族たちの姿に深く心を打たれ、ときには涙を堪えることができなかったのだそうです。
もっとも、このような絶賛を受けた当の著者はというと、こんな反応を返してみせたのでした。
「彼(キャメロン首相)が政治的干渉、慢性的な病床不足、そして現政権と前政権による混沌に満ちた改革についての文章は読み飛ばしてしまったのではないかと心配になる。そうではないと思いたいが」
この、いかにも英国人らしいアイロニーの精神は同書の中でも折に触れて披露され、それが大きな魅力になっていました(ついでに述べておくと、著者のパートナーであるケイト・フォックスはこの「英国人らしさ」を主題としたベストセラーを世に送り出した人類学者です)。
もちろんそれだけではなく、手術場面や患者との交流のまるで映画のようなリアルな描写や、脳外科手術という高度な専門治療の場面を描いているとは思えないほどの読みやすさと相まって、同書は大きな成功を収めました。そうした著者ならではの魅力的な文章は本書でも健在です。ただし、本書を間違いなく前作以上の大傑作に、そして世に溢れかえっている「専門医が教える本当のこと」のような凡書とは比べ物にならない質のものにしている理由は、本書の主題そのものにあります。
その主題とは「死」に他なりません。
*
本書の原題はAdmissionsというシンプルなものです。このadmissionという英単語には複数の意味があります。
第一に「(何かに)入ること」。学校に入学することや、動物園に入場することを意味する際に用いられる言葉です。医師である著者にとっては「病院への入院」がそのもっとも身近な用法でしょう。もちろん本書の中でも「入院」という意味で、この言葉が頻出します。そして、私たちの多くが人生の最後の日々を「入院」先で過ごすということも、きっとこの言葉が本書のタイトルに選ばれた理由のひとつなのでしょう。
そして、第二の意味は「告白」。自らの過ちを認め、それを率直に語るという意味です。本書はまさに「告白」の書だと言えます。著者が手術中、もしくはその前後に犯した過ちが率直に記述されているのですから。また著者は自らの人間的欠点や私生活における問題のことも正直に、ときにはそこまで書いてしまって本当に大丈夫なのかと心配になるほど正直に描いています。この正直さだけをとっても、本書は驚くべき一冊だと言っていいでしょう。
ところが、著者が「告白」しているのは医師として自分が犯した職業上の過失のことだけではありません。本書で著者は、専門医としての長い職業生活と私的な生活が織りなすようにして形作っていった内省そのものを告白しているのです。脳外科医として、患者のいのちと死に直接触れる経験を重ねてきた著者だからこそ達することのできた、その内省の深さこそが、本書を特別な一冊にしているのだと訳者は思います。
著者はその深い洞察にいかにして至ったかも詳しく述べています。
医師たる者は患者との間に「距離を保つこと」が必要だと、本書の中で著者は何度も強調しています。それが治療にとって、ひいては患者の利益にとって重要なのだと言うのです。一見すると冷たく感じられる表現ではありますが、自分が何らかの病を抱えて病院や医院を訪れたときのことを考えてみると、すぐにその意味が理解できます。
病院で出会う医師が個人的な感情やその日の気分の良し悪しで態度を変えるようでは困ります。専門家としての知識と技術に基づいて治療に取り組んでもらうことを、私たちは医師に期待するでしょう。それに担当医が自信なさげではこちらも不安になってしまいますから(たとえ内心ではどう思っていたとしても)少なくとも私たちが目の前にいるあいだは落ち着いた態度を示してもらう必要があります。
つまり、患者を前にした医師はできるだけ冷静に、客観的に治療に取り組まなければならない。そのために必要な医師の態度のことを、著者は「距離を保つこと」と呼んでいるのです。特に若い世代の医師たちは真っ先にそれを学ぶ必要がある、と。
ところが、いま著者は長年に及ぶ脳外科医としての現役生活を終えつつあります。そのいま、著者はこの「距離」がいかに曖昧になってきたかを告白しているのです。
いのちを救ってきた患者たち。救うことのできなかった患者たち。重い後遺症を残してしまった患者たち。手術をしないという決断をした患者たち。そして、その家族。
いま、著者はそうした人たちと自分が同じであるように感じると言います。医師と患者という、かつては明確であった境界線は、脳外科医としての濃密な経験の末に曖昧になっていったのだ、と。
医師としての人生が著者にもたらしたのはそのような変容、あるいは他者と自己に対する見方の本質的な変化であったようです。その変容は死をめぐる内省を、そしてそれを語ることを著者に促しました。その結果として生まれたのが本書だと言ってもいいでしょう。
本書にはさまざまな死が描かれています。避けることの出来なかった死。手術中のミスによる死。直接触れることのなかった死。そして、思わず目を背けたくなるような悲惨な死。
けれども、もはや著者はそうした死を「距離」を保ちながら語ろうとはしていません。自らの人生と存在とを重ねながら、そして遠くない将来にある自らの死を見据えながら、いま、著者は死について語りはじめました。
「よき死」とは何だろうか? それは私たちに可能なことだろうか? 私たちの社会はそれを可能にしているだろうか?
いずれも私たちが普段は考えようとしないこと、いや、むしろ、積極的に考えることを避けたがるこうした問いに、著者は正面から向き合っています。
臨床医としての濃厚な実経験に裏打ちされたその議論にはそれだけで重みがありますが、死をめぐる真剣な議論であるがゆえに、読んでいて心を揺さぶられることもあるでしょう。
「もう死なせてあげた方がいい」という医師たちの言葉にショックを受けることもあるかもしれません。安楽死をめぐる著者の見解には当然ながら異論もあるはずです。
けれども、私たちの誰もが避けたがるものであり、私たちの誰もが避けることのできないものとしての死について、自分自身で考え、語ることを、本書は私たちに促しています。
そのことが本書を特別なものに、そして私たちすべてにとって価値のあるものにしていると、訳者は思うのです。
私たちの誰もが、著者が描く患者たちと同じく、あるいは著者と同じく、やがて死すべき存在なのですから。
以上を踏まえ、本書の邦題は『医師が死を語るとき──脳外科医マーシュの自省』としました。原題が持つニュアンスの豊かさには及ばずとも、本書のもっとも重要なテーマをできるだけストレートに表す表題となっているとよいのですが。
copyright© OTSUKA Shinichiro 2020
(著作権者のご同意を得てウェブ転載しています。なお、
読みやすいよう適宜、改行や行のあきを加えています)