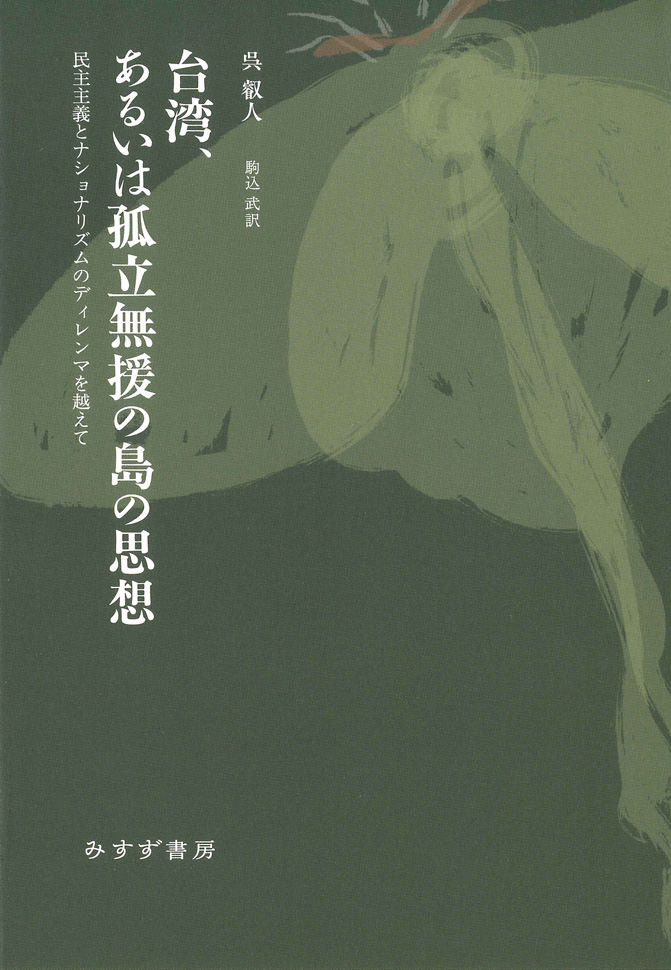本書は、呉叡人著《受困的思想:台湾重返世界》(台北:衛城出版、2016年)の日本語訳である。著者の呉叡人氏は1985年に台湾大学政治系を卒業、2003年にシカゴ大学で政治学博士の学位を取得、早稲田大学客員研究員を経て中央研究院台湾史研究所の助研究員に就任、現在は同副研究員である。著者にとって学問上の「師」というべき存在は『想像の共同体』で知られるベネディクト・アンダーソンであり、中文版《想像的共同体》の訳者としても知られる。さまざまな専門領域と複数の言語を横断しながら思索を展開する著者の専門をひとことで述べるのは難しい。さしあたり比較史的手法を駆使した「台湾政治史」と評することができよう。最初の論文集となった本書では台湾にかかわる“思想”を主眼とした論文を一書に編み上げている。
本書を手に取った読者は、カントやニーチェからハーバーマス、アーレントにいたるまで現代の「古典」ともいうべき書物を縦横無尽に使いこなす著者の博学、多言語能力に驚かされることだろう。だが、さらに重要なのは、本書が思想“研究”の書であるに止まらず、台湾をめぐる現実と格闘しながら著者自身が紡いだ思想の“表明”でもあることである。本書には、四方八方に張りめぐらされた二律背反的ディレンマの中で苦闘する著者の姿が刻み込まれている。いかなるディレンマであり、どのような苦闘なのか。「受困」「民族」「公民」のように鍵となる概念の訳語に即して説明した上で、本書が日本社会に投げかけている課題について訳者なりの見解を記すことにしたい。
1. 「受困」──「歴史の終わり」のその先
本書の中国語表題《受困的思想》における「困」という言葉は、日本語と同様に困難な状況に陥る意味合いである。とりわけ包囲されて立ち往生する文脈で用いられる。「受困」を言い換えて「孤立無援」「籠の中の鳥」「拘禁」とも表現している。著者自身が高橋和巳『孤立無援の思想』(1979年)を意識していると訳者に語っていたこともふまえて、本書では基本的に「孤立無援」と訳出した。
この場合の「孤立無援」とは、第一義的には台湾が今日の主権国家体系から排除されていることを意味する。台湾は「中華民国」という国号を有する、実質的な独立国である。それにもかかわらず、国際政治の表舞台では発言権を認められていない。その起源は、大陸での国共内戦に敗北した国民党政府が、中華人民共和国との国際的な正統性争いに敗れて1971年に国際連合を退出したことにある。
ただし、国際的に孤立無援の境遇に置かれたのは台湾に存立する国家であるばかりではない。その統治下にある民衆は国家暴力にさらされるばかりでなく、国際社会からも見棄てられた。そのことを自覚した人々は恐怖政治に抗しながら民主化運動を展開した。「中華民国」という国号を廃して「台湾共和国」独立を宣言すべきとする台湾独立論も半ば公然と語られるようになっていった。86年には国民党に批判的な政治勢力が民主進歩党(民進党)を結成、翌87年の戒厳令解除を契機として徐々に民主化が定着、中国大陸ではなく台湾を「本土」とみなす台湾本土化志向の高まりの下で台湾在来の言語や歴史がようやく学校教育にも組み込まれることになった。だが、これにより「籠の中の鳥」状態を脱することができたわけではなかった。90年代以降、大国化した中国が「台湾は中国の一部」という立場から独立志向に対して外交的・軍事的な圧力を強め、台湾包囲網を狭めてきたからである。
こうしたリアルポリティーク──著者はしばしばこれを「地政学」という言葉で表現する──における八方ふさがりの状況が「受困」である。とはいうものの、本書において「受困」は現実政治の文脈よりも、むしろ認識論的次元における文脈で強調されている。試しに本書(第4章)に収録された「賤民宣言」の一節を確認しておこう。
帝国の狭間ではかえってさまざまな形態の弱小者ナショナリズムが芽生え、成長しつつある。
奴隷はいまだ叛乱を続けており、理性はなおも完成していない。
にもかかわらず、帝国の指導者たちは早々に歴史の終わりを宣言した。
「歴史の終わり」はフランシス・フクヤマ『歴史の終わり』(1992年)を意識した表現である。フクヤマはヘーゲルの歴史哲学の語彙を駆使しながら、1991年のソヴィエト連邦崩壊をもって共産主義の破綻とリベラルな民主主義の正統性が確認されたとして、両極構造の消えた「歴史の終わり」において民主的国家が地上における「理性」を徐々に完成させ、「奴隷の反乱」を無力化していくだろうと予言した。だが、著者からするならば、帝国の狭間を生きる弱小者の叛乱は今もなお続いている。スコットランドにおいて、カタルーニャにおいて、沖縄において、香港において、そして台湾において……。だが、ポストモダニズムの洗礼を受けた思想界では、ナショナリズムに懐疑的な視線が向けられるばかりでなく、新たな主体を立ち上げる試みそれ自体が虚偽の同一性をねつ造するものとして批判される。叛乱の矛先が既成の社会主義国に向かう場合には、マルクス主義の知的伝統を軽視する「右派的」「反動的」見解ともみなされがちである。
ポストモダンの時代においてナショナリズム批判が生まれる由来を十分に理解し咀嚼しながら、それでも帝国に抵抗する「弱小者のナショナリズム」について語るとしたら、どのような語りがありえるのだろうか。ナショナリズムと多元的な民主主義はどのように並び立ちうるのだろうか。そうしたディレンマが「受困」という言葉の通奏低音をなしている。そこで著者を包囲しているのは現実の大国というよりも、むしろひとつの認識論的な枠組みである。
2. 「民族」──政治文化を共有する同盟関係
ナショナリズムをめぐる著者の思考において、中核的な重要性を占めるのは「民族」という概念である。この場合の「民族」は、日本語の文脈で一般的に理解される「民族」とは意識的な切断が図られている。著者は、本質主義的な「民族」概念、すなわち、共通の血統、言語、風俗習慣や価値体系などで結ばれた有機体としての「民族」というイデオロギーを批判し、それが巨大な政治暴力を生みだしてきたことを問題視する。その上で、「民族」を非本質主義的な方向で解釈し、共通の政治過程を通じて一定の政治文化を共有することになった人々が結ぶ“同盟”関係として捉え直すべきと論じている。この場合の同盟関係は永続的なものではなく、民主的政治体制の下で相対的安定性を備えて存続するものの、崩壊したり、再構築したりすることもあるものとされる。
「民族」という言葉は中国語でも「中華民族」という場合など本質主義的な意味合いで用いられることもある。著者はそうした解釈の磁場を十分に自覚しながらも、中国語で「ネイション」の訳語としてしばしば用いられる「国族」ではなく、「民族」という言葉を用いている。自らの国家を持たない弱者を想定しているからこそ、「国族」(「国民」)はそぐわないという認識に加えて、もともと欧米でも「民族(nation)」とは、一定の政治的文化を共有する人々の同盟関係を本質的な要素とするという認識に基づいた選択である。こうした観点からあえて「民族」という言葉を用いる著者の意図を生かすために、本書では基本的に原文通り「民族」と訳すこととした。ただし、「民族主義」については、日本語圏における慣例的な分析概念──例えばベネディクト・アンダーソンの「公定ナショナリズム」──と一貫性を持たせるために、原則的に「ナショナリズム」と翻訳した。日本語文脈では「民族」が分析され説明されるべき概念として登場するのに対して、「ナショナリズム」は分析概念としても使用されるという相違が、こうした訳し分けに影響している。
「民族」と関連の深い言葉として、本書では「種族」や「族群」も用いられている。「種族」は英語ではレイス(race)に相当するものであり、血縁意識を養分としながら「種族偏見」を生み出すという否定的なニュアンスで用いられている。本書では「人種」と訳した。
「族群」は基本的に「エスニック・グループ」と訳した。台湾の住民構成は自ら「原住民族」と名乗る台湾先住少数民族、中国大陸の福建省南部をルーツとする閩南人(福佬人ともいう)、広東省をルーツとする客家人、戦後に国民党政府とともに大陸から移住した「外省人」──「台湾省」以外の省を籍貫(本籍)とする人々の意──が「四大族群」と呼ばれるほか、近年東南アジアや中国大陸から移住した人々が「新住民」と称される。「種族」が血統意識を重視し、「族群」が言語的・文化的な差異にかかわるのに対して、「民族」は政治的次元に定位されている。したがって、著者は「民族」を論じるに際して、例えば閩南語がどのように「中国語」と異なるかという問題には立ち入らない。「台湾民族」について論じる際、相対的にはマジョリティである閩南人を「台湾人」と同一視する思考を意識的に斥けてもいる。さらに、エスニシティという点では単一集団と見られる人々の内部にもジェンダーなどさまざまな軸で個人的な差異があることに着目し、多元性と異質性をそなえた個人や集団がいかに政治的利害対立を調整・克服しながら「共同世界」を創り上げるかという問題に関心を注いでいる。
ネイションにしても、レイスにしても、エスニシティにしても、欧米起源の概念である。日本語ではレイスの訳語として「人種」ばかりではなく「民族」が用いられることもあるが、それはとりもなおさず「民族」概念が人種化されていることを示唆している。他方、台湾では日本語を介して「民族」概念を受容しながらも、台湾の状況に即して意味内容を換骨奪胎してきた。例えば、本書で著者も注目しているように、抗日左派のリーダーだった連温卿(1894-1957)は、「台湾民族」という言葉で反日本帝国主義という立場での「統一行動」(「同盟関係」!)の主体を表現していた(第15章)。
帝国日本の植民地支配にかかわる台湾人と日本人の経験の違いが、「民族」という言葉の意味のズレの中に刻み込まれている。本書の「民族」概念が日本語文脈で醸し出す微妙な違和感は、そうしたズレを感知するための手がかりとなるはずである。
3. 「公民」──「共和国」を支える人々
原著における「公民」は日本語では「市民」と訳した。ただし、そこにも重要なニュアンスの相違がある。日本語で「市民」という言葉は「国家からの自由」に力点を置いて理解されており、「公(おかみ)」の支配下にある「公民」とは対照的な存在とイメージされる。そのような理解には、国家が公共的な世界を強く管理統制してきた近代日本の歴史が投影されていると考えられる。これに対して、著者にとっての「公民」とは自主的に国家の意志決定に参与し、公共空間を形成しようとする人々である。「市民」という言葉は字義通り都市の民の意味であり、「香港市民」という用例のほか、離農した農民が都市で富裕な「市民」に転化するという文脈でわずかに用いられるに止まる。
著者の「公民」概念は、フランス語におけるシトワイヤン(citoyen)に重なるところが大きい。水林章によれば、シトワイヤンは日本語で「市民」と訳されるものの、語感はかけはなれている。「市民」は「政治とは関わりのない普通の人」というニュアンスが強いのに対して、シトワイヤンは「国家への自由」に力点があり、ポリス(政治社会)の構成員として政治的意志の形成に参与する自律的個人を指している(レジス・ドゥブレ他『思想としての〈共和国〉』みすず書房、2016年増補新版、51頁)。この点に着目するならば、「民族」の場合と同様、そのまま「公民」と訳すべきとも考えられた。だが、例えば著者がcivic nationalismを「公民民族主義」と訳し、civil societyを「公民社会」と訳しているのに対して、日本語ではそれぞれ「市民的ナショナリズム」、「市民社会」と訳すことが慣例となっている。中国語の「公民」をそのまま用いた場合、こうした分析概念としての対応関係が見失われてしまうと考えて「市民」と訳した。原語は、「国家への自由」に力点を置いた「公民」であることを念頭に置いて読んでいただきたいと思う。
この「公民」概念もまた、台湾の歴史的経験を基盤として語られていると考えられる。日清講和条約(1895年)により帝国日本に「割譲」された台湾は、カイロ宣言(1943年)で中華民国に「返還」されることになった。「割譲」と「返還」、どちらの局面でも「籠の中の鳥」のように日・中間の政治的取引の材料とされた。それにもかかわらず──あるいはそれゆえにこそ──社会は連続して高度の自主性を育んできた、と著者は論ずる。他方、近代日本では天皇を主権者とする「帝国」が上から強力に創出されたために「共和国」の思想を想像することさえ困難である。日本「本土」と通称される島々に住む人々は、東アジア各地で共和国を樹立しようとする試み──1919年上海における「大韓民国臨時政府」、1956年東京における「台湾共和国臨時政府」、そして今日の沖縄における「琉球共和国」等々──を圧殺してきた歴史に向かい合うことで初めて、「公民」という言葉に託された意味に接近できるようになるのだろう。
なお、関連して「本土」という言葉にもふれておきたい。自分たちの暮らす土地が「本土」であることを自明の前提とする人々は、「本土」について語る必要を感じない。他方、沖縄のように歴史的に「本土」中心主義に脅かされてきた土地で「沖縄こそ本土」と語るならば、現状へのプロテストとなる。台湾や、香港についても同様である。「本土化」は、台湾や香港とは別に「本土」と呼ぶ地域をもつ外来政権(清帝国、日本帝国、中華民国、中華人民共和国)の統治を前提としながら、“自分たちの生活する場所こそ「本土」である”と認識を転換させる志向をあらわしている。
投げかけられた課題──もうひとつの日台同盟に向けて
これまでの論からも明らかなように、著者は台湾を単位とした「共和国」を樹立し、またそのことを通じて「籠の中の鳥」状態を脱し世界へと回帰することを望んでいる。その点では著者の立ち位置を「(左翼)台湾独立派」として括ることも可能である。だが、中国統一を志向する国民党と、台湾独立を志向する民進党の対立の中で後者を支持するものとして理解するならば、それは正確ではない。本書において著者は国民党に対してはもちろん、民進党に対しても批判的な距離を保っている。また、著者の師であるベネディクト・アンダーソンがそうであったように、著者自身もマルクス主義の知的伝統の中に身を置きながら階級的な観点の重要性を主張し、とりわけ「黒潮論」では〈帝国─資本─国家〉からの解放を説く点でアナーキズムへの傾斜すら見せている。
日本社会では独立志向の在日台湾人が「日台右翼同盟」ともいうべき独特の言論の磁場をつくりあげてきたこともあって、「台湾独立」を口にした途端に「反動」「右翼」の烙印をおされがちである。著者もそのねじれた言論の磁場をよく自覚しながら、広い意味では「同志」であるはずの人々に対して鋭い批判の矛先を向けている。すなわち在日台湾独立派の「植民地支配肯定論」は日台間に新たな植民地主義的関係を生み出すに過ぎないと指摘し、本質主義化された中国人批判(「醜い中国人」)に対しては、中国政府と中国市民社会を峻別し、市民社会レベルでの連携を模索すべきだと説く(第6章・第7章)。
政治的マキャベリズムを戒める著者の姿勢は、沖縄問題への対応にもあらわれている。もしも台湾人が自らの独立のために琉球人を犠牲にしてよいと考えるならば、琉球人あるいは他の民族が自身の独立のために台湾を犠牲にしてよいということにならざるをえない、と著者は論を立てる。その上で、民族自決、民主、人権、平和、そして環境保護という理念に基づいて、米軍基地撤廃と琉球人による自決を支持すべきであると論ずる。さらに、台湾もまた日米への軍事的依存を破棄し、強権の覇権争いに巻き込まれることを拒絶し、カント主義の理念に拠りながら「永世中立」の立場で小国・弱国と連携して「オルタナティブな国際秩序」を追求すべきだと主張している(第10章)。
このような議論は、多くの場合、沖縄で米軍基地に抵抗している人々や、日本「本土」のリベラルな人々にとって歓迎すべきものと受け取られることだろう。だが、これが台湾人を宛て先として語られていることに留意する必要がある。訳者の知る限りでは、台湾独立派と総称される人々の中に、中国の侵攻に備えるために沖縄の米軍基地を必要と考える人は少なくない。そのため、八方ふさがりの現実の中にある台湾の人々に対して「弱者の共食い」を避けるべきだと説く著者の論は、時には台湾人の間であまりにも理想主義的と評されることもある。だが、あまりにも理想主義的と見える論の根底には、あまりにも惨憺たる現実が存在する。著者自身、南アフリカのツツ主教の著書にかかわって、人類の悪が善によって救われるという感動的なストーリーの深層には「エゴ、卑劣、衝突、対決、さらには、抑圧され隠蔽され、救済のしようのない怨恨と、分裂と復讐への欲望」につき動かされる現実を読み取るべきだと記している(第9章)。この二重化された読解の姿勢は、本書そのものに対しても向けられるべきだろう。善と悪、政治的なものと道徳的なものは、常に背中合わせに絡み合っている。著者は、偽りの突破口にすがることを拒絶しながら、まずは八方ふさがりの“運命を見つめる”作業を通じて、真の、相互触発的な解放の契機を探ろうとしている。
こうした著者の見解が非現実的なものとして斥けられるのか、それとも「日本」と「世界」に多くの共鳴者を見出して世界を変える力となるのか。それは、著者の課題であると同時に、日本社会と世界の市民社会の応答責任にかかわる課題でもある。賽は日本と世界の側に投げかけられているといってもよい。戦後日本においてかつて植民地支配下に台湾でなされた不正義を糾明して正義の回復を図る作業は、長く等閑視されてきた。中国大陸での侵略戦争にはある種の贖罪意識を抱いたとしても、台湾植民地支配についてはむしろ「恩恵」を施してやったといわんばかりの傲慢さへの開き直りが一般的だった。とりわけ左派・リベラル層の間では賞賛すべき「中国社会主義革命」のネガとして、蔣介石の統治する台湾は関心の外側に沈んだ。2000年前後に在日台湾独立派の政治的キャンペーンが功を奏して「中国の一部ではない台湾」という認識こそ普及したものの、それは「親日台湾」という単純化されたイメージの宣伝と表裏一体だった。
この「訳者あとがき」を執筆している2020年になってようやく、2つの出来事が「親日台湾」には還元されない別な認識──「民主主義台湾」という認識を広げることになった。ひとつは香港の民主化運動と、これに連帯しようとする台湾人の姿勢である。本書に収録された香港にかかわる論考でも、著者は香港の若者たちの動きに深い共感を寄せながら、香港民主化運動の深層に横たわる動きを浮かび上がらせている。もうひとつは新型コロナウイルス感染症への対応である。台湾政府の対応が的確であることが世界中の人々の眼前に明らかになった。長きにわたる民主化運動の結果として獲得された主権者意識と、これに基づく政府監視の姿勢が、政府に緊張感を与えたという認識も広がりつつある。他方、日本政府の対策の無残さは、日本社会に漠然とした憧憬を抱いていた台湾人に幻影からの覚醒を強いることにもなった。著者もそのひとりかもしれない。ただし、著者が愛着を抱いていた「日本」とは漱石であり、矢内原忠雄であり、高橋和巳であり、いわば「もうひとつの日本」の思想的系譜であることに留意する必要がある。
今や舞台は転換した。民主主義の「後進国」日本の人々は、多元的な民主主義の「先進国」台湾から多くを学ばなくてはならない。そう語っても驚く人は少ないだろう。だが、そのことだけを強調するのも一面的である。感染症への的確な対応にもかかわらず、台湾はWHO(世界保健機関)から相変わらず閉め出され続けている。覇権国家の取引の材料とされる「籠の中の鳥」状態を脱しえたわけでもない。そのことは、日本語版への序文で著者自身が記している通りである。また、2020年12月現在、「香港国家安全維持法」の影響もあって、民主化を求めて香港の街頭を埋め尽くしていた人々の姿は潮が引いたように消えている。そうした事態は著者が十分に予想していたことであり、明日の台湾が今日の香港のようになることさえ想定内なのだろう。そう考えることにより、本書全体にみなぎる緊迫感の一端を理解することができる。著者が香港や台湾のナショナリズムを「歴史構造上の長期的な要素と、政策・政治上の短期的な要素」を含む「マクロな歴史社会学的現象」(第11章)として把握する姿勢も、目の前の出来事に一喜一憂すればこそ、あえて氷河の深層に横たわる動きを見透かそうとする意志の表れと見ることができる。
日本社会の側では、著者による批判の矛先が中国ばかりでなく、アメリカとその「実質的な属国」(第4章)としての日本にも向けられていることに留意しなくてはならない。著者が求める台湾社会の「脱植民地化」も、日本社会が切実に必要としている「脱帝国化」もいまだ実現していない。正反対の場所から掘削作業を行っていることを自覚しつつ、「日台右翼同盟」とは異なる、もうひとつの同盟を構築できる地点を見定める必要がある。
著者が強靱な知性をもって多様な専門領域を横断し、現実と理論のあいだを往還しながら自らの思想を紡いでいるだけに、本書の呼び起こす波紋もまた多様なものでありうるはずである。本書を機縁として「自主独立なる者の平和的結合」を求める流れが大きなうねりとなり、世界に環流していくことを、訳者もまた、著者とともに願っている。
copyright © KOMAGOME Takeshi 2021
(著作権者のご同意を得て抜粋・転載しています。なお、
読みやすいよう適宜、改行や行のあきを加えています)
[付記]
当ウェブサイトへの転載にあたり、下記の通り訂正いたしました。
本書441頁13行目 「レジス・ドゥプレ」→「レジス・ドゥブレ」
本書449頁2行目 「読み取るべきだ記している」→「読み取るべきだと記している」