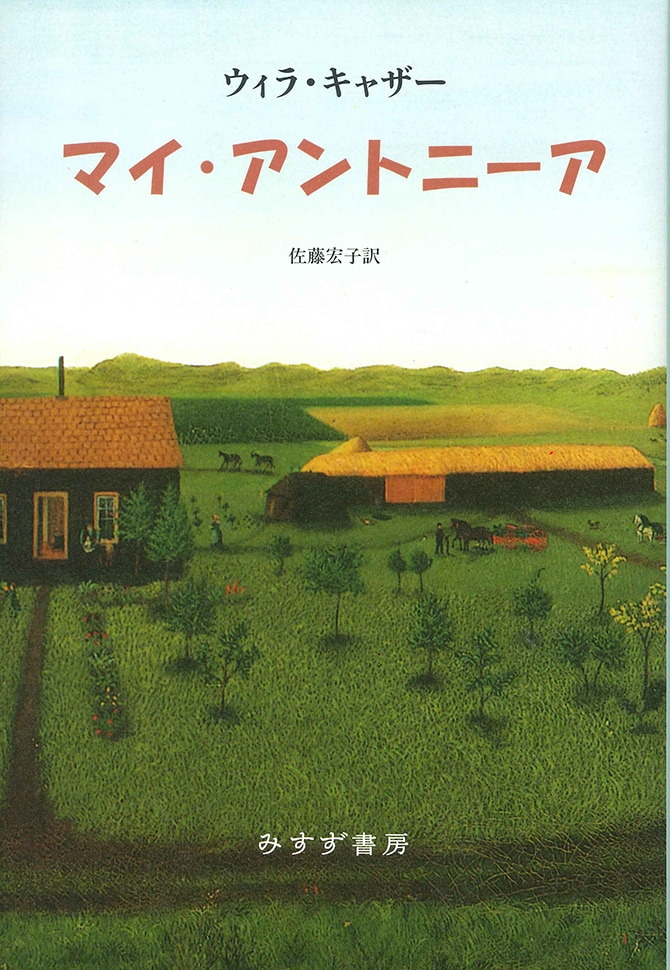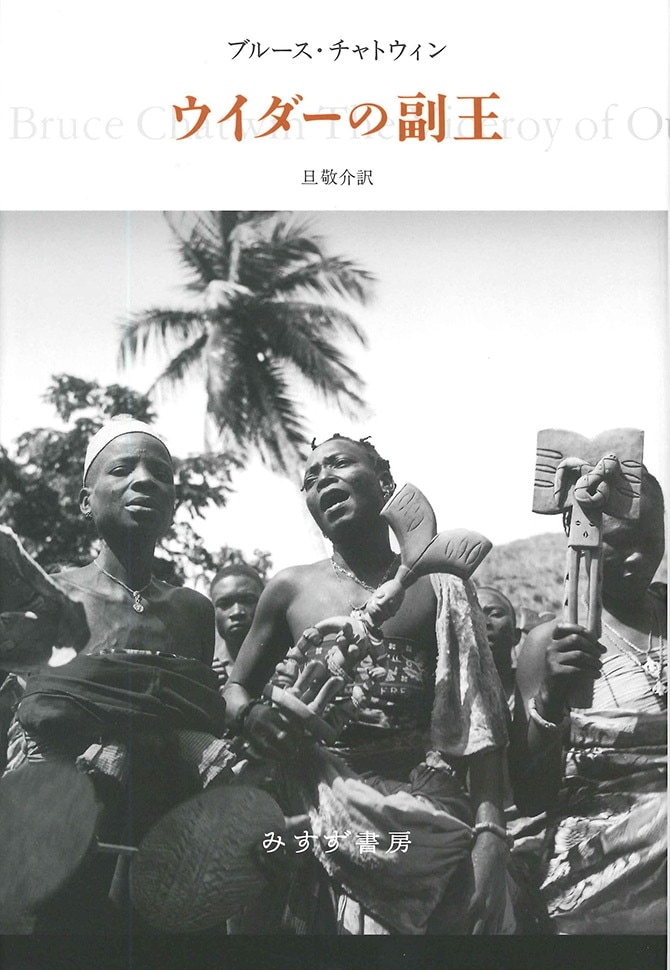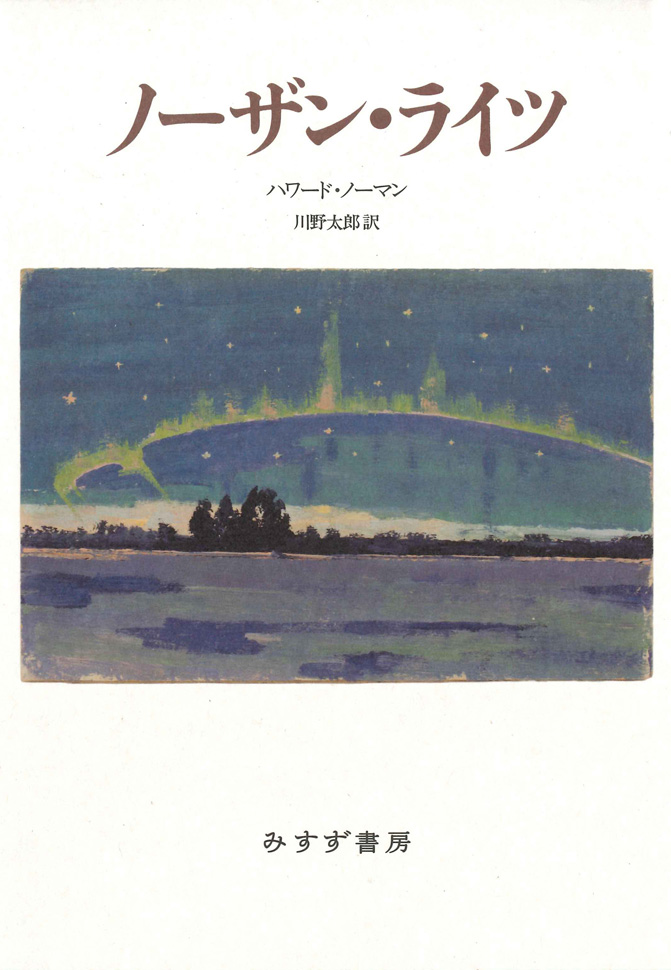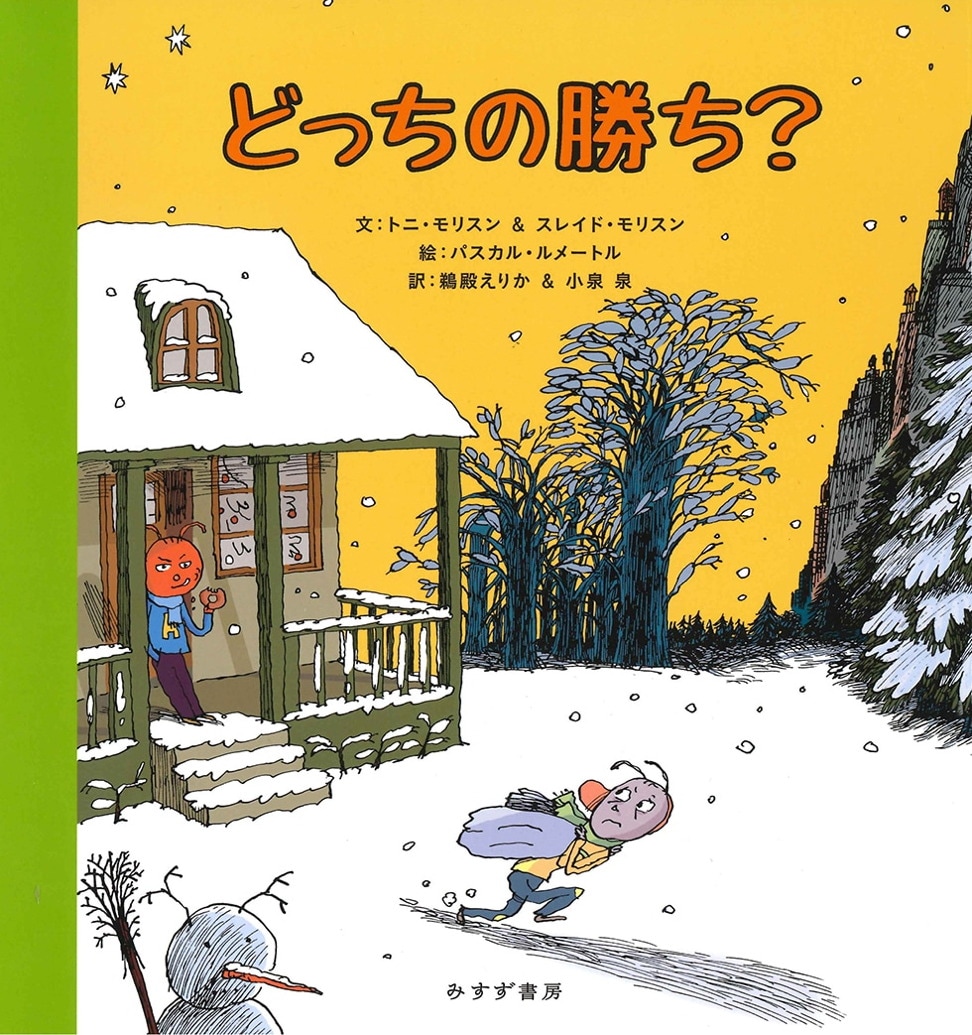青山 南
『テナント』は、1971年に出版された、バーナード・マラマッドの6冊目の長編である。マラマッドは1986年に71歳で亡くなったが、遺した長編は8冊で、そのうちの7冊は日本語に翻訳されており、唯一、この『テナント』だけが紹介が遅れていて、本書が初の翻訳である。
『テナント』は、マラマッドが書いた作品のなかではきわだって異色のものである。マラマッドの作品は、長編では『アシスタント』(1957年)[加島祥造訳、新潮文庫]が、短編集では『魔法の樽』(1958年)[阿部公彦訳、岩波文庫]がよく知られているが、ユダヤ人移民のアメリカでの苦難の日々のありさまを、前者では切実にリアルに、後者ではほとんど寓話のように、かつユーモラスに描いている。
いまでこそ、ユダヤ人はアメリカの政治経済に大きな力をもつようになっているが、かなり長い間、白人が主流のアメリカで、移民として冷遇されていた。第二次大戦後まもない1945年にはアメリカ・ユダヤ人委員会の支援のもとで総合雑誌『コメンタリー』が創刊されたが、アメリカ人としての存在をつよく主張していく雑誌として力を発揮していくことになる。
マラマッドは「ユダヤ系作家」とひとくくりにされるのは好まなかったが、あるインタビューで、「わたしの作品に登場するボーダーラインに立たされている人物たちはユダヤ的なバックグランドの影響下にあるが、わたしがユダヤ人について書くのは、かれらのことを知っているからで、かれらといっしょだと落ち着くのだ」と語っているように、ユダヤ人について書くと落ち着いていられたようである。
『テナント』は、その点、黒人が大きく出てきて、ユダヤ人と対決してくるのだから、マラマッドとしてもさぞや落ち着いて書いてはいられなかったろう。じっさい、『テナント』での黒人のふるまいやしゃべりの書きかたにはいまひとつ自信がなかったようで、デビューしてまもない若い黒人作家のジェイムズ・アラン・マクファースンに原稿を見せている。
では、どうして、慣れない分野に進んでいこうとしたのか。もちろん、新しいことを試みたいという作家としての野心もあっただろうが、なによりも1960年代という混乱の時代の波に押されたことはまちがいない。黒人の公民権運動から派生していく過激な黒人の運動、ベトナム戦争への反対行動から発展していく若者たちの過激な活動、それらの動きから展開される無秩序な社会の風景、そういったものに刺激されただろうことはまちがいない。
ソール・ベローは1970年に出した『サムラー氏の惑星』[橋本福夫訳、新潮社]ではニューヨークの荒廃した光景を描くことになったし、フィリップ・ロスは1971年に出した『われらのギャング』[青山南訳、集英社]では荒唐無稽な論理を展開する大統領を荒唐無稽に徹底風刺するという異色作を発表していて、いずれも1960年代の混乱があったがゆえの産物である。
2003年に『テナント』の新装版が刊行されたさい、ボスニアからアメリカに移住して作家になったアレクサンダル・ヘモンが序文を寄せて、こう書いている。「『テナント』はアメリカの文学の歴史においてターニングポイントになっており、文学にアイデンティティー・ポリティクスが台頭してきたこと、〈純粋芸術〉の可能性への信頼がなくなってきたことの始まりを示している。」
アイデンティティー・ポリティクスとは、『リーダース英和辞典第三版』によれば、「アイデンティティーの政治(人種・民族・宗教などをアイデンティティーとする集団の利害を主張する政治)」。『テナント』の最後には「慈悲を」が並ぶが、それはユダヤ人家主レヴェンシュピールの願いというよりは、アイデンティティー・ポリティクスにたいしてあげられたマラマッドの悲鳴といってもいいだろう。
copyright© AOYAMA Minami 2020
(著作権者のご同意を得て抜粋・転載しています。なお
読みやすいよう適宜、改行や行空けを加えています)