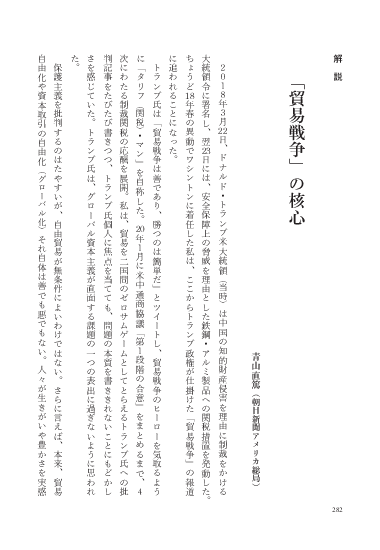
青山直篤「解説」全文(PDF、960KB)
ライオネル・ゲルバー賞受賞作
「『貿易戦争とは、階級闘争である』。そんな題名の新著で注目される米国の経済学者がいま、中国にいる。米国と中国などとの間で続く貿易摩擦の根底には、各国の内部で広がる経済格差がある、という主張だ。どういうことか」(朝日新聞、2020年9月18日付)。この出だしではじまるインタビュー記事を目にしたのは、ちょうど本書の企画も通り、翻訳権が取れてまもなくのこと。本書『貿易戦争は階級闘争である』(原題はTrade Wars Are Class Wars)の共著者で、北京大学ビジネススクールの教授を務めるマイケル・ペティス氏が、このインタビューのなかで、国際的な輸出競争が賃金の引き下げ圧力として働き、米中をはじめ各国の労働者に不利に働くメカニズムを端的に解説してみせていました。
この本のユニークな論旨に注目している日本のジャーナリストがいることを心強く感じ、ペティス氏にインタビューして記事を執筆した同紙アメリカ総局の青山直篤記者に、本書の巻末解説をお願いしました。解説では、ペティス氏との対話はもとより、これまでに青山記者がインタビューしてきたローレンス・サマーズ元米財務長官や、ロバート・ライトハイザー元米通商代表らとのやり取りも踏まえた独自の視角を加え、本書を読み解く際のよき補助線となってくれます。
奇しくも、英語版の原書はすぐれた外交関連書に贈られる「ライオネル・ゲルバー賞」(2021年)を4月に受賞し、ふたたび話題を呼んでいます。バイデン政権の対中政策が次第に明らかになり、ますます今後が気にかかる米中貿易戦争の行方を見定めるためにも、ホットな注目を浴びる本書をぜひお読みください。なお、青山記者による巻末解説(「貿易戦争」の核心)はこちら(PDF、960KB)からもご覧になれます。
青山直篤(朝日新聞アメリカ総局)
2018年3月22日、ドナルド・トランプ米大統領(当時)は中国の知的財産侵害を理由に制裁をかける大統領令に署名し、翌日には、安全保障上の脅威を理由とした鉄鋼・アルミ製品への関税措置を発動した。ちょうど18年春の異動でワシントンに着任した私は、ここからトランプ政権が仕掛けた「貿易戦争」の報道に追われることになった。
トランプ氏は「貿易戦争は善であり、勝つのは簡単だ」とツイートし、貿易戦争のヒーローを気取るように「タリフ(関税)・マン」を自称した。20年1月に米中通商協議「第1段階の合意」をまとめるまで、4次にわたる制裁関税の応酬を展開。私は、貿易を二国間のゼロサムゲームとしてとらえるトランプ氏への批判記事をたびたび書きつつ、トランプ氏個人に焦点を当てても、問題の本質を書ききれないことにもどかしさを感じていた。トランプ氏は、グローバル資本主義が直面する課題の一つの表出に過ぎないように思われた。
保護主義を批判するのはたやすいが、自由貿易が無条件によいわけではない。さらに言えば、本来、貿易自由化や資本取引の自由化(グローバル化)それ自体は善でも悪でもない。人々が生きがいや豊かさを実感できる国家や社会を築くことが目的であり、その目的を果たすための政策手段に過ぎない。
しかし冷戦終結後、米国主導で進められてきたグローバル化は、それ自体が目的と化したかのようだった。日米の疲弊した地方都市や農村を取材してきた私も、その行き詰まりを実感してきた。ただ、グローバル化の波はあまりに強力で、なすすべはない。「貿易戦争」を報じる私自身、そんな思考停止に陥りがちだった。
本書は、それを揺さぶる知的刺激に満ちていた。コロナ危機で米国社会が激しく動揺するなか、トランプ氏の再選をかけ大統領選が始まろうとしていた20年6月、英誌エコノミストなどの書評で知って読み、すぐに中国・北京にいる著者のひとり、マイケル・ペティス氏に連絡をとった。「Zoom」を使ってオンラインで取材する約束だったが、中国の通信状況を反映してか通話がしづらく、電話に切り替えて1時間以上、丁寧に話を聞かせてもらった。
ペティス氏は米金融界での実務経験などを経て、北京大学光華管理学院(ビジネススクール)教授として教鞭を執る。米投資情報誌バロンズのマシュー・クライン氏との共著になる本書では、世紀の「長期停滞」とも関連して論じられてきた「グローバル・インバランス」(世界的な経常収支の不均衡)について、新鮮な視点を提供している。
世界金融危機後に「長期停滞」の議論を提起したハーバード大学のローレンス・サマーズ教授は、「世界的に投資不足・貯蓄過剰に陥り、それが低金利とさえない成長、インフレ圧力の減退につながったという現実は、ほとんど誰もが認識している。私のように『長期停滞』という言葉を使う人もいれば、そうしない人もいるが、根底にあるのは同じ現象だ」と語る(2019年11月21日、評者によるローレンス・サマーズ氏へのインタビュー)。本書はこの現象について、主要国の国内の所得分配のゆがみや格差がもたらしたマクロ経済への影響を重視し、それが経常収支の不均衡となって現れたとみる。裕福でない人は、所得の多くを消費に回す。こうした消費性向の高い労働者や中間層の賃金が抑えられ、富裕層や大企業へ富が移転したことで、中国やドイツなどの消費や投資が伸び悩み(貯蓄が増え)、さらにその貯蓄が米国に押し寄せたことで、恒常的な経常赤字が引き起こされたととらえる立場である。
トランプ氏の関心はモノの貿易に集中していたが、現代の貿易不均衡を考えるうえで、より注目すべきなのは国際的な資金移動であるという点には、多くの経済学者が賛同するだろう。本書は世界経済の「見取り図」をこう描く。1997年のアジア通貨危機後、中国は人民元の上昇を避けるためドル買い介入を進め、輸出競争力を維持した。さらに、国有銀行を通じた融資の金利水準を低く抑えて大企業の借り入れコストを下げ、投資や輸出を拡大する。その結果、企業収益は増えるが、労働者の所得が抑えられたため、消費は中国の国内総生産(GDP)に比べ、きわめて低水準で推移した。米国の需要が急減したリーマン・ショック後は経常収支の黒字は縮小したが、補助金を通じた過剰生産の問題は残り、一帯一路構想を通じた国外での需要開拓の試みも、あらたな摩擦を引き起こしている。
さらに分析は、近年の不均衡の主因であるドイツへと進む。東西統一後の混乱を乗り切るため自由化改革を進めたドイツでも、大企業が収益性を高める一方、労働組合は弱体化し、雇用の外部委託や海外移転が進んで賃金も伸び悩んだ。国内の消費や投資が弱いため、輸出と引き換えに得た貯蓄はスペインやギリシャに流れ込み、貸し出しブームとその破綻を生む。欧州債務危機の後は欧州全体の需要が収縮して「ドイツ化」する傾向が生まれた。
誰かが貯蓄すれば、誰かが貯蓄を取り崩さなければ経済は回らない。その「最後の消費者」の役割を担ってきたのが米国である。それは、基軸通貨国としての「途方もない特権」ではなく、「途方もない負担」だったと本書は論じる。過去数十年間、黒字国の資金余剰は米国債の運用などを通じて米国へと流れ込み続けた。本来お金が必要な貧しい国ではなく、GDPでみれば世界一豊かな米国へ資金が流れ込んだのである。
「ただ、リーマン・ショックのような形でバブルが調整されると、低所得層にもはや借金をさせることはできず、大量の失業に直結する。こうした構図を考えれば、米国が進んで貿易赤字を受け入れ続けるとみるのは、ばかげている」。ペティス氏は取材に、そう断言した。
(以下、全文はPDFでどうぞ)
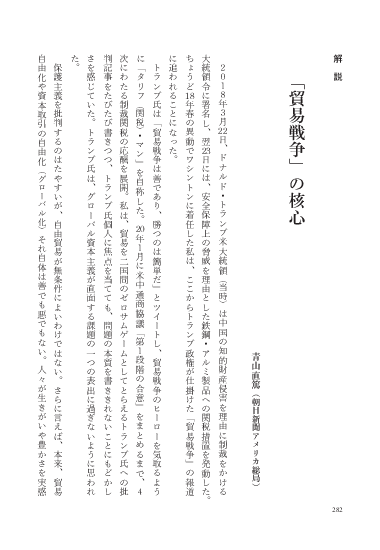
青山直篤「解説」全文(PDF、960KB)