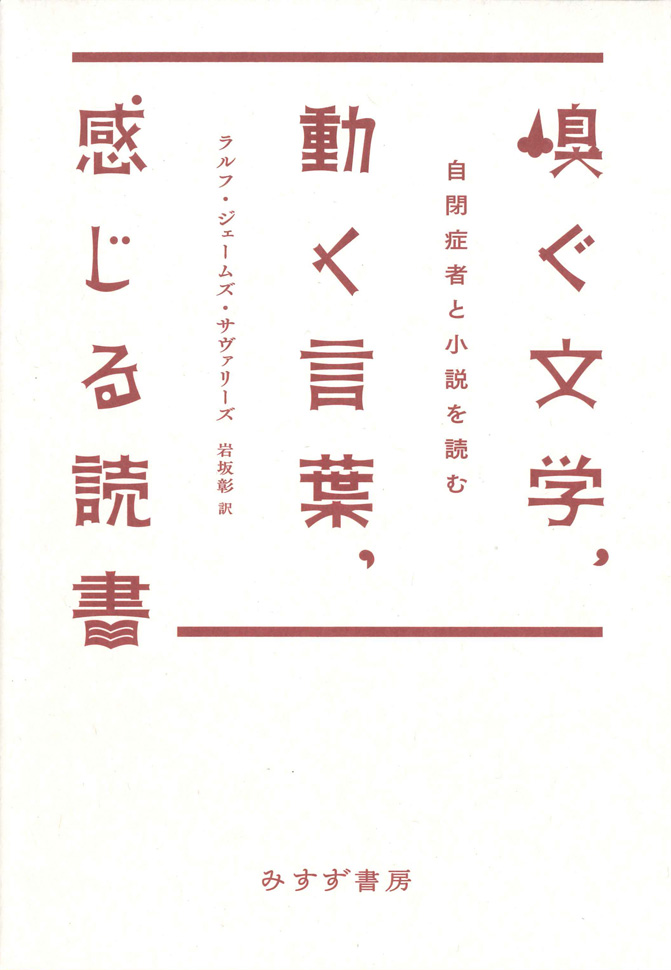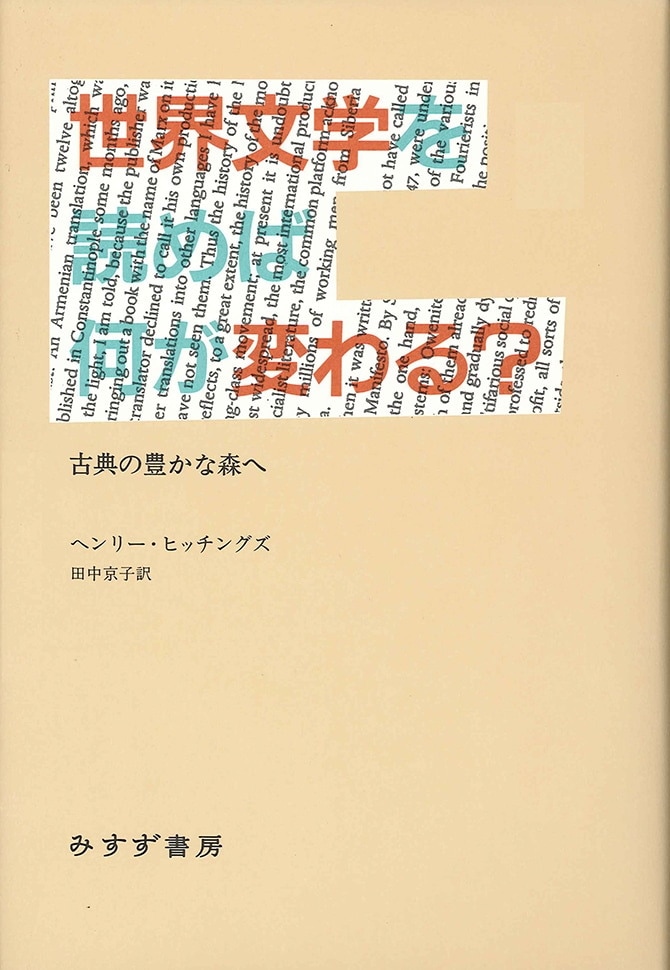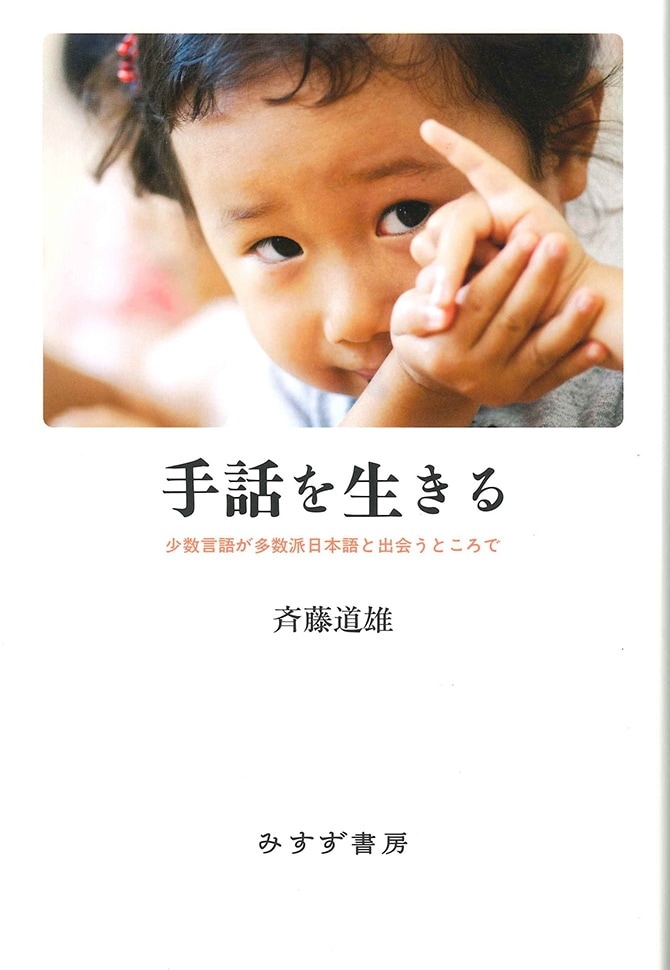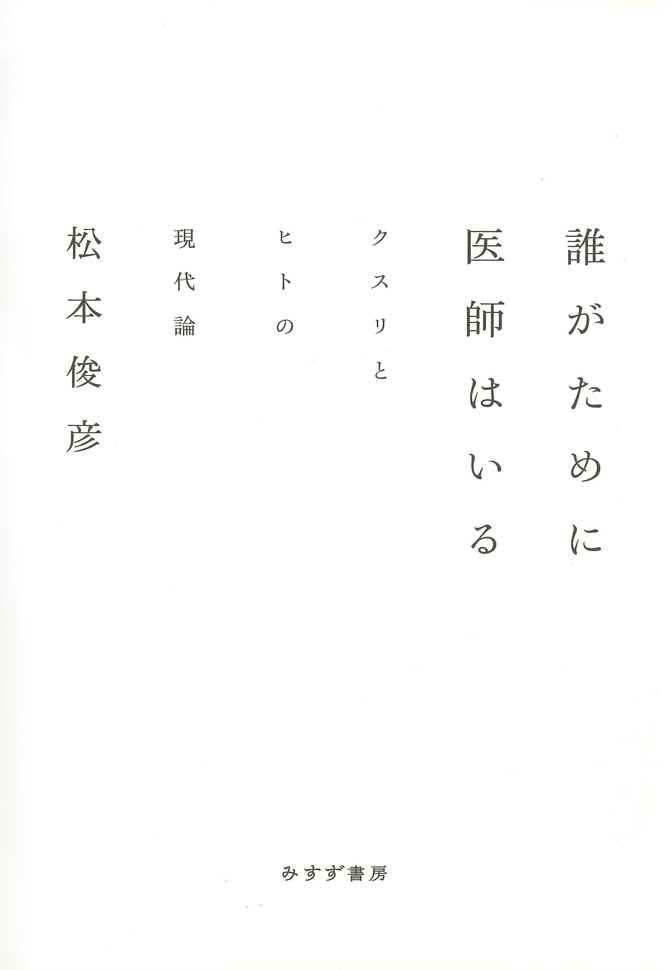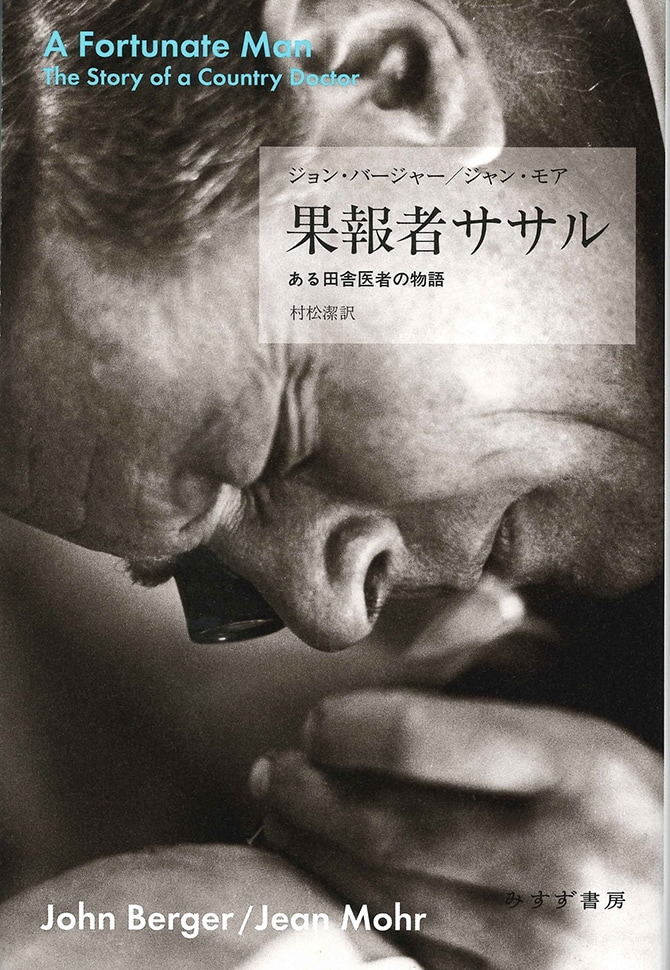本書に寄せて
スティーヴン・クーシスト
〔岩坂彰訳〕
本とともに暮らす人は遅かれ早かれ、言葉は生き物だということに気づく。書くことで気づくか、読むことで気づくか、あるいは読者反応理論を通じてか神経精神分析を通じてかは問題ではない。あるとき本の中の言葉や詩の一節がページから立ち上がり、大きな翼を広げる。読者も作者も、その言葉を忘れることはない。私の場合そのきっかけは、10代で命を落としかけるほどの重病を患い、病床で読んだD・H・ロレンスの詩だった。はじけた石榴〔ざくろ〕の実について心のままに詠んだ一節に出会ったのだ。
ぼくとしては、心臓が破れたほうがましだよ
割れ目のなかはとっても愛らしく暁の万華鏡のようなんだから。〔松田幸雄訳〕
後にロレンスが長く結核を患っていたことを知った。彼は危うい身体を持つ抒情詩人だった。ただ、初めて彼の石榴に出会ったときにわかったのは、その言葉が割れたガラスのように鋭く、謎めいて、そして気分を高揚させるということだった。こんな言葉は見たことがなかった。心臓が破れたほうがましだという発想だけでも、身体が利かず、生きることに懸命な10代の少年の興味を引くのに十分だったが、この詩の生きた言葉はそこから舞い上がり、これまで馴染んだものから遠く離れて飛び去った。割れ目に見えてきたとても愛らしい暁の万華鏡。傷は、希望へと通じるひび割れた扉かもしれないと思った。
これほど研ぎ澄まされた親密さを与えてくれた大人はそれまでいなかった。教師も、教会の聖職者も、そして両親もである。両親は私の目の障害を、感情的にも実際上も、触れてはならないこととして扱っていた。
見えてきた愛らしい暁の万華鏡、果物の心臓を持つ男の裂けた皮膚、その夜を暗示的に生き延びた人間。以前は、言葉は静止し、受動的で、見過ごされがちなものだったが、もはやそうではなかった。
障害者が、私たちがよく「エンパワー」された生活と呼ぶものを送ろうとしても、数々の障壁が立ちはだかる──すぐにヘレン・ケラーが思い浮かぶ。彼女はラドクリフ大学に入学を志望したとき、自分に読み書きの能力があることを証明してみせなければならなかった。さらには、そこに書かれた言葉や内面生活が彼女自身のものではない、と証明するために作られた検査も甘んじて受けた。目が見えず耳も聞こえず、何かを伝えるために筆記者を使う女性がどうして自発的な真の言語能力を持てるというのか、と疑われたのである。ケラーの場合は、彼女の天性の言語能力が「教師」アニー・サリヴァンのスキルをはるかに上回っていたために、すぐにとはいかなかったが、早い段階でことは決着した。
私の場合、うんざりさせられることもないわけではなかったが、ケラーほど厄介な目に遭わずに、話すことのできる盲目の作家として認められてきた。アメリカのある有名大学で教職を得るための面接を受けたとき、創作学科のひとりの教授が、もしあなたは目が見えないのなら、どうして世界をそれほど明瞭に描けるのかと尋ねてきた。法に触れるぎりぎりの質問だったが(この教授は私が盲目を装っているとでも思ったのだろうか)、その質問自体が、現代の一部の作家が言語の最も根本的なレベルの働きについていかに理解していないかを露わにしていた。彼は、すべての名詞はイメージであるとは思いもしなかったのである。
この教授は著名な作家で、私がそれに答えて言った内容をとうに理解していてしかるべきだったと思う。「私が苺と言う。あなたは苺を見る。私が戦艦と言う。あなたは戦艦を見る。私がそれに相当するものを見ているかどうかということは、あなたの受け取り方には何も関係しないのです──だからこそ、詩人は古来、魔術的と信じられてきたわけです」。もちろん、目の見えない人も見える人とまったく同じように心的イメージを生み出す。このことは、現代の神経科学が立証している。網膜の働きは必要ないのである。
しかし、文学の言葉は目に見えるものと同じくらい目に見えないものについて語る。それゆえ、盲目のジョン・ミルトンは悪魔の世界を描くのに最適の詩人だった。だが、より興味深いのは、読書を通じて目に見えないもの、名前のないものを感じ取ることから生じる明らかな、そしてしばしば神秘的な喜びであろう。喜びは、いつでも必ず慣れ親しんだものに関係するとは限らない。パブロ・ネルーダは若いころ、チリの外務省で働き、世界各地で何年も孤独のうちに過ごした。そのネルーダはこう語っている。
頑固な土地柄に慣れて育った
誰にも尋ねられたことはなかった
レタスが好きか、
それともミントのほうが好きか、
ゾウが貪り食うように、と。
答えを返すこともない、そこで
私は黄色い心を持つ。
文学的な意識からすると、孤独からは常に教えられることがある。ネルーダの想像力を通して見ると、孤独は比喩的に利用できるものであり、かつ忘れ難いものである。オリヴァー・サックスやスティーヴ・シルバーマンなどが書いたものに慣れ親しんだ読者の間では、自閉症(オーティズム)を持つ人は心の中で、ゾウのミントやそれが黄色い心に及ぼす影響について、瞬きひとつせずに──またはひどく瞬きながら──理解するとの認識が育ちつつある。自閉症者も目の不自由な人のように、あまり質問をされることがなかったし、最近までは答える者もほとんどいなかった。しかし、ボブ・ディランも歌ったように、「時代は変わる」。
本書『嗅ぐ文学、動く言葉、感じる読書』の中で、詩人で作家のラルフ・ジェームズ・サヴァリーズは自閉症スペクトラムの人々と関わり合う。彼らを研究するためでも、ヘレン・ケラーが受けたような検査をするためでもなく、孤独をよく知る彼らとともに古典的な文学作品を探究するためである。彼らは石榴の割れ目について、暁の万華鏡について、愛すべき心のひそやかな傷について多くを知っている。この卓越した本を読む者は、真に読むということの驚異を感じずにはいられない。教育学者パウロ・フレイレの金言を思い出す。「主体的に興味を抱き、読み、発見のプロセスをたどるという批判的な立場に立たない者に本物の研究はできない」。エミリー・ディキンソンはそのことを、こう表現する。
大切な言葉を飲んだり食べたりしながら
彼の心はたくましく育っていった
そのうちに自分が貧しい事もすっかり忘れ
自分の身体が塵だったことも忘れて
彼は暗い毎日を踊り明かした
この形見の翼も、もとは一冊の本に過ぎなかった
束縛を解かれた心は
何と人を自由にしてくれることか!〔谷岡清男訳〕
本書は読書についての本だが、私がこれまで出会ったどんな本とも違う。自閉症者は心の理論を持たない、言語障害を患っている、想像による遊びができない、といった有害な先入観やステレオタイプを脇に置き、テキサス州オースティンに住む言葉を話さない男性が『白鯨』の中を泳ぎつつ自分の感覚の物語を語るのに耳を傾けるといい。あるいはオレゴン州ポートランドに住むサイバーパンクの作家にしてコンピューター・プログラマーでもある女性が『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』を読み、六人のアンドロイドを「廃棄」する賞金稼ぎ、リック・デッカードの共感面での弱点を追究するようすを見てみよう。自閉症者はここに出てくるアンドロイドと同じように共感力を欠くと言われているのだが。
神経学的に多様な心は、読書に何をもたらすのだろうか。得られることは多い。よく言われる「絵で考える」才能は、文学が映し出す「感情の映画」においては有利でさえあるかもしれない。
W・H・オーデンはこんなことを書いている。「私たちはたいてい、読者としてはある程度、広告の少女の顔に鉛筆で口ひげを書き加えるハリネズミ〔いたずらっ子〕のようなものだ」。だが、もし私たちが鉛筆だったら、ハリネズミだったら、その少女だったら、広告だったら、口ひげだったらどうだろう。そしてその不確実性をつなぎとめる錨を持たないとしたら。つまり、ニューロティピカル(神経学的な定型発達者)の読者などそもそもいないとしたらどうなのか。そのときは、優れたニューロ・エイティピカル(非定型発達者)の読者が助言者となり、その者の力で私たちは多くの恩恵を得られるのではないだろうか。これは、その本質において私たちが「あえて踏み込む」ことのできる認識の中でもとりわけ想像力を働かせた仮定的な認識ではあるが──作家も、読者もみな、これまで無反省に考えられてきたよりもずっと複雑で意外な存在なのではないだろうか。
(著作権者のご同意を得てウェブ転載しています。なお
転載にあたりわずかな変更を加えた箇所があります)