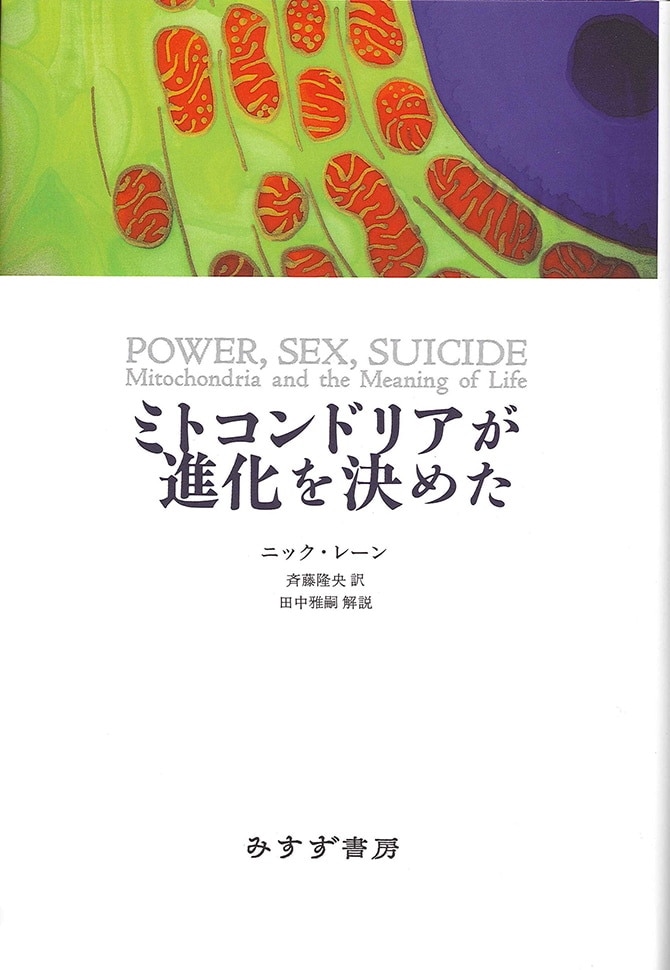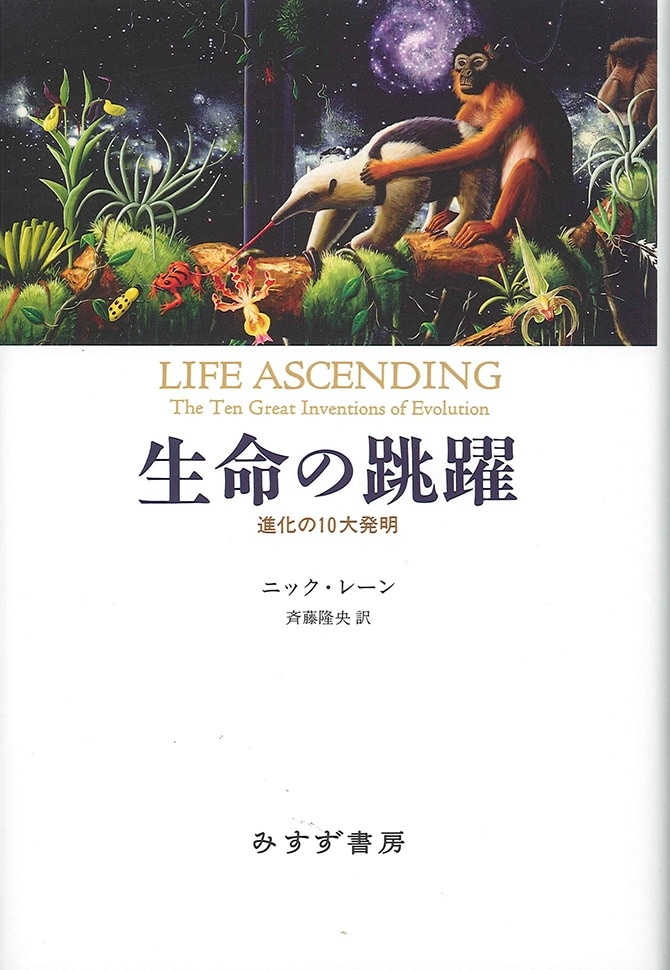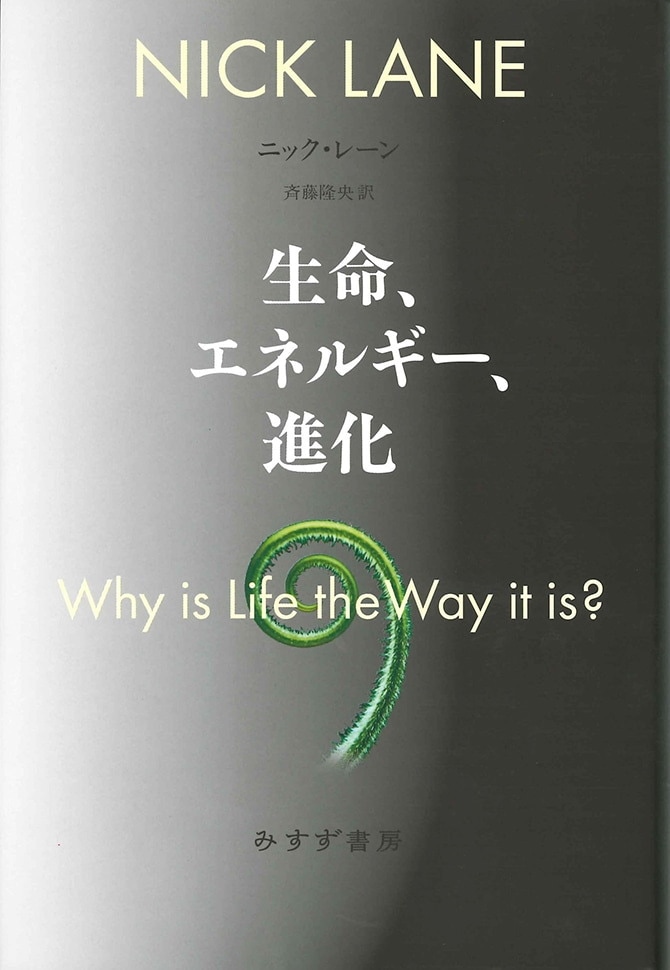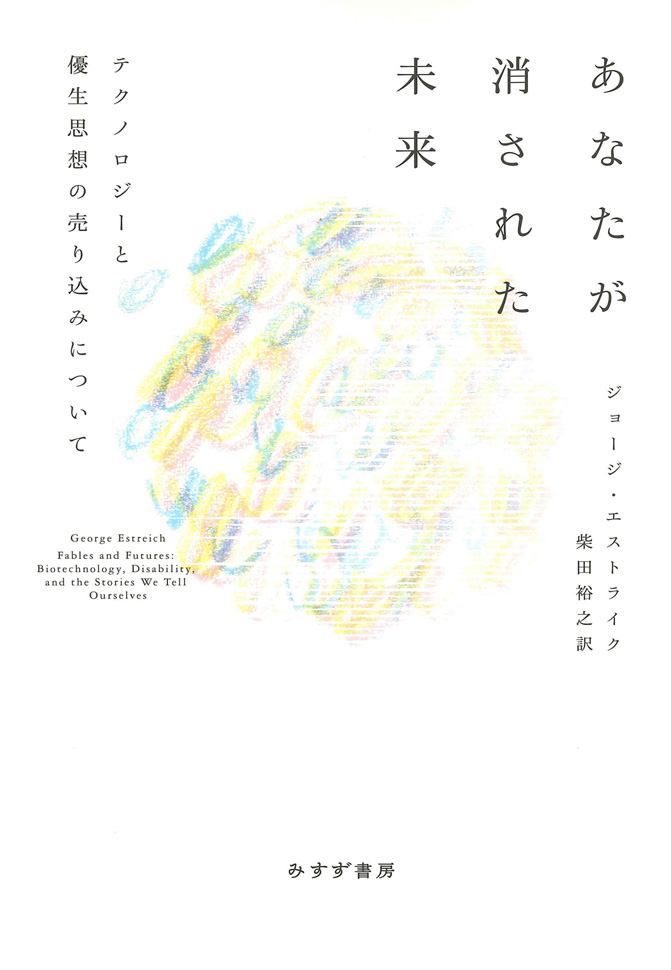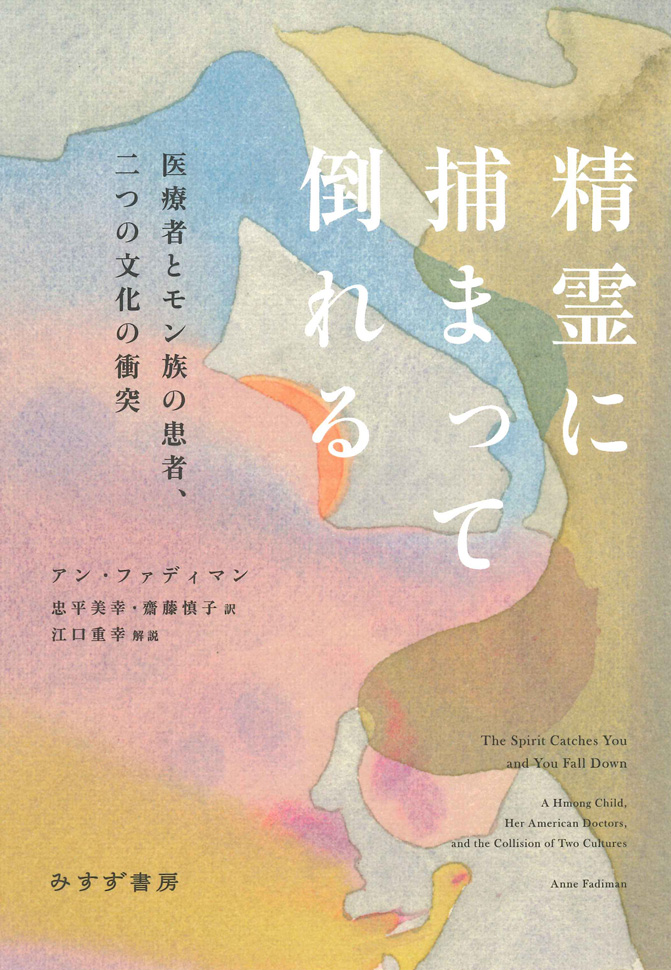(本文第1章「はじめに──がん、それは形を得た進化そのもの」からの抜粋です)
これはがんについての本である。がんがはるかな昔にどのように生まれ、現代においてどういったかたちで現れているか、そして未来はどんな運命をたどるかを綴ったものだ。がんがどこから来てなぜ今存在しているのか、どうしてこれほど治療が難しいのかが本書のテーマとなる。
それと同時に、本書では新しい切り口からがんを眺めていこうと思う。是が非でも取り除かねばならない対象としてではなく、コントロールして共に生きていけるように変えるべき存在として、である。
およそ20億年前に多細胞生物が誕生して以来、生命はがんとの苦闘を重ねてきた。私たちが地球上の生命について考えるとき、たいていは動物や植物のような多細胞生物、つまり多数の細胞で構成された生物が頭に浮かぶ。多細胞生物の体内にある細胞は、いってみれば分業体制で生活している。細胞同士が協力し、連携しながら、生きるうえで必要な体のあらゆる機能を分担している。一方の単細胞生物(細菌、酵母、原生生物など)には細胞がひとつしかないため、その1個の細胞で生命の維持にかかわるすべての仕事をこなしている。多細胞生物が進化の足がかりを築くまで、地球は単細胞生物のすみかだった。単細胞生物が支配したその20億年ほどのあいだ、世界にがんはなかった。ところが多細胞生物の登場が、地球という舞台に新しい「演者」を招き入れた。それが、がんである。
がんは私たちの一部であり、その事実は私たちが多細胞生物になったときから今に至るまで変わらない。がんの痕跡は太古の人類(エジプトのミイラから中南米の狩猟採集民まで)の骨格からも見つかっていて、170万年前に南アフリカの「人類のゆりかご」で暮らしたヒトの初期の祖先の骨からも確認されている。もっと古い時代の化石からもだ。数千万年前、あるいは数億年前の哺乳類や魚類、それから鳥類の骨にその痕跡は残っているし、恐竜が生物の頂点に君臨していた時代にもがんはあった。それをいうなら、生命がまだ肉眼では見えなかった頃にまでがんの誕生はさかのぼる。今の私たちが生物と聞いて思い浮かべるようなものがほとんど存在しないうちから、がんはこの世に生を享けていた。
がんをうまく手なずけるためにはその根本に目を向け、進化と生態系という動的な力がどのようにがんを形づくってきたかを理解しなくてはいけない。それだけにとどまらず、がんに対する私たちの見方を改める必要もある。一時的に現れるがどうにかなる問題としてがんを捉えるのではなく、多細胞生物である以上は避けて通れない現象として受け止めるのである。多細胞生物が登場するまでがんが存在しなかったのはなぜか。それは、がん細胞が数を増やそうにも、最終的に別の細胞に入り込もうにも、そうできる場所がなかったからである。多細胞生物であることそのものが、つまり複数の細胞による協力体制の極致ともいうべき存在であることが、私たちを否応なくがんにかかりやすくしている。
本書ではこの先、人体をつくる細胞同士がいかに様々なかたちで協力し合い、私たちを多細胞生物として成り立たせているかを見ていく。協力とはたとえば、細胞の増殖を調節し、必要とする細胞に資源を分配し、複雑な臓器や組織をつくり上げる、といったことである。そして、この協力的な性質につけ込む進化を遂げるのが、がんというものであることに目を向けていく。がんは無秩序に増え、体内の資源を搾取する。さらには、自分が生き残るための特殊なニッチへと組織をつくり変えることまでやってのける。要するにがんは協力体制を裏切り、多細胞生物として生きるうえで最も基本的な「ゲーム」のルールに従わない。
がんの本質をもっと明確にできれば、その予防と治療の効果をさらに上げる役に立つはずだ。また、がんに手こずっているのが私たちだけではないことも見えてくるだろう。多細胞生物はすべてがんの影響を受けている。進化の過程でがんとどうつき合ってきたかが、今の私たちをつくり上げているといっていい。がんとは何かを本当の意味で知るには、がんがどのように進化してきたのか、そしてがんと一緒に私たちがどういう進化を遂げてきたかを理解する必要がある。
(中略)
進化の視点から捉えるようになるまで、がんは私にとってあまり面白味のない病気のひとつでしかなかった。かつての私は研究を通して、生命の進化に関する深遠で根本的な疑問に取り組んでいた。たとえば、集団で暮らす生物がこれほど多いのはどうしてか。あるいは、いわゆる《裏切り者》に搾取されるおそれがあるにもかかわらず、集団内の協力が不安定にならないのはなぜか、といった問いである。それまではいつも、理論レベルでの疑問に惹かれていた。だから、果てしなく続く事実の羅列を暗記しなければならないうえに、その事実をまとめ上げる枠組みが存在しないようなテーマは敬遠していた。がんはまさしくそういうテーマに思えていた。理論の基盤がないままに、あのメカニズムこのメカニズムに関する膨大な数の研究が行われているのみ。その根底には基本原理が見当たらない。もちろん、人間の健康にとって重大な意味をもっているので、研究する価値は間違いなくある。ただ、自分でやってみようという気にはならなかった。
転機が訪れたのは、アリゾナ大学に移って博士研究員として働くことになり、ジョン・ペッパーと一緒に研究を始めたときである。ペッパーは、当時としては新しい分野だった「がんの進化」におけるパイオニアのひとりである。そのとき気づいた。がんは自分がすでに研究してきたことを細胞レベルで体現しているのだ、と。つまり、進化の途上にある大規模な系において、《裏切り者》に脅かされながらいかに協力を維持するか。がんとはそういう問題にほかならなかった。
がんに対する私の見方は変わり始めた。がんは私たちの体という生態系の中で、急速に進化しつつある生命だったのだ。進化する系や生態系がかならず従う規則は、がんにも等しく当てはまる。進化という枠組みの中にがんを位置づけることが、その複雑さをつかむための出発点となった。
20世紀の偉大な進化生物学者であり、進化という視点から考える先駆者であったテオドシウス・ドブジャンスキーは、こんな言葉を残している。「進化を考慮に入れない限り、生物にかかわるいかなる現象も理解することはできない」。以前の私にとって、がんが腑に落ちない存在だったのはこのためである。ドブジャンスキーが現代に生きていたら、さしずめこんな言葉を吐くのではないか。「進化を考慮に入れない限り、がんにかかわるいかなる生物学的現象も理解することはできない」。がんは複雑な存在であり、絶えず変化しながら私たちに大きな影響を及ぼしている。進化、生態系、そして協力理論を出発点にすれば、それがなぜなのかが見えてくる。ひいては、人間自身の本質に対する理解を深めることにもつながるに違いない。そして、がんが人間だけでなくあらゆる多細胞生物の特徴を方向づけてきたことも、そして今なお方向づけ続けていることも明らかになる。