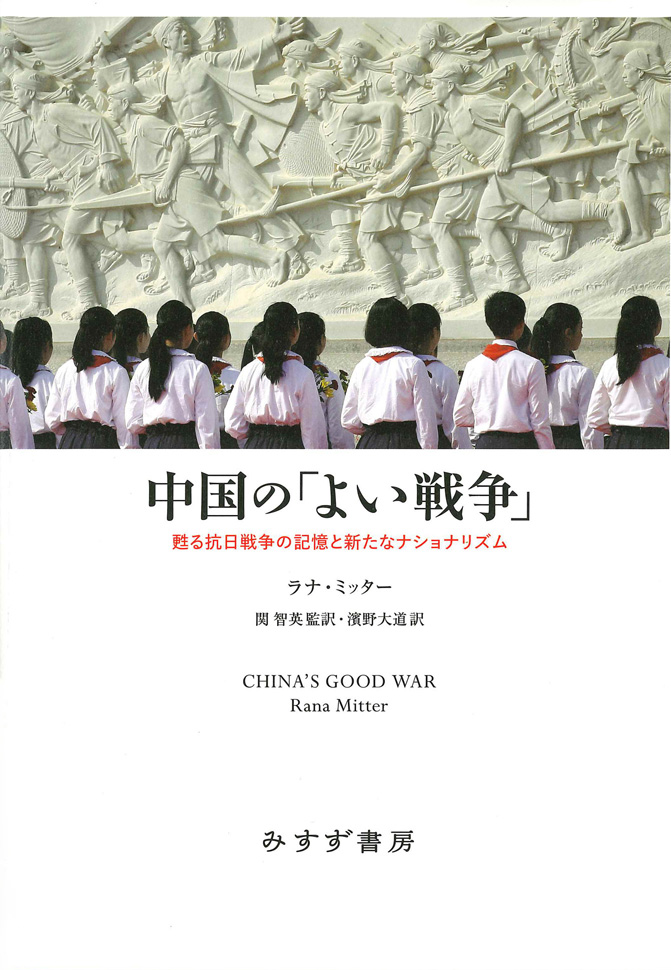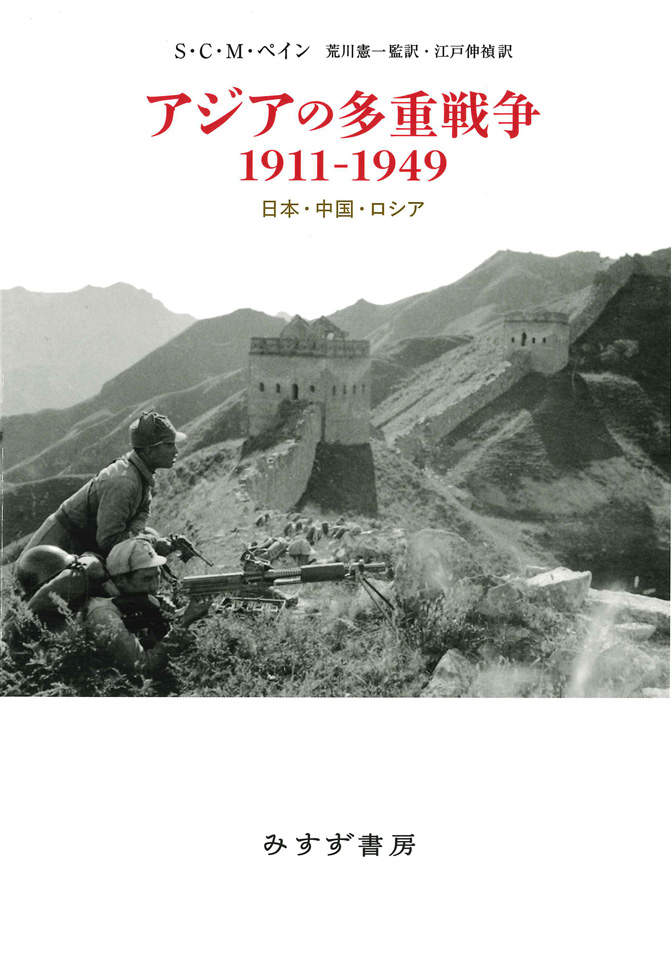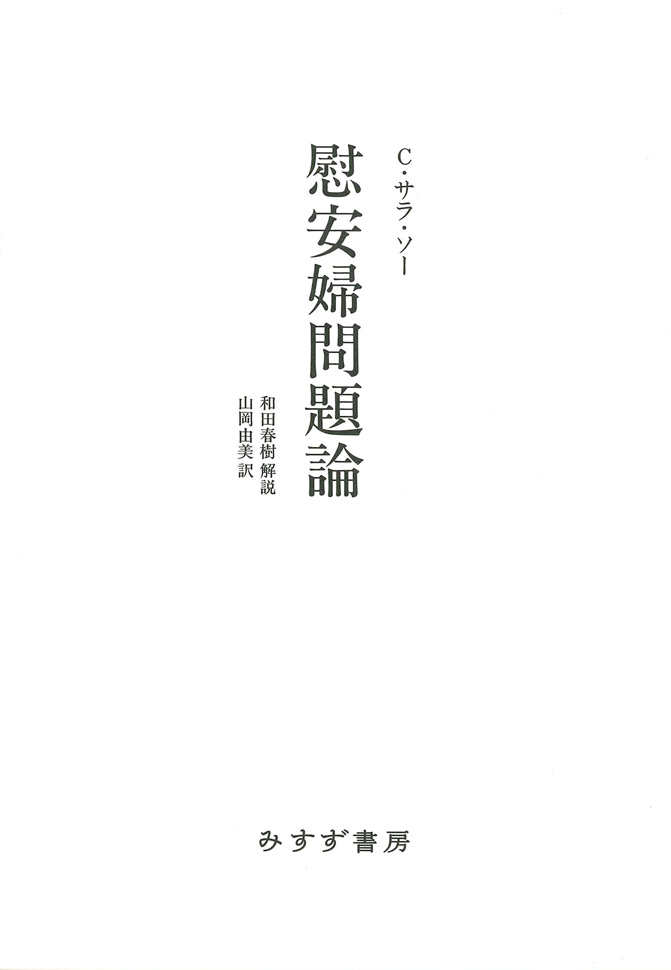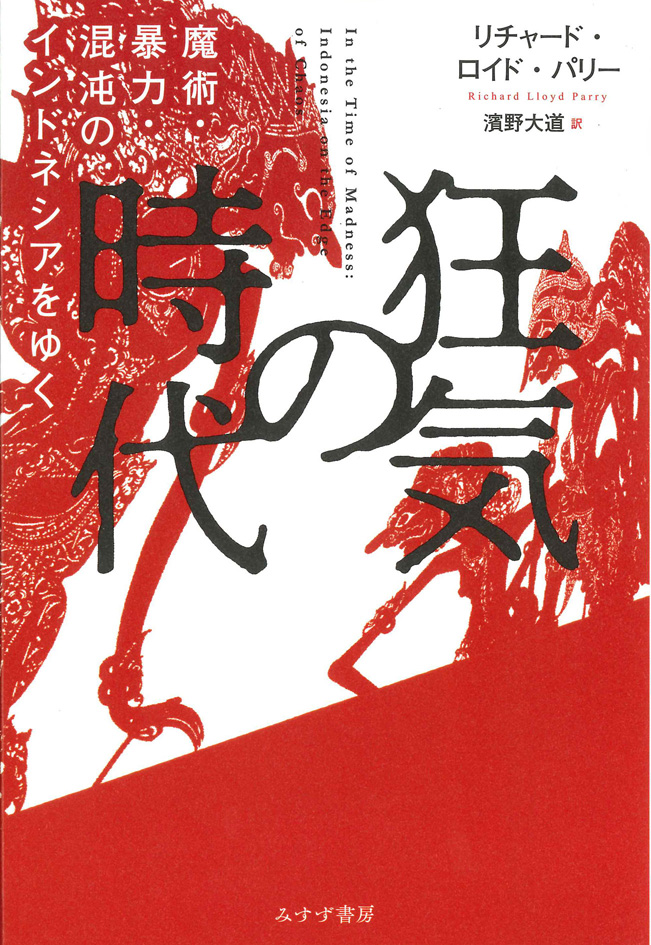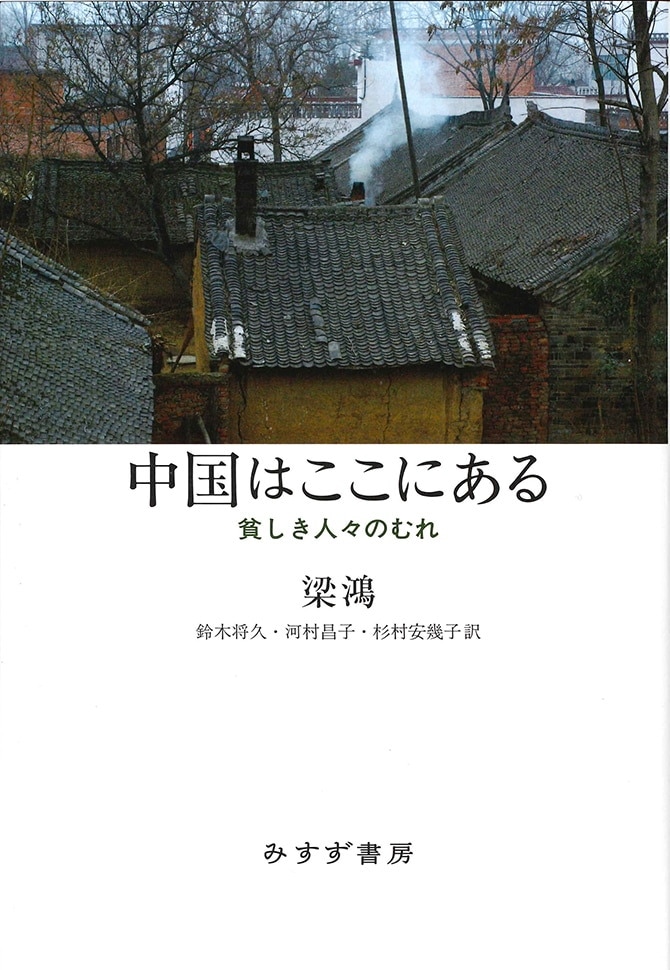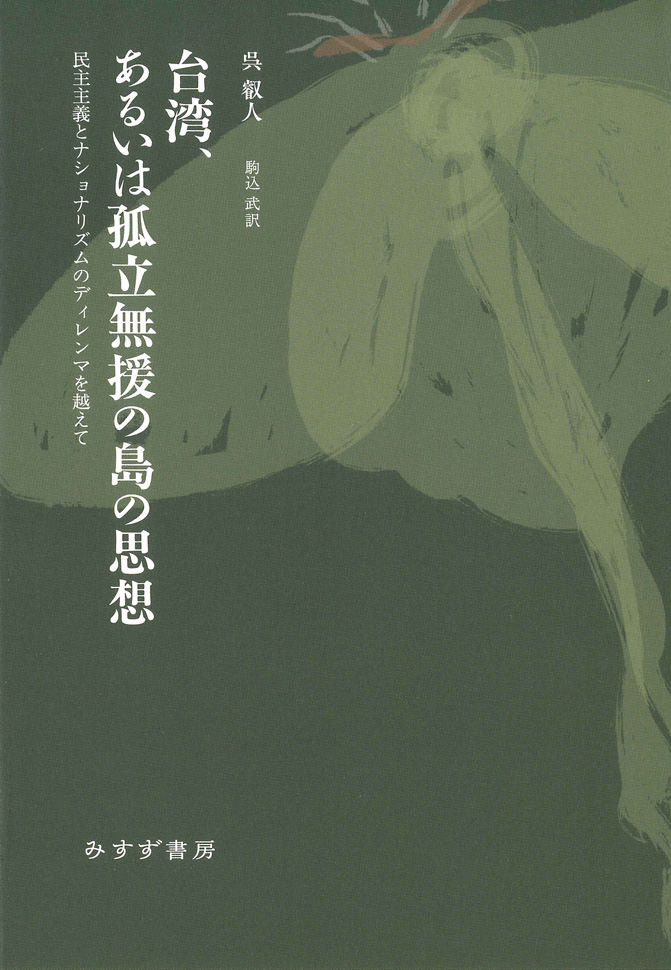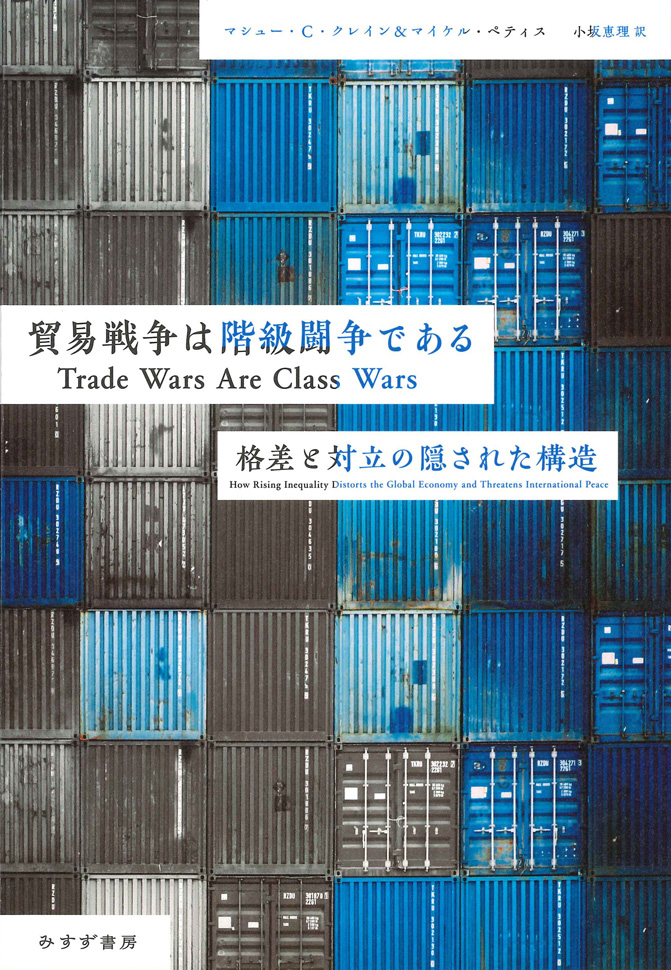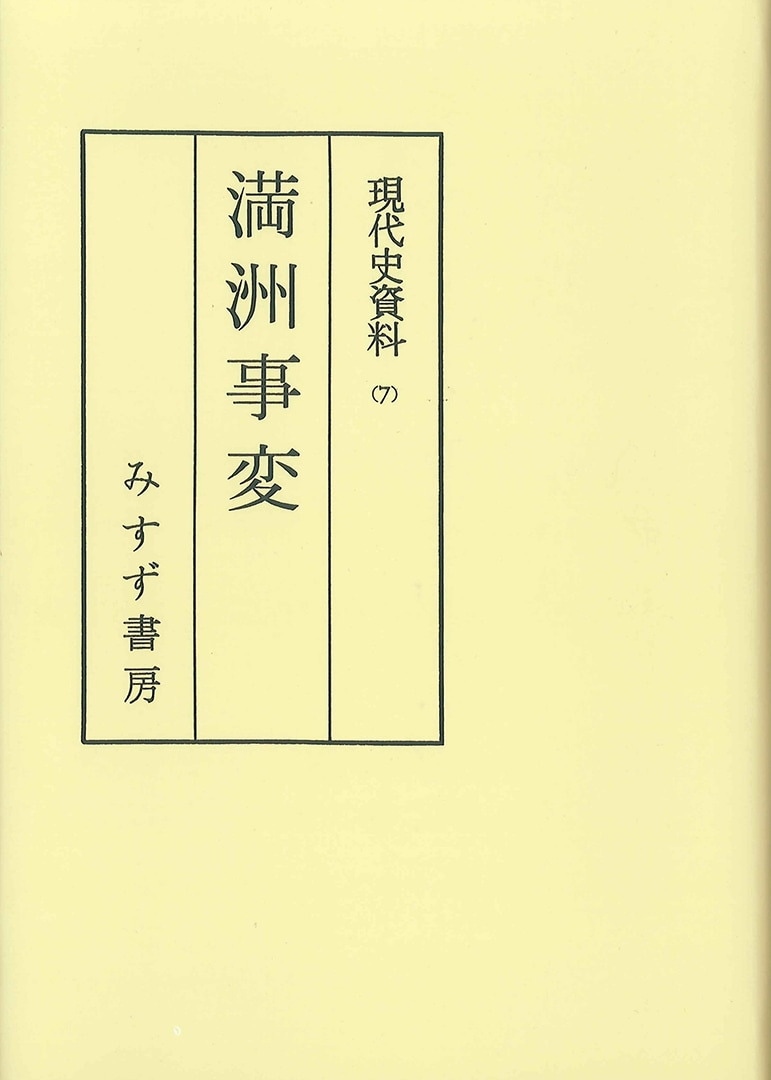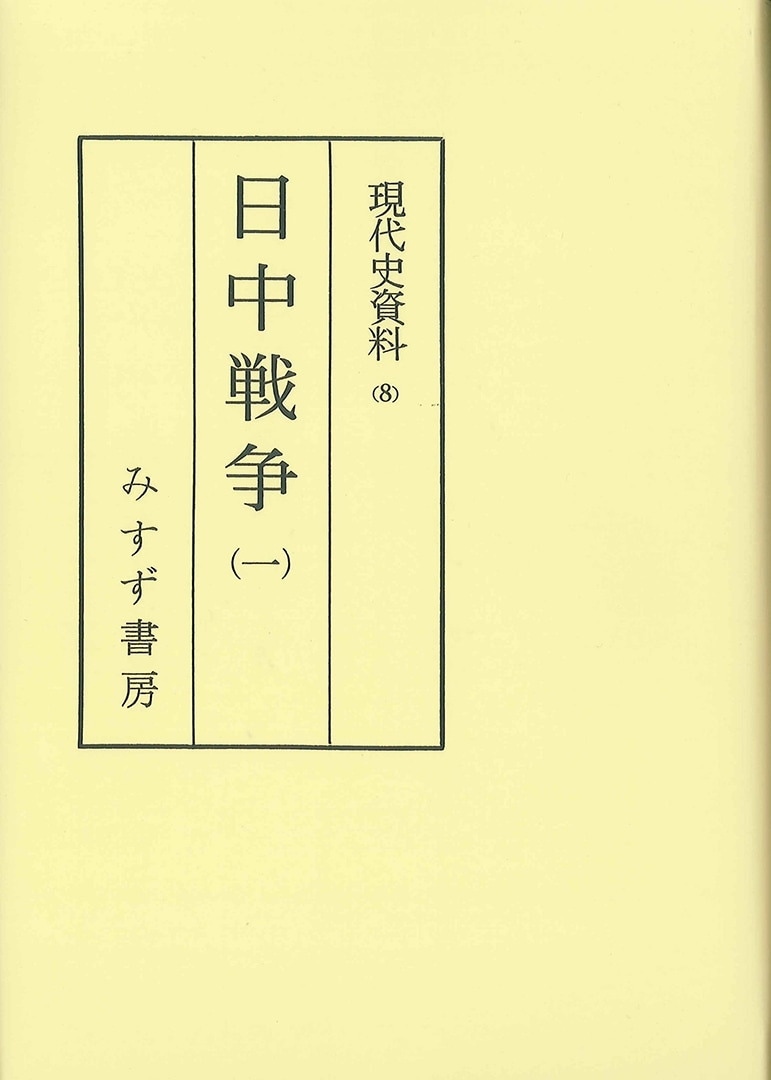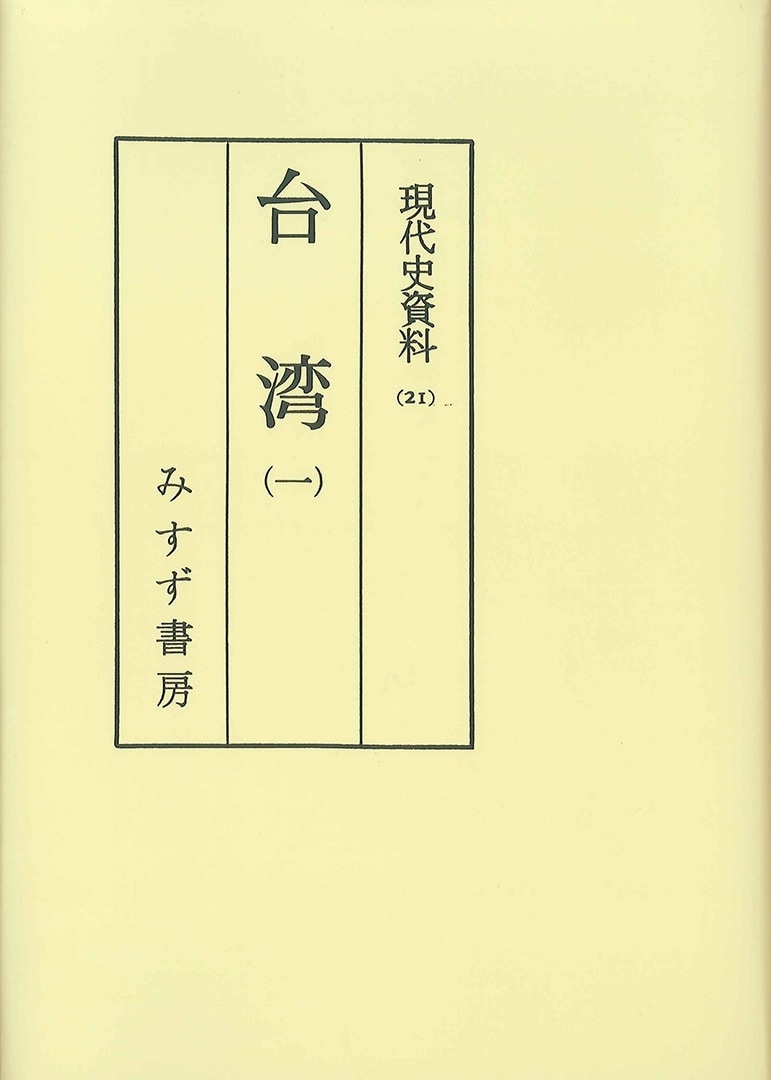いまから7年前の2015年のこと。この年の年頭に、当時の明仁天皇(現・上皇)が述べた「ご感想」の次の一節が、しずかな反響を呼びました。
本年は終戦から70年という節目の年に当たります。多くの人々が亡くなった戦争でした。各戦場で亡くなった人々、広島、長崎の原爆、東京を始めとする各都市の爆撃などにより亡くなった人々の数は誠に多いものでした。この機会に、満州事変に始まるこの戦争の歴史を十分に学び、今後の日本のあり方を考えていくことが、今、極めて大切なことだと思っています
(太字強調は引用者。宮内庁公式サイトの「天皇陛下のご感想(新年に当たり) 平成27年」より)
https://www.kunaicho.go.jp/okotoba/01/gokanso/shinnen-h27.html
奇しくもそれから半年後の同年7月に、中国の習近平総書記が、抗日戦争(日中戦争)の歴史研究について語った内容が、『中国の「よい戦争」』のなかに紹介されています。
局地抗戦と全国的な抗戦、正面戦場と後方戦場、中国人民抗日戦争と世界反ファシズム戦争といった重大な関係を総体的に把握しなければならない。七七事変〔盧溝橋事件〕以降の全面的な抗戦八年間の歴史だけでなく、九一八事変〔満洲事変〕以降一四年間の抗戦の歴史にも注目し、一四年間を一貫して研究すべきなのである
(太字強調は引用者。『中国の「よい戦争」』[以下「本書」]p. 100)
日本の天皇と中国の最高指導者が、それぞれ聴衆や意図するところは違えども、同時期に似た趣旨の発言をしている事実は興味を惹きます(いわゆる「15年戦争論」につながる見方です)。習氏のこの発言から1年半後の2017年より、中国では抗日戦争の開始時期が変更され、それまでの「8年抗戦」に代わって「14年抗戦」が正式な政府見解となりました。すなわち、1937年7月7日に起きた盧溝橋事件ではなく、1931年9月18日に日本軍が起こした柳条湖事件とそれに伴う中国東北部への侵略=満洲事変こそが抗日戦争(日中戦争)の起点であるとされ、中国の小中高校の歴史教科書の記述もそのように改められました。日本の歴史教科書の日中戦争に関する記述をめぐって、日中間で論争が起きたのは1982年、いまからちょうど40年前のことです。
そもそも、本書の原書China’s Good War (Harvard University Press, 2020) に興味を持ち、翻訳を企画したのは、対米戦争(太平洋戦争)の歴史に比べると、日中戦争の経緯についてはあまりよく知らないという自身の感触からでした。本書では、その日中戦争=抗日戦争の経緯を振り返るだけにとどまらず、この戦争が現代中国でナショナリズムの起爆剤として甦り、「よい戦争」として再評価されている流れを、政界・学界からソーシャルメディア上の議論までを通じて浮き彫りにしていきます。英オックスフォード大学で現代中国を研究するインド系の学究としての独自の立ち位置から中国を、そして日中関係をフラットに論じる議論は日本ではなかなかお目にかかれない斬新さです。欧米メディアに中国問題のご意見番としてよく登場しているのもうなずけます。英国の著者らしいアイロニーとウィットが随所に見られる点もチャーム・ポイントでしょうか。日中戦争の研究者である監訳者・関智英氏による充実した巻末解説も、よき補助線となってくれます。
そのミッター氏が、抗日戦争を描いた近年の中国映画(『南京! 南京!』『エイト・ハンドレッド―戦場の英雄たち―』)と比較して、同じ時期を舞台とする日本のヒット映画(『永遠の0』『この世界の片隅に』)の特徴を、こんな風に分析していたのが目に留まりました。
注目すべきことに、戦時中の中国との関係を描く日本映画はほとんど存在せず、圧倒的多数の作品は太平洋戦争に焦点を当てている。いわば太平洋戦争こそが、“本物の戦争”とみなされているといっていい。技術的にも文明的にも“先進的”であり、戦後には友人となった好敵手を相手にした闘い、それが日本にとっての太平洋戦争だった。盧溝橋事件から真珠湾攻撃までの期間は、その戦争ナラティブの前奏曲としてしかとらえられておらず、映画の興行的な成功は見込めないテーマとなる。日本には、日中戦争についての映画のための市場は存在しない
(本書p. 170)
虚を突かれる指摘でした。私たち日本人は、太平洋戦争(真珠湾、ミッドウェイ、ガダルカナル、サイパン、レイテ、硫黄島、沖縄、戦艦武蔵や大和、神風、各地の空襲、広島・長崎、玉音放送……)に比べて、日中戦争(盧溝橋、南京、重慶爆撃、731部隊、蒋介石、毛沢東……それに?)を、たしかに閑却視しているのかもしれません。満洲事変は推して知るべしでしょうか。日中のあいだに横たわる認識のギャップを、はからずも突きつけられた気がしました。このミッター氏の指摘は、さきの明仁天皇の言とも、どこかで響きあっているようにも感じます。中国にとって「よい戦争」なら、日本にとっては……? 読者のみなさんはどうお考えになるでしょう。このほかにも著者ならではの鋭い卓見が満載で、他書にはない読書体験を味わえます。たとえば次の一節なども。
2010年代なかばごろから中国と日本は、自分たちの第二次世界大戦の経験について相反する解釈を利用するようになった。日本の右派は、1930年代から1940年代に政府がアジアで主導した帝国の戦争にまつわる修正主義的な見解をかつてないほど声高に主張するようになった。そのような日本の修正主義的な見解は、国内のひとつの集団の内側にのみ浸透するものだった。しかしその集団には、政権与党である自由民主党の有力な政治家たちが含まれている。それはほぼ国内だけに向けられた動きであり、日本国内のリベラル派も強い反対の姿勢を保っている。日本国外において、1945年以前の日本のアジア侵略を肯定的に再評価する動きを支持する主要な集団は存在しない
(本書p. 241)
尖閣諸島(釣魚群島)をめぐる領土問題については、数十年にわたって小康状態が続いていた。しかし2010年代はじめ、東シナ海に浮かぶこれらの八つの岩がちの小さな無人島をめぐって緊張が高まりはじめた。島の沖に鉱物資源が埋蔵されている可能性にまつわる問題もあるものの、主として争いは主権にまつわる象徴的なものだ。これらの群島の領有権に関する中国側の解釈をひもとくと、第二次世界大戦の遺産を中国が流動的に利用してきたことがわかる。カイロ宣言の前半部分には、尖閣諸島についての言及はない。また、日本は日清戦争中の1895年に尖閣諸島を領土に編入したため、条項の「千九百十四年の第一次世界戦争の開始以後」という条件にも当てはまらない。ところが2013年になると、カイロ会談から70周年を契機として中国のマスコミは、カイロ宣言に書かれた文言こそが、尖閣諸島(釣魚群島)をめぐる中国の主張に国際法上のお墨つきを与えるものだったと大々的に報道した。(中略)
明白ながら、中国の公的情報源は驚くべき歴史の手品を行なおうとしていた。それが意味するのは、1943年のカイロ宣言と1945年のポツダム宣言から、現在の中国の政権へとまっすぐつながる道があるということだった。つまり中国共産党は、国民党の蔣介石が切った小切手を現金化しようとしたというわけだ
(本書p. 246-48)
今年は、前年の満洲事変を受けた1932年の「満洲国建国」から90年、1972年の日中国交正常化から50年の節目に当たります。さらに秋には中国共産党大会が予定され、10年前に就任した習近平総書記の続投もささやかれています。また、2月から続いているロシアによるウクライナ侵攻に関連して、満洲事変や日中戦争との類似性を指摘する日本の識者もいます。この機に、抗日戦争/日中戦争の歴史を改めて振り返り、日中関係の将来や現在の国際情勢を見る眼を鍛える一助としても、ぜひ本書をお手に取っていただけたら幸いです。