
2013.10.10
ジェームズ・C・スコット『ゾミア』
脱国家の世界史 佐藤仁監訳 池田一人・今村真央・久保忠行・田崎郁子・内藤大輔・中井仙丈訳
髙田茂樹訳
2013.10.10
シェイクスピアほど書き手によって異なる顔を見せる作家もいないだろう。提出したテーマによりそって相応の答えをいつも用意してくれているようだ。
『時の娘』という有名な推理小説がある。病院でぐうぜんリチャード三世の肖像画を目にした主人公が、彼は世間の人々が思い込んでいるような極悪人ではないと直感する。肖像画の顔が発するイメージが推理の出発点である。
「特性がないということが、エリザベス朝の文化にあっては、人間の美の理想的なかたちである」――つまり、この時代にあっては、個性的な特徴は必要ないし、かえって、ないほうが美しいのである。 ところが、シェイクスピアはちがっていた。
「目が蔑むものを私の心が愛するのだ」
『ソネット集』のダーク・レディーやクレオパトラはいかにもレオナルドの描いた『白貂を抱く貴婦人』とは様相を異にしている。劇作家の天才は当時の理想美の基準を逸脱して、ほくろや傷痕、醜いものやグロテスクなもののなかにも〈美〉を見出していったのである。これもまた、時代のイデオロギーに対する〈作家の自由〉の挑戦であろうか。
本書は、シェイクスピアの個別の作品ではなく作品群の全体を見渡して、多様な問題を提起・分析したブリリアントな一冊である。時代の不自由さのなかで、自由を探究した天才の世界へと招待するグリーンブラットによる久々の本格的な論考。

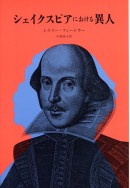


2013.10.10
脱国家の世界史 佐藤仁監訳 池田一人・今村真央・久保忠行・田崎郁子・内藤大輔・中井仙丈訳

2013.09.26
ユダヤ論集[全2巻] コーン/フェルドマン編 山田正行・大島かおり・矢野久美子・齋藤純一・佐藤紀子・金慧訳