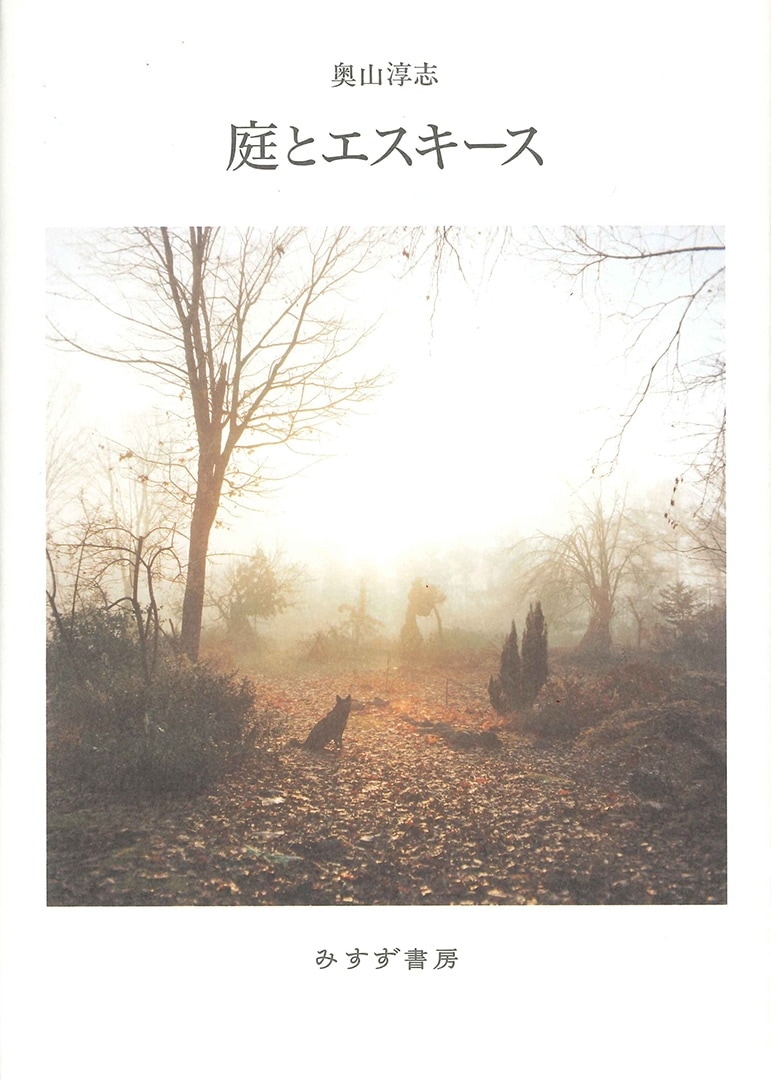奥山淳志
卵を温めていたことがある。小学生の三年生の頃だ。きっかけは当時読んでいた学研の『かがく』で、ブロイラーの孵卵場をルポした記事だった。「孵卵器」という聞き慣れない器具を使い、たくさんの卵を次々と孵化させるという孵卵場の作業工程は、動物の飼育に夢中だった当時の僕を一瞬にして惹き付けた。器械を使うとはいえ、人が鳥の代わりになって、あの丸くて可愛らしい卵からまだ瞳も開いていない雛鳥を誕生させるのだ。それは奇跡としか思えない行為だった。
しかし、釘付けとでも言ってもよいほどに興味を惹かれたのは、特集の最終ページに掲載されていた小さなコラム記事だった。そこには一見すると骨折でもして三角巾で腕を吊っているかのような少年のイラストとともに、「君にもできるかも?」といった見出しが付けられていた。怪我をしているようにも見えるのになぜか笑顔をたたえる少年の表情を不思議に思った僕は自然と記事に目を落とし、衝撃を受けた。コラム記事の内容は、人間の体温と鶏の体温は近いという根拠から、人肌で孵卵させる方法が簡単に記されていたからだった。イラストの中の骨折少年が笑う理由は骨折などではなく、手拭いを三角巾風に仕立て、自らの脇の下で卵を温めているからだったのだ。
僕はもういてもたってもいられなくなった。自分が卵を温めて雛鳥を孵化させる。もしそんなことができたら、「擦り込み」なんてよそよそしい言葉を使うまでもなく、僕が文字通りに雛鳥の親になる。雛鳥は僕のことを心から信頼してくれるに違いない。それはこれまで経験してきたペットショップで売られている雛鳥を買ってきて「手乗り」として育てていくといったものとは全く別次元の人と動物の関わりだと思えた。僕は小さなクチバシでコツコツと卵の殻を割って生まれてくる雛鳥を想像した。きっと、生まれたばかりの雛鳥はすぐに僕に懐き、すくすくと育っていくに違いない。きっと、僕の言葉だって理解するはずだ。「今日は何をして遊ぼうか」と愉快な会話だってできるだろう。そして、大きくなればどこか遠くへだって連れ立って出かけたりできるはずだ。僕にとってそれは夢と呼んでもよい世界だった。
そうなると問題は、どうやって鶏の有精卵を手に入れるかだった。さすがにペットショップで売られているものではないので、鶏を飼っている誰かから卵を分けてもらう必要があった。そこで僕は同級生たちに声を掛け、鶏を飼っている家がないかを聞いて回った。当時、僕が暮らしていたのはサラリーマン世帯ばかりの奈良の新興住宅地だったので、家禽として鶏を飼う家は皆無だった。しかし、その住宅地を一歩でると兼業農家からなる在郷集落が点在しており、庭先に禽舎を拵えて鶏を飼う家もときおり見かけた。そういう家にお願いすればきっと卵を分けてくれるに違いない。そう考えた僕はできるだけ地元出身の同級生に声を掛けたのだった。そして、この狙いは的中した。同級生の一人の家では一羽の雄鶏と五羽の雌鳥を飼育しており、卵は毎日のように産むのでそのひとつを持ってきてあげると最高の申し出を受けたのだった。
鶏の場合、孵化までの日数は約二十日だと、『かがく』に記されていた。同級生の家に出かけ、卵の入った小箱を無事に受け取った僕は「その日」に向けてさっそく温めることにした。真似たのはもちろんコラム記事に登場するイラストの少年だ。脱衣所からこっそり持ち出したバスタオルを縦に切って細めると、タスキ掛けの要領で首と腕に通してから脇の下のあたりで卵を保持できるように慎重に長さを調整した。そして、いよいよとばかりに小箱の中にある卵を静かに持ち上げると、脇下の奥に押し込んでからゆっくりと挟んでみた。脇が締まりきらないので最初は違和感があったがやがてこそばゆいような喜びが湧き上がった。最初、卵の感触はひんやりとしていたが僕の体温に馴染むにしたがってどこか柔らかな気配を帯び、まさに呼吸を始めたかのように思えたからだった。こうして卵を温めつつ、一日に2、3回ほど卵を回転させること、乾きすぎないようにときどき霧吹きで湿らせてやること。また、卵の中で雛鳥が成長しているかどうか懐中電灯で数日に一度は確認すること。これらを怠らずにやっていけば、二十日後には可愛い雛鳥の顔を見ることができるということだった。卵から顔を出した雛はきっと、か細くとも力強い声で鳴いてみせるに違いない。その瞬間まであっという間だ。卵を脇の下に抱いた僕は、巣の中で卵を抱く親鳥のように時を忘れてただただじっとしていたい気分になるのだった。
結果を先に言うと、卵が孵ることはなかった。冷やしちゃいけないと学校に行く時も脇の下に卵を潜ませていくこともあったし、家に置いていく場合であってもふわふわの綿に包み、使い捨てカイロで温めることを忘れなかった。夜も同じようにしてカイロで温め、寝相の悪さから壊れやすい卵を回避させた。それでも、卵をいくら懐中電灯で照らしてみてもその中に雛鳥らしき影を見つけることはできず、少しずつ悪臭を放つようになってしまった。
たった一度の失敗では諦めることができない僕は、同級生に頼み、もう一度卵をもらった。そして、同じようにそっと脇の下に挟むと今度こそは卵の中にいるはずの雛鳥と出会うのだと堅く誓った。しかし、結果は同じだった。脇の下の卵は日を追うごとに艶を失い、重さも軽くなっていって、最終的にはやはり嫌な臭いを放ち始めたのだった。そうなると僕は自分の目に映るものをもはや卵とは呼ぶことができなかった。同級生の手から手渡されたとき、卵には確かにはっきりとした存在感があった。何か声を発するでもない。動くこともない。目の前の世界の中の小さな点のような存在だった。でも、その小さな一点には沈み込むほどの重さを備えた存在感があった。それが今ここにあるのは、面白くも何ともないただの丸い物体でしかない。僕は自分が卵の中の雛鳥を殺してしまったという残酷さに気づくこともなく、すぐに興味を失った。その証拠に、この嫌な臭いを放つ卵をその後どうしたのかすら思い出すことができない。飼っている動物が死んでしまうと庭の百日紅の下に埋めるのが常だった。しかし、僕は滑らかな肌を持つこの木の下にあの卵を埋めたという記憶はない。
こうして脇の下で鶏の卵を孵化させるという僕の計画は挫折という結果で終わってしまった。今でもあの頃の自分の胸のうちを思い返すと、一体僕は何をしたかったのだろうかと奇妙な気持ちになる。当時の僕は犬、手乗りインコ、ハムスター、種々の野鳥などを同時期に飼っていて、動物を飼うという欲求は満たされていた。いずれの動物たちもよく懐いてくれて愛らしく、僕の日々は〝動物と暮らしている〟という実感の中にあった。それでも卵から孵すという行為には並々ならぬ好奇心を抱いた。
僕にとって「鳥を飼う」という経験は、四歳の頃に兄が飼い始めた十姉妹に始まる。小さな十姉妹たちは夕方になると、藁で編まれた小さな壺巣の中に収まり、ぎゅうぎゅうになって眠っていた。つぶらな瞳と三角の小さく尖ったクチバシがこちらを向いて並んでいる姿はいつ見ても愉快な気持ちにさせてくれた。そんな十姉妹がある日、小さな小さな卵を一つ、また一つと産み、家族で代わる代わる腹に抱えて温め、やがて指先にも満たないほどの愛らしい雛が孵る。この様子を繰り返し見てきたからだろうか。ある日卵から雛が現れるということを不思議に思ったことはない。だから僕が自分で卵を孵そうと思ったことは生命の秘密を感じたかったとか、そういうことではないような気がする。だとしたら何だろうか。なぜ、あの日の僕は卵を温めることを決意したのだろうか。もう四十年も近くの前のことだ。今となっては、あの日の僕は自分ではないような遠い存在でもある。だから想像でしかないのだが、僕は手のひらのなかで〝存在〟が生まれる姿を見てみたかったのかもしれないと、ときおり思い出すようにしてここに至ることがある。生命ではなく存在。それは名前と置き換えることができるものかもしれない。誰もがそうだろうけれど、僕は新たに迎え入れた動物の名前を考えるのが大好きだった。手のひらの中にいる動物の顔を覗き込み、指先に伝わる重さや毛並みの感触、鼻や耳を動かす際の仕草、光る瞳といった印象を掬いあげるようにして名前を付けた。それが鳩の場合は「ポッポ」でハムスターの場合は「ハムちゃん」なのだからネーミングセンスのあまりの貧しさに呆れ返ってしまうけれど、名前を付けた途端に動物たちが僕の中ですうすうと穏やかに息を吸い始めることを感じていた。それは生命という誰のものかわからない大きく捉え難いものではなく、胸のうちに棲むことになった小さな存在が生まれたことに気づく瞬間でもあった。この小さな存在が産声を上げようとする、その確かな一瞬を僕はきっと手のひらの中で感じてみたかったのだろうと思う。
今回の本で、僕は自分とともに暮らしてくれた動物たちのことをたくさん書いた。その多くはすでにいなくなった動物たちばかりだ。文字通り、生命を終えてしまっている。でも、存在の行方がどうなったかと問われると上手く答えられない。確かに生命とともにその存在も消えてしまっている。しかし、存在が名付けられることにはじまるとすれば、僕は今日も胸の内であの懐かしい動物たちの顔を一匹一匹思い浮かべ、その名を呼ぶことができる。もちろん、甘美な記憶ばかりではない。せっかく名付けたはずのその名を貶めるようにぞんざいに扱った動物たちもいる。それでも動物たちはいつもあの温かな毛並みや鮮やかな羽毛を輝かせ、確かに存在してくれている。僕はその事実に少しだけ安心し、明日も新しい朝を迎えることができる。
Copyright © OKUYAMA Atsushi 2021
(著者のご同意を得てウェブ掲載しています)