萩原朔太郎 2
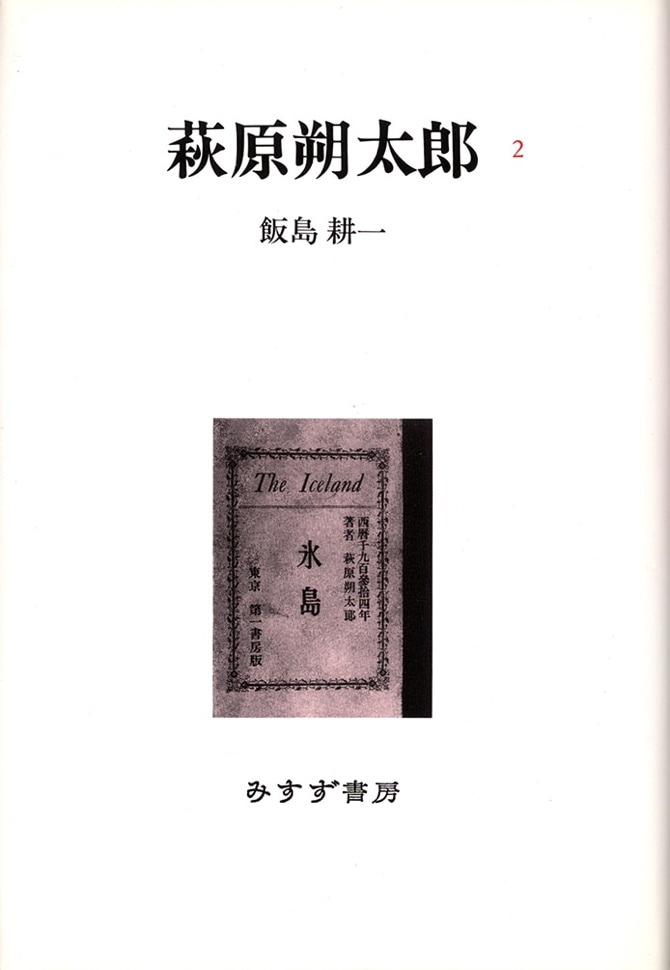
| 判型 | 四六判 |
|---|---|
| 頁数 | 240頁 |
| 定価 | 3,520円 (本体:3,200円) |
| ISBN | 978-4-622-07080-1 |
| Cコード | C1095 |
| 発行日 | 2004年1月5日 |
| 備考 | 在庫僅少 |
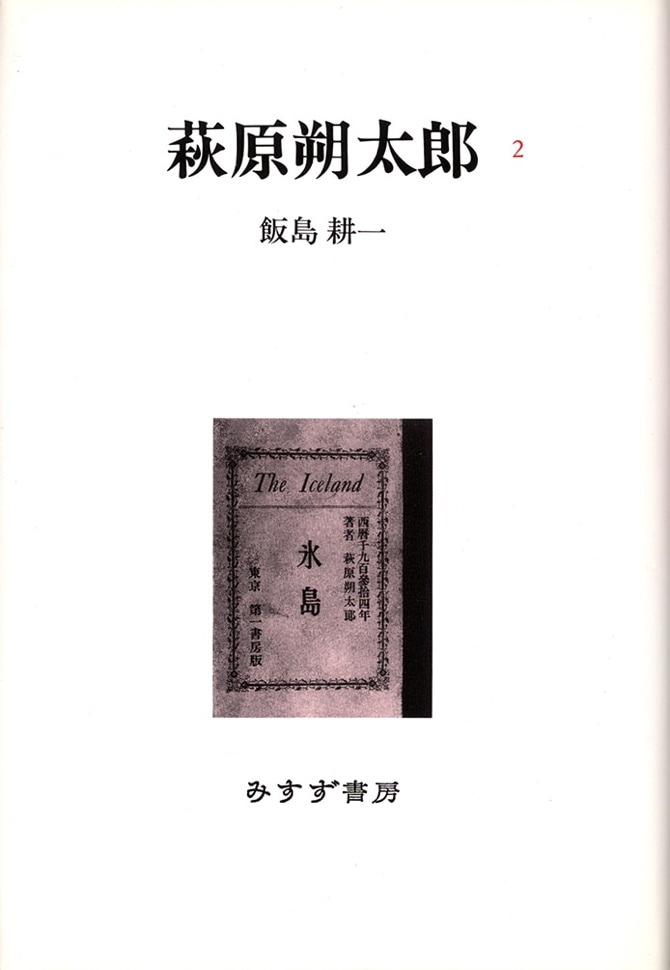
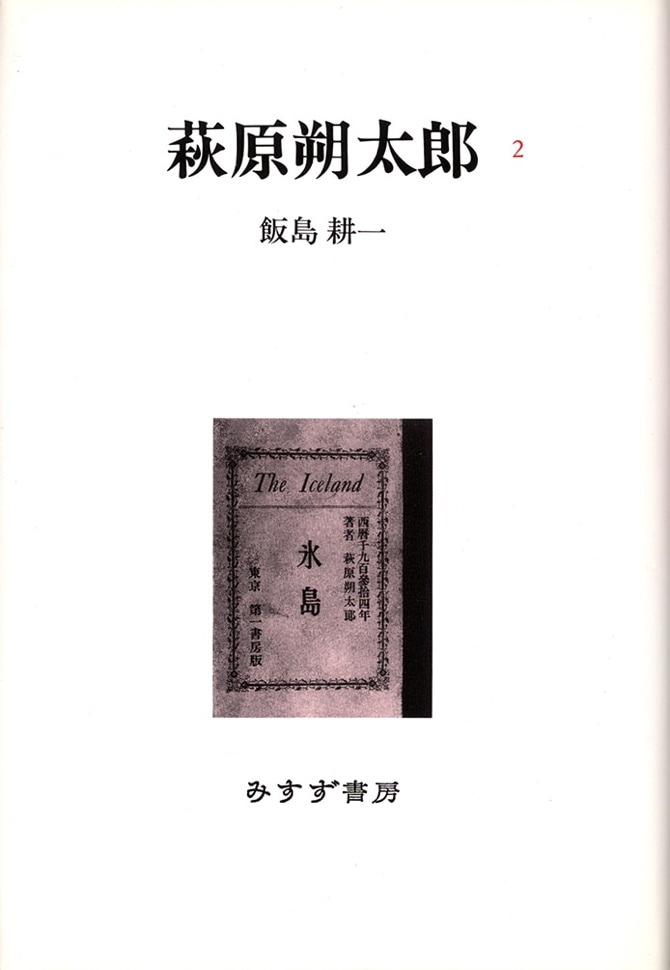
| 判型 | 四六判 |
|---|---|
| 頁数 | 240頁 |
| 定価 | 3,520円 (本体:3,200円) |
| ISBN | 978-4-622-07080-1 |
| Cコード | C1095 |
| 発行日 | 2004年1月5日 |
| 備考 | 在庫僅少 |
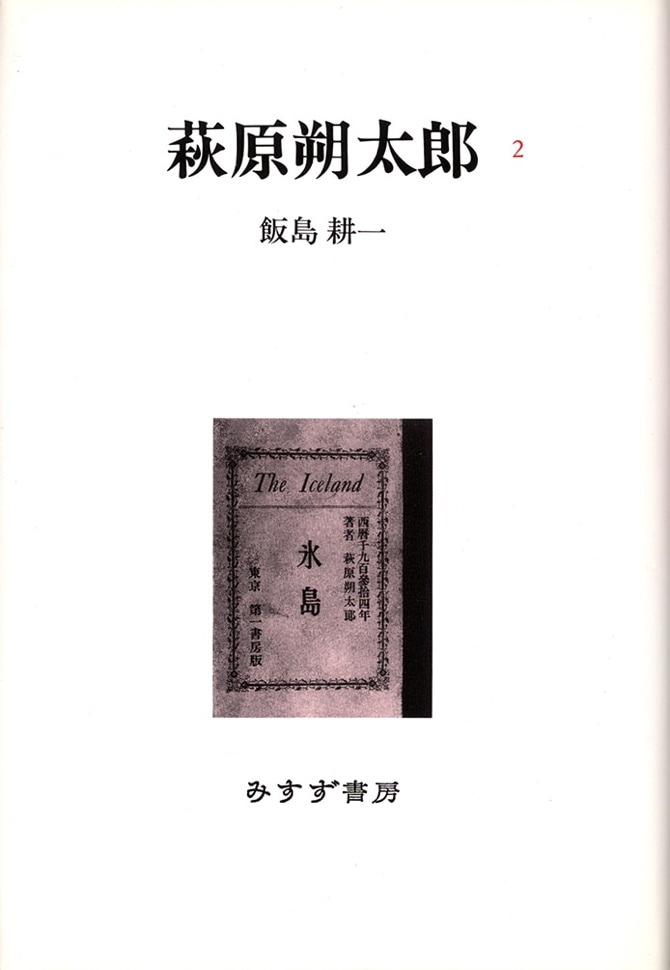
「ニイチェに憧れながら、ついにニイチェにはついて行けず、深い〈喪失〉感に陥る。そのニイチェ的メタフィジックの〈喪失感〉と〈日本への回帰〉は、この詩人のもとに一度に手を携えてやってきた。しかし朔太郎は〈日本への回帰〉で、必ずしも単純な国粋主義を唱えたわけではなかった。彼は〈西洋的なる知性〉をもって〈日本の青春性〉を見なおそうと提唱したのだ。こうしてぼくは、朔太郎の想定した〈日本への回帰〉を正当に実現したのは、意外なことに『旅人かへらず』の西脇順三郎ではないかという仮説を立てた」(〈日本への回帰〉とは何であったか)。
日本の近現代詩人たちは第二次世界大戦にたいしていかに向き合い、どう対処したのか? 日本の近代詩を代表する朔太郎はこの悲惨にたいして、どのような姿勢を示したか? モダニズムや保田与重郎、ボードレール、西脇順三郎・戸坂潤・瀧口修造などを論じつつ、著者は朔太郎の〈本音〉が奈辺にあったかを追尋してゆく。朔太郎の軌跡を辿りながら、自らの戦中・戦後体験を踏まえてなされる著者の言説に、今こそ、耳を傾けるべき秋であろう。