うつし 臨床の詩学
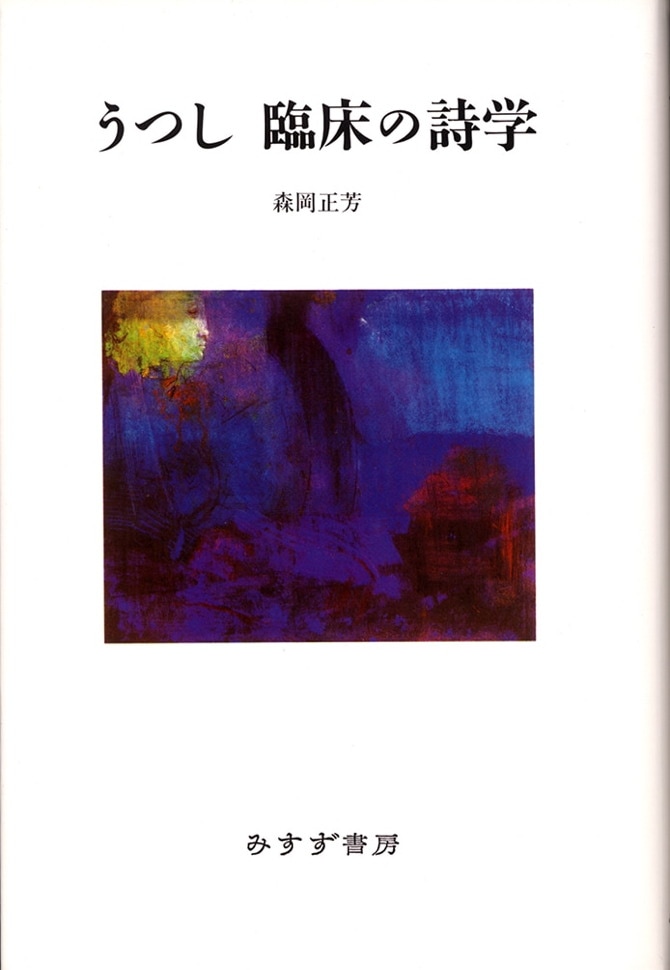
| 判型 | 四六判 |
|---|---|
| 頁数 | 232頁 |
| 定価 | 2,860円 (本体:2,600円) |
| ISBN | 978-4-622-07159-4 |
| Cコード | C1011 |
| 発行日 | 2005年9月1日 |
| 備考 | 現在品切 |
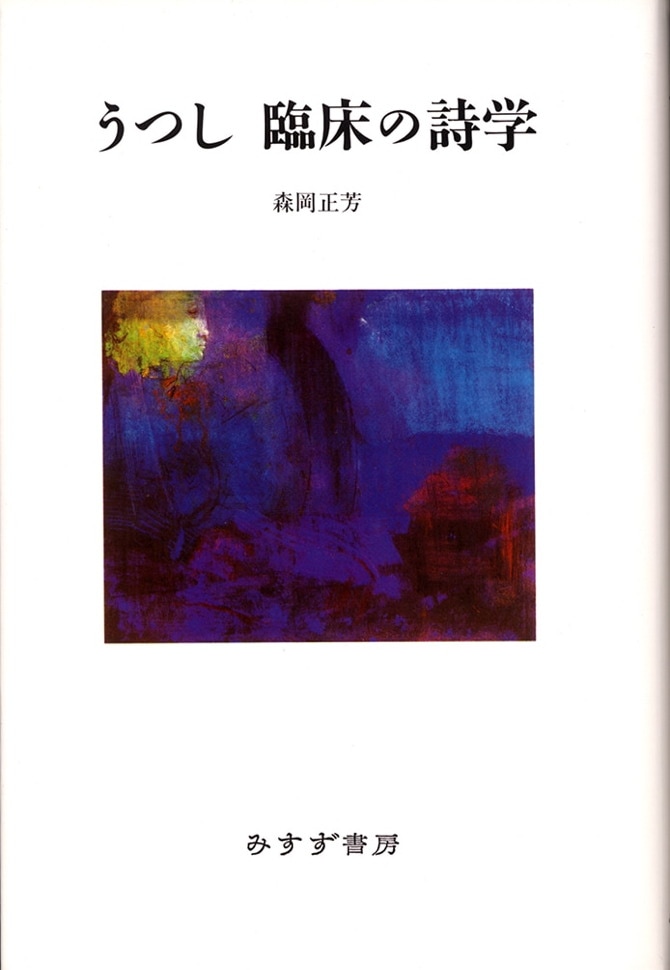
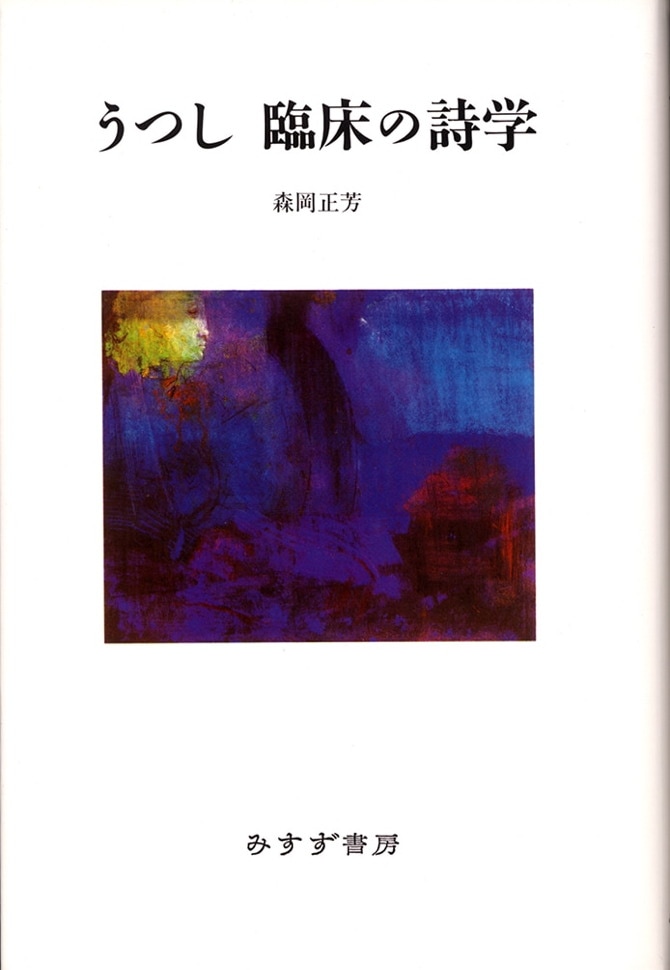
| 判型 | 四六判 |
|---|---|
| 頁数 | 232頁 |
| 定価 | 2,860円 (本体:2,600円) |
| ISBN | 978-4-622-07159-4 |
| Cコード | C1011 |
| 発行日 | 2005年9月1日 |
| 備考 | 現在品切 |
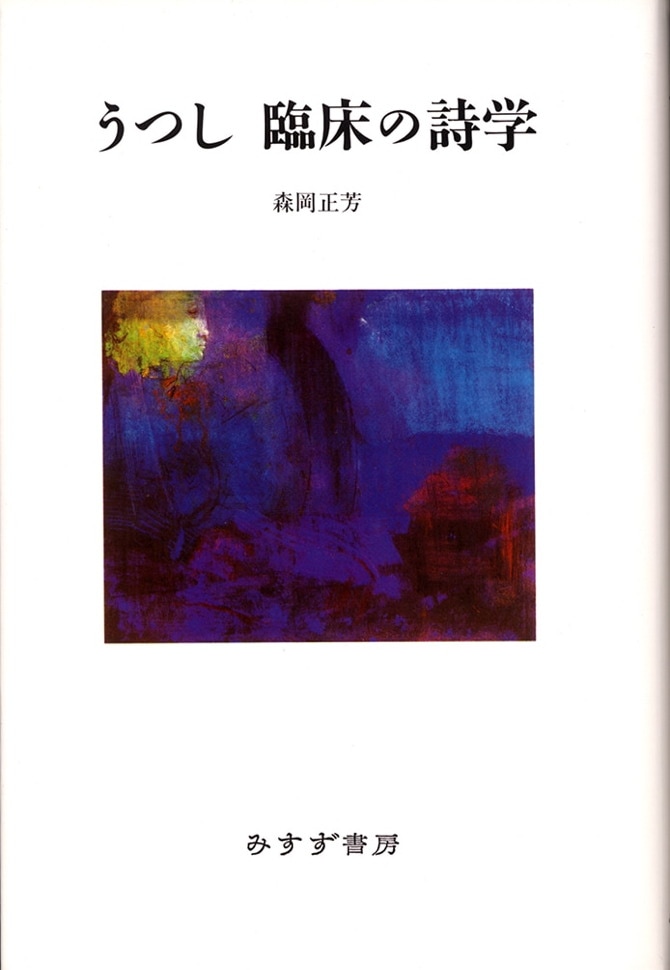
〈見えないものに対する感性、これは臨床の場に欠かせない。内心の変化、個人のその人らしさ、あるいは、一つ一つの出会いや体験に含まれる独自の感じや細部のニュアンスは見えないものであるが、それを映し合いの作業のなかで見えるものとしていく。セラピーという仕事はこのようにとらえられるのではないか。さまざまなセラピーで重要な働きをなす「イメージ」とは「うつし」という言葉が内包する多義的な意味に重なり合う〉
多くのクライエントたちの訴えの背後にある目に見えないものに、どうすれば近づくことができるのか。絆や「ともにある」関係をつくるために、発生状態の主観性、自己性の創造的な回復をめざした「他者の私の生」を構成するためには、どのようなスタイルが大切なのだろうか。サイコセラピーの臨床場面で日々問われている問題を、著者は「うつし」という言葉をヒントに、多方向から考察する。
豊富な症例や幅広い文献から、実際的・文化論的に臨床現場のあり方をさぐった本書は、現役のセラピストや心理臨床を学ぶ者には必読であろう。人と人とのつながりを考えるための最も基本的で困難な問題に分け入ったヒューマンな書である。
序 心で見るかんじんなこと
1 絆をつなぐ
2 はじめの写し
3 映し合う——感の世界
4 移し換える——反転
5 移りゆきの時空
あとがき
索引
『うつし 臨床の詩学』という本を書いた。「今度はとうとう臨床詩学か。まったく何でも臨床をつけたらいいというもんでもないやろ」という声が聞こえてきそうである。「人がぎりぎりに追い込まれて苦しんでいるのが臨床場面なのに、詩学などのどかなこと言うて」という声もあがりそうだ。しかし、こういう言い方は詩人たちに失礼にあたるだろう。
先日、芭蕉生誕の地伊賀上野に講演途中立ち寄った。上野城内にある芭蕉記念館で、芭蕉の句作、手紙などの自筆本を見ることができた。実に繊細で真実のこもった書。実兄や親族に宛てた絶筆となった遺言書など、その筆跡から直接伝わってくるものに胸がつまる。芭蕉にかぎらず、詩の一行に命をかけるということは言葉に偽りなく真実であろうと思う。
この本で書きたかったことは、人生を「詩的」に詠嘆することではなく、また詩を技法としてセラピーに応用することでもない。ハードな現実に苛まれ、強い破壊的な情念にとりつかれるということは、人生のところどころでは誰もが抱える。その情念を直情的な行動へと露出するのではなく、ある形式をもった言葉にしていく。その言葉は人と深く共有できる。情念と適切な距離をとることができ、その情念とつきあいやすくなる。
うっかりすると通り過ぎてしまう生活のさまざまな場面も、よく見ると心動かされる瞬間がある。それを逃さず活写する。詩にはそういう役割があった。詩によって選ばれた場面は生き生きとよみがえる。そこでは生起するものだけでなく、生起すること自体が救われる。日常生活の詩学の実践こそ、セラピーの発想の源泉と考えたい。(2005年11月 森岡正芳)