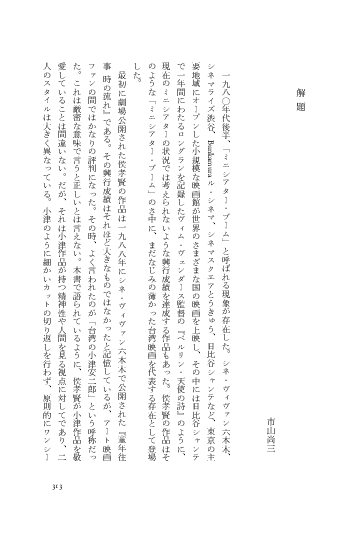
市山尚三「解題」はPDFでもお読みになれます(667KB)
侯孝賢監督作『好男好⼥』(1995年)、『憂鬱な楽園』(1996年)、『フラワーズ・オブ・シャンハイ』(1998年)の3作品で製作を⼿がけた映画プロデューサー・市⼭尚三⽒による『侯孝賢の映画講義』解題(全⽂)を以下に掲載い たします。
市山氏は「東京フィルメックス」の創設者として数多くのアジア映画の秀作を⽇本に紹介され、また2021年からは東京国際映画祭プログラミング・ディレクターを務められています。
市山尚三
1980年代後半、「ミニシアター・ブーム」と呼ばれる現象が存在した。シネ・ヴィヴァン六本木、シネマライズ渋谷、Bunkamuraル・シネマ、シネマスクエアとうきゅう、日比谷シャンテなど、東京の主要地域にオープンした小規模な映画館が世界のさまざまな国の映画を上映し、その中には日比谷シャンテで1年間にわたるロングランを記録したヴィム・ヴェンダース監督の『ベルリン・天使の詩』のように、現在のミニシアターの状況では考えられないような興行成績を達成する作品もあった。侯孝賢の作品はそのような「ミニシアター・ブーム」のさ中に、まだなじみの薄かった台湾映画を代表する存在として登場した。
最初に劇場公開された侯孝賢の作品は1988年にシネ・ヴィヴァン六本木で公開された『童年往事 時の流れ』である。その興行成績はそれほど大きなものではなかったと記憶しているが、アート映画ファンの間ではかなりの評判になった。その時、よく言われたのが「台湾の小津安二郎」という呼称だった。これは厳密な意味で言うと正しいとは言えない。本書で語られているように、侯孝賢が小津作品を敬愛していることは間違いない。だが、それは小津作品が持つ精神性や人間を見る視点に対してであり、2人のスタイルは大きく異なっている。小津のように細かいカットの切り返しを行わず、原則的にワンシーン・ワンショットを貫く侯孝賢のスタイルはむしろ溝口健二に近いと言えるだろう。それにもかかわらず侯孝賢が「台湾の小津」と言われたのは、『童年往事 時の流れ』に日本家屋が出てくることが大きく関係している。歴史的に考えると日本の植民地であった台湾に日本家屋が出てくるのは当然であるが、その当時はそういう知識さえ一般的には欠けていたように思う。当時の日本の観客は日本家屋で繰り広げられる家族の物語を描いた侯孝賢に小津の再来を感じたのである。
翌1989年に日比谷シャンテで公開された『恋恋風塵』は侯孝賢の日本での評価を更に引き上げた。この作品に描かれる山村の風景、そして素朴なラブストーリーに、今の日本では消えつつある「昔懐かしさ」を感じた観客は多かっただろう。この「昔懐かしさ」は日本の侯孝賢ファンにとっての重要な要素となる。同じ年、『悲情城市』がヴェネチア映画祭で金獅子賞を受賞。翌年の日本での劇場公開も大成功をおさめた。この映画が玉音放送で始まることは当時大きな話題となった。劇場には映画ファンのみならず、台湾が日本の植民地であったことを知る高齢者たちも詰めかけた。私が日比谷シャンテでこの映画を見た時、舞台挨拶などない通常興行にもかかわらず、上映終了後に拍手喝采する高齢の観客がいたことを覚えている。続く『戯夢人生』は台湾も含むほとんどの国で興行的に苦戦したにもかかわらず、日本ではそれなりの興行成績をあげたのは、この作品が日本占領下の台湾を扱っていたことと無縁ではない。
私が侯孝賢と仕事をしたのは、この後に製作された『好男好女』『憂鬱な楽園』『フラワーズ・オブ・シャンハイ』の3作品である。この3作品はいずれも日本ではそれまでのような興行成績をあげることができなかった。それは、この3作品において、侯孝賢が自分に割り当てられた一つのイメージ、言うなれば「ノスタルジックな世界を撮る巨匠」というイメージを払拭しようとしていたことが大きな原因だと思う。いつだったか正確に覚えていないが、当時侯孝賢が「自分が『冬冬の夏休み』や『恋恋風塵』のような映画を撮った方が皆が喜ぶのはわかってる。でも今はそういうものを撮りたくないんだ」と言ったことを記憶している。映画監督の中には、ある程度イメージが決まった段階でそのイメージを壊さないような映画を作り続ける者も少なくはない。大抵、そういう監督は自分の作品の劣化版を再生産し、結局代表作と言われるものを超えることはできない。侯孝賢のこの言葉を聞いた時、私はこの人こそ真の映画作家だと確信した。そしてその確信は今も変わっていない。
本書は侯孝賢が自作についてほとんどのことを包み隠すことなく話している様子が記録された貴重な文献である。しかも、世界的な巨匠の座を築いた『戯夢人生』以前より、自らのスタイルを変貌させようとした『好男好女』以降についてより詳しく語られているところが面白い。特に興味深いのは、俳優についてさまざまなことを言及している点だ。私が思うに、侯孝賢の世界を最も体現している女優は『恋恋風塵』と『悲情城市』に主演した辛樹芬(シン・シューフェン)だろう。侯孝賢にとってやや不運だったのは、辛樹芬が俳優を続けるつもりがなく、結婚してアメリカに渡ってしまったことだ。例えば、『好男好女』のヒロインが辛樹芬だったら、映画はどうなっていただろうか? 『好男好女』が松竹に提案された時、現在と過去をカットバックする複雑な脚本は既に出来ていたので、なぜ実際には白色テロの時代の物語を正面から描くことをせず、このような錯綜した構成を考えたのかはわからない。公開前のインタビューでは「現代の若者たちに過去の事件に興味を持ってもらいたいと思った」と言っていたが、それは後付けのような気がする。本書で侯孝賢は、伊能静は現代の場面ではよくやっているが、過去の場面は今一つだった、と認めている。こう言うと怒って否定されそうな気もするが、侯孝賢は伊能静に白色テロの時代を全編演じさせるのは無理だと思い、現代と過去をカットバックする形式を考えたのではないか、と思えてならない。それでは、なぜ伊能静をキャスティングしたのか、という疑問がわく。伊能静をキャスティングした経緯ははっきりとは知らないが、確か、当時ミュージシャンとして売り出そうとしていた伊能静を誰かから推薦された、という話を聞いた。その程度のことで台湾近代史三部作の最後を飾る作品の主演女優を決めるとは俄かには信じがたい。だが、後述する『フラワーズ・オブ・シャンハイ』のキャスティングから判断すると、そういうことがあっても全くおかしくないのが侯孝賢という監督なのである。
見方によっては「いい加減」とも言えるような大雑把さは、侯孝賢と仕事をするうちに何度か遭遇した。だが、その「いい加減」なところが逆転して素晴らしい作品を生み出すところが侯孝賢の凄さである。本書でも触れられているが、『憂鬱な楽園』の企画の発想を思いついたのは『好男好女』でカンヌ映画祭に参加している時に高捷(カオ・ジエ)、林強(リン・チャン)、伊能静の三人が楽しく過ごしているのを見たことがきっかけだ。恐らくは『好男好女』の現代パートが十分には現代の台湾をとらえていないと感じていた侯孝賢は、初期作品のように短期間で彼らを起用した現代ものを作ろうと考えたのだろう。カンヌ映画祭が終わって間もない6月に侯孝賢が新作の撮影準備を始めたという報告を聞いて当時の私は驚き、慌てて松竹社内を調整して出資の手はずを整えたのだが、その時、侯孝賢は本気でその年の9月のヴェネチア映画祭に間に合わせようとしていたようだ。本書にある通り、『憂鬱な楽園』の撮影は混乱を極め、8月にいったん撮り終わったものの、10月に後半を全て撮り直すことになった。前半の美術や装飾を見るとわかるように、侯孝賢はこの映画で意識的にこれまでの自分のスタイルを変えようとしていた。だが、その結果に自分自身納得がいかず、後半を自分の良く知っている世界、つまりチンピラやくざが喧嘩や軽犯罪に明け暮れている世界に寄せ、逃げ切りを図った。いわば、かなり行き当たりばったりで作られた映画なのだが、その行き当たりばったり加減が実に魅力的に昇華されたのである。恐らく、日本のそれまでの侯孝賢作品のファンの多くはこの映画を見て愕然としたに違いない。だが、本書でも侯孝賢が触れているように、当時、多くの日本の映画監督たちがこの映画に勇気づけられた、と語っていた。実際、この映画に触発された作品を撮った中堅監督がいることも知っている。私にとってもこの『憂鬱な楽園』は自分が関わった作品であることは割り引いても、侯孝賢作品のなかで最も好きな作品である。
話を元に戻そう。『好男好女』で現代のパートを登場させたことが『憂鬱な楽園』のきっかけとなったことは今述べた通りだが、この流れは更に『ミレニアム・マンボ』に繫がっているのではないかと思う。私は『ミレニアム・マンボ』には直接関わっていないのであくまでも憶測だが、『憂鬱な楽園』で描ききれなかった現代の台湾を描くことにあらためてチャレンジしたのではないだろうか。それは必ずしも成功したとは言えないが、この映画のために侯孝賢が舒淇(スー・チー)と出会ったことは後の展開を考えると大きな意味があったと思う。
もし、『好男好女』の頃に侯孝賢が白色テロの時代の女性を十分に演じられる女優に出会い、現代の視点を伴わない正攻法な語り口の作品が出来ていたら、その後の侯孝賢のフィルモグラフィーはどうなっていたのだろうか? それでも侯孝賢は自分のスタイルを崩す方向に向かったかもしれない。だが、伊能静との出会いがあってこそ生まれた『憂鬱な楽園』のような作品が作られることはなかっただろう。こう考えると、侯孝賢の中にある「いい加減さ」が彼の豊かなフィルモグラフィーを生み出す源泉になっているのではないかと思えてくる。
侯孝賢の「いい加減さ」を表すもう一つのエピソードとして、『フラワーズ・オブ・シャンハイ』のキャスティングについて述べておきたい。これまで、マギー・チャン(張曼玉)の名誉のために話さないようにしていたのだが、本書で侯孝賢が暴露している通り、トニー・レオン(梁朝偉)の相手役である小紅役には当初マギー・チャンが予定されていた。この作品について松竹はそれまでの作品の3倍近くの資金を出資していたこともあり、可能であれば日本の女優を1人使ってほしい、という要望を出していた。侯孝賢は、最も若い双玉(映画のラスト近くで、なじみ客の若旦那が結婚すると知って阿片入りの酒を飲ませようとする役)なら台詞も少ないので、日本人をキャスティングしてもいい、と応じたので、私は十代の女優のオーディションの用意をしていた。そこに侯孝賢から、マギー・チャンが出演できなくなったので、小紅役に日本人を使いたい、という連絡が入った(正確に言うと、その時点ではマギー・チャンはスケジュールの都合で出られない、ということだった。マギー・チャンが上海語を喋る自信がないので断ったことがわかったのは、映画が完成した後のことである)。私は、この役を日本人が演じるのは無謀だと思った。その当時、香港映画や台湾映画で活躍していたマギー・チャンとイメージが重なる女優の名前を何人かあげたのだが、それに対して返ってきた侯孝賢の答えはこうだった――「そんな女優たちでマギーの代わりがつとまると思うか?」 ベストな女優がつかまらない時、それに準ずる女優を探すよりも、全然違うところからキャスティングする、という大胆な発想である。こういった発想はどこから出てくるのだろうか? あるいは、自分のイメージとは異なっても、スケジュールが十分にあり、現場であれこれ揉めることのない女優なら、自分の演出で作品として成立させてみせる、という自信なのかもしれない。実際、小紅役に抜擢された羽田美智子は、マギー・チャンとは全く似ていないが、小紅の役を十分に演じていたように思う。因みに、侯孝賢はオーディションの際に演技をさせる、脚本を読ませる、ということは一切しない。ただ、幾つか俳優に質問して雑談するだけだ。その時、最初に必ず聞くのがその俳優の「星座」である。当時は話のきっかけにしているだけだと思っていたが、本書に何度も「星座」の話が出てくることからすると、かなり真剣に「星座」による相性を信じていたのではないかと思われる。
当初日本人をキャスティングする予定だった双玉役がどうなったかについても触れておきたい。「日本人を2人も起用するのは大変なので、双玉役は台湾で探す」という侯孝賢の意向により、十代の女優を対象にしたオーディションは行われなかった。その後、双玉役がどうなったのかは全く気にかけていなかった。恐らく、台湾でオーディションを開き、こちらが名前を聞いてもわからない新人女優を使うのだろう、ぐらいにしか思っていなかった。撮影が始まり、現場に行って驚いた。何と、一番下の助監督が双玉を演じていたのである。自分の出番がない日は彼女は助監督に戻り、カチンコを叩いていた。脇役とは言え、ラスト近くにはかなりの見せ場がある役だ。この役に助監督をキャスティングするという発想には驚くしかないが、出来上がった映画を見ると彼女がそのような事情でキャスティングされたとは誰も気づかない名演技だった。
侯孝賢の「いい加減さ」について幾つか例を挙げたが、実は映画製作はこのような「いい加減さ」がなければ進まないことが多い。全てが計画通りに進むことなど稀で、大抵は予期せぬ事態が起こって軌道修正を迫られる。そのような時にしばしば事態を打開するのが「いい加減さ」なのである。通常、映画監督はそうやって「いい加減に」解決したことを正直には語らない。何か後付けの理由をつけ、さも最初から想定していたように振る舞うものだ。侯孝賢も、公開前などに行われたインタビューではその傾向があった。だが、本書に収められた講義では包み隠さずにその「いい加減さ」を語っているように思える。その意味では、侯孝賢研究という点ではこれまでにない画期的な著作と言えるだろう。
最後に、そんな侯孝賢が本当に凄いと思った瞬間について話しておきたい。『フラワーズ・オブ・シャンハイ』にはかなり緻密に書かれた脚本が存在したが、その第1稿のラストは主要人物それぞれの「その後」を表すショットで構成されていた。その最後に来るのが羽田美智子演じる小紅が阿片で呆然とした状態でよろよろと階段を上がってゆく、というものだった。完成した映画のラストはそれとは異なる。そこでは小紅だけの「その後」が示されるが、それは脚本にあったショットとは全くの別物である(それが何であるかは映画を見ていない人も多いと思うので、敢えて書かないでおく)。編集ラッシュを見た私は、思わずうなった。脚本通りなら、それはそれで人生の儚さを表現するラストとして成立しただろう。だが、実際に採用されたラストシーンは、そのような想像の範囲をはるかに超えるものだった。どう解釈するかはそれぞれの人によると思うが、ある意味、恐ろしく人生の真実をついたショットでもあると思えた。カンヌ映画祭の公式上映ではじめて作品を見た羽田美智子も「まさかあのシーンを最後に持ってくるとは思わなかった」と驚きを隠さなかった。そのシーンは、別のシーンのついでに「こういう設定で撮ってみよう」と言われ、何の準備もなく撮られたものだという。侯孝賢が、このシーンをラストに使うかもしれない、と言っていたら、羽田美智子の表情はかなり違うものになっていただろう。その時、侯孝賢がそれをラストに使おうと考えていたかどうかは定かではない。もしかすると、本当に適当に思いつきで撮ったシーンに過ぎず、編集の段階でラストに使おうと考えたのかもしれない。ここにもまた一つの「いい加減さ」がある。だがその「いい加減さ」が映画をより豊饒なものにしているのである。これは凡人が真似てできることではない。侯孝賢だからこそ成しえることのように思えてならない。
Copyright © ICHIYAMA Shozo 2021
(著作権者のご同意を得て転載しています)
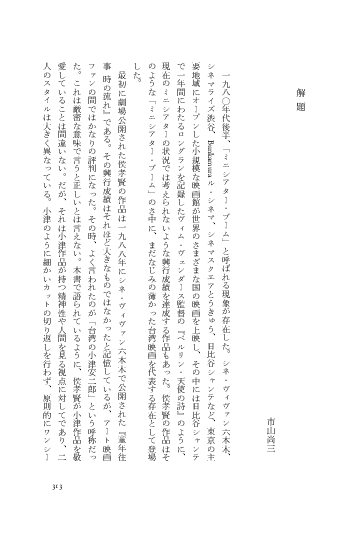
市山尚三「解題」はPDFでもお読みになれます(667KB)