
2017.09.26
『中井久夫集 4 統合失調症の陥穽 1991-1994』最相葉月「解説 4」より
[第4回配本・全11巻]
網野徹哉『インディオ社会史』巻末「謝辞と解題」より抜粋
2017.09.12
ここで書名について説明したいと思う。「インディオ社会史」には「インディオ社会の歴史」というよりも「インディオの社会史」という意味を込めている。そしてインディオ世界の社会史的探求へと私を誘ったのも、『ペドロ・パラモ』同様、一冊の書物であり、それは博士課程に進学してすぐに読んだカルロ・ギンズブルグの『チーズとうじ虫』であった。
異端審問の遺した裁判記録を基に、イタリア・フリウリ地方に住むひとりの民衆、粉挽き職人メノッキオの脳裏に構築された特異な思考世界を活写した同書を一読し、ああ、一生のうちでこんな歴史が書ければ悪魔に魂を売ってもよいくらいだ、と私は呻いた。いやしかし、もしかすると、メノッキオのような人間は、アンデスにもいるのではないか。インディオ版異端審問ともいえる偶像崇拝根絶巡察の記録を冀求したゆえんである。アンデス植民地世界の底辺において、日々の労働の辛苦に喘ぎながら、しかし心の安寧と喜悦を求めて死んでいった無数の男女たちの生に少しでも近づきたい、そしてなんとか彼らの視点に立って当時の社会の歴史を描き出したい、という思いが、それ以降の私の勉強の駆動力となった。
とはいえ、先住民の真の生に接近することは至難の業であった。首長層やヤナコーナなどをのぞけば、インディオの大部分は、日常的には非文字的空間に沈潜している。ケチュア語をはじめとする先住民言語の音声的世界にあって、彼らが支配者の言葉であるスペイン語と触れる機会は一生のうち僅かであったろう。文書的観点から見れば、沈黙の海を漂うインディオたち、彼らはそのまま生きていれば、いっさいの痕跡を歴史に遺さないような人々である。
そうした日常にとつじょ亀裂がはいる。彼らの異教的実践を暴きだすべく派遣された巡察使によって検挙され、発話を強制されることによって、彼らはおずおずと、胸中にある伝統的神々への思いを打ち明けはじめる。だがそこにはメノッキオの示した胆力の強さはめったに感じられない。自らが構築した思想に対する矜恃を基点として、抑圧者たる異端審問官に対して積極果敢に抵抗を試みるフリウリの粉挽き職人とは異なり、暴力をちらつかせて睥睨する巡察使の前で、被告の先住民たちが、体を硬直させている様子は、史料を読む者にも伝わってくる(第七章、補論参照)。
ヨーロッパの民衆史家よりも、私たちはさらに困難な情況におかれている。先住民発話者の眼前には、たいてい通辞が立ち塞がっていた。被告のケチュア語が、通訳の言語的フィルターによって捩じ曲げられ、さらにそれを巡察使や書記官が植民地主義的インディオ観によって再調理することで、支配する側にとって聴き心地のよい言葉に変貌して紙葉に刻印されていく。そのありさまを、これまで、何度、何度、目の当たりにしなければならなかったか! 最終的に私たちが手にする文書の「インディオの言葉」は、幾重にも折り曲げられ、さまざまな意思によって汚染されたものでしかないともいわれれば、そう、としか答えようがない。表象の不可能性。
しかし、とはいえ、インディオ大衆、いや先住民に限らず、混血者の、黒人の、そしてスペイン系の下層民すべてをそこに含まねばいけない、そうした彼らの生きた世界に近づく努力を放棄してはならぬ。底の見えぬどろどろに汚れた沼に投じられた鉛の錘が、水藻や汚泥に遮られながら、しかしゆっくりと沈んでいって、最後に、ずん、という重い響きとともに水底に触れる瞬間。そのような感覚とともに、ごく偶(たま)さかではあるが、数多くの史料をめくり通したあげくに、インディオたちの魂に触れたのではないか、という微かな思いを手にすることがあるのだ。メノッキオほどの情熱はなくとも、彼らの怒りが、喜びが、思想が、静かに流れ出す瞬間。こちらが息絶えるまで、その「ずん」を待って、日々学び続けることこそがインディオ社会史であると、この頃になって、少しわかってきたような気がする。もとより、ここに輯録したすべての論攷がそうした僥倖の結果などとは、到底、いえないが。
〔……〕
copyright © Amino Tetsuya 2017
(著者のご同意を得て抜粋転載しています)
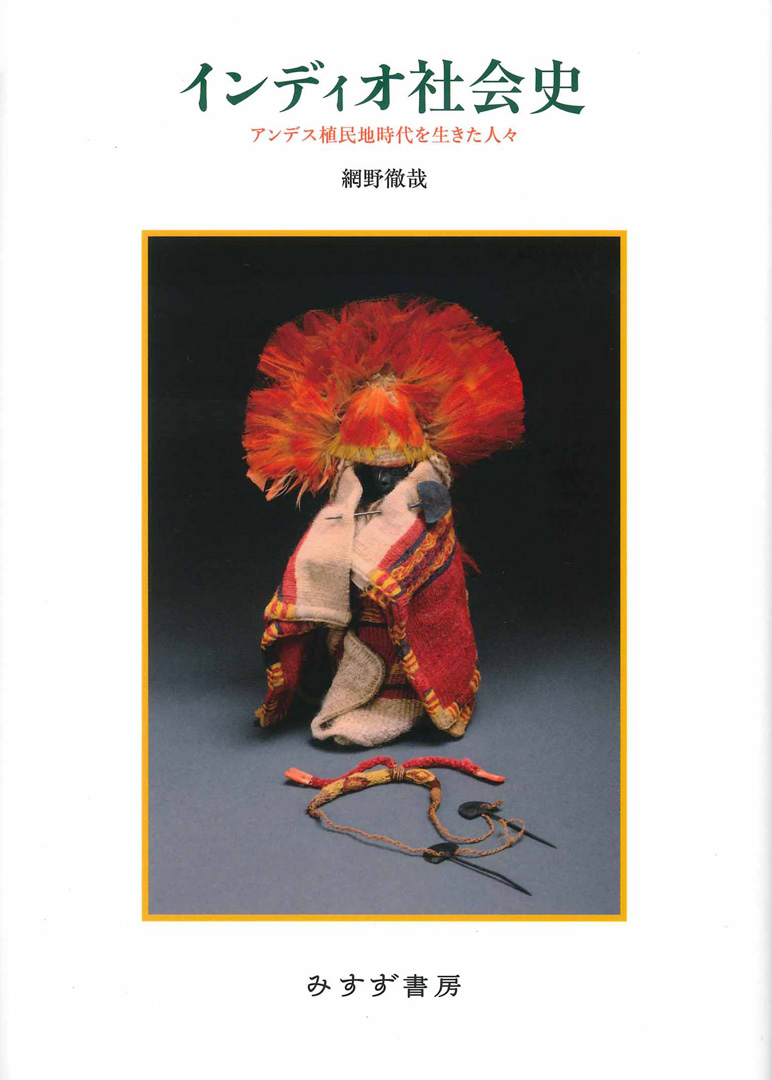

2017.09.26
[第4回配本・全11巻]

2017.09.08
アトゥール・ガワンデ『予期せぬ瞬間――医療の不完全さは乗り越えられるか』