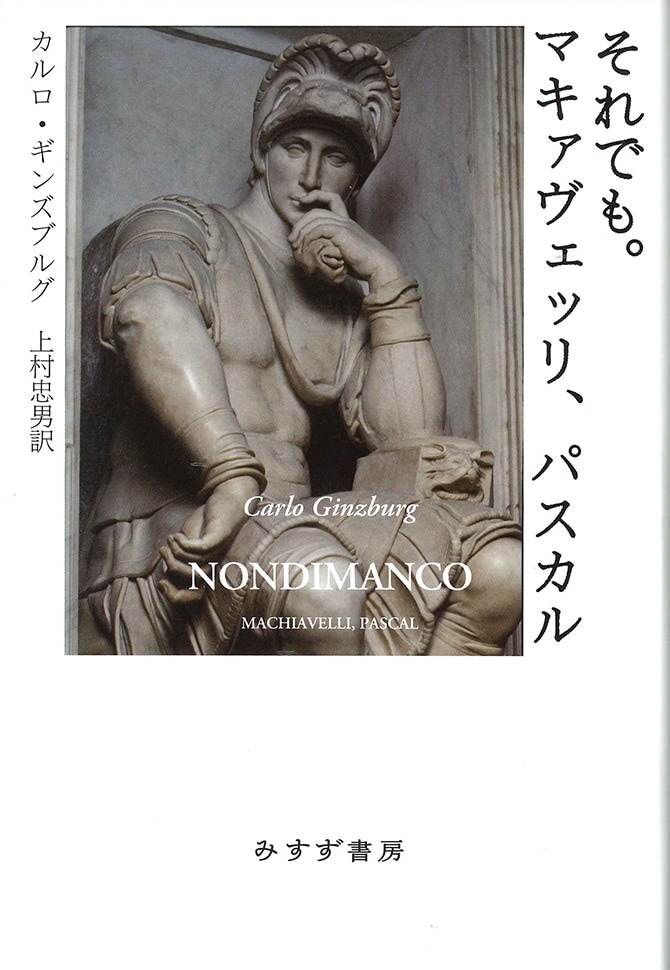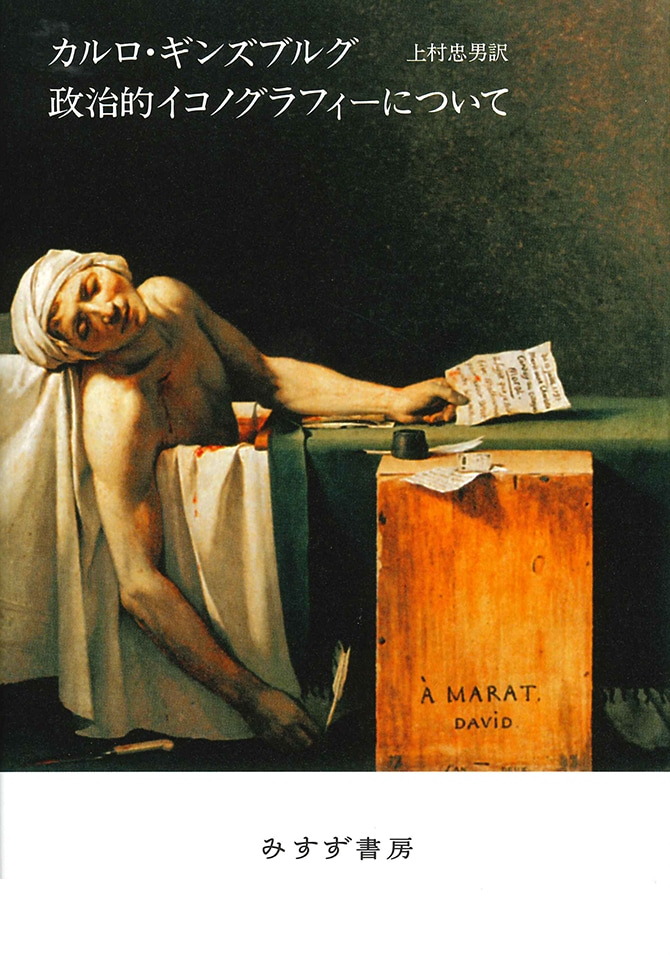エッセイという形式を借りながらテクストを丹念に読みこむことをつうじて調査研究を進めていく歴史家ギンズブルグ。
「エッセイの曲がりくねっていて気まぐれで不連続な進行は試験の厳密さとは両立しえないようにみえる。が、おそらくこのように柔軟性に富んでいるからこそ、エッセイは、まさしく、制度的な諸学科の手から逃れ去ってしまいがちなもろもろの形状を捕捉することに成功する」。
非文学的なテクスト(とくに異端裁判の記録)から仕事を始めながら、やがて文学的テクストにも取り組むようになるだろうというというギンズブルグの予感の起源には、『チーズとうじ虫』の16世紀のフリウーリの粉挽きメノッキオが「人間が書物の読み方を自分のものにする仕方はしばしば予測がつかない」と教えてくれたこともあったと明かされています。
歴史家が真実に接近すべく採用する「エッセイ」という形式の戦略を、その実践である本書の「序論」より抜粋します。
ひらめきをかたちに。ジャンプを厳密さの中で着地させる秘密の一端が記されています。
序論
(抄)
アドルノは「形式としてのエッセイ」で書いている。《エッセイは前進していくなかで真実に近づく。〔中略〕その諸概念はエッセイ自体には隠されている到達点(terminus ad quem)から光を受けとるのであって、出発点(terminus a quo)から受けとるのではない》。
ここでもほかの場所でも、アドルノはジャンルとしてのエッセイに固有の非演繹的な要素を強調している。エッセイの読者には、総じて紆余曲折に満ちた道のりの最終到達点は、定義からして未知であって、ここから、この文学形式の最良の見本を読むなかでの驚きはやってくる。しかしながら、作者には、最終的にどこに行き着くかは、しばしば彼または彼女が書き始める前から、知られている。調査研究を始める前にすら知られていることがありうると想定することは、エッセイの形式的特徴が提供する可能性を大きく増進させることを意味する。これが、わたしが――意図してではなかったとしても――おこなってきたと考えていることである。
(中略)
エッセイをモンテーニュからディドロへと、そしてさらに彼らを超えて進歩していったひとつのジャンルと受けとめる者は、おびただしい数の注が付いているからといって怖じけることはないだろう。博覧強記は、ひとつの文学形式としてのエッセイのはるか遠い起源をなす宴会での議論における支配的な要素なのである。
そしてラテン俗語のエクサギウム(exagium)=「釣り合い」に由来する「エッセイ」という語の語源そのものが、そのジャンルを、ジャン・スタロバンスキーがわたしたちに想い起こさせてくれたように、もろもろの観念を検証に付す必要性と結びつけているのである。しかし、その語はつねに、《とどのつまり、わたしがここになぐり書きするごった煮のような文章はすべて、わたしの人生のエセー(essais)の記録以外の何ものでもない》というモンテーニュの有名な一節(『エセー』3.13)にあるように、「テスト」と「努力」のあいだで揺れ動いている。この両義性は事の実相を雄弁に物語っている。イタリア語のプローヴァ(prova)(立証)のことを考えてみれば十分なように、唯一の事例ではないとしてもである。どの検証も最終的なものとはみなすことができない。アドルノも、エッセイについて語りつつ、《自己相対化はその形式のうちに内在している》と忠告している。
エッセイの曲がりくねっていて気まぐれで不連続な進行は立証の厳密さとは両立しえないようにみえるかもしれない。が、おそらくこのように柔軟性に富んでいるからこそ、エッセイは、まさしく、制度的な諸学科の手から逃れ去ってしまいがちなもろもろの形状を捕捉することに成功するのである。
トマス・モアの『ユートピア』が所属しているジャンルにかんしてクェンティン・スキナーとわたしとのあいだで見解の相違が生じていることが教訓的かもしれない(第一章を見られたい)。『ユートピア』はあるひとつの文学ジャンルを創始した稀有なテクストのひとつなのだから特別なケースである、と異議を唱える者がいるかもしれない。だが、エリザベス朝イングランドで燃え上がった韻の正統性をめぐる論争のような一見したところではテクニカルな論争がいったいどのようにしてモンテーニュに始まるその大陸的起源を無視するほどまでに誤解されるというようなことになりえたのか、とわたしは自問せざるをえない(第二章を見られたい)。この種のケースは容易に見つけ出すことができる。調査研究というチェスのゲームでは、文学上のルーク〔城のかたちをした駒、王将〕はまっすぐに直進しようとして頑として譲らない。これにたいして、ジャンルとしてのエッセイはナイトのように予見しえなかった仕方で動き、ひとつの学科からもうひとつの学科へ、ひとつのテクストからもうひとつのテクストへジャンプする。
(中略)
わたしは歴史家としての仕事を非文学的なテクスト(とくに異端裁判の記録)を吟味することから始めたが、そのさい、レオ・シュピッツァーやエーリヒ・アウエルバッハやジャンフランコ・コンティーニのような古典学者たちによって発展させられてきた解釈道具を手助けにしてきた。
遅かれ早かれわたし自身、文学的テクストにも取り組むようになるだろうというのは、たぶん避けがたいことであった。しかし、この調査研究上の新しい経験は過去に学んだ教訓を考慮に入れていた。その抱懐していた考えが理由で異端裁判所によって死刑を宣告されたフリウーリの粉挽きドメニコ・スカンデッラ、通称メノッキオから、人間が書物の読み方を自分のものにする仕方はしばしば予測がつかないということをわたしはつかみ取った。
以下の頁でわたしは同じような見通しのもとで、ルキアノスとトマス・モアを読んだバスコ・デ・キロガ、ルキアノスを読んだトマス・モア、モンテーニュを読んだジョージ・パットナムとサミュエル・ダニエル、ベールを読んだスターン、等々にアプローチしている。これらのケースのそれぞれで、わたしはある原典が再作動される様子ではなくて、なにかもっと広くてもっと移ろいやすいものを分析しようと試みてきた。読むことと書くこととの関係、現在と過去の現在との関係がそれである。