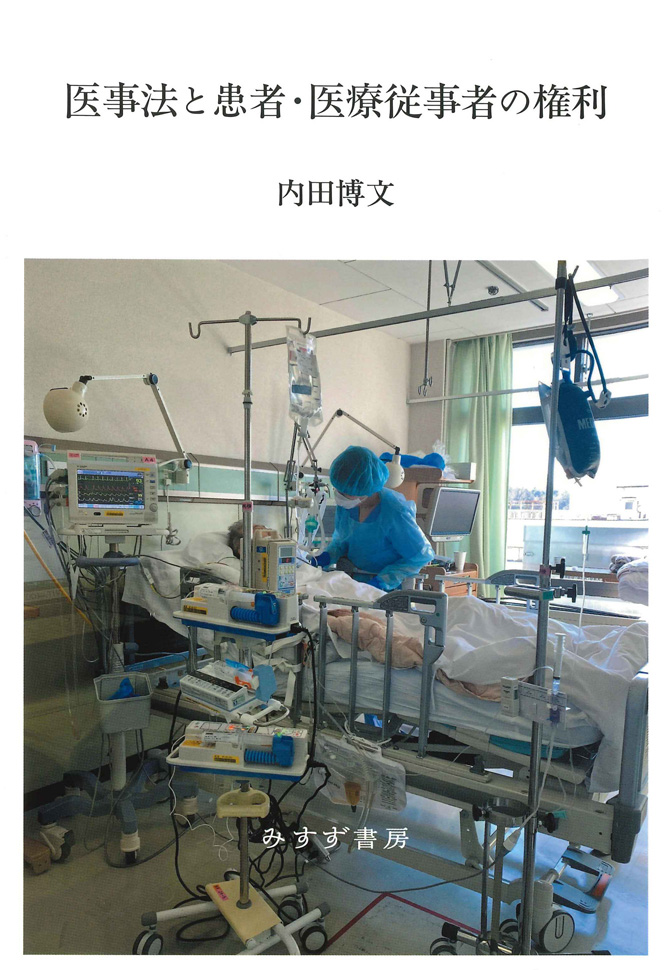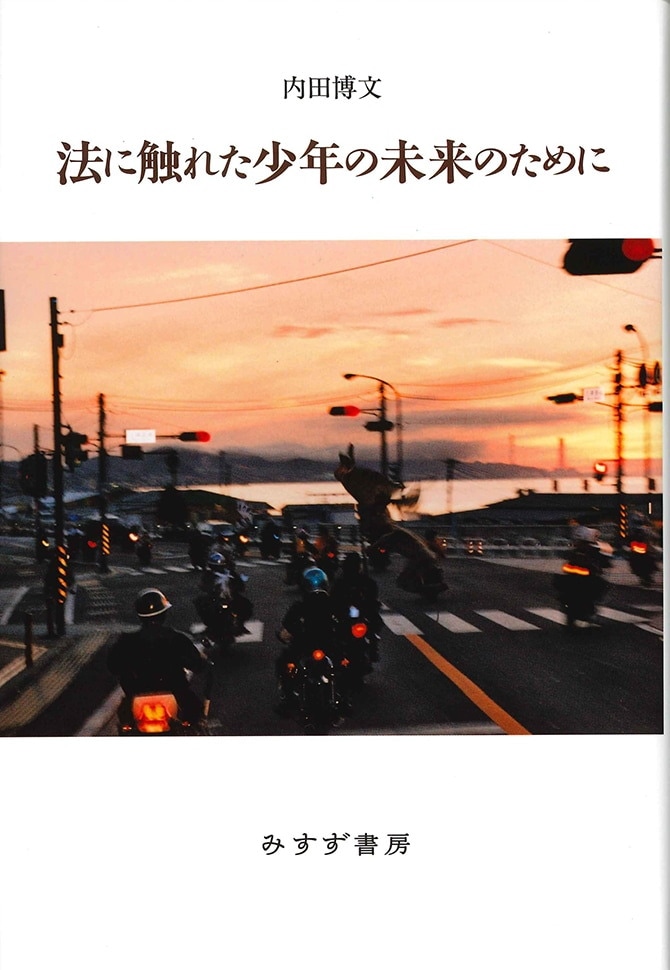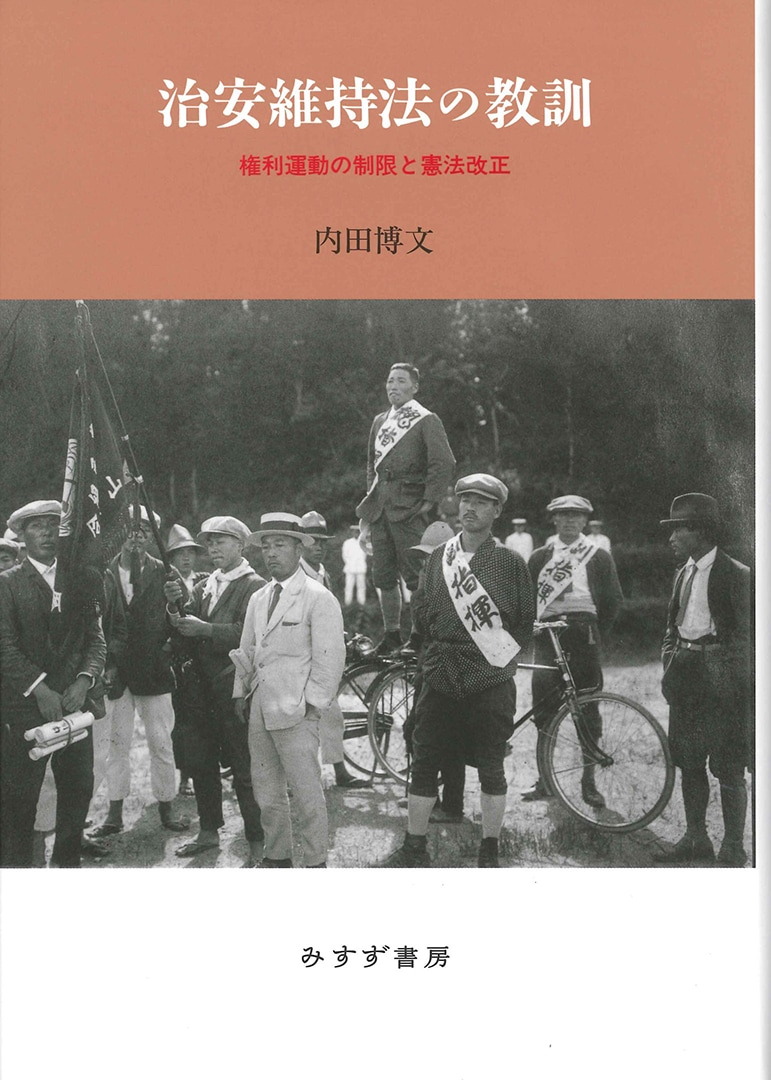本書の著者である刑法学者は、広島県府中市の市立病院廃止差し止めを求める住民訴訟において、訴訟代理人から裁判所への意見書の提出を依頼された。その経験が医事法・医事法学研究の出発点のひとつとなった。
各地の公立病院が閉鎖され、病床の計画的削減が進むのが日本の医療である。医療に無縁の人はいない。
裁判所はいわば門前払いに等しい判断を行い、原告の請求を棄却した。悔しい思いをしたが、現行の医療法では、住民の命を守れないことが明らかとなった。急ピッチで進んでいる医療崩壊を食い止めるためには、医事法の改革が急務であることを強く実感させられる出来事であった。
医療ないし医学が疾病の予防に、そして疾病した場合には病気を治療し、健康を取り戻すことにあるとすれば、医事法ないし医事法学の役割も、この予防及び治療に奉仕することにある。この役割を果たす上で何よりも重要なことは、患者・家族の方の、そして医療従事者の方の思いを共有することである。
(略)説明のための説明としてではなく、医療ないし医学を、そして医事法ないし医事法学を改革するための前提として見直しを行う。(「終わりに」より)
以下、著者による本書の「趣旨」を掲載する。
新型コロナウイルスの感染のまん延は、日本の政治、経済、社会の歪さ、脆弱さを顕在化させた。医療制度及び医事法もその例外ではない。否むしろ、その歪さ、脆弱さをもっとも顕在化させたのは医療制度、医事法の分野であったといってもよい。新型コロナ患者の治療に真摯に取組めば取り組むほど膨大な赤字が出て、廃業に追い込まれる病院が各地で現出している。病院を辞める医師、看護師等も数多く生まれていると報じられている。これらは決して一過性の現象ではない。構造的な問題である。国民の命と健康を守る医療制度、医事法ではなく、国策に奉仕する医療制度、医事法となっているために、今回のような事態が発生すると、国民の命と健康を守れないだけではなく、医療制度自体も、そして医療従事者の勤務と暮らしさえも守れないという事態が生じることになる。
しかし、この構造的な問題だということを、専門家も含め、どれほど多くの人たちが知っているのか。多くの人たちはそのことを知らない。教えられていない。日本の医療はよくできている、先進国のそれと比べても勝るとも劣らないものだと信じている。その優れた日本の医療がどうしてこのような「医療崩壊」ともいえる事態を引き起こしているのか。多くの国民は戸惑っている。原因が分からないだけに大きな不安に襲われている。政府のみならず、国民もパンデミックの状態に陥っている。専門家もその原因と処方箋を提示できていない。
先進国の医療制度及び医事法を参考に、そして、その中には3度も違憲判決が言い渡されたハンセン病強制隔離政策の教訓も含まれているが、日本における数多くの医療事故、薬害の教訓に基づいて、日本の医療制度及び医事法について「正しい診断と処方箋」を提示することが本書の狙いということになる。医療従事者や法律家を含む多くの専門家、マスメデイア、そして国民もその情報をいまだ自己の物とするには至っていないが、ヨーロッパ諸国では、患者の権利法等という形で患者の権利を法制化し、この患者の権利を中核とする医事法に基づいて医療制度を拘制することによって、国民の命と健康を守る医療制度を実現し、「医療崩壊」の発生を防止し、医療従事者と患者・家族の信頼関係を確保し、医療従事者の勤務とくらしを守ることとしている。
医療事故、薬害の被害者の方々も患者の権利の法制化を強く望んでおられるが、日本では、それが今も実現できていない。真の医学教育、医事法教育が圧倒的に不足しているためである。
この医療教育、医事法教育は医学部生のためだけのもの、法学部生のためだけのものでは決してない。すべての国民は病気と無関係ではない。とすれば、医学教育、医事法教育はすべての国民にとって必須不可欠のものということになる。しかし、そのための体系書も圧倒的に不足している。これまで出版された医事法の本の多くは、現行の日本の医事法の説明に終始しており、「正しい診断と処方箋」を国民に提示しているとは到底言えない。
もっとも、これもやむを得ないといえるかもしれない。医療制度は多角的な側面を持ち、これに応じて医事法も多角的な側面を持つからである。すなわち、①国・自治体と医療施設及び医療従事者との関係、②医療施設及び医療従事者と患者・家族の関係、③国・自治体と患者・家族の関係、という3面関係がそれである。①は法学の分野では行政法の分野に属する。②は民法の分野に属する。③は福祉法の分野に属しする。したがって、医事法は、行政法、民法、福祉法をすべて包含した法分野ということになる。
しかし、法学研究、法学者は細分化されているために、このように多分野にまたがる医事法に手を出すことを避けてきたきらいがある。一部の民法の研究者が主にアメリカ法等を参考に、②を中心にして医事法を講義してきたというのが現状である。
これでは、医事法の全体像を把握することが困難となる。患者の権利の理解も不十分ということになる。患者の権利は、この3面関係のすべてに及ぶからである。医療従事者の勤務と生活を守るということも問題の外ということになってしまう。ヨーロッパに見られるような、弁護士会自治に匹敵する「医師会自治」といったことにも視野が及ばないということになる。それは主として①に属する問題といえるからである。国・自治体が一方的に医療従事者を管理・監督し、国策に奉仕させているという面に焦点をあて、専門家自治と専門家規律に基づいて編み出される科学的知見を国・自治体が尊重し、その医療行政に反映させる仕組みになっているヨーロッパ諸国のそれと対比させるということが②の柱となる。他方、被害当事者の方が強く訴えられる「与えられる医療から参加する医療」への転換が問題となる局面は、②だけではなく③でも重要となる。②だけの医事法の講義ではそれを扱うのも難しいということになる。
このように、これまでの医事法の本は、量的に少ないだけでなく、内容的にも偏ってきた。これに対し、②だけではなく、①についても、③についても「正しい診断と処方箋」を提示したいというのが本書の狙いである。①にも②にも③にもかかわるというのが刑事法の特徴である。①でも②でも③でも規律の強制という問題が生じるからである。そのために、時には問題が刑事裁判にまで至ることもある。刑事法研究者が医事法を最もよく論じ得るといえるかもしれない。