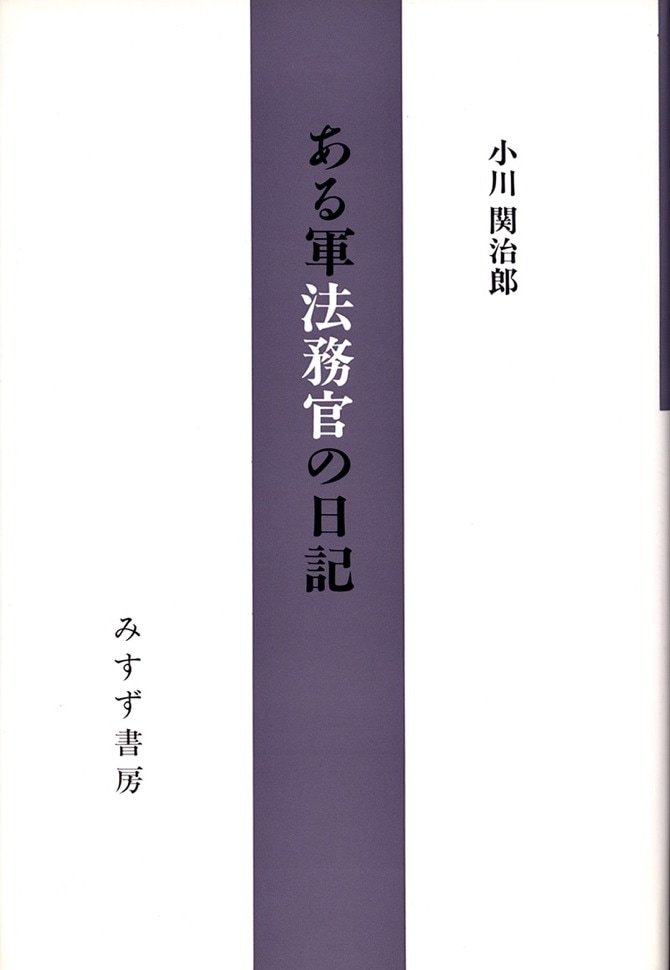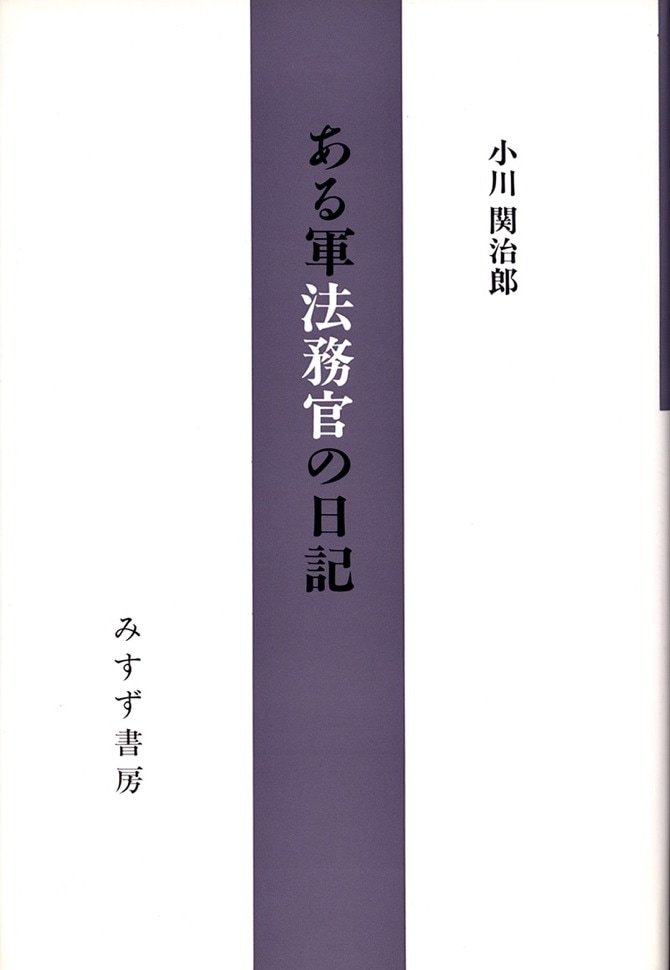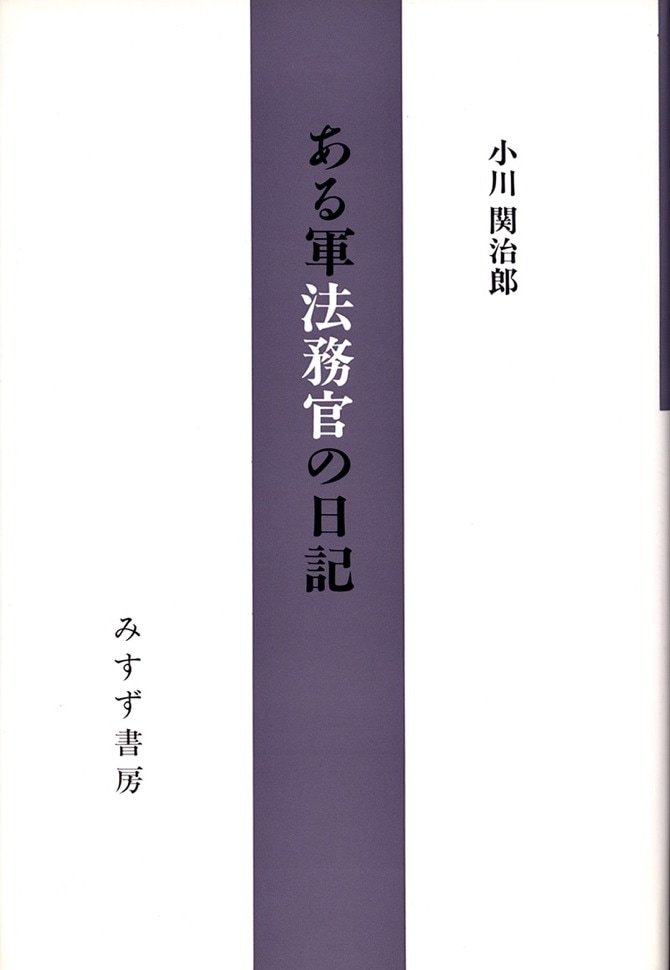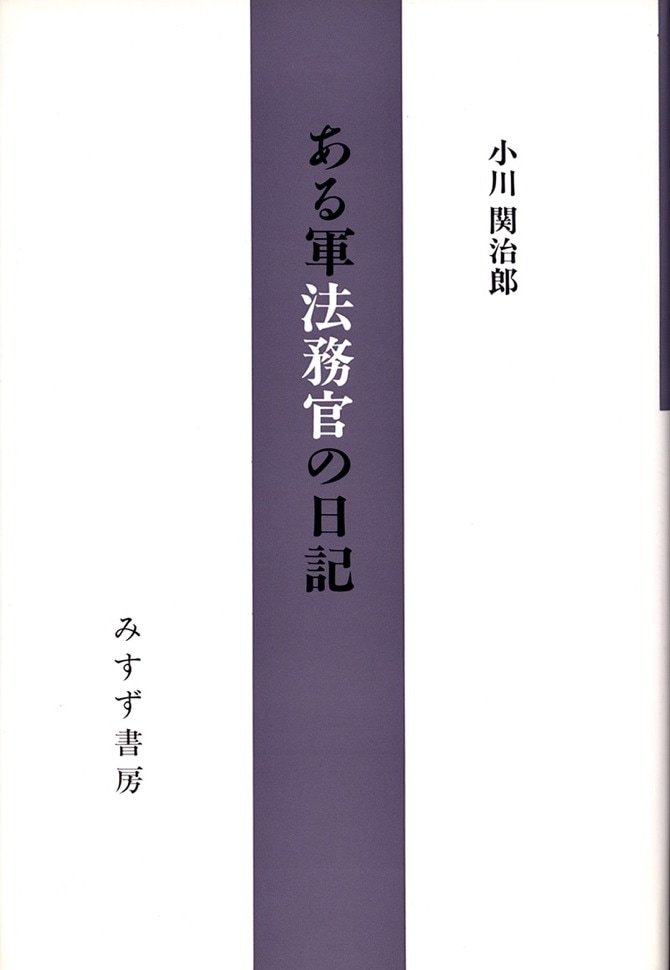大杉栄らを虐殺した甘粕正彦大尉、軍務局長・永田鉄山を斬殺した相沢三郎中佐、二・二六事件の青年将校たちの黒幕と目された真崎甚三郎大将——彼らを裁く軍法会議に、裁判官として陸軍法務官・小川関治郎は臨んだ。いわば、昭和史の転換点を法廷から見たのである。
それにしても陸軍法務官とは、あまり聞き慣れぬ存在である。近代国家の軍隊組織のなかで、法に照らして軍の規律を維持する任に当たったのが、憲兵と法務官であったが、軍事警察の憲兵に比しても、その存在は遙かに知られていない。
本書は、その陸軍法務官であり、歴史的裁判にも臨んだ人が、中国に侵攻する軍と行を共にしたさい、その個人的観察と印象を綴った日記である。期間は、昭和12年10月から翌13年2月まで。その間、松井兵団と共に、陥落した南京に入城した。軍隊の秩序維持の職責にある者として、また戦闘集団のなかで軽視されがちなその職責を果たそうと努めた者として、彼がそこで見たものは何であったのか。あるいは見えなかったものは何であったのか。
戦争の大義を信じた彼は、後世から見れば歴史に敗れた者かもしれない。しかし、法務官という立場ゆえに感じざるを得なかった矛盾を語る言葉もまた、真実である。いま、歴史的議論の前提に、その言葉に耳を傾けることも必要なことであろう。