崇高なるプッサン
SUBLIME POUSSIN
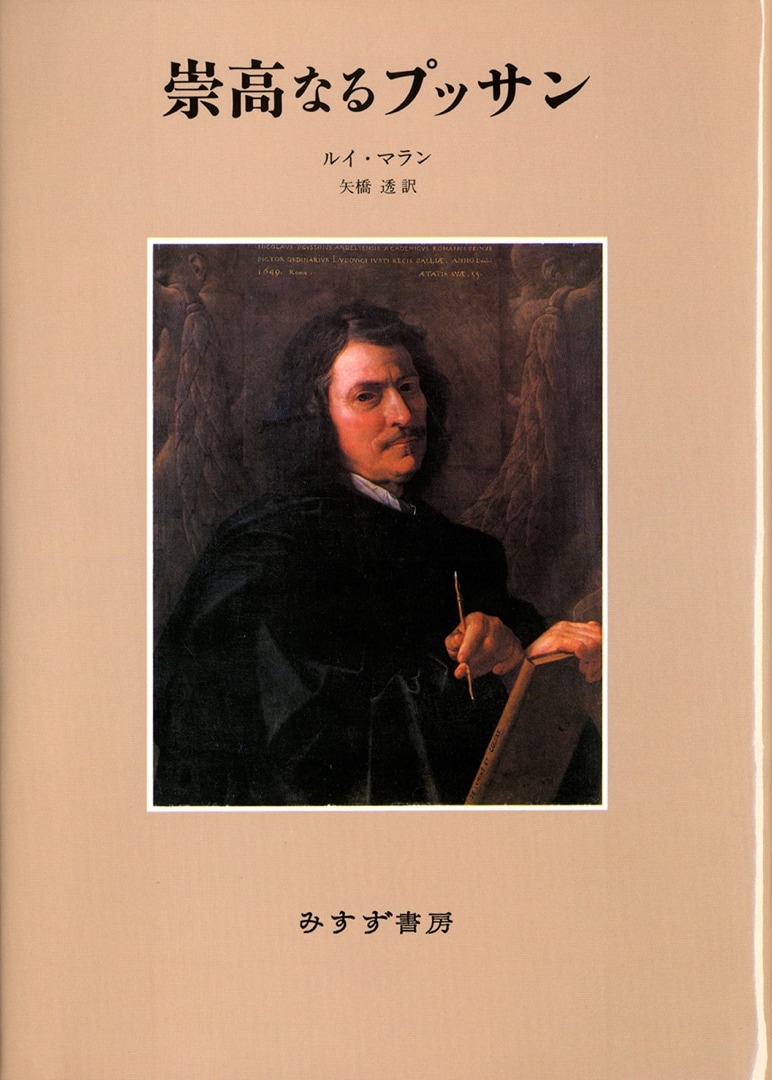
| 判型 | A5判 |
|---|---|
| 頁数 | 266頁 |
| 定価 | 4,950円 (本体:4,500円) |
| ISBN | 978-4-622-04405-5 |
| Cコード | C3010 |
| 発行日 | 2000年12月15日 |
| 備考 | 現在品切 |
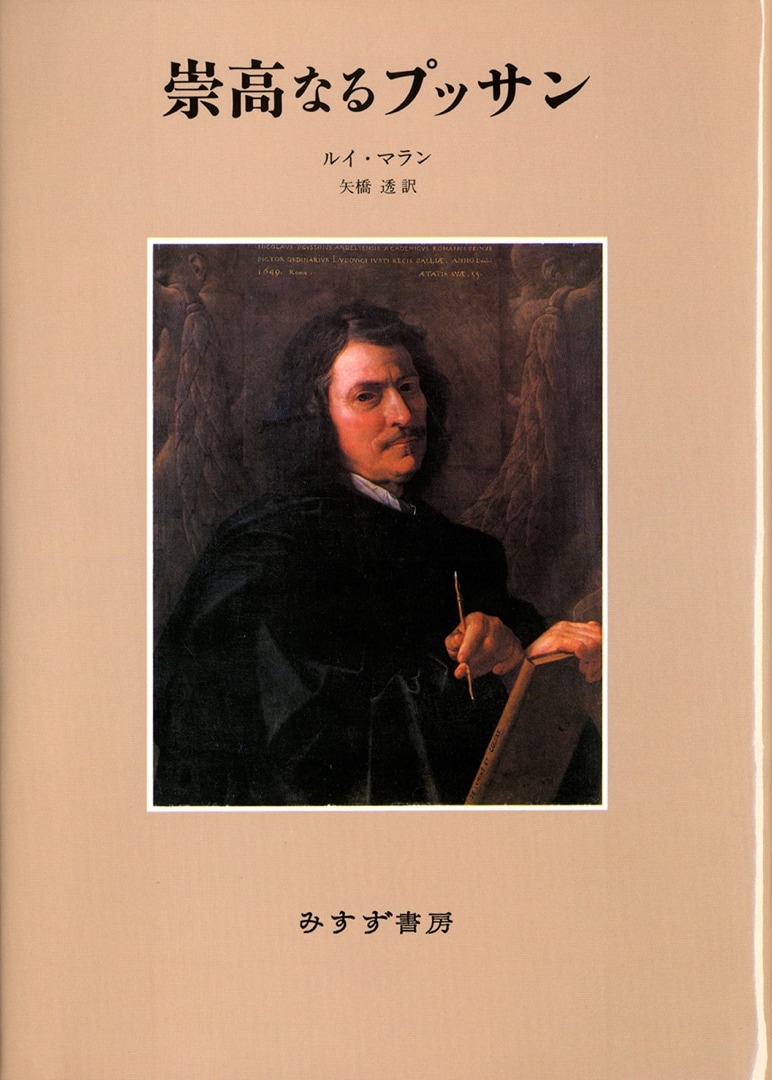
SUBLIME POUSSIN
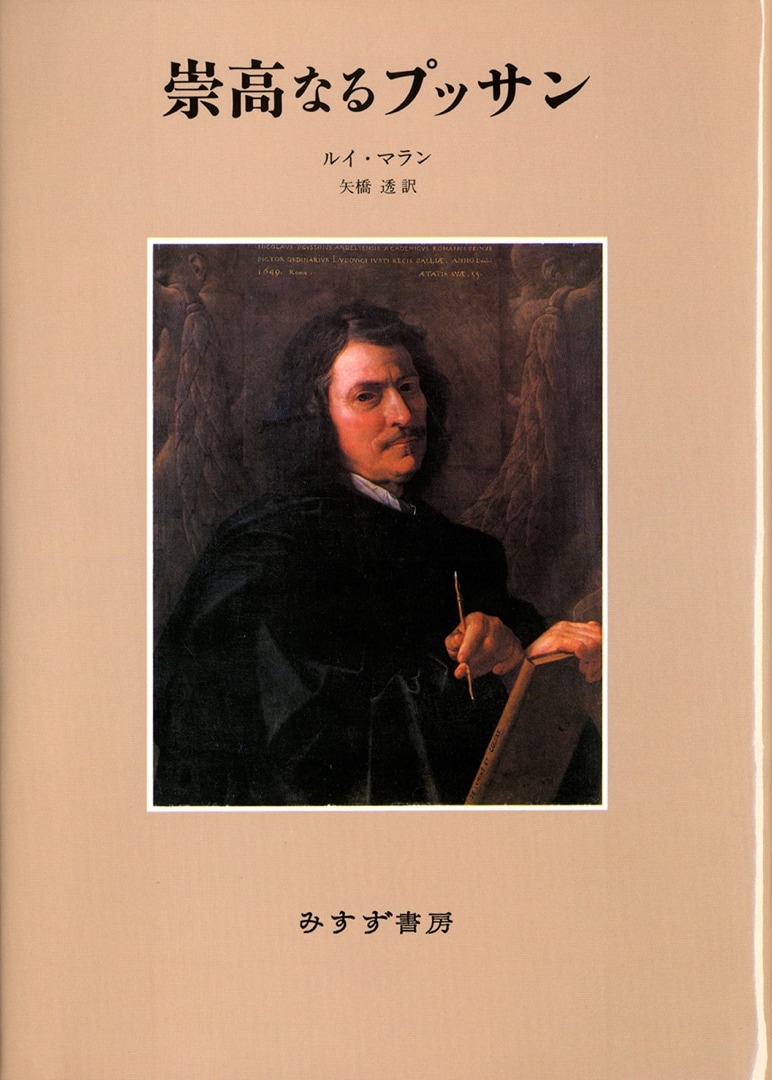
| 判型 | A5判 |
|---|---|
| 頁数 | 266頁 |
| 定価 | 4,950円 (本体:4,500円) |
| ISBN | 978-4-622-04405-5 |
| Cコード | C3010 |
| 発行日 | 2000年12月15日 |
| 備考 | 現在品切 |
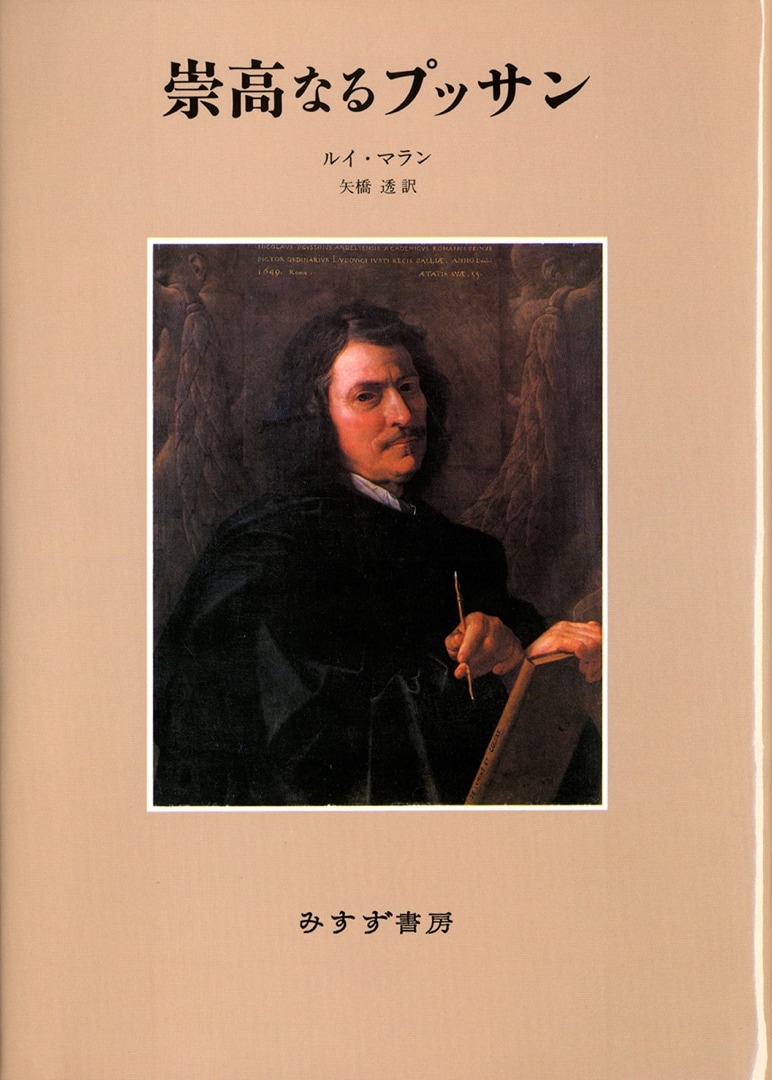
絵画における崇高は、はかり知れないことによって逆説的に形づくられる。崇高とは、崇高の理論の不可能性のことであり、その不可能性の〈異形化〉である——
著者は晩年、17世紀古典主義を代表する画家ニコラ・プッサンに、その思考を集中させていた。本書には、絵画の記号学のマニフェストとして名高い「画像の描写」から、プッサンの『アルカディアの牧人たち』を扱ったパノフスキーの論文〈Et in Arcadia ego〉への透徹した批判、フーコーの『ラス・メニーナス』論に匹敵する表象の網の目の精緻な解読である二枚の自画像論、風景画を素材に〈崇高〉の問題を扱った論文群にいたるまでの9章に、付録4編を集成する。
そこで展開されるのは、美術批評の白眉ともいえるスリリングな言説であり、一見何気ない慎ましい外観を呈するプッサンの絵画から、「表象しえないものとしての崇高の問題」を経由することで、17世紀のコンセプチュアル・アートとも言うべき驚くべき思考の痕跡と、見る者の欲望に無限に開かれた揺動する形象の戯れが浮かび上がってくる。
現代フランスを代表する美術批評家・思想家であったルイ・マランの遺著。