理性の使用
ひとはいかにして市民となるのか
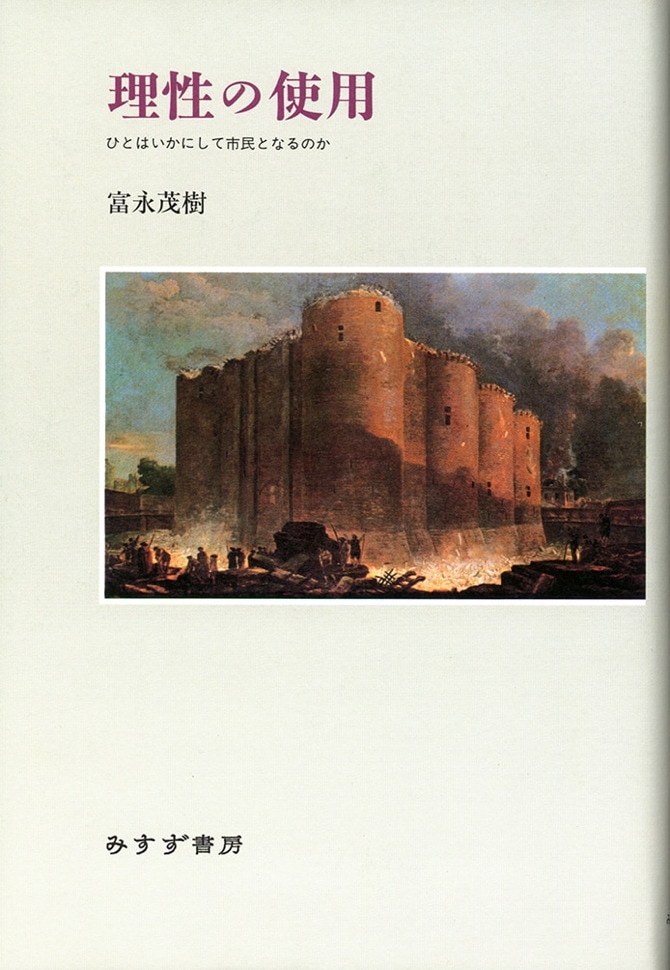
| 判型 | 四六判 |
|---|---|
| 頁数 | 272頁 |
| 定価 | 4,180円 (本体:3,800円) |
| ISBN | 978-4-622-07130-3 |
| Cコード | C1036 |
| 発行日 | 2005年1月24日 |
| 備考 | 在庫僅少 |
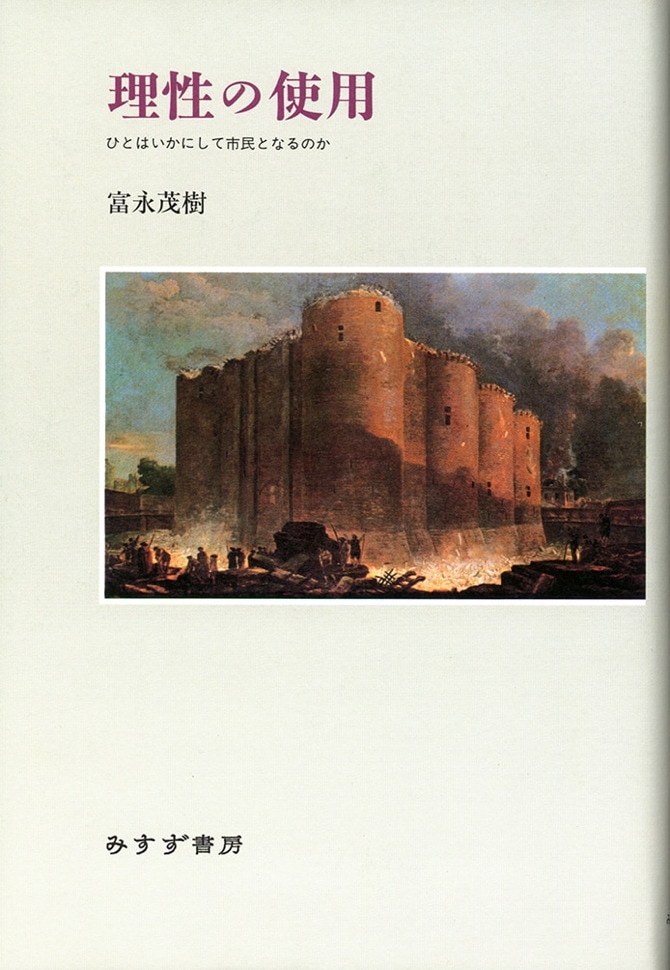
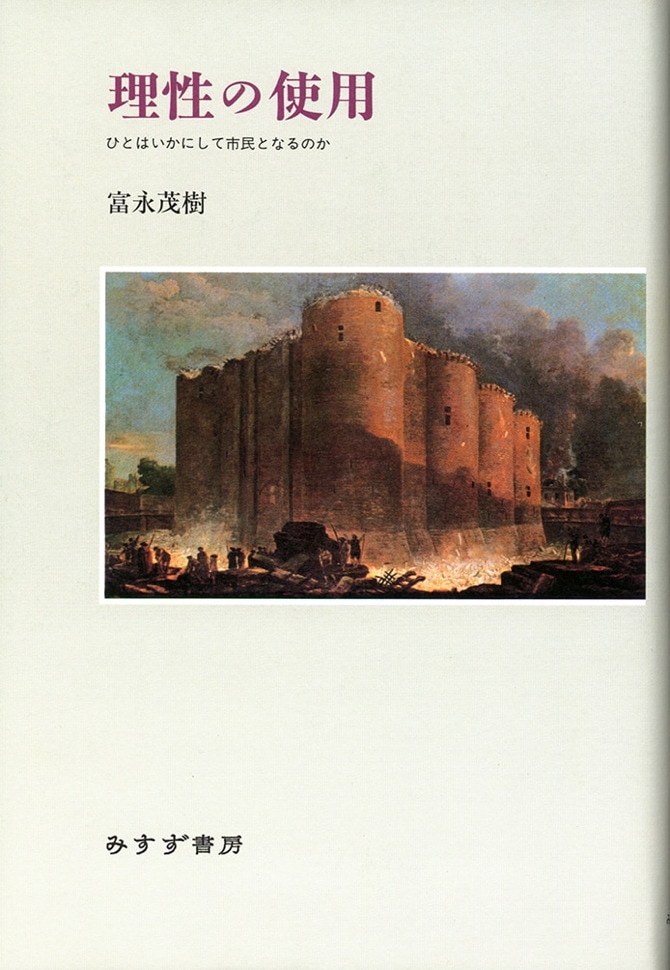
| 判型 | 四六判 |
|---|---|
| 頁数 | 272頁 |
| 定価 | 4,180円 (本体:3,800円) |
| ISBN | 978-4-622-07130-3 |
| Cコード | C1036 |
| 発行日 | 2005年1月24日 |
| 備考 | 在庫僅少 |
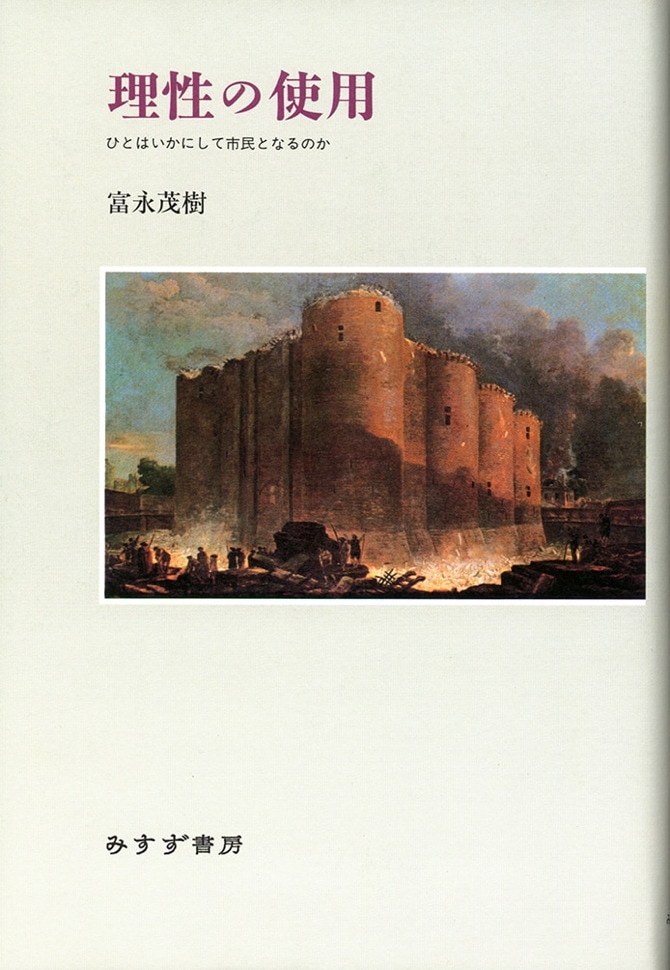
カントは「啓蒙とはなにか」という問いに答えて、それが、「未成年状態からの脱却」つまり他者に指導されることなしに自身の悟性を使用できる状態に到達することであると述べ、そのために必要なのは「理性の公的な使用の自由」であると説いた。
そして、フランス革命期においてもっとも有名になったパンフレット『第三身分とはなにか』でシエースは、「第三身分はなにを要求するのか」に「なにものかになること」ときっぱりと応答することになる。
本書は、18世紀後半に、また革命期に構想され、しかしさまざまな困難に遭遇した啓蒙と市民の形成にかかわる議論、コンドルセの教育論からシエースの社交に対する無関心を示唆する言説、さらにはピネルの狂人の社会化をめぐる論理などを、力強くしなやかに分析・批評してゆく。
世界のなかに散らばりながら、読書をとおしてみずからを啓蒙し、公衆の一部としての市民になる人間存在。その社会化や社交、コミュニケイションという具体的な場に理性をおくことで、それがもつ政治的性格を明らかにし、さらには、理性の使用が語られるさまを見ることによって、近代以降の世界に生きるわれわれ自身のありようにまでかかわる問題にふみこむ本書は、現代の学問水準を示すとともに、ひととひとの交流について示唆を与えてくれるだろう。
船と駱駝、18世紀の終わりころに開始したのを確認できる事態にとってぜひとも必要なもの、世界のなかに散在し、あるいはその片隅に閉じこもっているわれわれに、あらためてコミュニケーションを可能にしてくれると『永久平和論』のカントが奨めるものはいったいどこで出会えるのだろうか。
いや、どこへ行けばよいのかは実はそれが必要であると知った時点からすでにわかっていたのだ。だからともかく今いる場所を離れるだけでよい。よく見わたすなら船も駱駝もいたるところにいる。われわれはただ、ある思考方法に囚われてここから離脱することを知らないでいるだけなのである。
コンドルセの採用した、そしてフーコーの言葉を借りるなら「人口」という視点で社会を眺める考えかたは、人間を個々の存在から無限大に遠ざかった人類というところにおくが、同じ視点はまた個人を、社会から自身を切り離して無限小に局地化させる。極端な広がりと極端な縮小、そのふたつを奇妙に重ねあわせることで、他にも生きる場所があるとは教えてくれない思考がわれわれを支配している。
そんな思考に囚われていては、離脱を考えることさえできなかったはずである。それから200年あまりを経て、メディアの高性能化と多様化はたしかに書物を乗り越えたかもしれないけれど、ケータイやインターネットが船や駱駝の役割を果たすとは期待できないだろう。なぜならわれわれはやはり思考方法を変えようとはしていないのだから。
そこから脱け出すこと、だがそのためにはまずそうした思考自体について知ることが問題であり、それこそが「啓蒙の困難」や「中間集団の消滅」、「読む機械の出現」といった事態そのものにもまして、今回の本の最大の主題なのだった。(2005年3月 富永茂樹)