社会生物学論争史 1
誰もが真理を擁護していた
DEFENDERS OF THE TRUTH
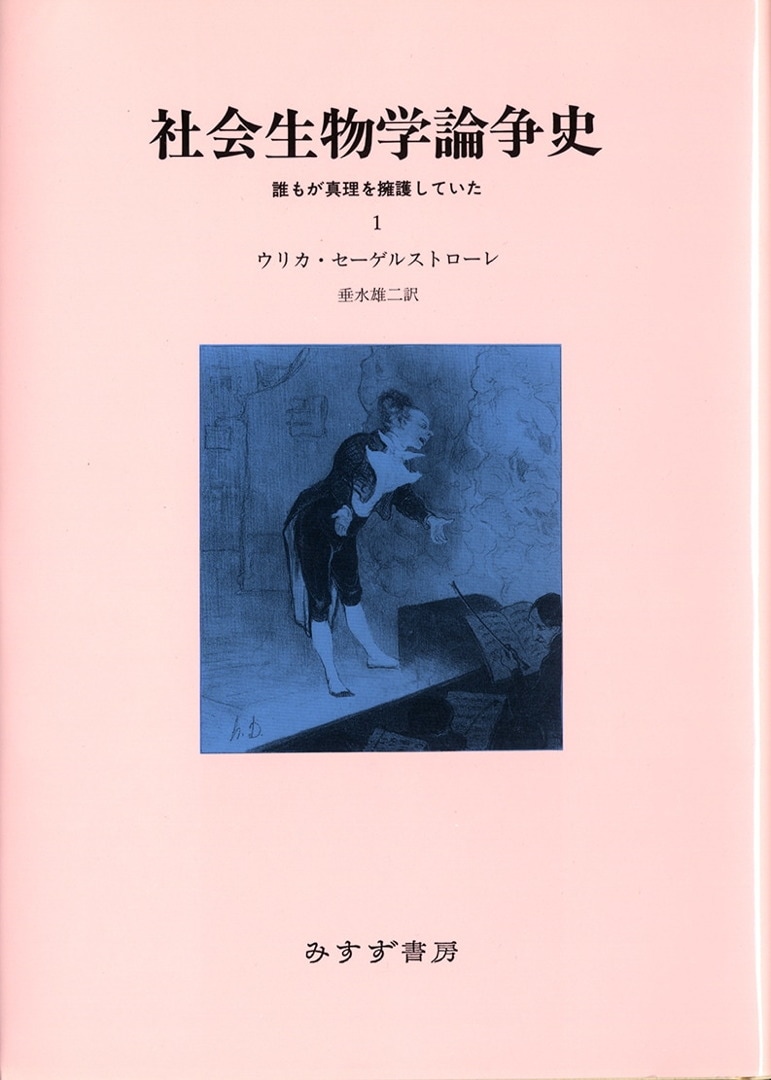
| 判型 | A5判 |
|---|---|
| 頁数 | 376頁 |
| 定価 | 5,500円 (本体:5,000円) |
| ISBN | 978-4-622-07131-0 |
| Cコード | C1040 |
| 発行日 | 2005年2月22日 |
| 備考 | 現在品切 |
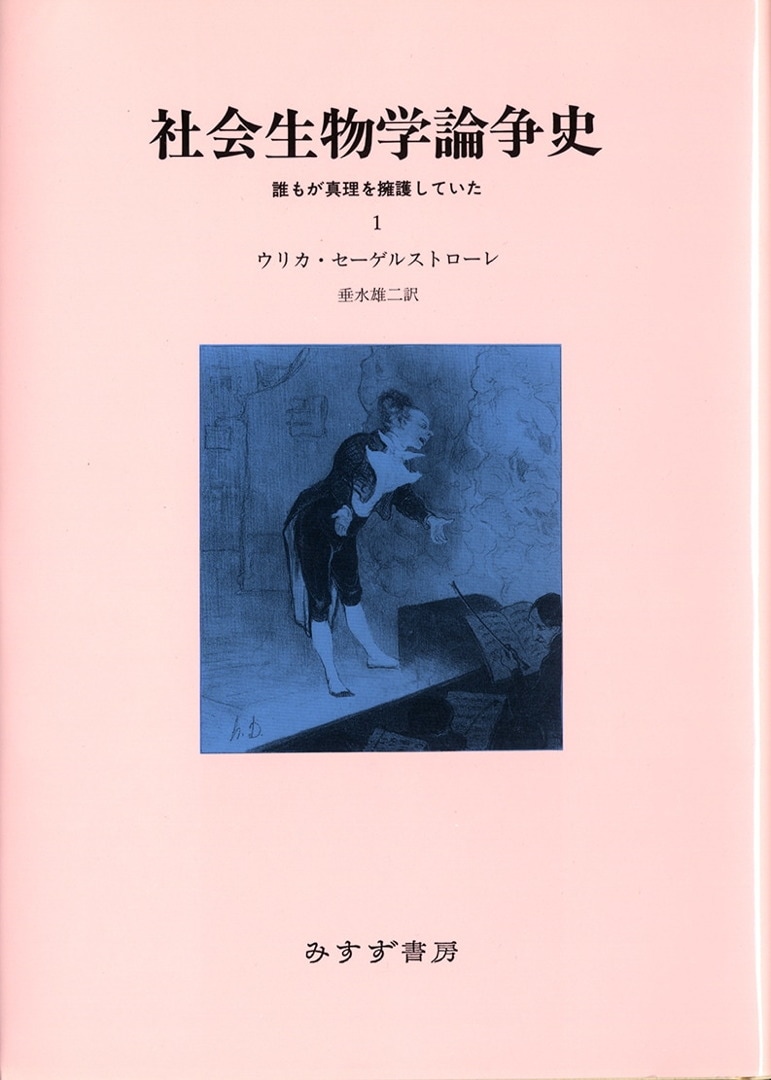
DEFENDERS OF THE TRUTH
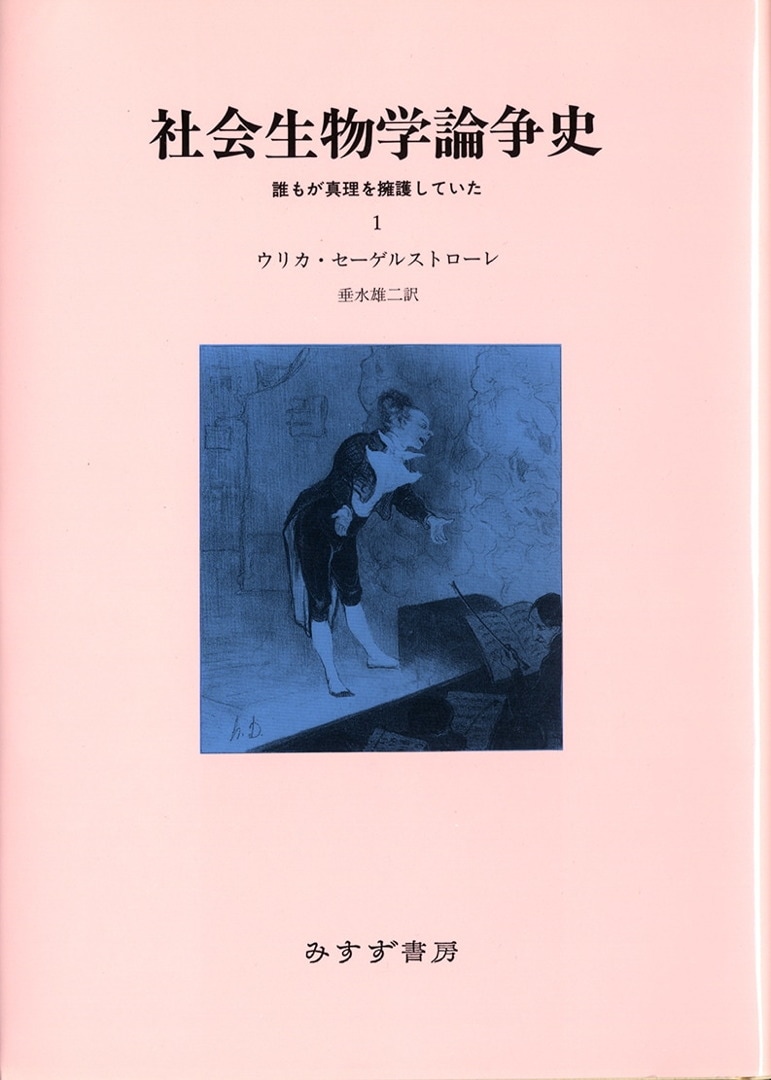
| 判型 | A5判 |
|---|---|
| 頁数 | 376頁 |
| 定価 | 5,500円 (本体:5,000円) |
| ISBN | 978-4-622-07131-0 |
| Cコード | C1040 |
| 発行日 | 2005年2月22日 |
| 備考 | 現在品切 |
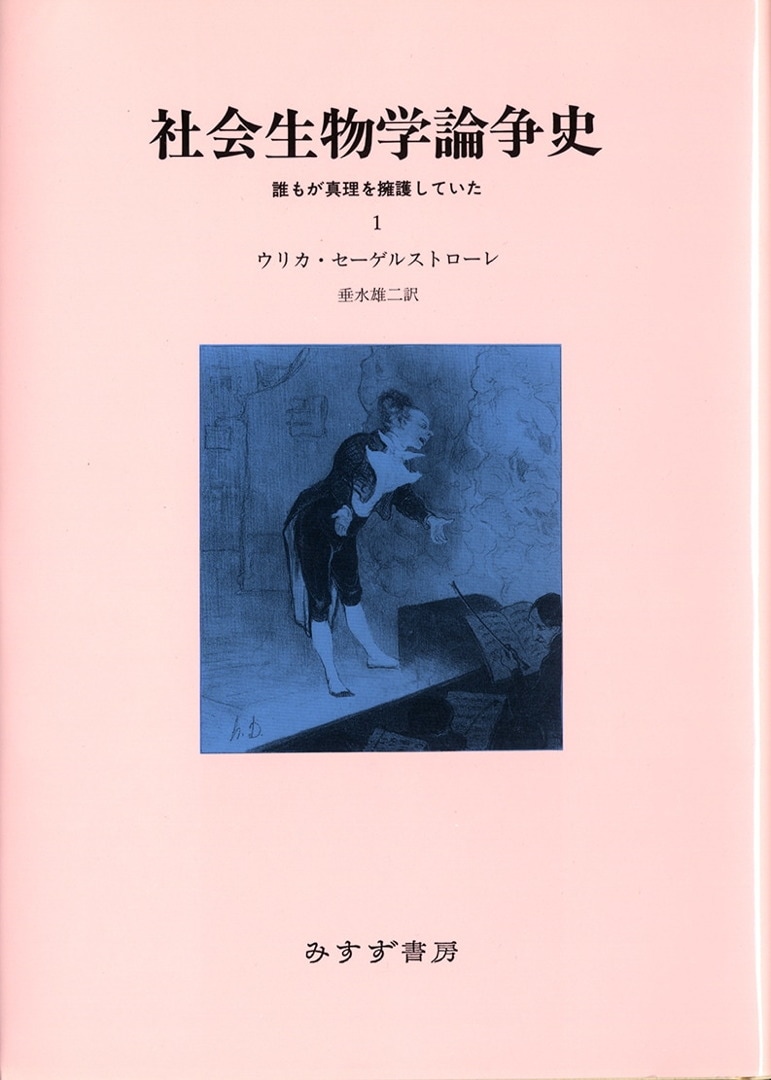
エドワード・O・ウィルソンの大著『社会生物学』(1975)は、出版されるやたちまち非難の嵐を巻き起こした。とりわけ動物行動の研究を人間社会に適用すると明言したその最終章をめぐって、社会の現状維持を正当化し人種差別を肯定する悪しき遺伝子決定論であるとの批判が向けられたのである。
論争はイギリスにも飛び火し、やがてドーキンスとグールドは、やや論点をずらしながら、大洋をはさんで果てしなく思われる応酬をくり広げていく。だが、四半世紀をへて、社会生物学は一方でたとえば進化心理学のような学問分野を生み、また論議の焦点のいくらかはサイエンス・ウォーズやヒューマン・ゲノム・プロジェクトのほうへ移り、等々、社会生物学論争は、少なくともほぼ、終幕を迎えているといっていい。あの仮借ない戦いは、何だったのか。
著者セーゲルストローレが科学社会学者としてインタヴューする相手は、グールド、ドーキンス、メイナード・スミス、ハミルトン、メダワー、ルリア……もちろん〈首魁〉ウィルソンとルウォンティンをはじめ、論争の立役者のほぼすべてから、ゴシップも含む得がたい証言を一手にあつめた。そこにきわめてバランスのとれた迫真の考察を加え、セーゲルストローレは論争の顛末を一気に語りおろす。社会生物学論争に言及するとき、本書を避けては通れない。全2巻。
はじめに
1 真理をめぐる闘いとしての社会生物学論争
科学的真理と道徳的真理は同じものか/学問的な工作としての社会生物学論争/オペラに見立てた社会生物学論争
第一部 社会生物学論争で何があったのか
2 社会生物学をめぐる嵐
創り出された社会生物学論争/まじめな科学的批判の欠落/社会生物学研究グループの活動/社会生物学論争は回避できたか/「環境主義」パラダイムの優越
3 衝突に突き進む同僚——ウィルソンとルウォンティンの正反対の道徳的かつ科学的課題(アジェンダ)
大物どうしの激突/ウィルソンの実証的プログラム/ルウォンティンの批判的な課題/嗜好の問題
4 英国派とのつながり
群淘汰から血縁淘汰へ——集団的改宗か科学的雪崩現象か/ビル・ハミルトン——孤独の人/メイナード・スミスと逸した機会/ジョージ・プライス——原理主義(ファンダメンタリズム)を奉じた科学者/コップの中の嵐か——ドーキンスと英国における論争
5 社会生物学の秘められた背景
ハーヴァード大学によるハミルトンの発見——トリヴァースとデヴォア/相互扶助論/〈人間と動物〉会議——触媒的な出来事/ウィルソン流の社会生物学——ある目的のための総合/名前に何かがあったのか——「社会生物学」がはらむ意味
6 適応主義への猛攻——遅ればせの科学的批判
適応主義のどこがまちがっているのか/完璧な人間などいない/サンマルコのスパンドレル——ロイヤル・ソサエティをうろたえさせたグールドとルウォンティン/スパンドレルへの反応/もと適応主義者の懺悔/トロイの木馬としての社会生物学論争/断続主義に断点を入れる
7 淘汰の単位と、文化との関連
淘汰の単位をめぐる論争における真と誤り/ハーヴァードの全体論と英国のお手玉遺伝学/淘汰のレヴェル——存在論的異議申し立て/文化の問題/ハミルトンの「人種差別的」論文/遺伝子は必要か
8 批判に適応する社会生物学——『遺伝子・心・文化』
社会生物学は自らをつくり変える——それとも?/メイナード・スミス数式をチェックする/ルウォンティン屈辱を感じる/エドマンド・リーチはエソロジーがお好き
9 道徳的/政治的対立はつづく
新しい潮流の台頭/「人種差別主義者」という誹謗と反論/ナビのエピソード——科学におけるマナーとモラル/批判者たちは実証的プログラムを考案する/もうたくさんだ! と社会生物学者たちは言う/誰がまちがったのか
用語解説
三幕のオペラに見立てて語りおろす社会生物学論争の四半世紀。いや正確には、終幕は近いがまだ幕は下りていないと著者セーゲルストローレは考えています。舞台には〈真理〉と〈明快)が登場して洪水のように光が当てられ、スモークは一掃されて、誰もが勝利を宣言し退場する、その場面は将来の増補版で書き加えられるかもしれないと。
筆の立つ著者のこと、ウィルソンが水差しの氷水を頭から浴びせられた有名な1978年の全米科学振興協会(AAAS)集会の事件はもちろん(セーゲルストローレは若い研究者として現場を目撃した)、ワーテルロー駅のベンチに座って髪をかきむしりながら血縁淘汰の計算をしている孤独な大学院生ウィリアム(ビル)・ハミルトンの肖像など、読後忘れられない。
社会生物学論争は、自然科学分野の、そのまた一部の生物学の、アメリカの研究者間に起きた限定的な争いなんかではない。ここに登場する、いわゆる文科系の学者たちの錚々たる顔ぶれ。たとえば社会人類学者ではマーガレット・ミード、マーシャル・サーリンズ、エドマンド・リーチ、等々。クロード・レヴィ=ストロースも「社会生物学は90%正しい」といったという一言で顔をのぞかせる。ミードを徹底的に批判することになるデレク・フリーマンは精細なウィルソン批判を展開する。ノーム・チョムスキーは社会生物学の批判者側から味方にひきいれようとさかんに働きかけられた。なにしろ、ウィルソンの主張では、人間社会を研究する社会科学と人文科学は将来、社会生物学の一分科にすぎなくなるであろうとも解釈されたから……。
三中信宏氏(『生物科学』2006年第2号)、松原洋子氏(『思想』2005年10月号)、大谷卓史氏(BIONICS、2005年10月号)、林真理氏(『図書新聞』2005年10月15日号)、青野透氏(『日経サイエンス』2005年8月号)、渡部潤一氏(『読売新聞』2005年4月24日号)、渡辺政隆氏(『朝日新聞』2005年4月10日号)ほか書評多数。
なおE. O. ウィルソン『社会生物学』の邦訳は、1300ページをこす大冊で新思索社から出ています。