〈科学ブーム〉の構造
科学技術が神話を生みだすとき
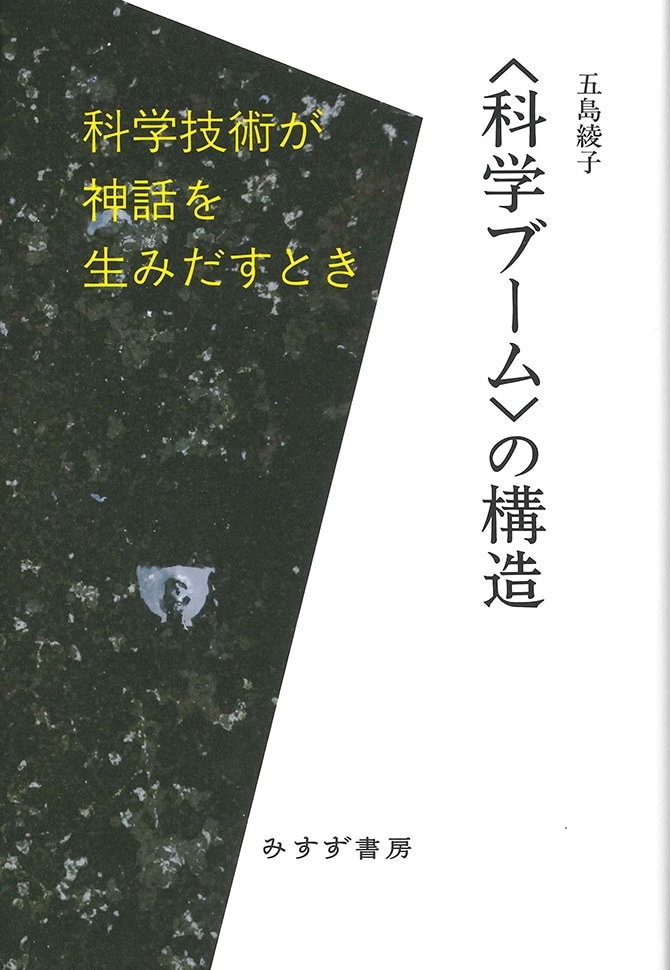
| 判型 | 四六判 |
|---|---|
| 頁数 | 288頁 |
| 定価 | 3,300円 (本体:3,000円) |
| ISBN | 978-4-622-07840-1 |
| Cコード | C0040 |
| 発行日 | 2014年7月9日 |
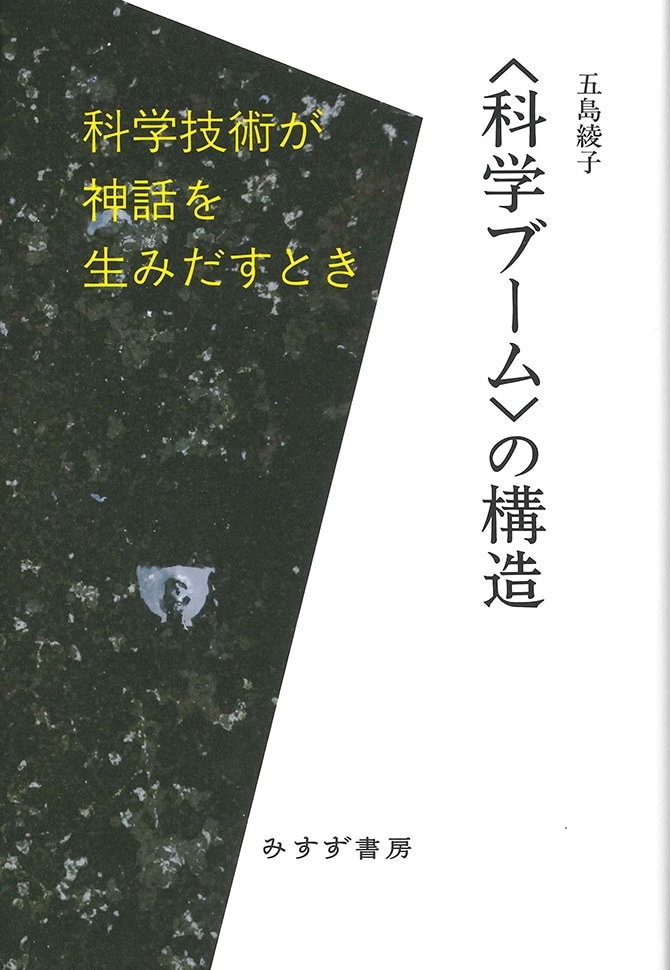
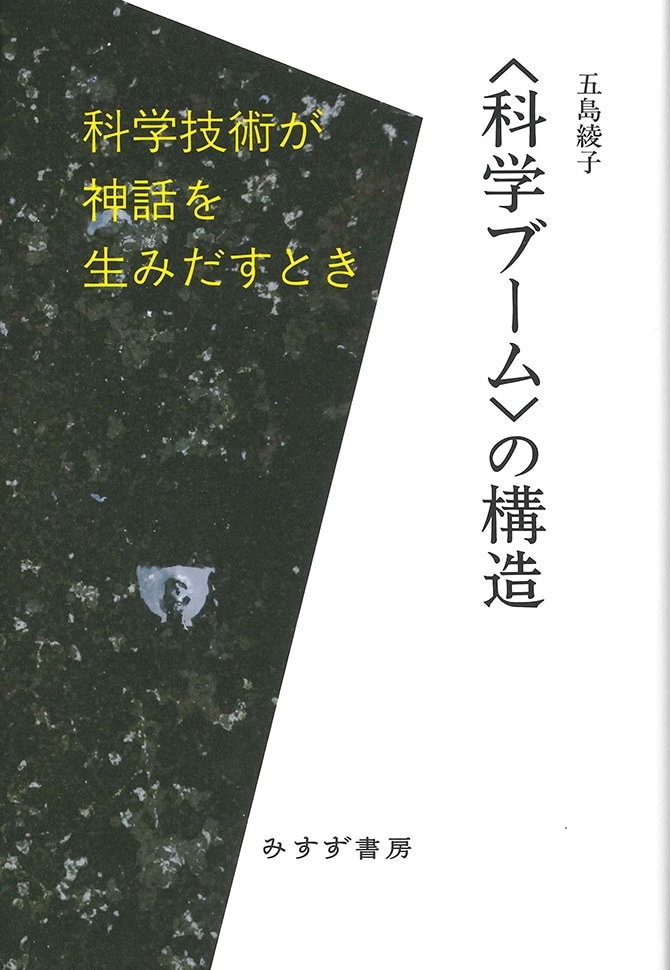
| 判型 | 四六判 |
|---|---|
| 頁数 | 288頁 |
| 定価 | 3,300円 (本体:3,000円) |
| ISBN | 978-4-622-07840-1 |
| Cコード | C0040 |
| 発行日 | 2014年7月9日 |
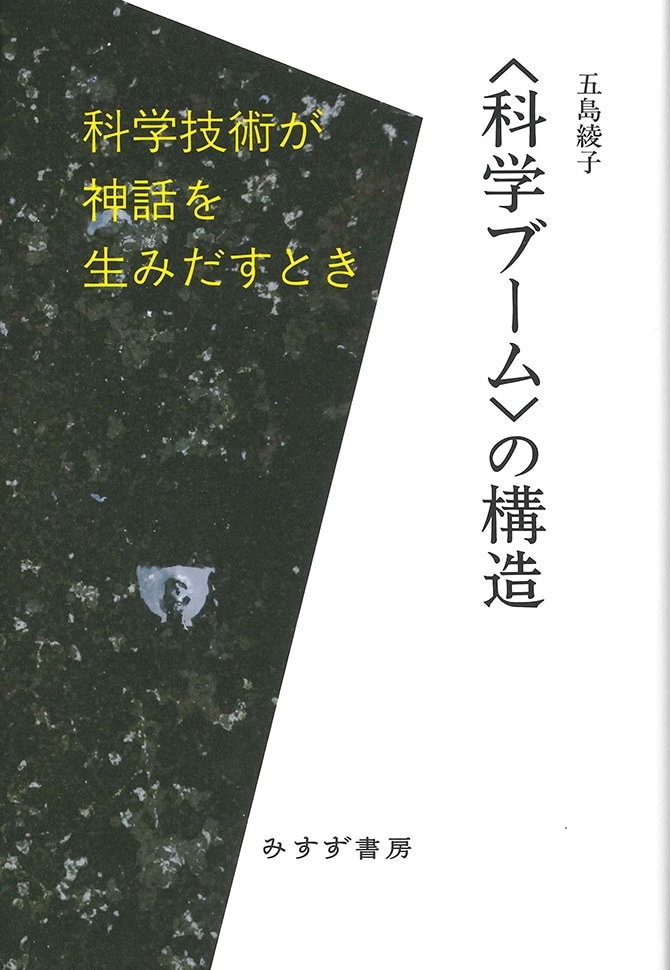
本書に言う〈科学ブーム〉とは、特定の科学技術に対する社会的関心が急激に高まり、個人・企業・国や自治体に対して、その関連研究や関連商品への投資(購買)が煽られる現象である。マイナスイオン・ブームや超伝導ブームなど、近年の事例も複数思い浮かぶほど、現代社会においてはこうしたブームの盛衰が絶えない。その渦中では科学技術の効能が報道メディアを通じて誇大に喧伝され、先端科学技術の難解さに乗じた「神話」がつくりだされ、ブームの維持のために利用される。科学技術への不信や盲信、そして利権の問題も、多くはブームに関連して生じているのである。
漠然とした科学技術への期待や依存心、あるいは漠然とした科学不信・科学者不信の気分がどのように仕掛けられ、科学技術の現実や既存の社会状況とどのようなチャンネルを通じて作用し合い、科学と社会の趨勢を動かすに至るのか? 事例研究の対象として50-60年代の殺虫剤DDTのブームと90-2000年代のナノテクノロジーブームをとりあげ、熱狂の拡大と終息の過程をたどり、ブームが生みだす神話とその裏にある科学技術の実像の関係性をあぶりだす。メディア、行政、専門家、産業界など、ブームに加担する各種アクターたちの動向のパターンも浮彫りにする。
ブームに踊らされずに科学技術の展望を見極めるには、どのような視点が必要なのだろう。小手先の教訓ではなく、科学の見方そのものを会得するための必読書。
はじめに
科学技術のブームとは
科学の世界における神話
自然科学の世界になぜ神話が?
神話が語られるとき
科学的思考と神話
科学の評価と神話
本書の目的
本書の問い
化学史の中でみる二つの事例の関係性
有機化学の誕生と展開
DDTと『沈黙の春』
ナノテクノロジーへ
専門家と専門家コミュニティ
専門家と非専門家の線引き
専門家とは
学問の細分化
社会における専門家コミュニティの役割
科学的定義と専門家コミュニティ
冥王星騒動と惑星定義委員会(IAU)による定義
科学的不確実性を伝える役割
アメリカの研究促進体制
第一章 DDT殺虫剤をめぐるブームと神話
テクノロジーとしてのDDTの確立
一九世紀後半、研究開発型ベンチャーの成長の時代
理想の条件をもつ殺虫剤とは
DDTブームの構造と神話を読み解く
DDTブームが生まれた土壌
殺虫剤をめぐる研究促進体制
ヒ酸鉛の代替殺虫剤として
軍事テクノロジーとしてのDDTの成功
軍部に協力する科学者コミュニティと財団
ロックフェラー財団の活動
DDTブームIの勃興
戦略的軍事利用の成功
メディアの力
マラリア制圧とDDTの評価
軍事利用から農業用へ
DDTブームIの遺したもの
ブームIからブームIIへ
マイマイガ根絶作戦
専門家たちの動向
ブームIIの社会的背景
DDTの大量生産・大量消費
危機の先ぶれ
生態系への影響の研究
米国魚類・野生生物局
生物学の主流から外れて
研究促進体制の中での論争
DDTブームI・IIの影響
殺虫剤のイノベーション
抵抗性の問題
クリア湖のカイツブリの悲劇
発ガン性への注目
第二章 『沈黙の春』とDDTブームの崩壊
『沈黙の春』は何を問うたか
『沈黙の春』の登場
DDTの生態系への拡散
カーソンと産業界、科学界の関係
専門家の対立と和解
DDT規制
DDT全面規制に至るまで
DDTブームは新しい概念を生みだしたか
『沈黙の春』の検証
リスク学の誕生と市民参加
食物連鎖・生物濃縮の概念とカーソン
殺虫剤開発の新しい動き
環境主義思想の萌芽
DDTのWHOによる地域限定復活から見えてくるもの
ふたたび蔓延したマラリア
第三章 世界を駆けめぐったナノテク神話とブーム
サイエンス・フィクションと真実の間
世界を巻き込んだナノブーム
イノベーションを競い合う時代のブーム
地球環境問題との関連
迫られる「選択と集中」
研究費獲得競争の時代
極微の世界へのあこがれ
ナノテクノロジーに向かうアメリカの事情
軍事から経済へ
クリントン政権の狙い
ナノテクノロジーの政策化
第四章 アメリカのナノブームの構造と神話
ブームの火種
ファインマン神話
『創造する機械』
ドレクスラーの「アセンブラー」
分子製造の概念
走査顕微鏡の登場
NNIの発進
研究促進体制とブーム
ナノ・ハイプの役割
ドレクスラーを排除する
NNIの技術目標とナノブーム
化学者たちとドレクスラーの論争
リチャード・スモーリー
ジョージ・ホワイトサイズ
論争の意味
研究支援の場の構築
NNIのジレンマ
定義の曖昧さとブーム
汎用された定義
専門家コミュニティの定義
推進派と懐疑派
ナノブームの終焉後
第五章 科学・技術の歴史的展開とブーム
19世紀の三つの概念
20世紀の有機化学の展開
有機合成の時代
DDTブームとフォーディズム
巨大分子の合成へ
化学合成の限界と、生命体のものづくりへの関心
20世紀におけるナノテクノロジーへの収束
ボトムアップ型ナノテクノロジーへの流れ
原子・分子を「視る」から「操作する」へ
原子・分子がゆるくつながる──ナノ粒子の存在
自己組織化、自己会合と超分子化学
トップダウン型ナノテクノロジーへの流れ
ナノブームがナノテクノロジーに与えた影響
第六章 日本のナノブーム
日本に「ナノテクノロジー」が導入されるまで
科学技術基本法の成立と知の市場化
ナノテクノロジー戦略の導入
日本のナノブームの構造
メディア型のナノブームI
ナノブーム立ち上がりに影響を与えた科学者たち
市場型のナノブームII
カーボンナノチューブをとりまく神話
CNTがナノテクの中心
CNTがイノベーションを導く?
ナノ商品のブームの後に
CNT開発の巨大プロジェクト事例
ナノカーボン応用製品創製プロジェクト
応用研究が成功しなかった理由
日本のナノブームを振り返って
おわりに
謝辞
注記
索引