ノイズ
始まりの本
音楽/貨幣/雑音
BRUITS
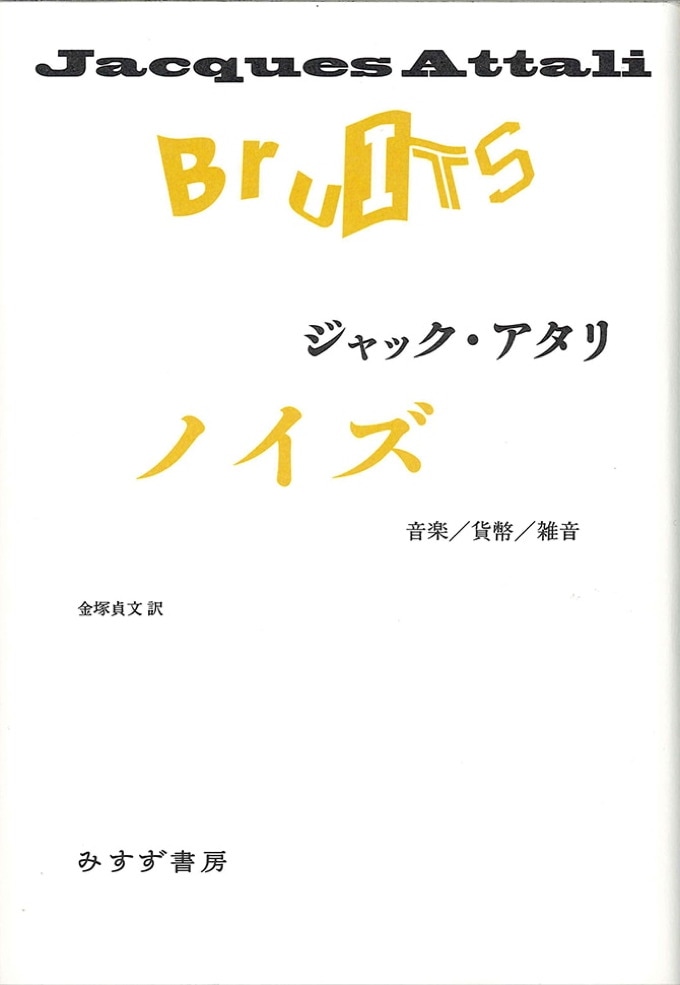
| 判型 | 四六変型 |
|---|---|
| 頁数 | 306頁 |
| 定価 | 3,520円 (本体:3,200円) |
| ISBN | 978-4-622-08351-1 |
| Cコード | C1310 |
| 発行日 | 2012年4月10日 |
| 備考 | 現在品切 |
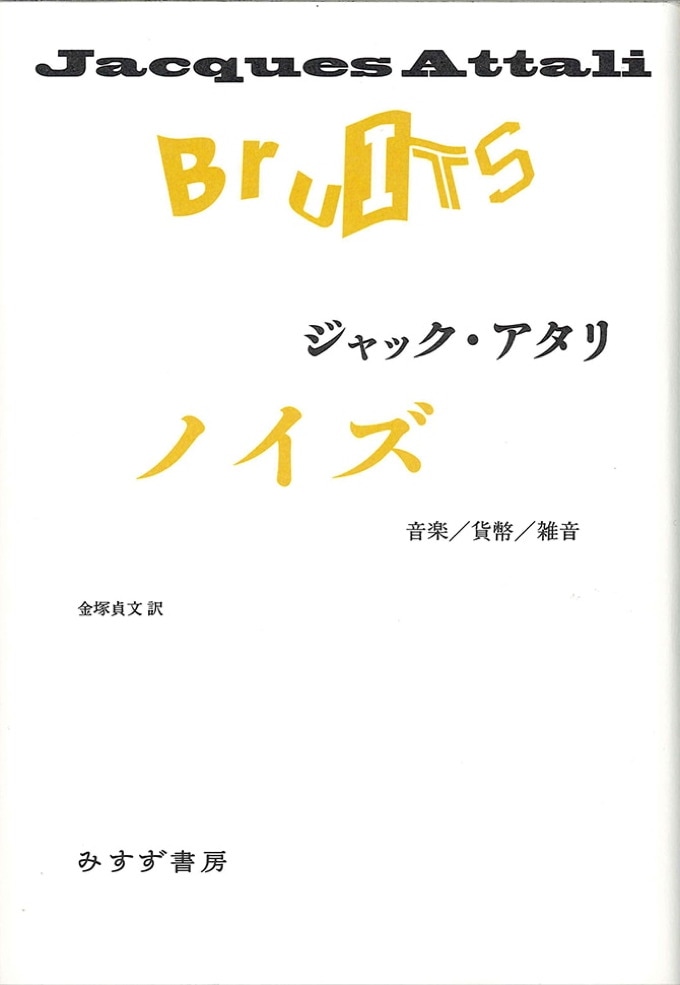
BRUITS
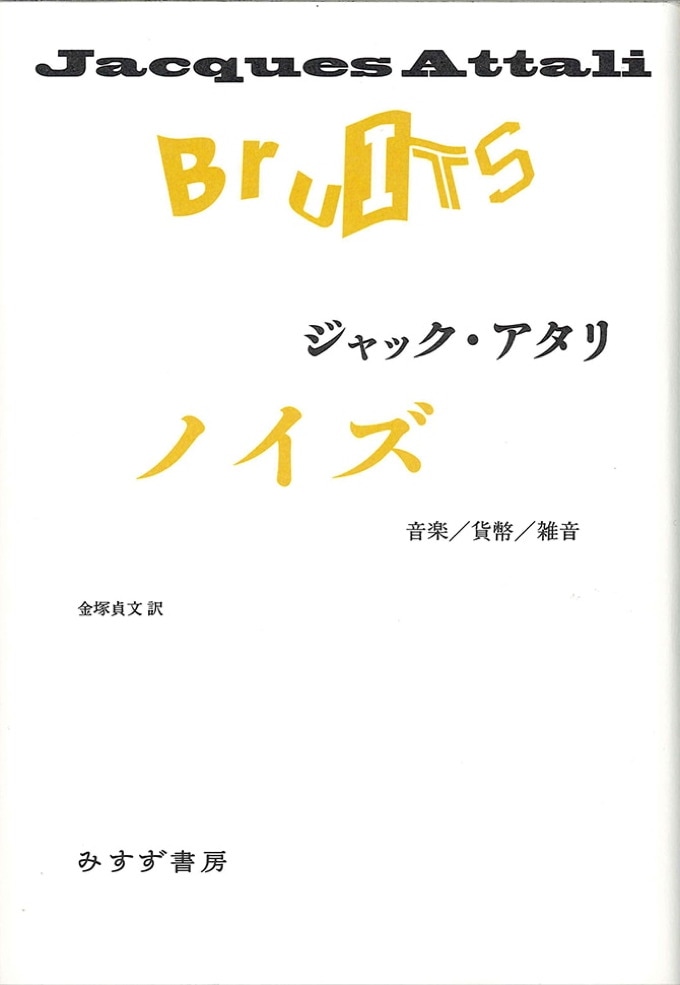
| 判型 | 四六変型 |
|---|---|
| 頁数 | 306頁 |
| 定価 | 3,520円 (本体:3,200円) |
| ISBN | 978-4-622-08351-1 |
| Cコード | C1310 |
| 発行日 | 2012年4月10日 |
| 備考 | 現在品切 |
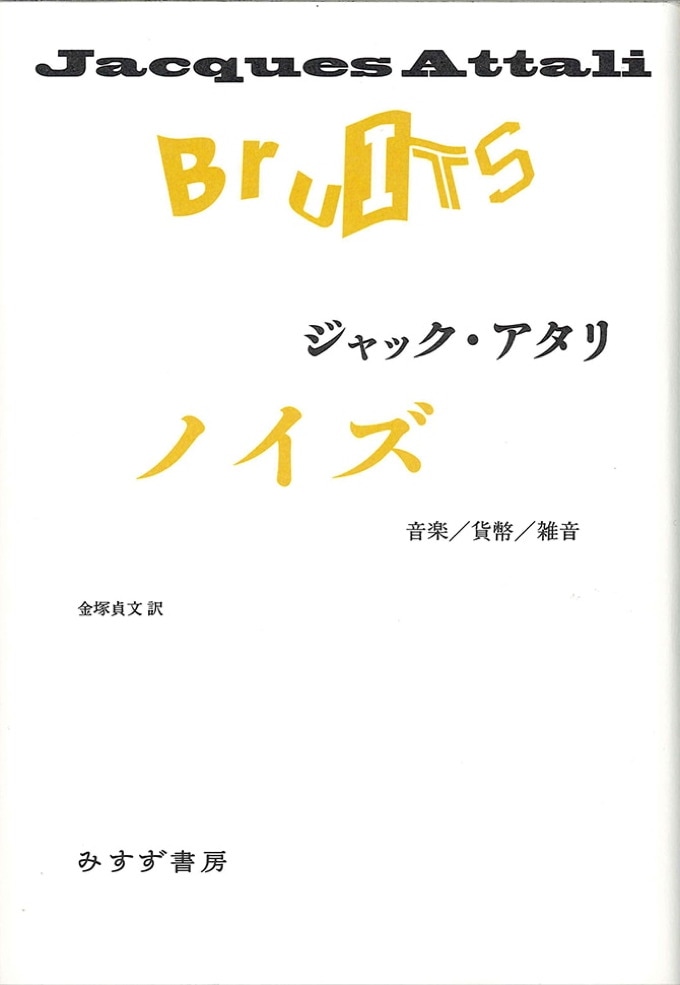
「不確かでうつろいやすく、ささやかでかすかな流れとなって、音楽はわれわれの世界、そしてわれわれの日々の生活の隅々にまでゆきわたっている。今、それは、条理を失った世界の中で、安らぎを見出し得るのはBGMしかないかのように、われわれには不可欠なものとなっている。今日、音楽の流れるところにはすべてまた、貨幣がある。(…)商品となった非物質的な悦びたる音楽は、記号の社会、物質的でないものまでが売買される社会、社会関係が貨幣に統合された社会を告知しているのだ。
音楽は、予言的であるが故に告知する。音楽は、いつの時代にもその原理のうちに、来たるべき時代の告知を含んでいたのだ。」
「「本書は、音という素材に社会の告知を聴くことへのアピールである」。音楽の変容を通し描出される、消費社会/文化の近未来図。アタリ的/根源的音楽史観。
改版にあたって、「三十五年前の予言——〈始まりの本〉版への訳者あとがき」と、「解説」(陣野俊史)を付す。
聴く
権力の雑音(ブリュイ)
雑音と政治/科学、メッセージ、時間/鏡/予言
資本以前の音楽家
浮浪者(ヴァガボン)/召使い
音楽による理解
供える
音楽空間——供犠のコードから使用価値へ
使用価値と供犠的コード/雑音、殺人の模倣/供犠の模倣としての音楽
コードの力学
四つの系(レゾー)/秩序、コード、系(レゾー)/破壊過程——雑音による秩序と臨界点/コード清算の力学
音楽と貨幣
音楽の外で生産される貨幣——母型製作者(マトリサー)/同時的なものの出現
演奏する
演奏、交換、ハーモニー
召使い音楽師から企業音楽家へ/商業音楽の出現/音楽の集権化された計画化/事物価値の告知としての音楽/交換とハーモニー/ハーモニーの訓練/ハーモニーの組合せ理論と経済発展/オーケストラの隠喩(メタフォール)
スターの系譜学
古典演奏家の系譜学/民衆スターの系譜学/演奏の経済学
反復への流れ
組合せ理論の崩壊——反ハーモニー/音楽の社会化/反復のショーウインドウとしての演奏
反復する
録音の定位
言葉を凝結させる/レコードとラジオ/交換と使用の対象/交換時間と使用時間
二重の反復
連続的反復——意味の不在/市場の生産——ジャズからロックへ/供給の生産/需要の生産——ヒットパレード/メッセージの通俗化/若者の監禁/バックグラウンド・ミュージック/反復と意味の破壊/二つの循環の分岐——完成/権力のコンサート/権力の音楽家——アクターからマトリサーへ/権力の非局所化
反復、沈黙、そして供犠の終焉
反復と沈黙/雑音の制御/使用時間の盗み/死のストック
反復的社会
反復の経済学/増殖の危機
作曲する(コンポーゼ)
亀裂
新たな雑音/「UHURU」——「フリー・ミュージック」の経済の挫折/演奏と作曲——ジョングルールへの還帰
作曲の相互交通的価値
身体の新しい統一/相互交通/雑音からイマージュに——作曲のテクノロジー
作曲の経済学
訳者あとがき
〈始まりの本〉版への訳者あとがき
解説——アタリ『ノイズ』はどう書き継がれねばならないのか (陣野俊史)
原注
文献一覧
「原書の初版が出版されたのは1977年、いまから三十五年前(翻訳の初版は1985年)。パソコンなどまだ夢だった時代、おそらく著者アタリはタイプライターを叩き、訳者は二百字詰めの原稿用紙に万年筆を走らせていた、そんな時代である」……
「今回の日本語版新版の刊行に際して、原書改訂版を適宜参照して、部分的な改訳の参考にさせてもらうことはあったが、全編を翻訳し直すことはあえてしなかった。初版が一つの音楽作品だとすれば、改訂版はそれを現代風(とはいっても、もう十一年前になるが)にアレンジしてインプロビゼーション=作曲したものであり、新しい一つの作品と解釈すべきであろう。そして、今後もまたさらにアレンジされて書き継がれるものと考えられるとしたら、初版は初版として、それら一連の新作の起源となるであろう古典として、読まれる価値が増しこそすれ、決して色褪せることはないと確信するからである。十八世紀のクラシック音楽に二十世紀の社会のあり様が告知されていたように、二十世紀の『ノイズ』には来たるべき世界が告知されているのだ。
〈始まりの本〉シリーズの一冊として刊行されるに当たって、三十年前の拙訳にかなり手を入れさせてもらった」……