戦争文化と愛国心
非戦を考える
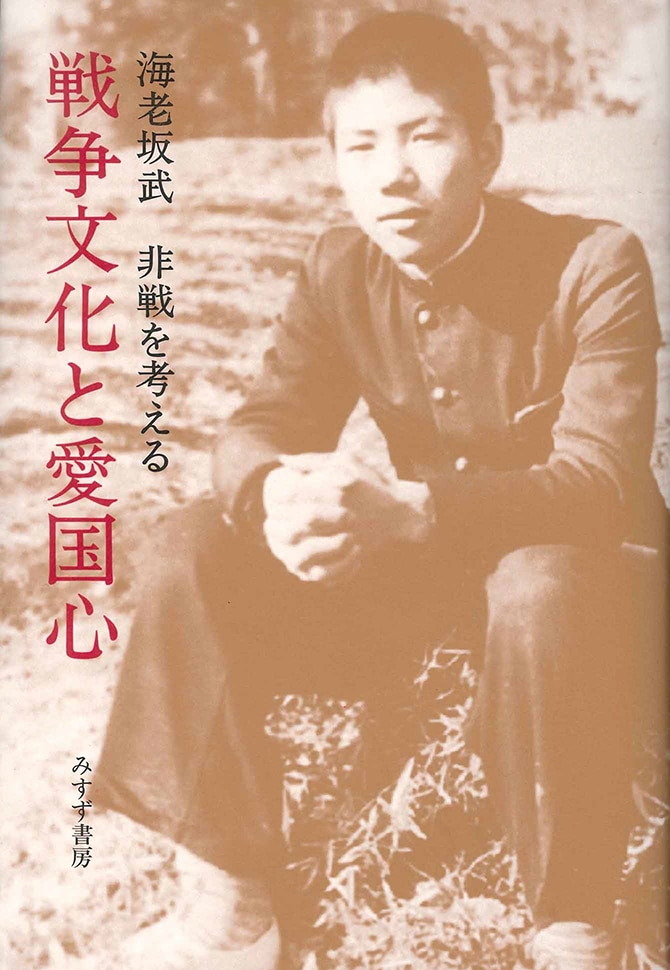
| 判型 | 四六判 |
|---|---|
| 頁数 | 352頁 |
| 定価 | 4,180円 (本体:3,800円) |
| ISBN | 978-4-622-08518-8 |
| Cコード | C0095 |
| 発行日 | 2018年3月15日 |
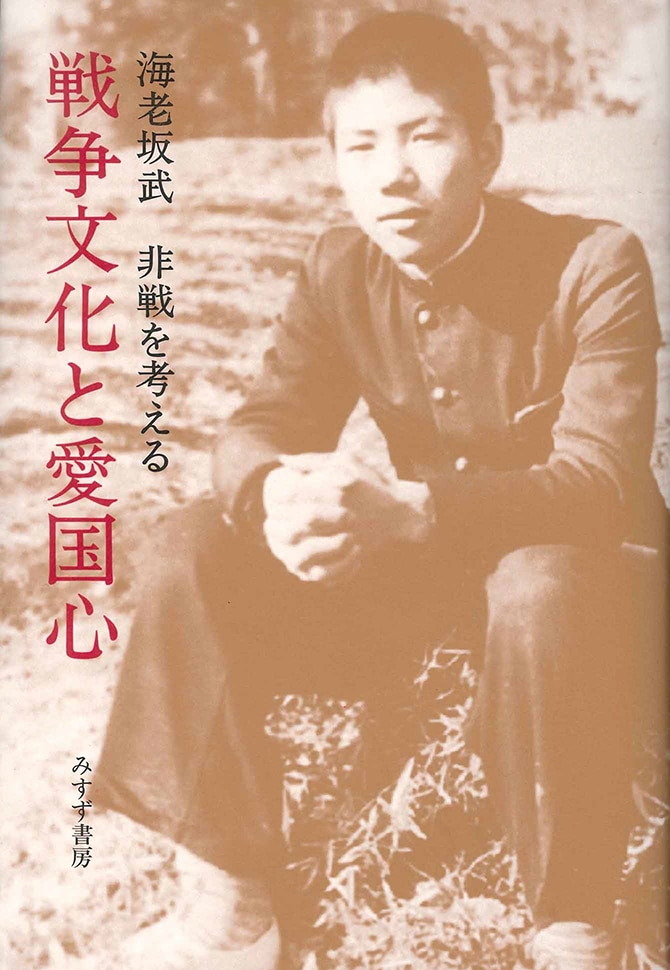
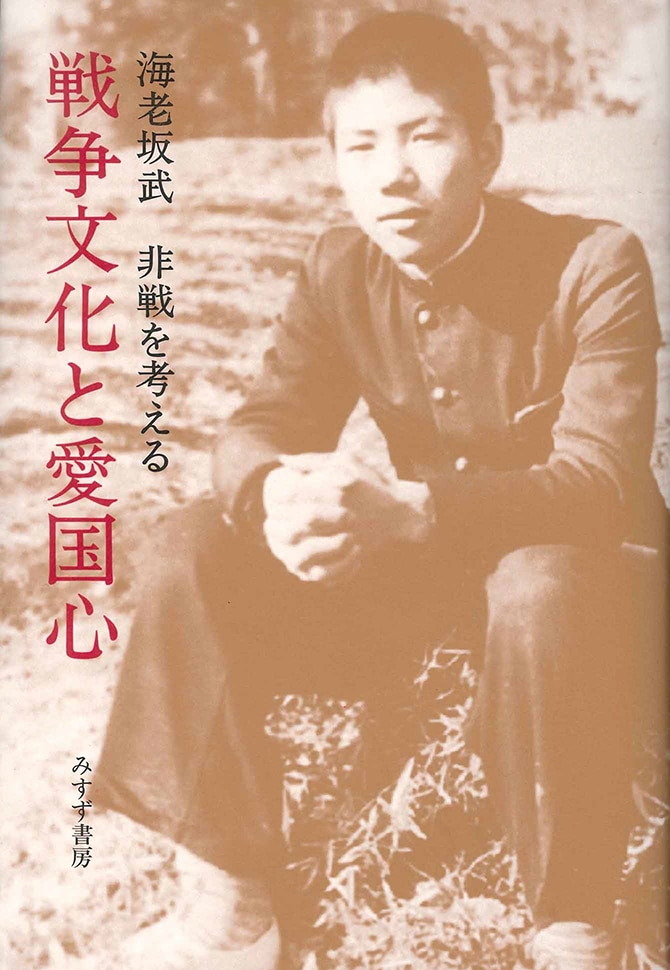
| 判型 | 四六判 |
|---|---|
| 頁数 | 352頁 |
| 定価 | 4,180円 (本体:3,800円) |
| ISBN | 978-4-622-08518-8 |
| Cコード | C0095 |
| 発行日 | 2018年3月15日 |
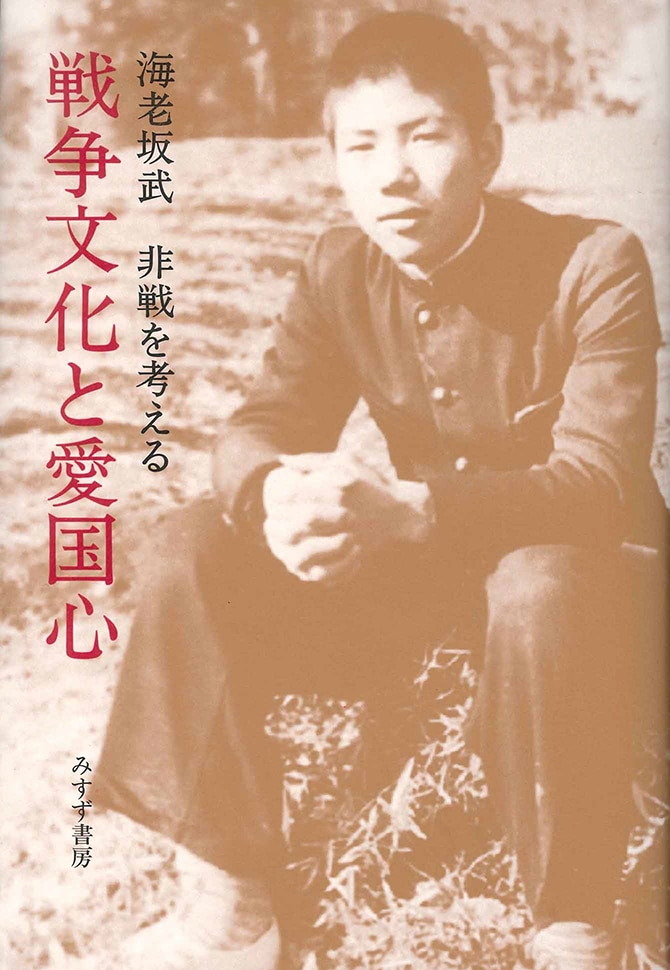
「大東亜戦争」の始まりを国民学校一年生で迎え、「皇国の少国民」であることが最初のアイデンティティだった……
教科書に歴史物語、軍歌。家庭では新聞や雑誌、ラジオを通じて、戦争の言葉を、時代の狂気を擦り込まれた少年時代。その鮮やかな記憶に語らせながら、著者は戦争を誘発し、戦争への道を用意する〈戦争文化〉が、何によって、誰によって形作られ、どのように生活に忍び込み、日本を覆っていったかを検証してゆく。
〈私〉の経験を出発点に、さらにその外へ——1930年代の戦争文化を最大限に呼吸し、そのために生き、死んでいったわだつみ世代の若者たち。敗戦後の混沌と虚脱の中、価値の180度の転換を迫られた大人たち。戦争文化をさっさと脱ぎ捨てたかに見えた日本人一般の心の転回。
戦争文化は本当に解体されたのか。その核心にあった、あの〈愛国心〉はどうなったのか。
明治の時代の〈愛国心〉論議と〈愛国心〉批判、フランスに目を転じて、アラン、ジャン・ジオノの非戦論、さらに日露戦争時に始まる兵役拒否と不服従の思想。丸山眞男、加藤周一、鶴見俊輔ら「戦中世代」の残したものを受け止めなおしつつ、「戦後世代」の言説もみわたし、戦争文化と愛国心の歴史、そして、それに立ち向かう非戦の思想の系譜をたどる。政党でもなく、団体でもない私たち一人一人が、出来合いの処方箋のないところで、それでも何かを考え、何かを作り出してゆくために。
第一章 国民学校一年生——言葉を擦り込まれた少年
1 「コクミンガッコウ イチネンセイ」
国民学校
背景
教師たちの養成
2 「アカイ アカイ アサヒ アサヒ」
3 日の丸教育
4 教室風景
5 愛国節をうなる
新聞
6 そこのけそこのけ軍歌がとおる
軍歌のパトロン
7 英雄と悪人の歴史物語
第二章 戦争文化とは何か
1 騙されたではすまない
2 戦争のない世界は恐ろしい
3 反面教師として
4 フランス歴史学から
5 若者たちの戦争文化——『きけ わだつみのこえ』
6 学者たち
第三章 古い上着よ さようなら
1 八月十五日
2 闇市洗礼
3 野球と歌と
4 新制中学一年生——新憲法の申し子
5 見える人たち
6 傷を残した人々
7 混沌と虚脱の状態の中から——手のひらを返した日本人
8 思い違いとナイーヴさ
9 言葉の引っ越し
10 チボー家世代
第四章 愛国心の行方
1 戦後の「愛国心」論議
2 清水幾太郎『愛国心』
構成
清水の位置——愛国心の脱構築
3 丸山眞男のナショナリズム論
4 二つの不思議
5 三つの愛国心論
姜尚中『愛国の作法』
佐伯啓思『日本の愛国心——序説的考察』
テッサ・モーリス=スズキ『愛国心を考える』
6 パトリオティズムとナショナリズム
どう区別するか
パトリオティズムは愛、ナショナリズムは憎悪
第五章 非戦思想の源流
1 内村鑑三
「義」のための戦争
非戦主義者の誕生
戦時の姿勢
愛国心について
2 幸徳秋水
非戦論—反戦争文化論
愛国心論
軍国主義論
帝国主義論
非戦—反戦闘争の継続
兵役は?
第六章 兵役拒否と不服従の思想の源流
1 徴兵忌避
2 矢部喜好の肖像
3 村本一生と明石真人
4 フランスの非戦論 1——アラン
5 フランスの非戦論 2——ジャン・ジオノ
6 百二十一人宣言——アルジェリア戦争の中から
第七章 非戦の原理から不服従の思想へ
1 憲法平和主義について
2 『きけわだつみのこえ』と原水爆禁止運動
3 「戦争の犠牲者」「戦争の被害者」——-三つの目隠し
4 久野収と鶴見俊輔
5 大熊信行
6 鶴見良行
7 脱走兵支援運動
8 小田実
9 市民的不服従と良心的拒否
終章 少数の力のために
1 私たちはどこにいるのか
2 少数の力のために
注
参照文献
あとがき