ハチは心をもっている 電子書籍あり
1匹が秘める驚異の知性、そして意識
THE MIND OF A BEE
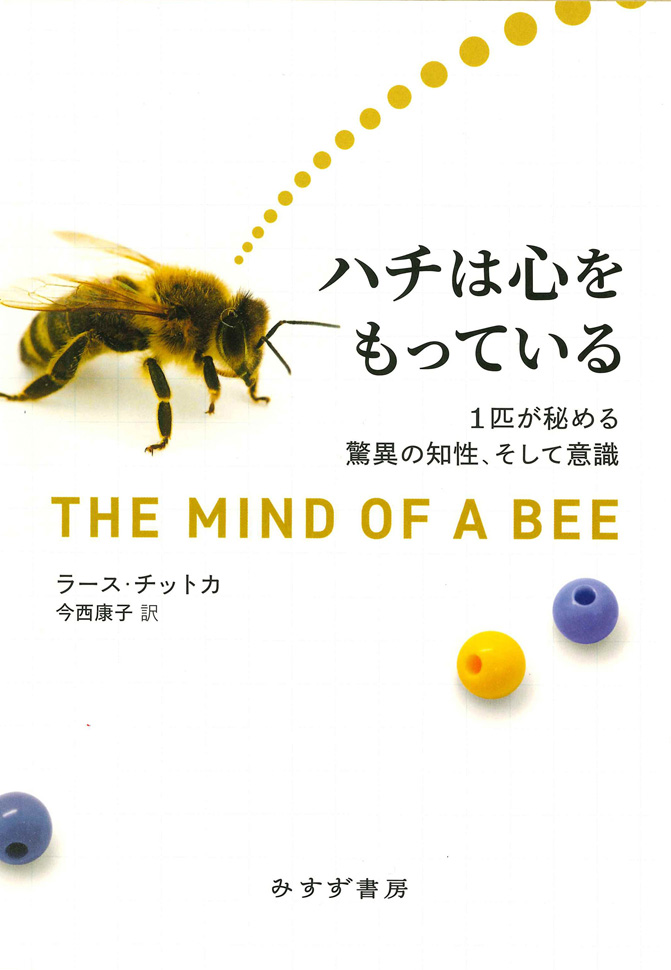
| 判型 | 四六判 |
|---|---|
| 頁数 | 352頁 |
| 定価 | 3,960円 (本体:3,600円) |
| ISBN | 978-4-622-09767-9 |
| Cコード | C0045 |
| 発行日 | 2025年2月17日 |
| 電子書籍配信開始日 | 2025年2月25日 |
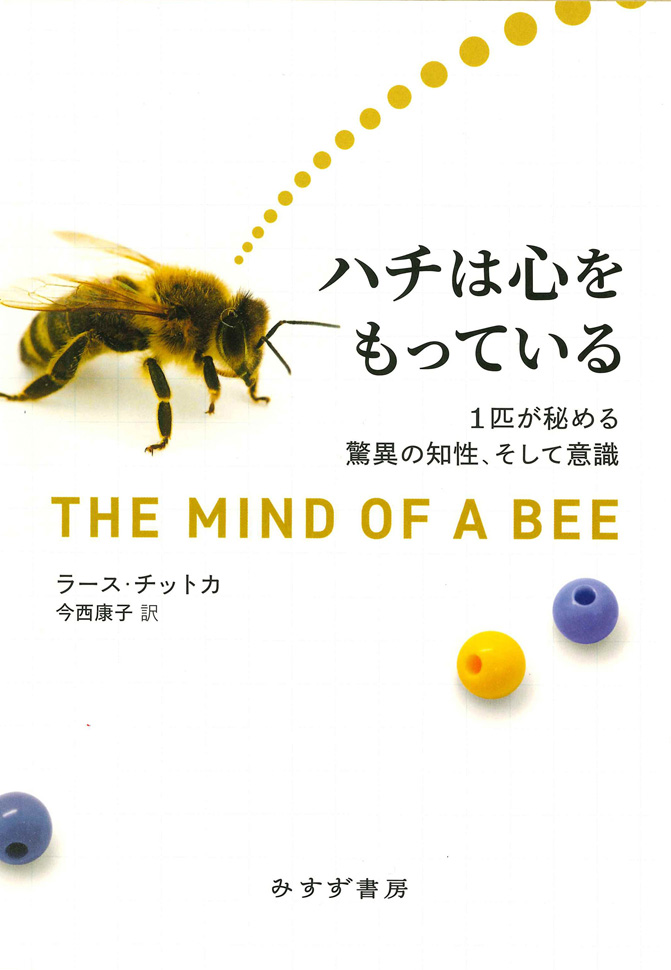
THE MIND OF A BEE
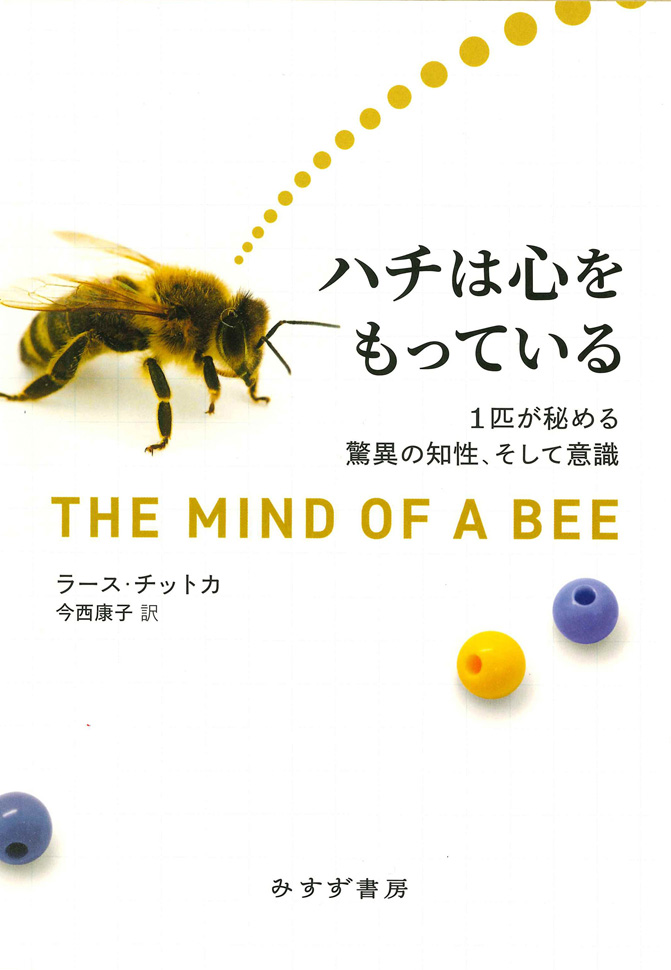
| 判型 | 四六判 |
|---|---|
| 頁数 | 352頁 |
| 定価 | 3,960円 (本体:3,600円) |
| ISBN | 978-4-622-09767-9 |
| Cコード | C0045 |
| 発行日 | 2025年2月17日 |
| 電子書籍配信開始日 | 2025年2月25日 |
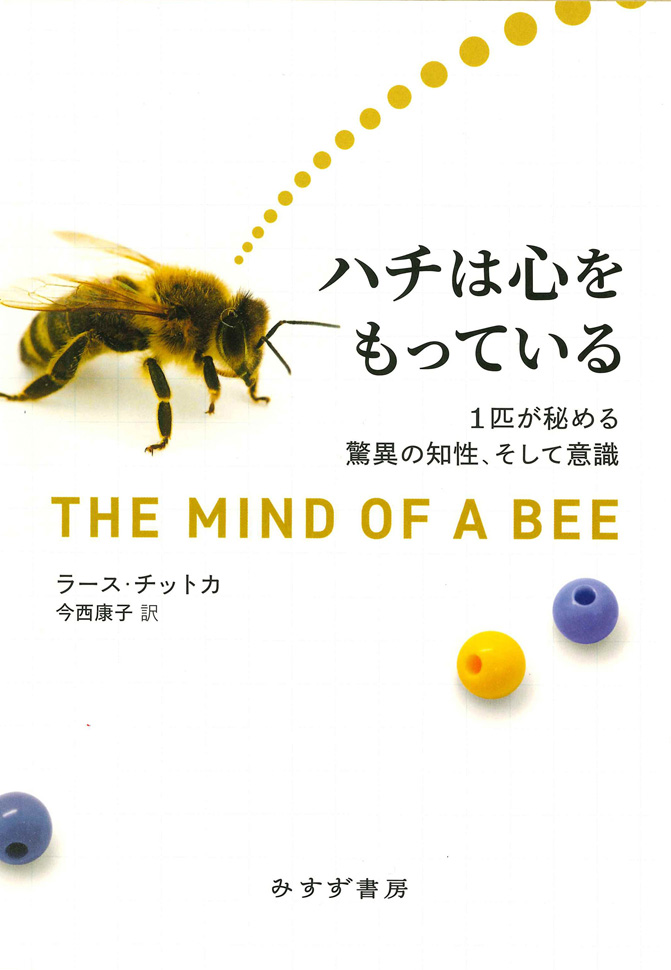
ハチは「群知能」だけでなく、1匹1匹も高度に進化した心をもっていた! ハナバチの認知研究の権威である著者が、1匹の内にある驚くべき精神生活を説き明かす。
もちろん、ハチの心は人間の心とはまったく異なる。しかしハチの心が「原始的」だと思ったら大間違い。本書の読者はまず、ハチの賢さに驚嘆するだろう。どんな課題もたちどころに学習し、瞬時に効率のよい判断を下して問題解決する。数を数え、道具を使い、ほかのハチやほかの動物から問題解決の方法を盗みさえする、等々……。この速くて柔軟な心は、採餌や帰巣の必要、ハチの形態やサイズなどに適う方向へ、進化の手が精巧に磨き上げてきたものだ。
ファーブル、カール・フォン・フリッシュ、マルティン・リンダウアー、そしてもちろん著者自身も含め、数多の研究者たちがアイデアを凝らした巧妙な実験によって、その「異なる心」の解明に挑んできた。ハチの内面を探る実験のおもしろさも本書の大きな読みどころの一つだ。
著者はハチの個体が「パーソナリティ」をもち、「自他」を区別し、内的表象を形成し、苦痛や情動を経験するといった心的機能も探っている。本書を読む前と後で、ハチはもちろん、すべての昆虫への見方が変わらずにはいられない。
1 はじめに
ハチであるとはどのようなことか
野生の採餌者にとっての課題
花畑マーケットの買物客の心
複雑な判断、コミュニケーション、住まい作り
他者を理解する上でその心が経験する世界を想像することが重要なのはなぜか
社会性種か、単独性種か
本書のロードマップ
人類の長い歴史のなかで
2 不思議な色で世界を見ている
カール・フォン・ヘス vs カール・フォン・フリッシュ──ハチの色覚をめぐる論争
カール・フォン・フリッシュとナチ
異なる色彩の世界
ハチの色覚は花の色に対応して進化したのか?
3 ハチの異質な感覚世界
マルティン・リンダウアーと時刻補正されたハチの太陽コンパス
ハチの偏光知覚
地磁気に対する感受性
触角、最も奇妙な感覚器官
触角でどのように味を感じるのか
触角(フィーラー)での触覚と聴覚
ハチの電界に対する感受性
4 「単なる本能」なのか?
ジャン=アンリ・ファーブルと、昆虫は反射的機械装置だという考え方
巣作りをするミツバチは本能と知能をどう組み合わせているのか
ハチの行動についての、シンプルだが間違っていた初期の説明──「帰巣本能」
ハチは「本能で」花に引かれるのか?
学習と本能が手に手を取って進化する
5 ハチの知能とコミュニケーションの起源
三畳紀のハチの祖先──このうえなく残忍な肉食動物
カール・フォン・フリッシュとハチのダンス言語の発見
ダンス言語の進化
マルハナバチの行動はダンスの元祖か?
なぜミツバチはダンスするのか?
6 空間についての学習
ハチはランドマークを利用して飛行する
文脈学習
ハチの心に認知地図はあるか?
ハチのナビゲーション実験用のランドスケープをつくる
ハチの経路統合
ハチをレーダーで追跡する
時差ぼけにしたミツバチで認知地図を探る
においが遠い記憶を呼び戻す
ハチと「巡回セールスマン問題」
7 花についての学習
電子機器で作った造花の扱い方を学ぶ
ハチはどのように花に注意を向けるのか
ハチの脳に備わる変速装置
ハチはどれだけの情報をひと目で処理できるか?
花を弁別する速さと正確さのトレードオフ
ヒトの顔の形をした奇妙な花
花弁の肌理についての学習
温血動物であるハチは花の温度をいかにして学ぶか
虹色の花に眩惑されるか
ハチはいかにして規則性(ルール)を学ぶのか
花はいつ蜜を出すかを学習する
空間概念を学習する
概念学習課題を単純化によって速断
8 社会的学習と「群知能」
どの花を訪ねるべきかを他のハチから学ぶ
他のハチを遠くから観察して学習する
異なる種から学習する
観察によって盗みの技を学習する
ハチの文化と伝統?
観察によって道具の使い方を学習する
新たな住処を求めて移動する分蜂
ダンスコミュニケーションで新居を見つけ出す
ミツバチ分蜂群の民主的意思決定
知的群集内の心をもたぬ(マインドレス)個体、なのか?
9 そのすべてを背後で支えている脳
ハチの脳の基本構造
ハチの脳内にある神経細胞の発見
ハチの脳内の視覚情報処理ニューロン
単一特徴検出ニューロンでどれだけのことができるか?
学習可能な1個のニューロン
キノコ体──ハチの情報保存用ハードディスク
単純な脳回路による複雑な学習
昆虫の中心複合体──高度なナビゲーション装置
中心複合体は意識の座なのか?
ハチの脳波
異なる生活様式、よく似た脳
10 ハチの「パーソナリティ」の個体差
マイクロチップを用いてハチの「パーソナリティ」を探る
同じ遺伝子で異なる運命──ハチのコロニーでの専門特化
感覚の感度の個体差から生じる分業
体のサイズ、感覚システム、役割の専門特化にみられる個体差
経験を積んだ結果としての役割の専門化
採餌ルートの個体差
速さと正確さのトレードオフに見られる個性
知能の個体差
オスカー・フォークト──マルハナバチからレーニンの脳へ
脳の構造と知能の個体差
知能が高いと適応度も高いのか
学習がのろくてもまだ絶滅していないのはなぜか?
11 ハチに意識はあるか?
ハチは痛みを感じるか?
痛みの主観的側面
捕食者との遭遇後の長期にわたる心理的変化
ハチの情動
自己生成刺激と外部からの感覚刺激の区別が意識の進化の起源なのか?
マルハナバチの自己イメージ
自己と他の生き物を区別する
ハチにオフライン思考はあるか?
形状をイメージする
ハチにメタ認知はあるか?
12 終わりに
──ハチの心に関する知識はハチの保全にどんな意味をもつか
謝辞
訳者あとがき
「ハチの心」の研究へのあくなき挑戦──推薦の辞(小野正人)
図版出典一覧
註と参考文献
索引
「はじめに」[抄](WEBみすずサイト「新刊紹介」)