列島哲学史
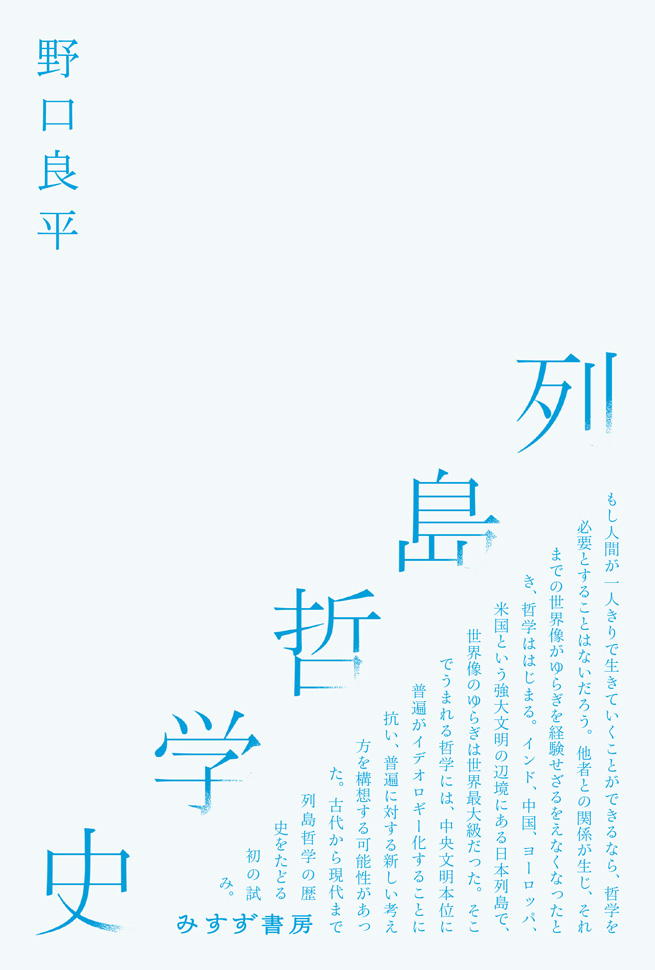
| 判型 | 四六判 |
|---|---|
| 頁数 | 304頁 |
| 定価 | 3,960円 (本体:3,600円) |
| ISBN | 978-4-622-09802-7 |
| Cコード | C0010 |
| 発行日 | 2025年9月16日 |
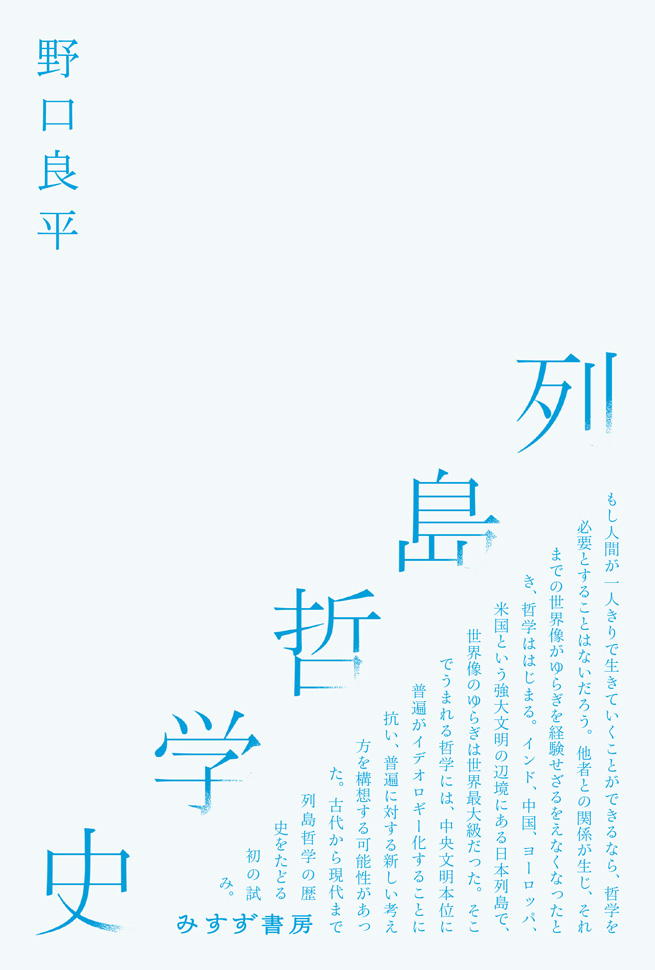
列島哲学史
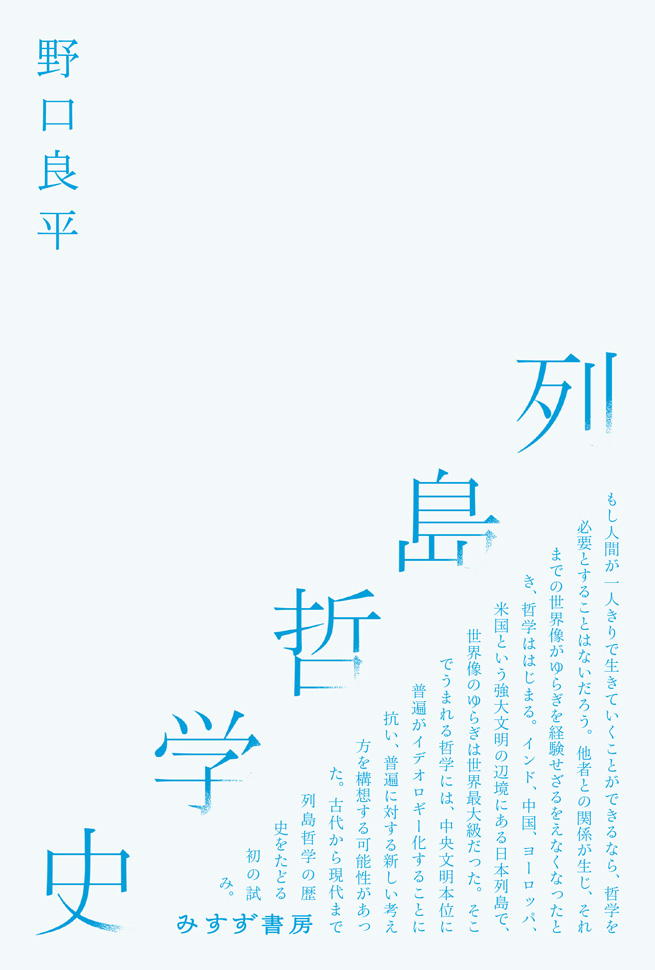
| 判型 | 四六判 |
|---|---|
| 頁数 | 304頁 |
| 定価 | 3,960円 (本体:3,600円) |
| ISBN | 978-4-622-09802-7 |
| Cコード | C0010 |
| 発行日 | 2025年9月16日 |
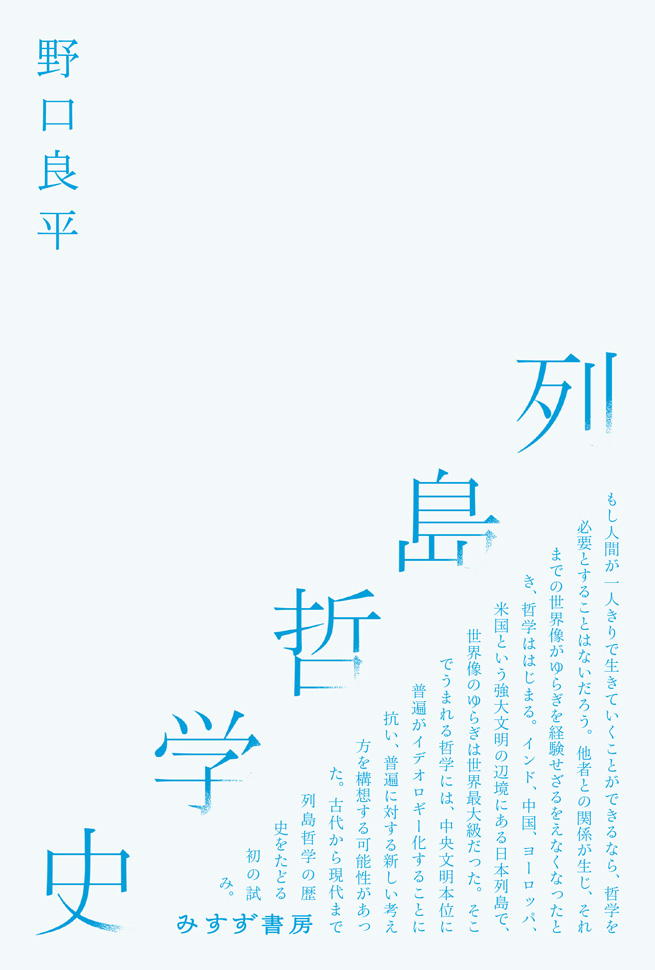
もし人間が一人きりで生きていくことができるなら、哲学を必要とすることはないだろう。他者との関係が生じ、それまでの世界像がゆらぎを経験せざるをえなくなったとき、哲学ははじまる。インド、中国、ヨーロッパ、米国という強大文明の辺境にある日本列島で、世界像のゆらぎは世界最大級だった。そこでうまれる哲学には、中央文明本位に普遍がイデオロギー化することに抗い、普遍に対する新しい考え方を構想する可能性があった。古代から現代まで列島哲学の歴史をたどる初の試み。
はじめに
1 太夫・才蔵モデル
2 孤立性と辺境性
3 「日本人」になるということ
4 記紀の世界像
5 遅れ反応の回路
6 「あはれ」から「無常」へ――「下からの普遍性」の発見
7 日本語の生成へ
8 応仁の乱前後
9 西欧の衝撃と第二の鎖国
10 近世のほころび
11 ユートピア的構想の探求
12 内在と関係の対話
13 つくられた制度と制度をつくるもの
14 追い越さないという選択肢
15 戦時下のせめぎあい
16 戦中と戦後のあいだ
17 イソップ寓話のように
おわりに
注
あとがき
索引