
2017.07.11
急進的啓蒙とは。自由・平等・理性・人権概念の普遍性と現代的意義を問う
ジョナサン・イスラエル『精神の革命――急進的啓蒙と近代民主主義の知的起源』森村敏己訳
[第3回配本・全11巻]
2017.07.11
1989年、中井久夫は20世紀最大のギリシャ詩人、コンスタンディノス・カヴァフィスの訳詩集『カヴァフィス全詩集』(みすず書房、1988)で読売文学賞研究・翻訳賞を受賞した。80年春に神戸大学医学部教授となって9年、55歳だった。
難解で知られるハリー・スタック・サリヴァンの講演録を翻訳したとき、中井はサリヴァンが講演した講堂を調べ、しかるべき聴衆を配置し、自分がサリヴァンになって講演しているつもりで訳した。今回も部屋の家具をカヴァフィスの書斎の雰囲気に似せ、独訳や仏訳などを吟味し、自分の訳をテープに入れて繰り返し聞きながら、4年をかけて翻訳を吟味したという。
〔…〕
中井と詩の関わりは、戦後初の入学生となった旧制甲南高等学校時代にまでさかのぼる。2人の国語教師からリルケとヴァレリーを学び、図書館に寄贈された九鬼周造の蔵書から原書を借りて筆写し、持ち歩いた。「打ちひしがれた占領下、私たちを圧倒したヨーロッパの精神の謎に分け入りたかったのだろう。ドイツ語、フランス語の他、若いほうの教師といっしょに西洋古典語に手を染めたりもした」(「私の人格形成期の言語体験」『私の日本語雑記』岩波書店、2010)。
多感な季節に養われた言語感覚は、寡黙がちだが内なる戦闘状態にある統合失調症の患者へのアプローチに手がかりを与えただろう。中井はよく診察室でメタファーを用いた。何も決めつけず、誰も傷つけない、開かれた言葉。たとえば、患者と一緒に絵を描きながら、「この鳥は羽をあたためていますね」というように。
中井の詩の定義はこうであった。「詩とは言語の徴候優位的使用によってつくられるものである」(「世界における索引と徴候」)。また、こうも書いた。「詩とは言語の徴候的使用であり、散文とは図式的使用である。詩語は、ひびきあい、きらめき交わす予感と余韻とに満ちていなければならない」(「私と現代ギリシャ文学」)。もう少し平易な文章もある。「私の予感的な言語意識は次の行を予感する。この予感が外れても、それはそれで「快い意外さ la bonne surprise」がある。詩を読む快楽とは、このような時間性の中でひとときを過ごすことであると私は思う」(同前)。
書棚に並んだ本の背表紙が視界に入るだけで中身が呼び戻されて苦しくなるほど超人的な記憶力をもつ中井にとって、因果から解放され、未来に大きく飛翔させてくれる詩的言語は生きていくために切実な乗り物だったのだろう。
〔…〕
(copyright Saisho Hazuki 2017)
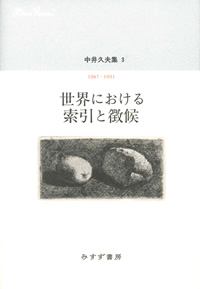

2017.07.11
ジョナサン・イスラエル『精神の革命――急進的啓蒙と近代民主主義の知的起源』森村敏己訳
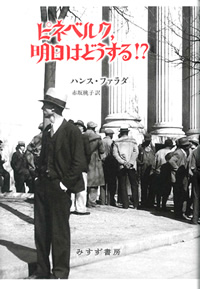
2017.06.27
ハンス・ファラダ『ピネベルク、明日はどうする!?』 赤坂桃子訳