ある学問の死
惑星思考の比較文学へ
DEATH OF A DISCIPLINE
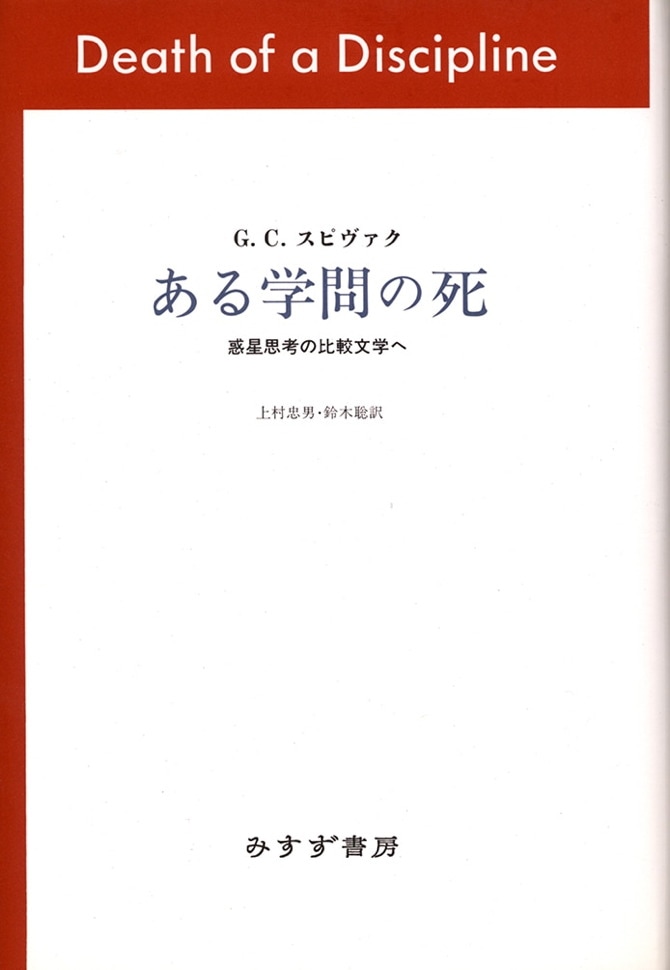
| 判型 | 四六判 |
|---|---|
| 頁数 | 224頁 |
| 定価 | 2,860円 (本体:2,600円) |
| ISBN | 978-4-622-07093-1 |
| Cコード | C1010 |
| 発行日 | 2004年5月25日 |
| 備考 | 現在品切 |
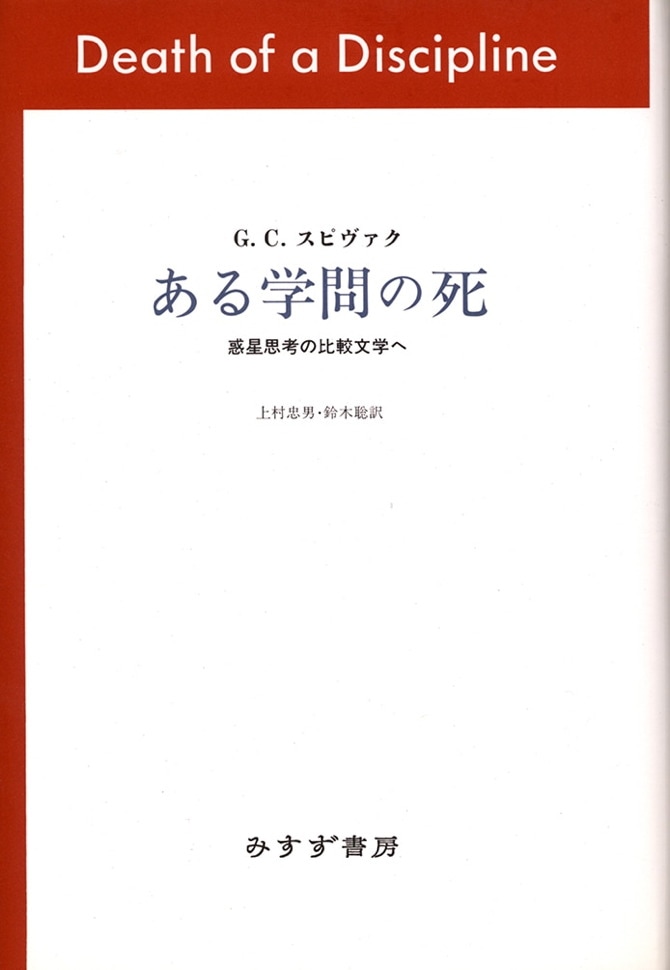
DEATH OF A DISCIPLINE
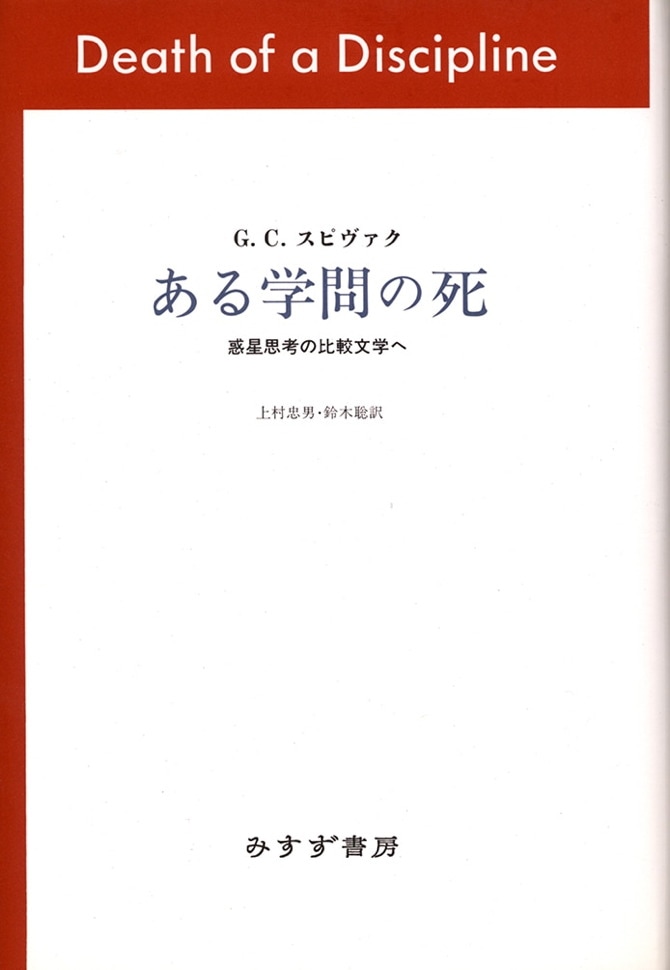
| 判型 | 四六判 |
|---|---|
| 頁数 | 224頁 |
| 定価 | 2,860円 (本体:2,600円) |
| ISBN | 978-4-622-07093-1 |
| Cコード | C1010 |
| 発行日 | 2004年5月25日 |
| 備考 | 現在品切 |
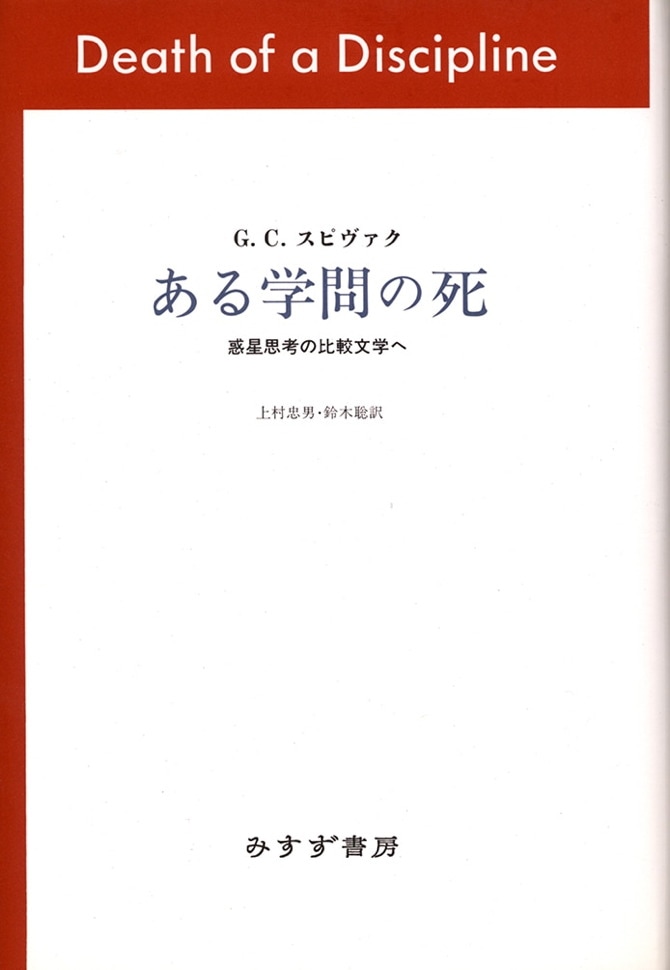
「比較文学と地域研究は、協働することによって、地球上の南の諸国民文学を育むだけでなく、地図が作成されたあかつきには消滅するべくプログラムされている、世界各地に無数に存在する土地固有の言語による著述を促進することもできる。… わたしたちは一致協力することによって、それらの言語に境界の連帯性を提供することができる。それらの境界は、たやすく、幾度となく繰り返し横断することができるのである。これこそは、来たるべき比較文学が恒常的に仕掛ける、底辺からの中断作用にほかならない。グローバリゼーションのアイロニーである」
第二次大戦下の亡命知識人を中心にアメリカに生まれ、ヨーロッパ諸国民の言語に基礎を置いた「比較文学」と、冷戦構造のもとに誕生した「地域研究」。グローバリズムが席巻するいま、この二つの分野の伝統的なあり方からの脱却は、どのような方向にむけられるべきなのか。両者の連携および「ヨーロッパの他者」たちの視線のもとでみずからを「他者化」することは、いかにして可能なのか。著者は、グローバリズムに対峙する惑星的思考のなかで、新たな比較文学を志向する。
『サバルタンは語ることができるか』で知られるスピヴァクが、今の大学教育、文化や文学研究のあり方を批判しつつ描いた、来たるべき学問論。日本でも大学教育をめぐって再編が進んでいる現在、著者の透徹した議論に耳を傾けたい。
謝辞
第一章 境界を横断する
第二章 集合体
第三章 惑星的なあり方
原註
訳者あとがき——惑星思考の比較文学へ