故国喪失についての省察 1
REFLECTIONS ON EXILE AND OTHER ESSAYS
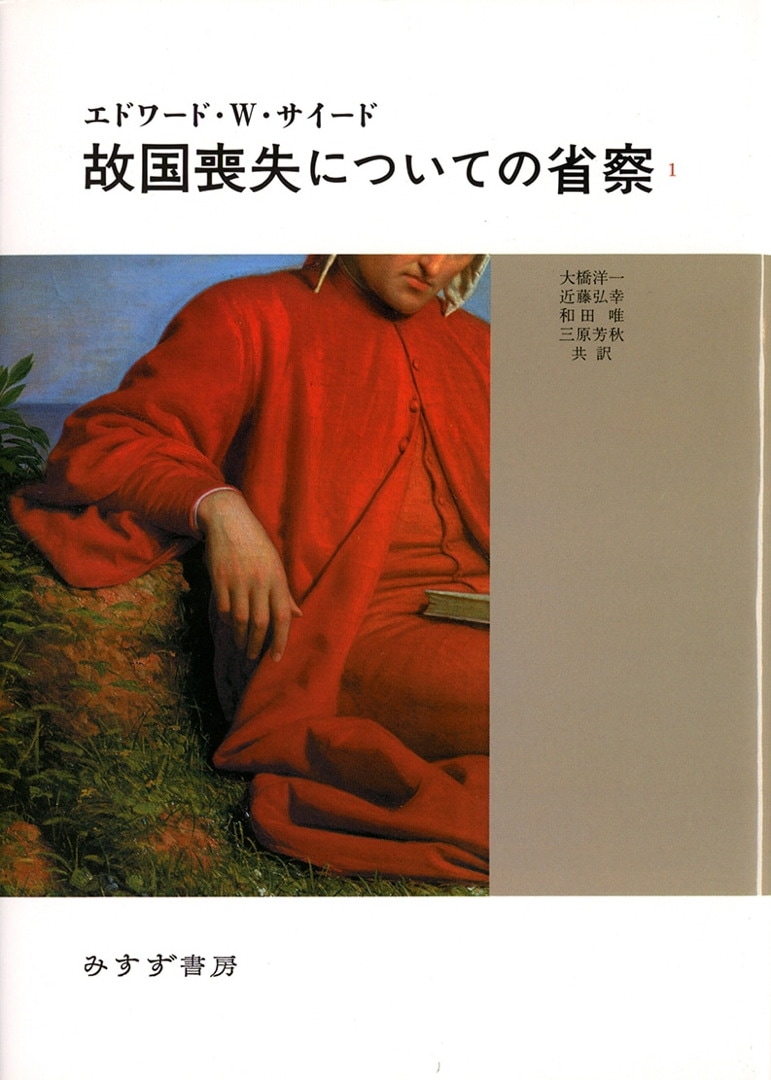
| 判型 | A5判 |
|---|---|
| 頁数 | 368頁 |
| 定価 | 4,950円 (本体:4,500円) |
| ISBN | 978-4-622-07203-4 |
| Cコード | C1010 |
| 発行日 | 2006年4月6日 |
| 備考 | 現在品切 |
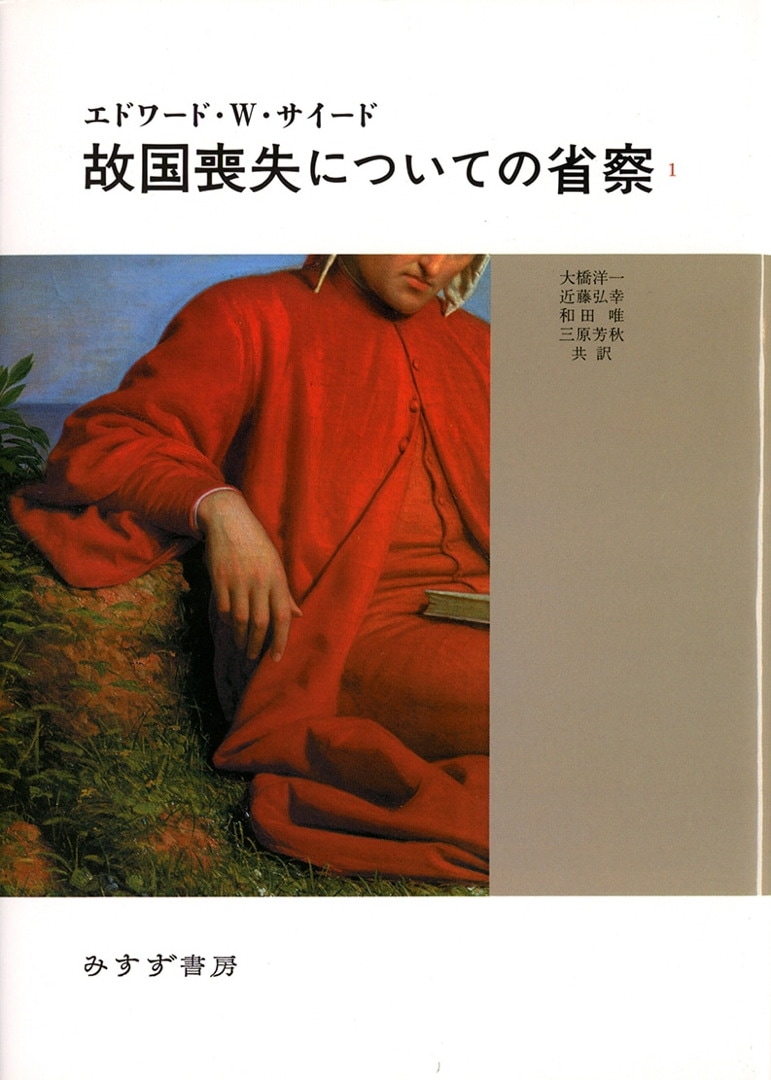
REFLECTIONS ON EXILE AND OTHER ESSAYS
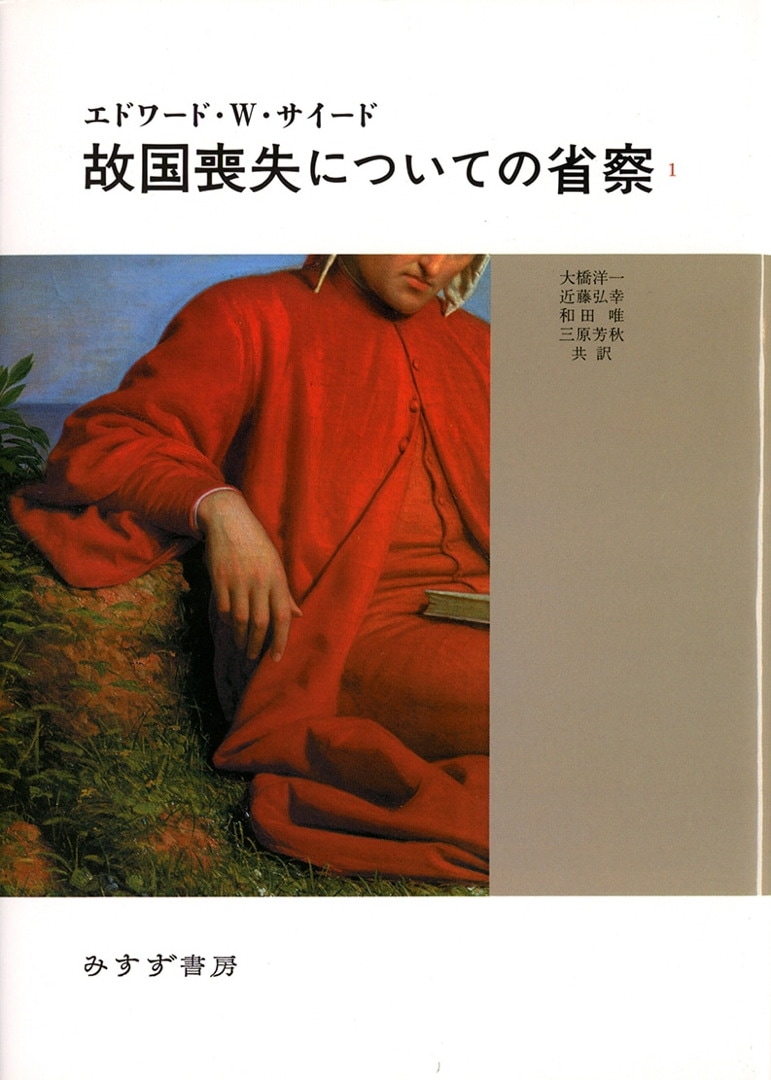
| 判型 | A5判 |
|---|---|
| 頁数 | 368頁 |
| 定価 | 4,950円 (本体:4,500円) |
| ISBN | 978-4-622-07203-4 |
| Cコード | C1010 |
| 発行日 | 2006年4月6日 |
| 備考 | 現在品切 |
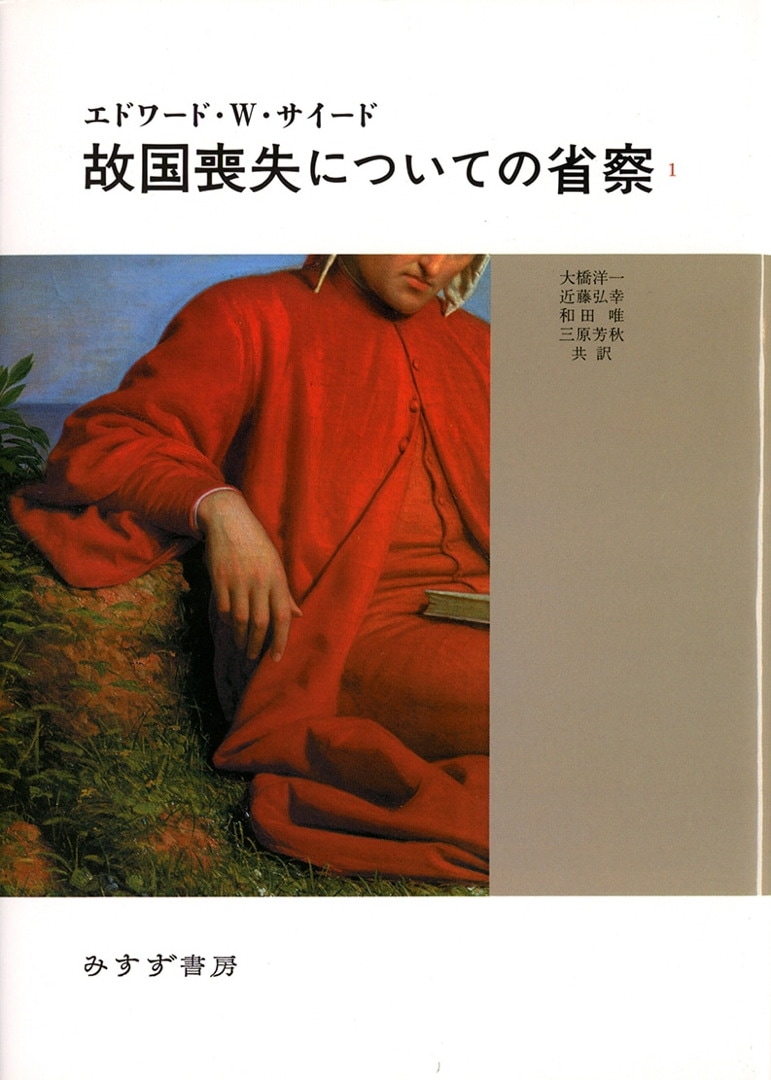
〈文学の研究は抽象的なものではないし、また否応なく有無を言わせぬかたちで、文化の領域に、それもその歴史的状況がわたしたちの発言や行動に大きく影響する、そんな文化の領域に位置づけられる。わたしはずっと「歴史的経験」というフレーズを使ってきた。なぜならこのフレーズは術語でもなければ隠語でもなく、形式的かつ専門的世界から離れて、生きられたものへと、争われたものへと、直接的なものへと——わたしが本書のエッセイのなかで、なんども立ち返るものへと——そうしたものへと開かれた道筋を示唆しているからである。けれどもまたわたしは、誰にもまして、空虚な人文主義のもつ危険性が現実的なものであることを知っている〉(序文より)
本書はサイードの35年にわたる批評実践の集大成とも言うべき評論集である(全2冊)。本書1が収録するのは前半期の評論群。最初期の作品はメルロ=ポンティ論である。英文学の助教授としてキャリアを歩み始めたサイードがなぜメルロ=ポンティなのか。それに続くT・E・ロレンス、コンラッドとニーチェ、ヴィーコ、フーコー、オーウェル、ヘミングウェイ、グレン・グールド、ブラックマーらを扱った評論で、サイードは何を問題にしているのか。表題となり、全体を低通している「故国喪失」と批評実践の結びつきとは何か。
どの評論からも聞こえてくる、ゆるぎない一貫性をもったサイードの声を耳にするとき、真の批評実践とは何かという問いへの、ひとつの答えをそこに見出すだろう。完成品としての主著群からはむしろはっきりとは見えにくい、サイード批評のエッセンスにじかに触れているような手ごたえを堪能したい。
序 批評と故国喪失
1 受肉の迷宮——モーリス・メルロ=ポンティ
2 未解決のアマチュア———E・M・シオラン
3 終わりなき内戦——T・E・ロレンス
4 偶然性と決定論のはざまで——ルカーチの『美学』
5 コンラッドとニーチェ
6 ヴィーコ——身体とテクストの鍛錬=学問(ディシプリン)に関して
7 どん底への観光旅行——ジョージ・オーウェル
8 黒幕——ウォルター・リップマン
9 信仰者にかこまれて——V・S・ナイポール
10 エジプトの儀礼
11 批評の未来
12 故国喪失についての省察
13 ミシェル・フーコー 1927-1984
14 演奏された時を求めて ピアニスト芸術における存在と記憶——グレン・グールド
15 牛の角に突き殺されない方法——アーネスト・ヘミングウェイ
16 R・P・ブラックマーの地平
17 被植民者を表象する——人類学の対話者たち
訳注
解題
原注