信じない人のためのイエスと福音書ガイド
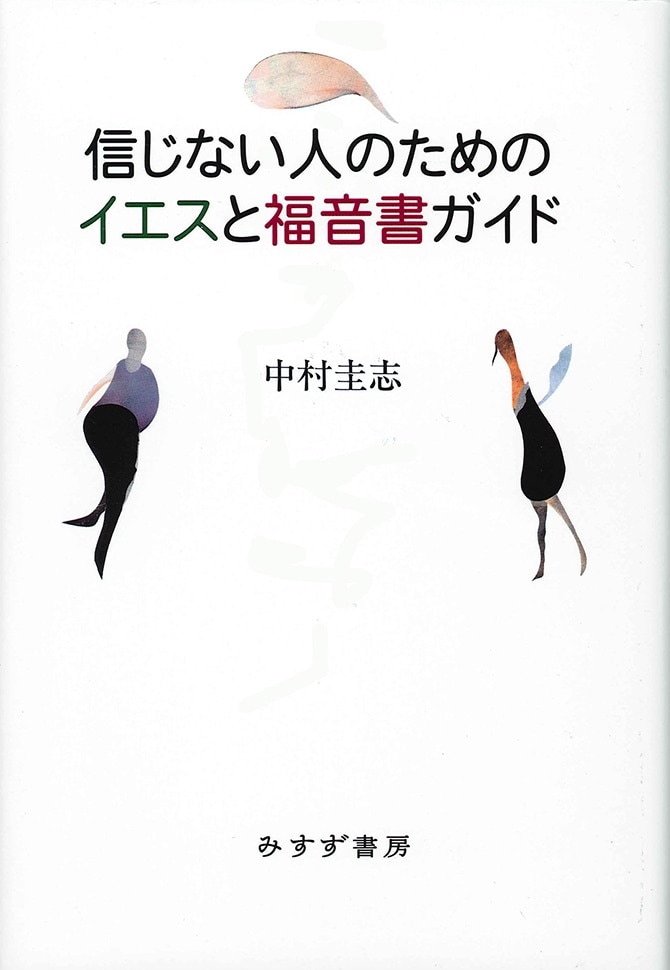
| 判型 | 四六判 |
|---|---|
| 頁数 | 288頁 |
| 定価 | 2,750円 (本体:2,500円) |
| ISBN | 978-4-622-07546-2 |
| Cコード | C1014 |
| 発行日 | 2010年9月24日 |
| 備考 | 現在品切 |
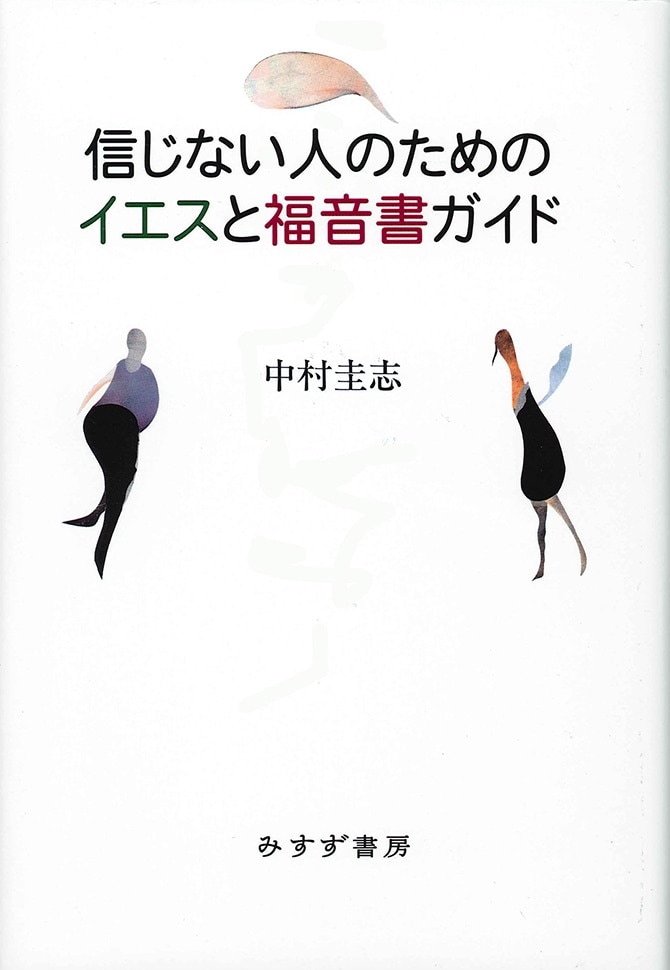
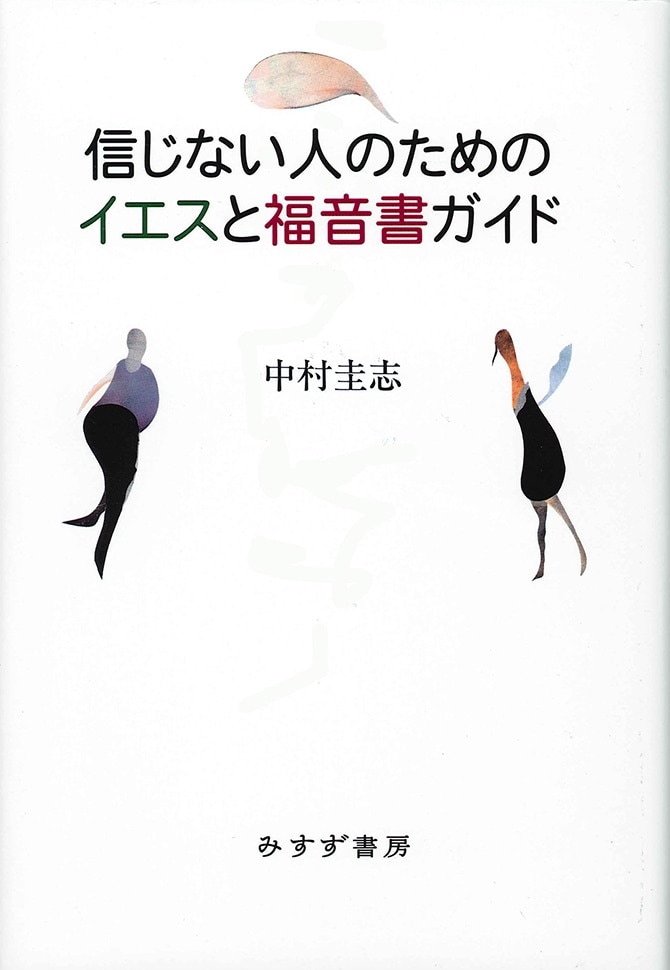
| 判型 | 四六判 |
|---|---|
| 頁数 | 288頁 |
| 定価 | 2,750円 (本体:2,500円) |
| ISBN | 978-4-622-07546-2 |
| Cコード | C1014 |
| 発行日 | 2010年9月24日 |
| 備考 | 現在品切 |
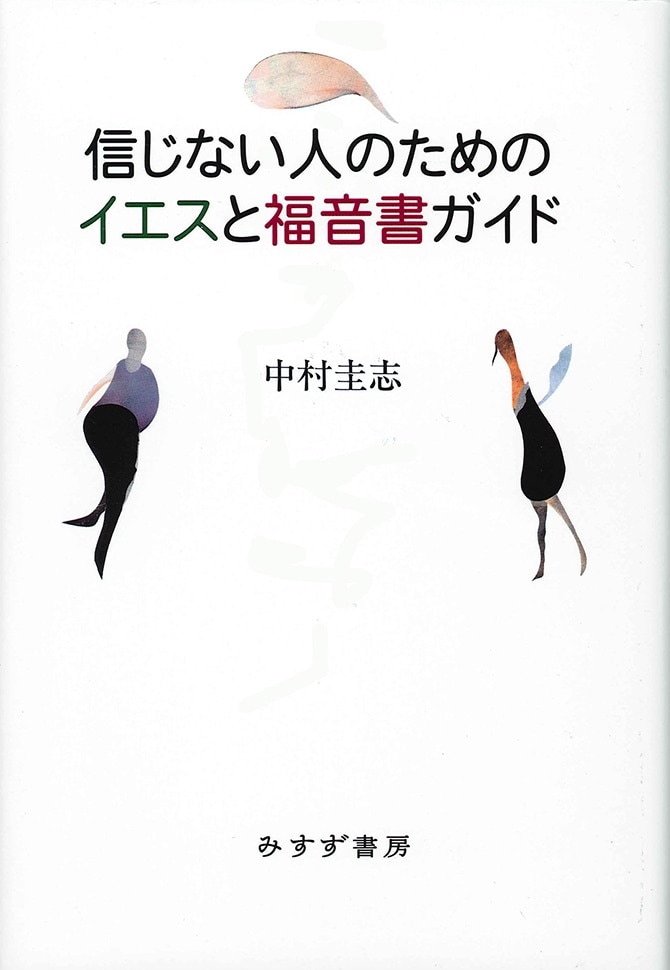
「キリスト教について紹介した本はたくさんありますが、本書の特徴は、宗教について懐疑的な人の合理精神を極力尊重している点にあります。イエスについて記録している四種の福音書の構造と内容を平明に示し、“信じない”一般読者が福音書に目を通したときに面食らってしまう点について、“たとえばこう考えてみてはどうか?”とサジェストしているにすぎません」。
キリスト教は、開祖イエスの生と死に人生の意味の源泉を求めようとする宗教である。イエスを信じる信じないにかかわらず、そもそもイエスとは何者かを知ろうとすることは、西洋文化の伝統を理解するうえで欠かせない。イエスの生涯を記録した福音書(マルコ、マタイ、ルカ、ヨハネ)の物語は、どのように成り立っているのか。パウロの信仰義認論とは何か。多数の図表を織り交ぜながら、イエスのメッセージを立体的に比較対照して、キリスト教のロジックの核心に迫る。
〔カバー画:秋山淑子《impromptu #3》(1994年)、《impromptu #6》(同)より〕
はじめに
キリスト教とは?/背景的知識——世界の宗教
第I部 イエスについての整理
1 イエスはどこの誰か?
イエスについての概要/当時の宗教状況/パレスチナの地理
2 誰が伝えているのか? 何に書いてあるのか?
福音書/物語の概要/《宗教学的考察》開祖の言説
3 「神の子」「キリスト」とはどういう意味か?
イエスの称号/屈折した「神的存在」
4 生前の活動はどのようなものであったか?
(1)病気治しと社会的タブー破り/(2)弟子の選別/(3)律法学者らとの論争/(4)終末に関する説教/(5)受難(逮捕・裁判・処刑)/《宗教学的考察》「物語」の特徴——神的権威のロジック
5 イエスの死はどのように記憶されたか?
死と「復活」/記憶の媒体/《宗教学的考察》挫折のロジック
6 イエスが救いであるとはどういう意味か?
贖罪死と高挙/信仰義認論/《宗教学的考察》信仰のロジックをめぐって/キリスト教のアイデンティティ?/付論——反復のロジックと一回性のロジック
第II部 四福音書・新約聖書についての整理
1 福音書の構成
四種の福音書、五段階の物語/共観福音書とQ資料
2 マルコ・マタイ・ルカ福音書
マルコ福音書の概観/マルコ福音書のディテール/マタイ福音書の概観/マタイ福音書のディテール/ルカ福音書の概観/ルカ福音書のディテール
3 ヨハネ福音書
ヨハネ福音書の概観/ヨハネ福音書のディテール
4 新約聖書の構成
二十七文書の合本/(1)パウロ直筆の手紙/(2)福音書と使徒言行録/(3)パウロの名による手紙/(4)その他の文書/「選外」となった文書——外典、グノーシス文書/新約世界の歴史
5 ユダヤ聖典(旧約聖書)の構成
キリスト教理解の背景/旧約聖書の構成/旧約世界の歴史
第III部 四福音書・パウロの手紙 サンプルチェック
はじめに——エピソードを横断的に見る
A 生誕物語
A1 神の子の誕生/A2 初めに言(ことば)ありき
B デビュー前の物語
B1 洗礼を受ける/B2 荒れ野にて
C 伝道物語
C1 ペトロを弟子にする/C2 故郷に拒否される/C3 罪を赦す権威/C4 悪霊祓い/C5 罪人と食事する/C6 ファリサイ派と徴税人/C7 らくだと針の穴/C8 幸いだ!/C9 たとえ/C10 あなたもそうしなさい/C11 わたしも罪に定めない/C12 放蕩息子の帰還/C13 すでに裁かれている/C14 おいしい水/C15 パンの奇跡/C16 子供と犬ども/C17 あなたはキリストです/C18 山上での変身/C19 わたしはある/C20 ラザロの復活/C21 エルサレム入城/C22 目を覚ましていなさい
D 受難物語
D1 女の塗油/D2 最後の晩餐/D3 裏切りの予告/D4 ペトロの否み/D5 ピラトの尋問/D6 イエスの死
E 復活物語
E1 復活/E2 顕現
P パウロの手紙
P1 贖(あがな)いの業/P2 死に至るまでの従順/P3 信仰によって義とされる/P4 権威とデタッチメント/P5 死者の復活
結論——メッセージと読解の多面性
おわりに
付録1 四福音書 内容一覧
付録2 パウロの手紙 内容一覧