戦後日本デザイン史
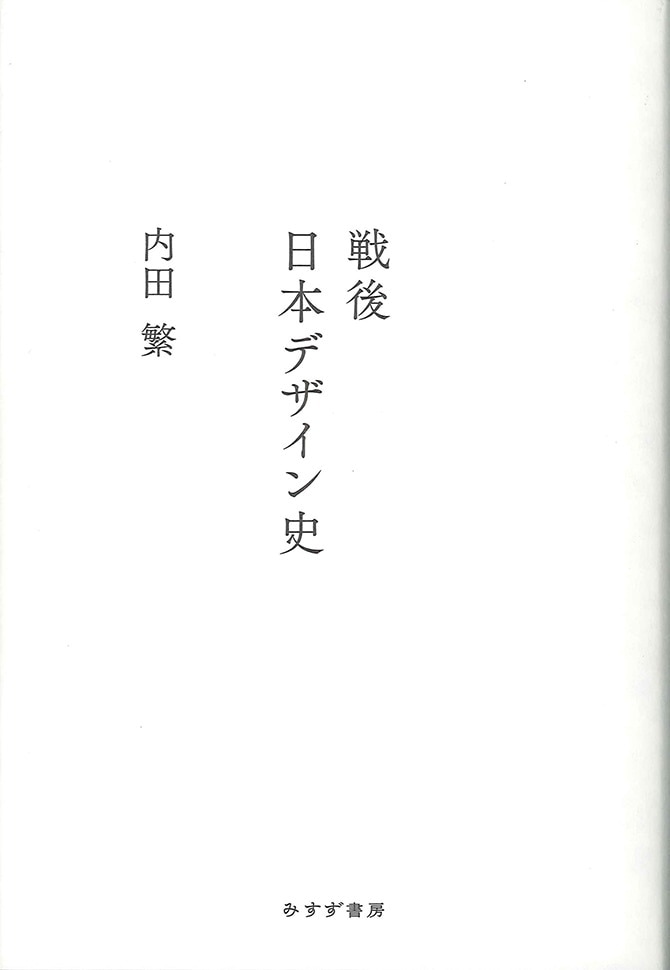
| 判型 | 四六判 |
|---|---|
| 頁数 | 416頁 |
| 定価 | 3,740円 (本体:3,400円) |
| ISBN | 978-4-622-07576-9 |
| Cコード | C0070 |
| 発行日 | 2011年8月25日 |
| 備考 | 現在品切 |
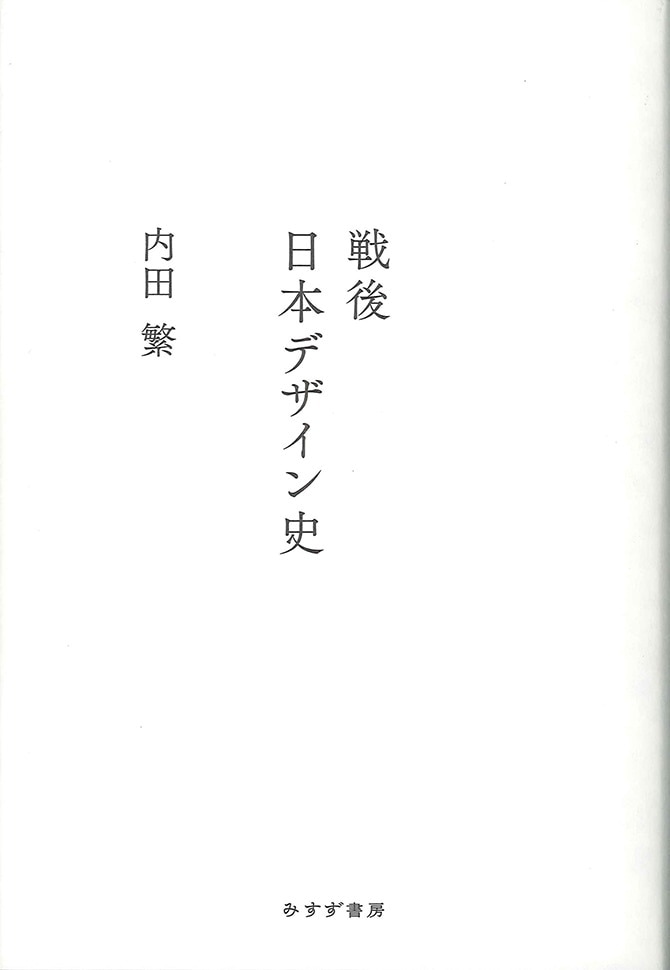
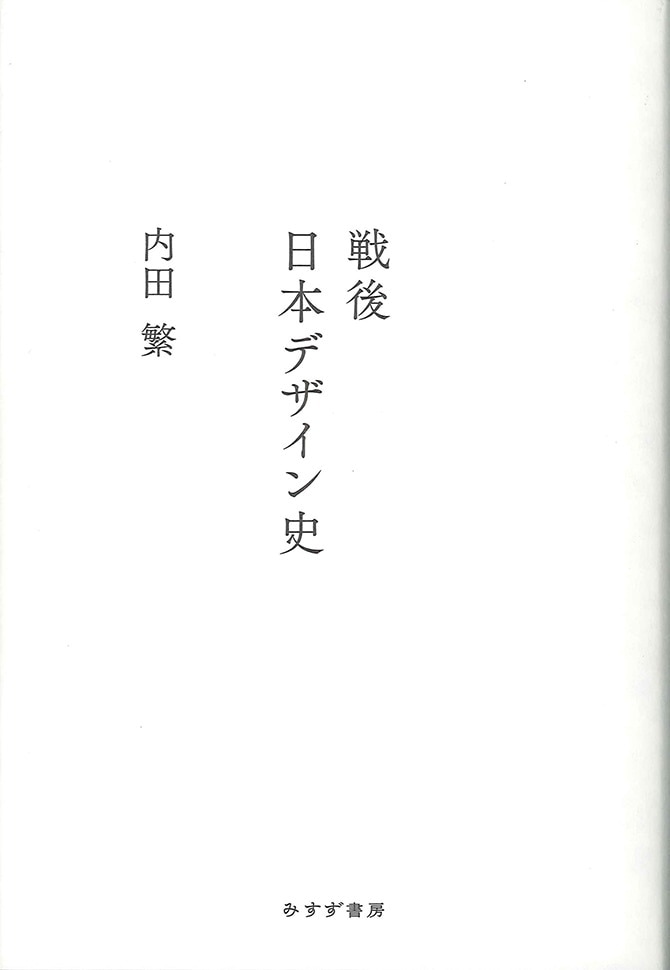
| 判型 | 四六判 |
|---|---|
| 頁数 | 416頁 |
| 定価 | 3,740円 (本体:3,400円) |
| ISBN | 978-4-622-07576-9 |
| Cコード | C0070 |
| 発行日 | 2011年8月25日 |
| 備考 | 現在品切 |
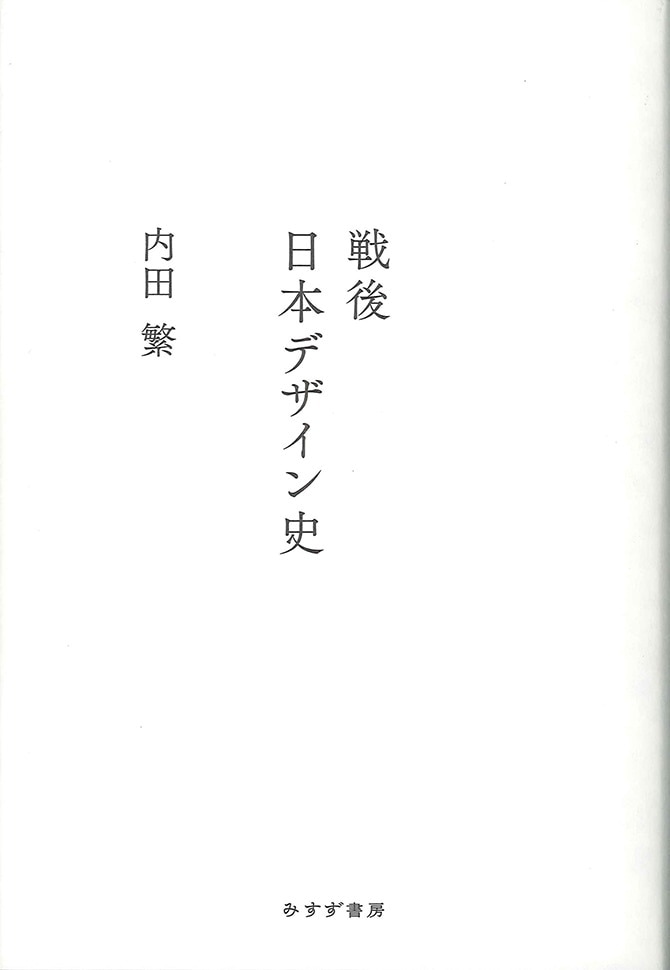
日本の戦後デザインは時代とどう向きあい、何を達成してきたのだろうか。
敗戦後、進駐軍用住宅と備品の製作で学んだアメリカンライフ。大量消費・画一化の産業社会に抵抗した60年代。日常の風景をつくろうとした70年代。モノよりイメージを売ったバブル期の企業戦略。デジタル隆盛下のコミュニケーションをかたちにするデザイン——。
時代の「いま」をつくるべく闘った、多くのデザイナーたちがいた。彼らの仕事には日本の伝統的美意識や、風土が育んだ身体・空間感覚が受け継がれ、いまや転換期にある世界のデザインに大きな示唆を与えようとしている。
インテリア・デザインの第一人者が、グラフィック・ファッション・プロダクト・インテリアなど諸領域にわたるデザインの歩みを描く。戦後史から未来へと、「人間の幸福と日常」のためのデザインを求めて、大きな視野を開く書。
はじめに 瓦礫の山を越えて
第一章 戦後デザインの出発——50年代
焼け跡の占領下から
進駐軍のデザイン
■デペンデント・ハウス
デザイン運動の黎明期
■日本デザインコミッティー
■グッドデザイン
■無地はスマートか
集団化するグラフィック・デザイン
■日宣美
■グラフィック55
デザインの社会的発展
■Gマークの発足
■毎日産業デザイン賞
戦後の製造業とデザイン
■1951年——日本のプロダクト・デザイン元年
■日本人の生活を変えたプロダクト
■インダストリアル・デザイナーの登場
第二章 工業化社会への疑問——60年代
高度経済成長の余波
もはや戦後ではない
■アメリカン・ウェイ・オブ・ライフ
■新たな消費社会の形成
■工業化社会の矛盾
世界デザイン会議
東京オリンピック
■夢の超特急
■国立屋内総合競技場……丹下建三
■ビジュアル・コミュニケーションとアートディレクター
ペルソナ展——若者たちの嵐
《空間から環境へ》展
インテリア・デザインの自立
■倫理的な秩序としての内部空間……岩淵活輝の登場
■ポップアートによる軽やかな空間表現……境沢孝の挑戦
■ミニマリズムと価値の転換……倉俣史朗の活躍
パラダイムの変換
■世界を揺るがした1968年問題
■ラディカリズム——工業化社会から情報化社会へ
アンダーグラウンド演劇とポスター
日宣美解散
第三章 工業化社会から情報化社会へ——70年代
戦後の終わり
■沖縄の本土復帰
■日中国交回復
■日本列島改造論
■オイルショック
■政治倫理の改革
大阪万博EXPO70
■マスタープラン
■アーバンデザインからマスターデザイン
■お祭り広場
■未来都市としての万博と景観計画
■岡本太郎と太陽の塔、未来空間
■お祭り広場の装置と芸術家の参加
企業戦略とアートディレクター
■街化された百貨店——西武百貨店の文化戦略
■ものから現象へ——パルコのイメージ戦略
■美の追求——資生堂のデザイン
■物語の夢——サントリーの広告
インテリア・デザインのゲリラ的展開
■フジエ・テキスタイルと北原進
■バルコンと内田繁・三橋いく代
■バー・ラジオと杉本貴志
■アートコレクターの家と植木莞爾
■ランブリング・ホームと森豪男
失われたカオス
■インサイド・ゼミ
■東京デザイナーズ・スペースと《ONE DAY ONE SHOW》
70年代のファッション・デザインの動向……高田賢三・三宅一生
DECOMAS委員会とCIの普及
ライフスタイルとパーソナル化へと向かうプロダクト
■70年代の社会と産業の動向
■団塊の世代のライフスタイル
■メーカーの組織力とプロダクトの変化
■新しいゲームの誕生
第四章 デザインの多様性——80年代
バブル景気とその時代
■日常性の喪失——バブル期のデザイン
■多様なる実験
複雑に交差するグラフィック・デザイン
■デジタル時代前夜
■田中一光の牽引力
■サブカルチャーと雑誌の躍動
挑戦しつづけるインテリア・デザイン
■多様性への挑戦——拡大する時代の要請
■ホテル イル・パラッツォのコラボレーション
■「連続した時間」「切断された時間」——飲食空間とブティック
■ファッション・デザイナーとの対話
・三宅一生と倉俣史朗
・山本耀司と内田繁
・コム・デ・ギャルソンと河崎隆雄
・高田喜佐と三橋いく代
文化推進力としての家具デザイン
■KAGU東京デザイナーズ・ウィーク’88
■日本人にとっての家具デザイン
世界に躍進したファッション・デザイン
プロデュースされた流通とプロダクト
■新しい流通の台頭
■無印良品とアクシス
■組織化されたプロダクト
第五章 環境の時代に生きるデザイン——90年代〜2010年
■ポスト・バブル社会のデザイン
■日常へのまなざし
三宅一生の周辺から
■プリーツ革命
■ものづくりの原点を問うことから生まれる衣服
広がるグラフィック・デザイナーの領域
■デジタル隆盛のなかで
■商品開発とコミュニケーション・デザイン
ローカリズムとグローバリズムの間で
■茶室から見えるもの
■ミラノサローネの真価とは
環境の時代のニューインダストリー
■サステナブルとユニバーサル
■インディペンデント・デザイナーたちからの提案
ポストバブルの都市とデザイン
■変化する東京の風景
■地域開発とデザインマネジメント
戦後のデザインが貫いたもの
■SO+ZO展の意味
終章 人間のためのデザイン
デザインとは何か
■デザインと文化人類学
■モノ至上主義からの脱却
■「モノの論理」から「関係の論理」へ
21世紀のデザインのあり方
■「弱さ」という感覚世界のデザイン
■変化 微細 いま
■これからのデザイン
人間・社会共同体・関係
デザイン・情報・イメージ
デザイン・環境・技術
おわりに 「無常観」から「無常美観」へ
■「美」は哲学
■「わび」というパラダイム
写真提供
人名索引
参考文献