高校図書館
生徒がつくる、司書がはぐくむ
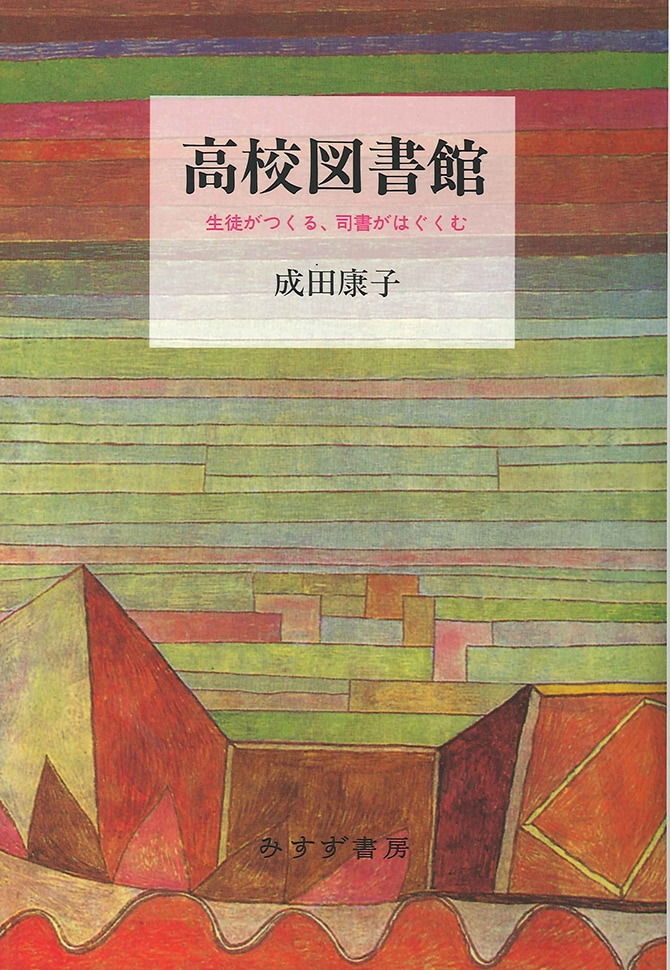
| 判型 | 四六判 |
|---|---|
| 頁数 | 280頁 |
| 定価 | 2,640円 (本体:2,400円) |
| ISBN | 978-4-622-07789-3 |
| Cコード | C0000 |
| 発行日 | 2013年11月6日 |
| 備考 | 現在品切 |
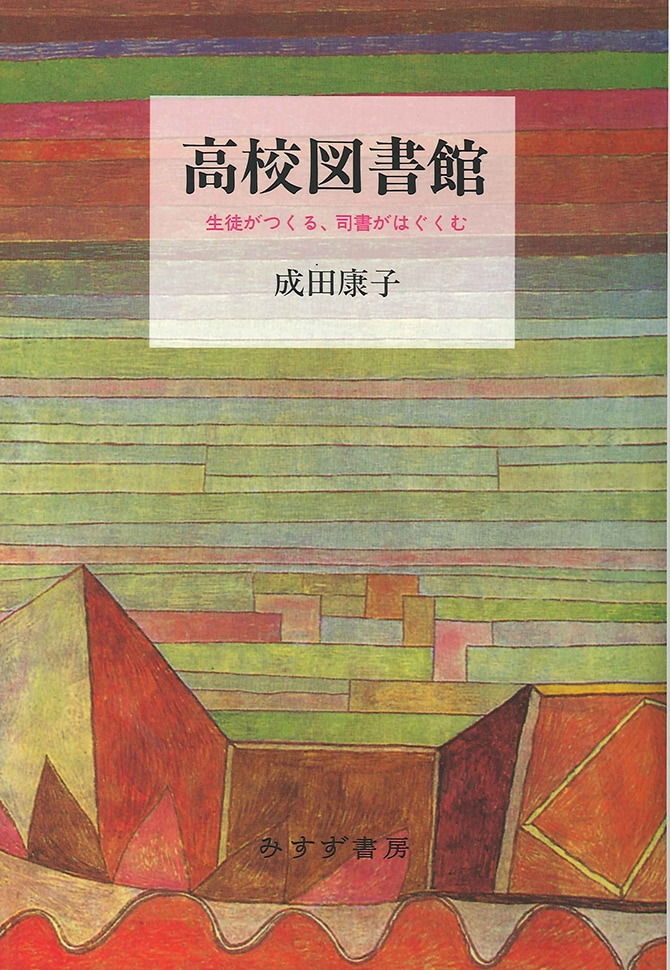
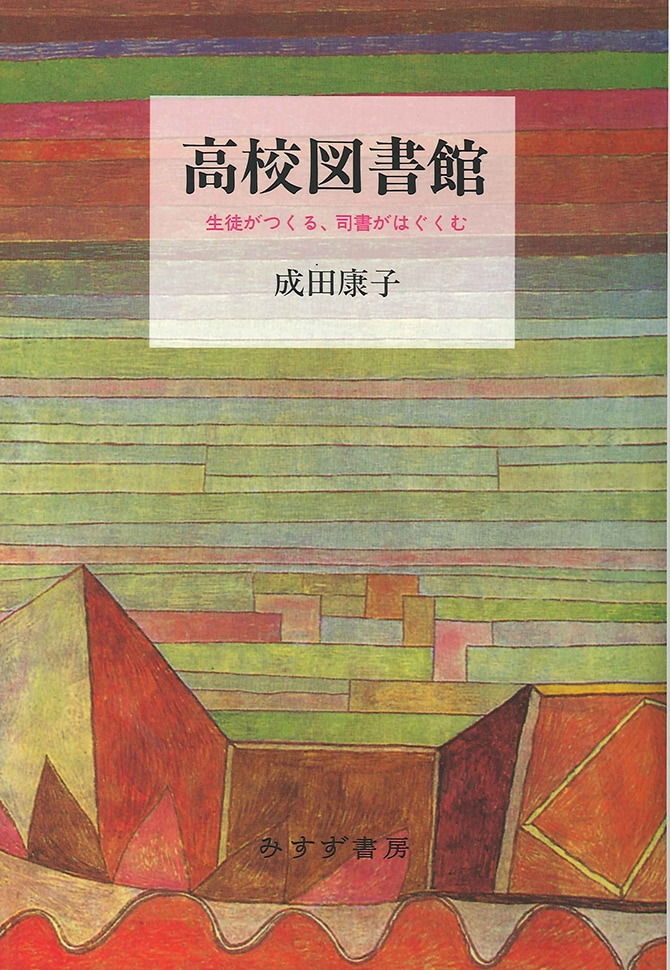
| 判型 | 四六判 |
|---|---|
| 頁数 | 280頁 |
| 定価 | 2,640円 (本体:2,400円) |
| ISBN | 978-4-622-07789-3 |
| Cコード | C0000 |
| 発行日 | 2013年11月6日 |
| 備考 | 現在品切 |
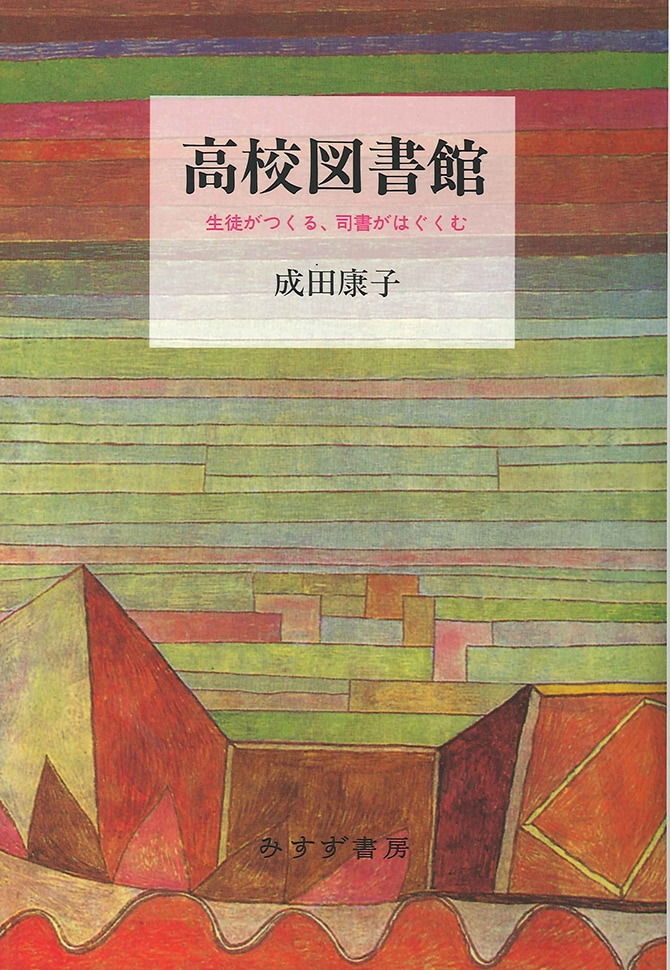
学校図書館は、生徒が「評価」されない稀有な場所である。
大人一歩手前の高校生にとって、そんな場所に「対話」のできる司書がいることは決定的に重要だ——それぞれの事情に耳をかたむけ、個々の希望や関心と資料とを繋げる人。さらに教師たちと資料を繋ぐ人でもある。高校図書館の活性化は司書の対応にかかっている。
しかし現実には、埃をかぶったままの図書館や、司書が不在で閉まっているところもある。図書館予算も少ない。「学校司書」の法制化は、まだ途についたばかりだ。
司書として30年のキャリアをもつ著者が、生徒や教師たち、さらに地域の人たちの応援を得て、「もっと自由でもっと楽しい場所にしたい」と日々模索する現場からの報告。図書館報の作成や学校祭参加、学外活動まで、具体的な示唆に富み、問題点も浮き彫りになる。
高校図書館に特化したはじめての本であり、同時に、広く学校図書館のあり方について再考をうながすだろう。「出版ニュース」誌の連載を一冊にまとめた。
はじめに
I 札幌月寒高校のころ
1 月高図書館のカウンターから——ブックトークの愉しみ
2 パスファインダーって何?
3 北海道高等学校図書研究大会
4 どうつくる学校図書館——鳥取県司書研修から
5 “冒険する図書館”——北海道・北広島市図書館
6 本をすすめる、すすめ合う
7 文字・活字文化推進機構のこと
8 教育再生は読書から
9 「学校図書館賞」受賞
10 卒業生54人の寄せ書き
II 大麻高校のころ
1 大麻高校図書館での第一歩
2 「購入希望用紙」という入口
3 「司書になりたい」夢がかなうためには
4 子どもに応える読書環境を
5 私が“人生”に出会った本
6 選書は楽し
7 パスファインダーで資料は活きる
8 読書空間のレイアウト
9 生徒の成長をもたらす読書へ——きっかけは一冊の本
10 読書の動機づけは大人の役割
11 高文連図書専門部のこれから
12 図書委員の活動
13 私の考える“高校図書館”
14 新入生に伝える「高校図書館とは何か 」
15 貸出冊数にこだわらずに
16 「朝の読書」の応援企画
17 専門性を深める——リカレント講座研修
18 同窓局員の回想から
19 メディア・リテラシーは語り合うことから
20 教育実習生を迎える
21 貸出カウンターから生まれる関係
22 図書館報づくり——意欲が育つ秘訣
23 言葉が共感を生む——図書館報「のほほ〜ん」一周年
24 キャリア教育をサポート
III 札幌南高校にて 1
1 発展する対話の向こうに——利用者のひとりとして
2 学校で展開する読書活動
3 司書教諭との協働
4 読書感想文にかかわって
5 夏休み、研修に出かける
6 書架整理は本を生かす
7 生徒が本に出会う日
8 マンガを活かす
9 私を育てた思い出の図書館
10 生徒の読書を見守る
11 “局員とともにつくる”とは
12 本、まわる
13 ひとりになれる時間
14 書店へ行こう
15 教科書から本へ、アクティブに
16 「BOOK CAFÉ四面書架」——学校祭参加
17 探究型の学習へ
18 出会いの演出を心がけて
IV 札幌南高校にて 2
1 学力テスト問題のピクトグラム
2 生徒と北海道立図書館を訪問する
3 『みんなでつくろう学校図書館』
4 予算の着実な執行を
5 正解のない問いを考える場として
6 学校図書館は教育全体のインフラ
7 子どもの未来のための予算
8 「本は利用されるためのものである」(ランガナタン博士の第一法則)
9 書店への動線
10 心が弱ったときの優先席
11 「専任」「専門」「正規」の学校司書
12 学校司書は何をどう研修するか
13 見えてきた道筋——学校司書の法制化
14 図書館を見て志望校を決める
15 「言語活動の充実」再考——図書館機能の発揮を
16 三重県の学校図書館行政から学ぶ
17 学校風土から「学び」をおもう
18 対話あふれる図書館
19 本をめぐるキャッチボール
20 『ルピナスさん』から贈られた人生の送りかた
あとがき
付録 なぜ学校司書の法制化が必要か
略年表 学校図書館から見た学校司書法制化への動き