生のものと火を通したもの
神話論理 I
LE CRU ET LE CUIT
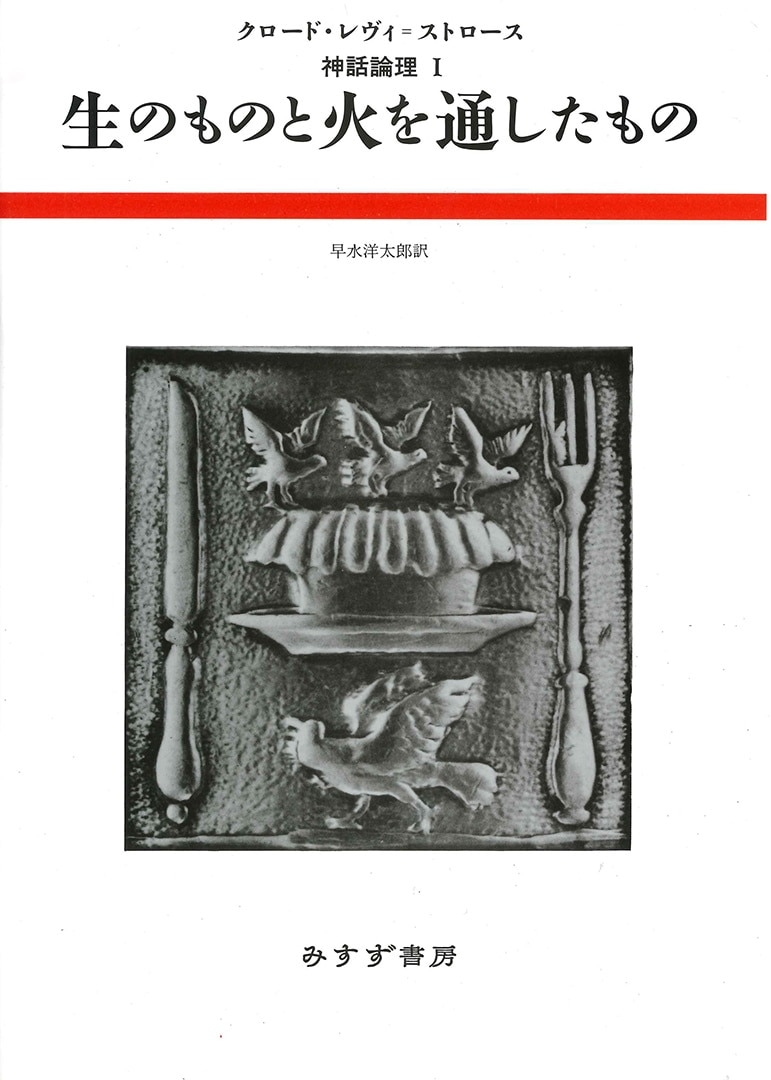
| 判型 | A5判 |
|---|---|
| 頁数 | 576頁 |
| 定価 | 8,800円 (本体:8,000円) |
| ISBN | 978-4-622-08151-7 |
| Cコード | C1010 |
| 発行日 | 2006年4月14日 |
| 備考 | 在庫僅少 |
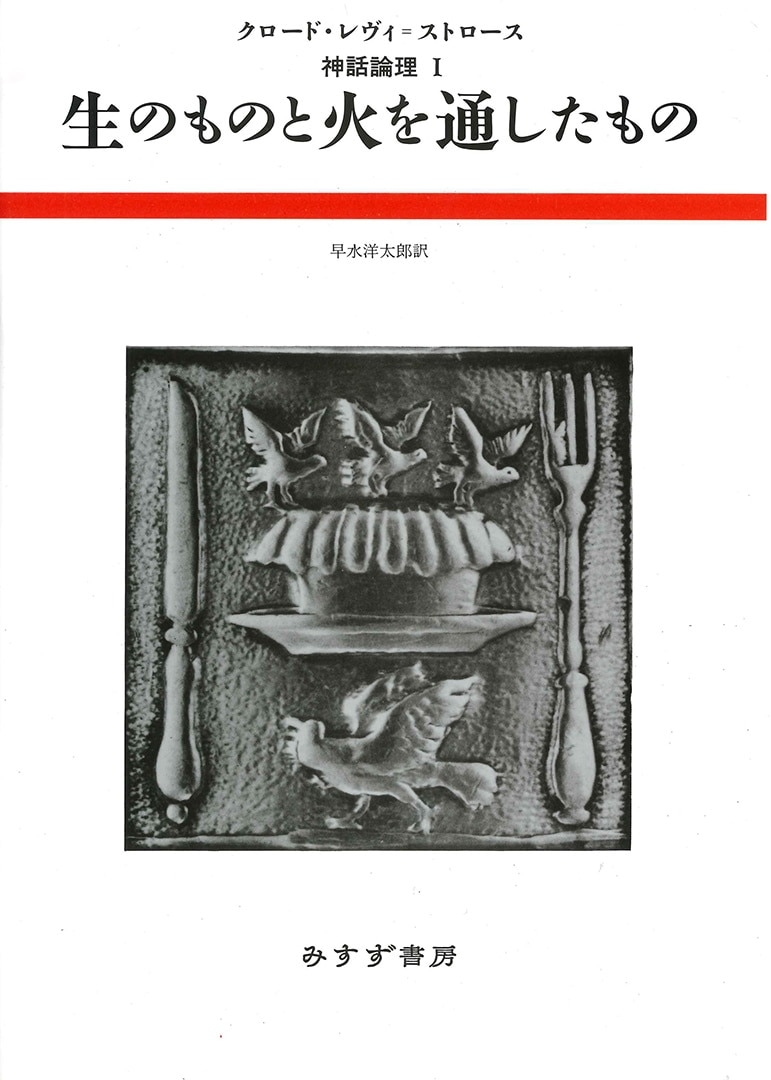
LE CRU ET LE CUIT
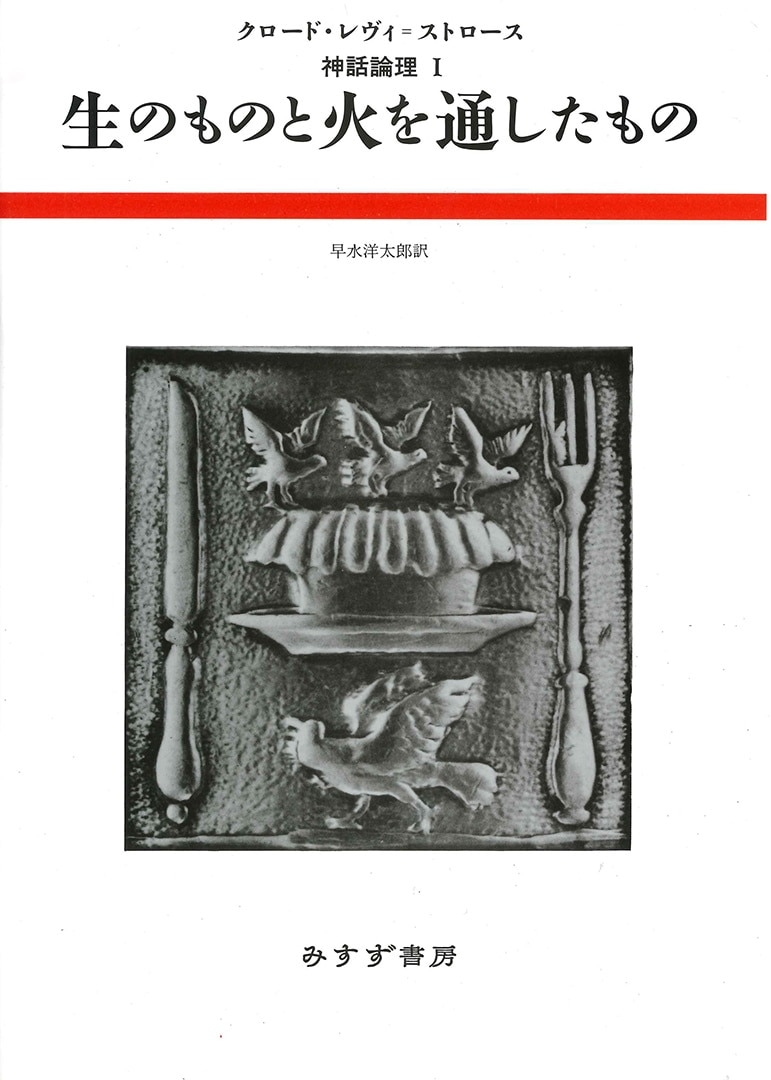
| 判型 | A5判 |
|---|---|
| 頁数 | 576頁 |
| 定価 | 8,800円 (本体:8,000円) |
| ISBN | 978-4-622-08151-7 |
| Cコード | C1010 |
| 発行日 | 2006年4月14日 |
| 備考 | 在庫僅少 |
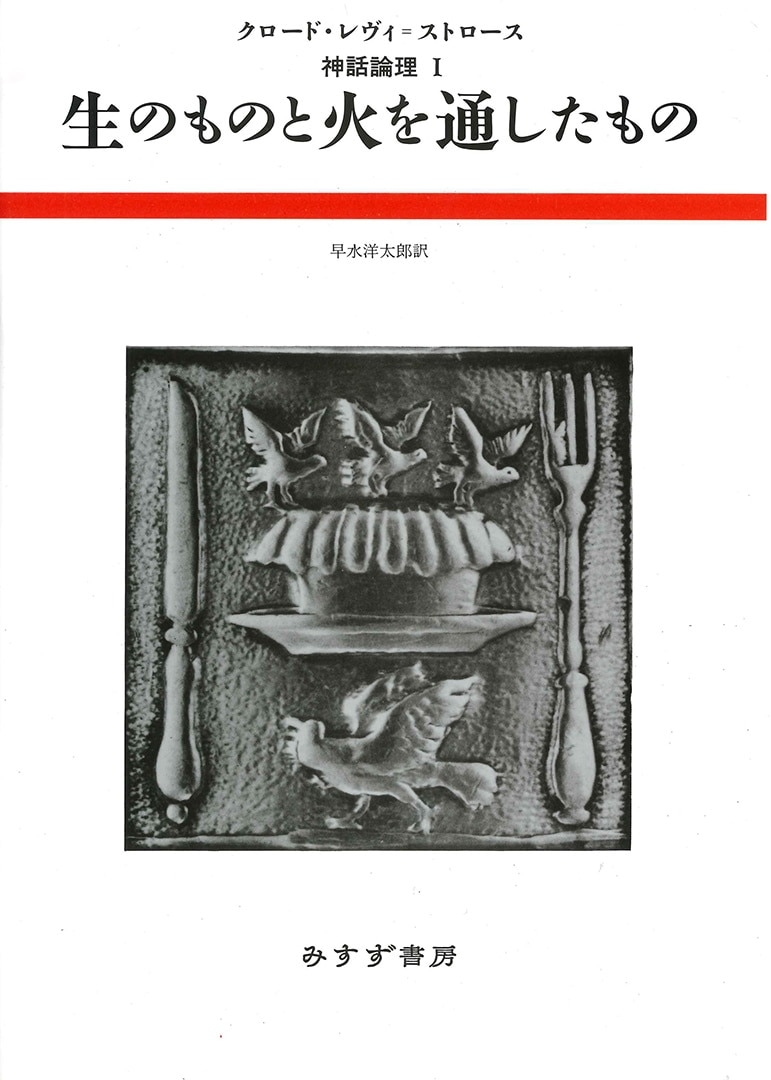
〈わたしは、先住民の哲学において料理が占める真に本質的な場を理解しはじめた。料理は自然から文化への移行を示すのみならず、料理により、料理を通して、人間の条件がそのすべての属性を含めて定義されており、議論の余地なくもっとも自然であると思われる——死ぬことのような——属性ですらそこに含められているのである〉(本書239ページ)
構造人類学の探究の頂点に位置し、20世紀思想の金字塔と讃えられるレヴィ=ストロースの主著『神話論理』(全5巻・原著は全4巻)を、ここに刊行する。10年以上の年月をかけ、ほぼ2000ページを費やして成ったこの大著は、南北アメリカ大陸先住民の813の神話を扱いながら、自然から文化への移行を読む驚くべき想像力、南アメリカのボロロの神話から北アメリカまで範囲を広げた地理的運動のダイナミズム、神話の論理にみられる二項対立の思考への構造分析の緻密さによって、まさに比類がない。神話的思考の普遍性をしめした、圧巻の文明批判の書でもある。
『生のものと火を通したもの』『蜜から灰へ』『食卓作法の起源』『裸の人1・2』の5巻は、それぞれが独立しながら相互に関係し、さらに『神話論理』全体が『今日のトーテミスム』『野生の思考』から『やきもち焼きの土器つくり』まで、著者のほぼ全著作と照応している。他巻同様、音楽的構成のきわだつ神話論理I『生のものと火を通したもの』は、「序曲」に続いて、全体の基準神話となるボロロの「鳥の巣あさりの神話」が論じられる。
ここからすべては始まるのだ。
凡例
記号表
序曲
I
II
第1部 主題と変奏
I ボロロの歌
a 鳥の巣あさりのアリア/b レチタティーヴォ/c 第一変奏/d 不連続という間奏曲/e 第一変奏の続き/f 第二変奏/g コーダ
II ジェの変奏(六つのアリアとそれに続く一つのレチタティーヴォ)
a 第一変奏/b 第二変奏/c 第三変奏/d 第四変奏/e 第五変奏/f 第六変奏/g レチタティーヴォ
第2部
I 行儀作法についてのソナタ
a あからさまな無関心/b カエテツのロンドー/c 子供の礼儀作法/d 笑ってはならない
II 短い交響曲
第一楽章 ジェ/第二楽章 ボロロ/第三楽章 トゥピ
第3部
I 五感のフーガ
II オポッサムのカンタータ
a オポッサムの独唱/b ロンドー形式のアリア/c 第二の独唱/d フィナーレのアリア 火と水
第4部 平均律天文学
I 三声のインヴェンション
II 二重逆転カノン
III トッカータとフーガ
a プレヤデス星団/b 虹
IV 半音階の曲
第5部 三楽章からなる田舎風の交響曲
I 民衆的主題にもとづくディヴェルティメント
II 鳥たちの合唱
III 結婚
アマゾニア先住民と神話世界——『神話論理』の現在(木村秀雄)
訳者あとがき
動物図集
文献
神話索引
総合索引
『裸の人』2の刊行をもちまして、レヴィ=ストロース『神話論理』は邦訳全5冊が完結いたしました。原著刊行から四十年越しのシリーズ完結です。
フランス語版第 I 巻の出版は1964年、みすず書房はその二年後に日本語版版権を取得し、『野生の思考』(1976年)の名訳で知られる故・大橋保夫先生に、『野生の思考』の次に翻訳をお願いする予定だったときいています。構造主義が日本に本格的に紹介されつつあった当時、訳者は大橋先生をおいて考えられませんでした。
大冊のため共訳のチームが組まれ、じっさいに『野生の思考』の直後から翻訳が始まりました。しかし原著者の文章をつかみとる困難に加えて、訳語や文体をめぐる訳者間相互の厖大な調整、その上に諸事情も重なって、ようやく大橋訳「序曲」が月刊『みすず』に掲載されたのが1992年初頭のことでした(『みすず』1992年1月号・2月号に分載)。
全巻の翻訳態勢を見直し再スタートという矢先に、大橋先生は急逝なさいましたが(1998年)、動き出したプロジェクトは巨大な車輪が少しずつ回るように前進しました。第 I 巻・第 II 巻を単独訳された早水洋太郎先生は、大橋保夫先生門下です。第 III 巻と第 IV 巻1・2では、吉田禎吾先生・渡辺公三先生・木村秀雄先生を中心とする共訳になっていることはごらんのとおりです。それにしてもさらに年月がかかったのは、総力を結集して翻訳にのぞんでも、生い茂る神話の森の奥深くまでレヴィ=ストロースの踏み跡を見通すのはとてもむずかしいことだったからです。
著者レヴィ=ストロースの生前に日本語版をお目にかけられなかったのが悔やまれますが、これまで長いあいだお待ちいただき、さまざまに支えてきていただきました読者のみなさま、関係者のみなさま、本当にありがとうございました。 感謝申し上げます。(2010年2月)