絵の幸福
シタラトモアキ論
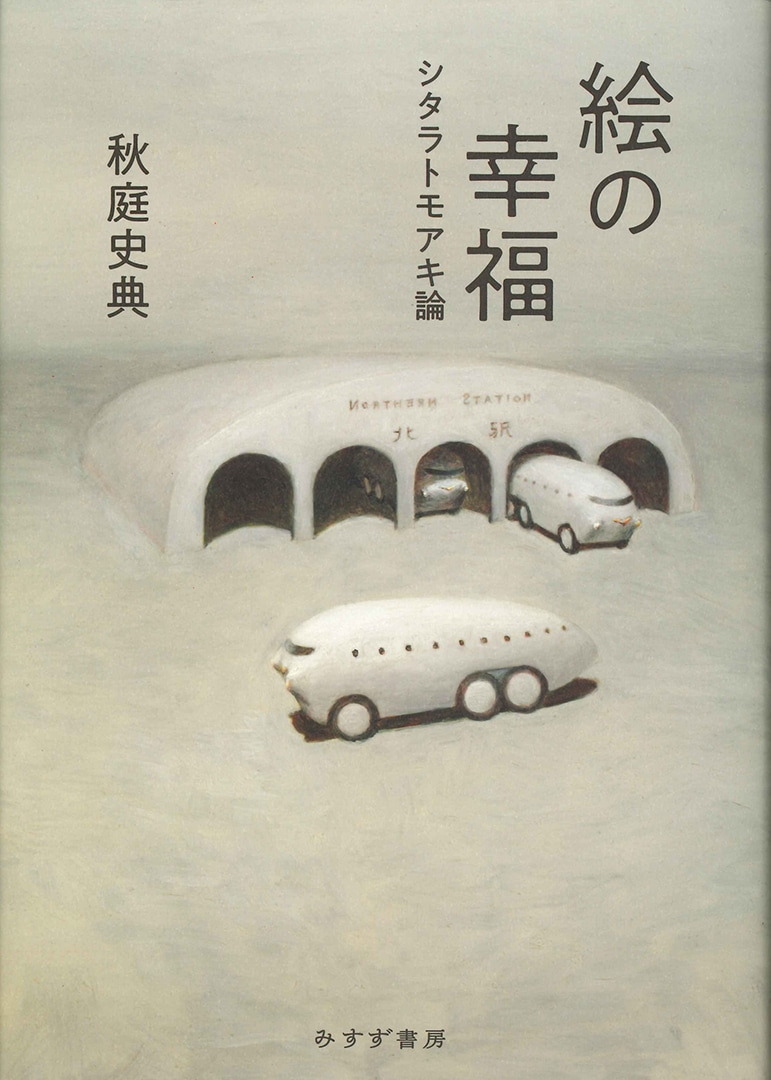
| 判型 | A5判 |
|---|---|
| 頁数 | 188頁 |
| 定価 | 4,400円 (本体:4,000円) |
| ISBN | 978-4-622-08932-2 |
| Cコード | C1071 |
| 発行日 | 2020年9月16日 |
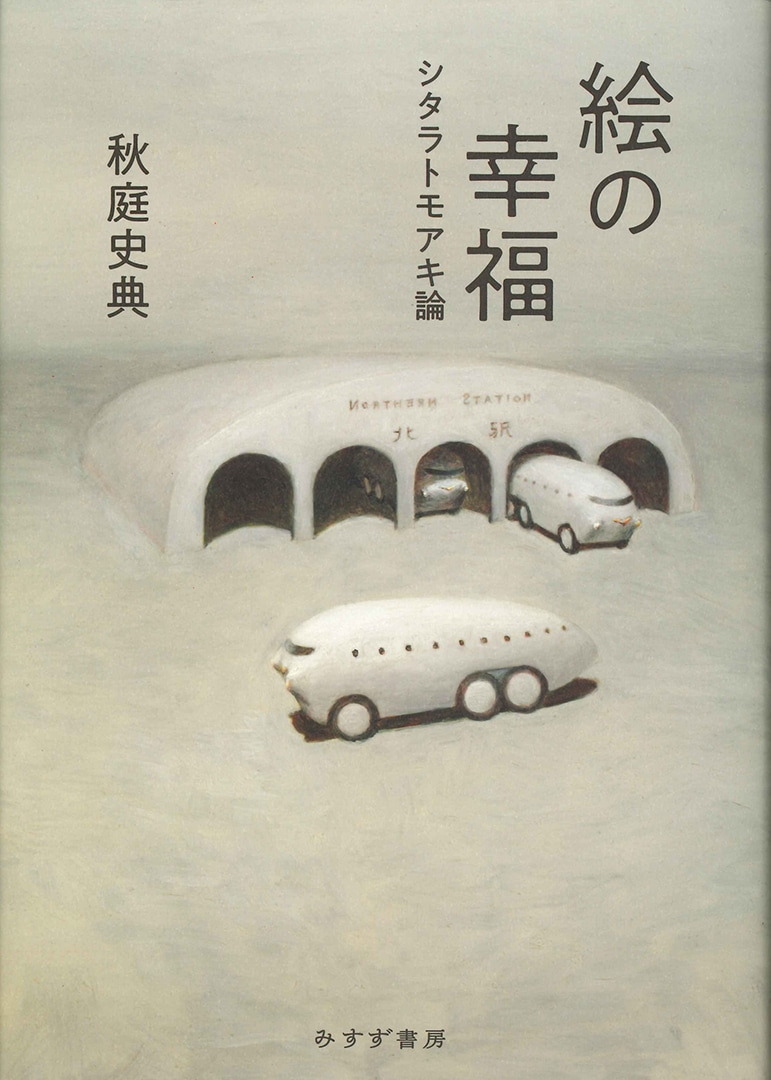
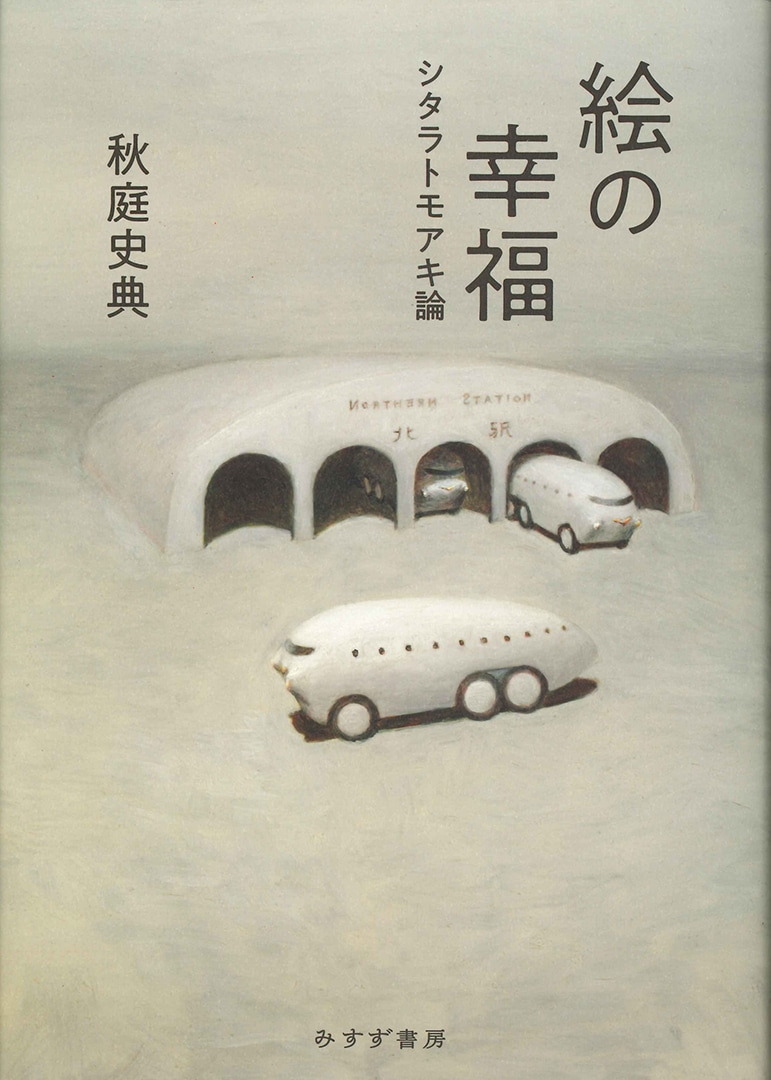
| 判型 | A5判 |
|---|---|
| 頁数 | 188頁 |
| 定価 | 4,400円 (本体:4,000円) |
| ISBN | 978-4-622-08932-2 |
| Cコード | C1071 |
| 発行日 | 2020年9月16日 |
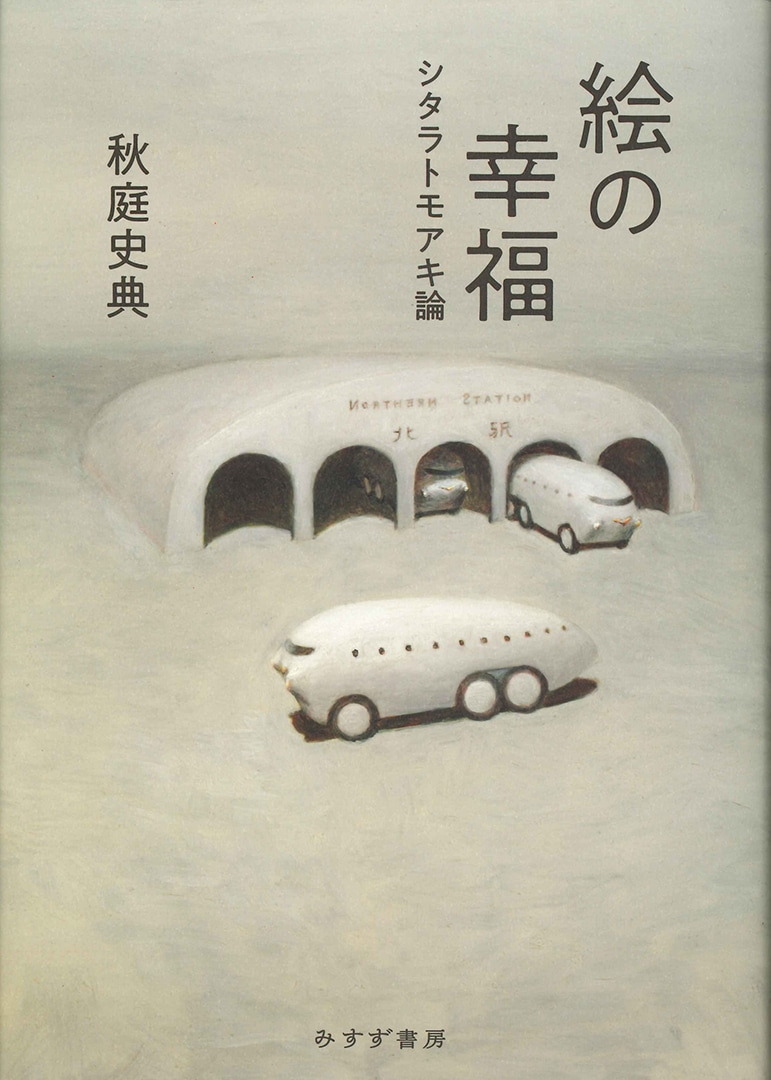
幼少時から「息をするように絵をかいてきた」画家・設楽知昭は、ある時、絵をかくとはどういうことかがわからなくなった。ぐにゃぐにゃになり、血みどろになり、言いよどみながら、生や死という、人間であればだれもが対峙するものと向き合う画家。そのリハビリテーションの試みを、美学研究者が追った。
著者が画家を観察しつつ、芸術制作をみる基礎においたのは、ギリシア語の「中動態」すなわち能動/受動、主体/客体の対立とは別の考え方だ。
見ることとかくことが直結して反転するよう、鏡に指で描いて写し取る。等身大の人形を吊ってポリエステルフィルムにトレースをする「人間写真機」。透過光と反射光の原理。人工夢—透明壁画。二つ折り。雲と穴。模型。妄想をかくのでなく、かくこと自体が妄想であった大きなノート。
いつしか絵とそうでないものとの区別が働かなくなり、力の抜けた「無為の場」が現れる。絵をかきながら、そんな〈仕組みをつくる〉こと。自分を自分として生きるという希望、すなわち「自由」。
画家は愛知県立芸術大学教授として長年、学生の教育にも尽力してきた。学生と対話し、技法やアイデアの練り方を語っている。画家にとっての幸せとは、人が幸せに生きるとは。論考・対話・画集を一冊にした美しい本。
はじめに
I 絵を描くことがわからなくなった画家
第1章 生きるとは
第2章 絵が生き続けるために
第3章 絵が生き続けさせるものたち
第4章 絵のしあわせ
II シタラと学生の対話
《大きな私と小さな私》
《片腕ノ私ガ手ヲ洗オウトスル》
タイトルをつけるということ
線で描くことについて思うこと
「五十年分の光の映画」(芸術祭のパンフレットの挨拶文)
白土舎の個展
《透明壁画──人工夢》
《ロボットになって街を歩いた》
《ガール・ピアニカ》《母の炎》
《胴切り》《空穴》《クピドの現われる街》《曇空二穴ノ空イテイル絵》
《ホテル・パシフィカ》
凸と凹の絵
《二つ折りにして封筒にいれました 手紙》
《モレスキンの大きなノート》
《鏡》《鏡ヨリモノタイプ》
あとがき
参考文献