免疫から哲学としての科学へ
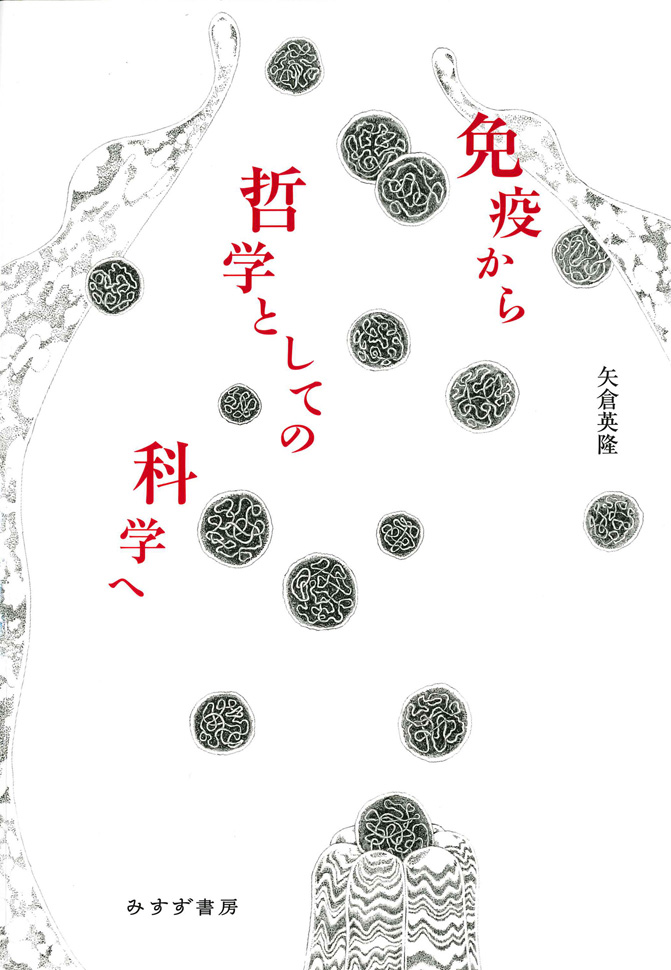
| 判型 | 四六判 |
|---|---|
| 頁数 | 352頁 |
| 定価 | 4,400円 (本体:4,000円) |
| ISBN | 978-4-622-09600-9 |
| Cコード | C1040 |
| 発行日 | 2023年3月16日 |
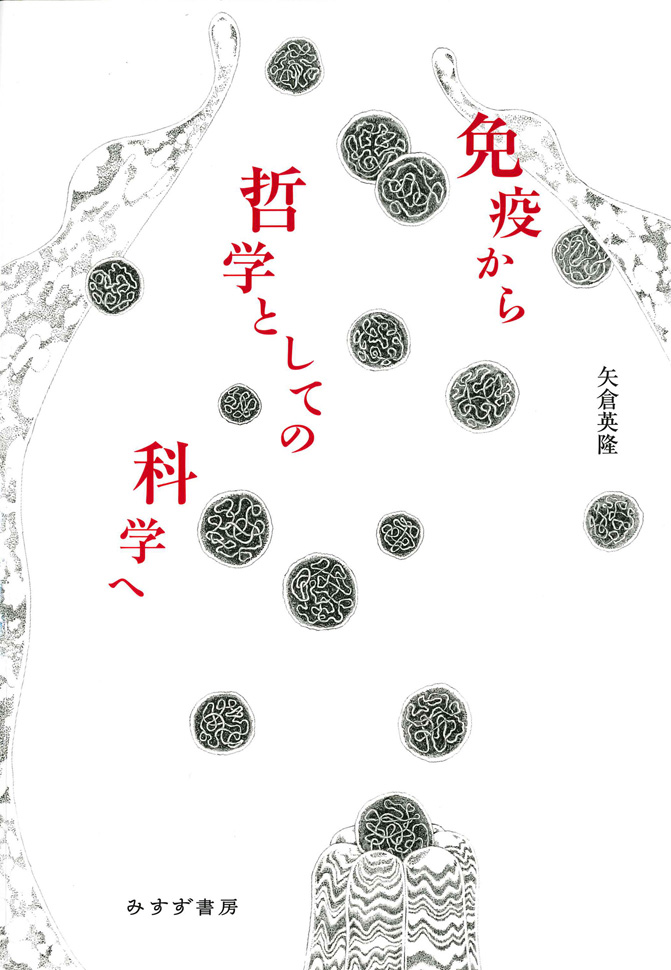
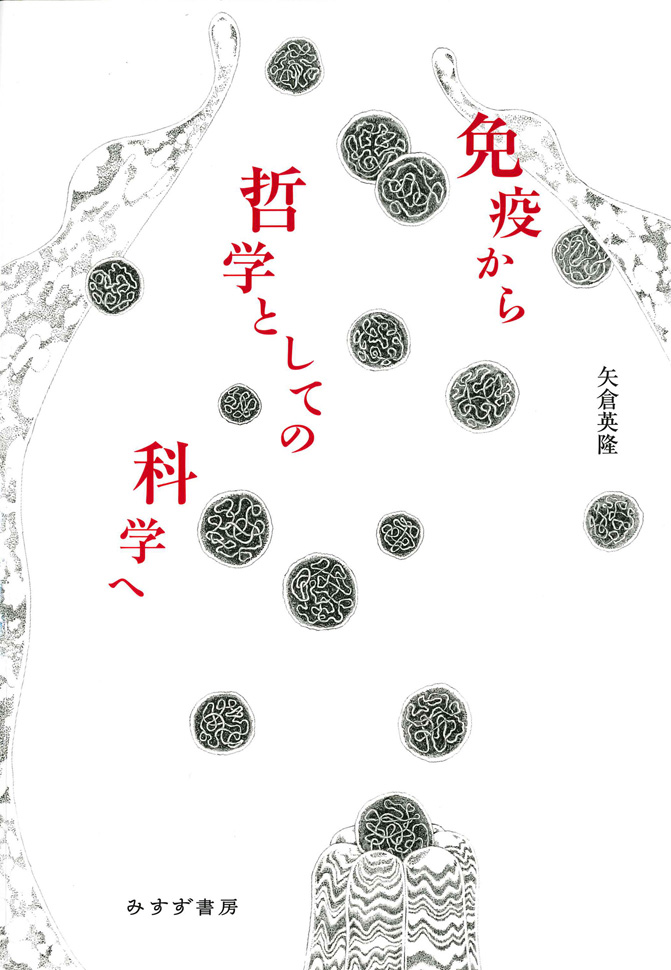
| 判型 | 四六判 |
|---|---|
| 頁数 | 352頁 |
| 定価 | 4,400円 (本体:4,000円) |
| ISBN | 978-4-622-09600-9 |
| Cコード | C1040 |
| 発行日 | 2023年3月16日 |
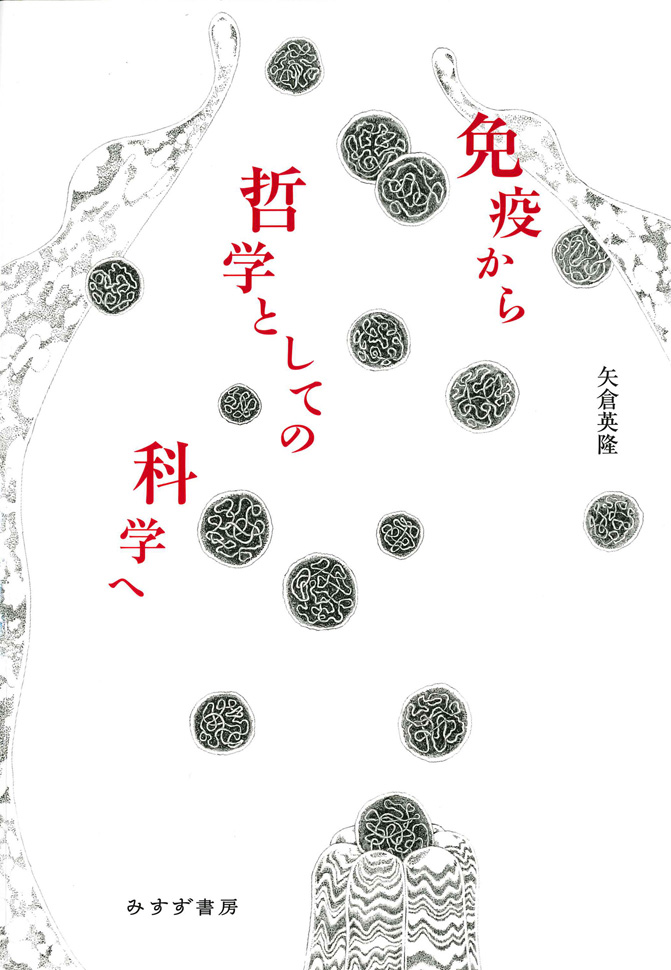
免疫学における30年以上の研究生活が終わりに近づいたとき、著者は大きな不全感を抱えていた。長いあいだ科学の領域にいたものの、免疫というものの全体あるいは本質は何なのか、さらにいえば、科学という営みが持つ特質とはどういうものなのかという根源的な思索が欠落していたことに気づいたからである。この不全感を埋めるために、著者はフランスでの哲学研究の道を選んだ。免疫学が生み出す成果には哲学的問題が溢れているからである。しかし著者がそこで見たものは、科学的であろうとする哲学の姿だった。そして現代の科学一般はそもそも、哲学を必要としているようには見えない。
科学は解が出るよう自然に問いかける一方で、哲学は解が得られないにもかかわらず真理の探究に向かうという逆説的な営みである。そして科学がそのつど解を得て前に進むのに対し、永遠に開かれた探求こそが哲学であるといわれる。免疫という現象を理解するためにはその両方が必要ではないか。またそうすることは、科学と哲学が実り多い関係を結び直す契機となりうるのではないだろうか。
免疫の働きは防御だけではなく、実証科学が明らかにしたその姿を本書で追うことは驚きの連続である。そこへ哲学から渡された橋から見える眺望は、さらなる驚異と知的刺激に満ちている。
英訳刊行
Immunity: From Science to Philosophy (Routledge, 2024)
https://www.routledge.com/Immunity-From-Science-to-Philosophy/Yakura/p/book/9781032776590
はじめに
第1章 免疫学は何を説明しようとしてきたのか
1 「免疫」という言葉、あるいはメタファーについて
2 免疫学が確立される前に明らかにされていたこと
3 近代免疫学の誕生
4 新しい選択説の出現
5 免疫を担う主要要素はどのように発見されたのか
6 免疫反応の開始はどのように説明されたのか
7 クローン選択説に対抗する新しい理論的試み
8 新しい理論的枠組みを生み出すもの
第2章 自己免疫、共生、そしてオーガニズム
1 自己免疫
2 微生物との共生
3 胎児との共生
4 共生が問いかける問題
5 オーガニズムとは何をいうのか
第3章 オーガニズム・レベルにおける免疫システム
1 ぼやける免疫システム内の境界
2 オーガニズム全体に浸透する免疫システム
3 情報感知システムとしての免疫
4 内部環境、ホメオスタシスを再考する
第4章 生物界に遍在する免疫システム
1 細菌の免疫システム
2 植物の免疫システム
3 無脊椎動物と無顎類の免疫システム
4 免疫を構成する最小機能単位
5 ミニマル・コグニション問題
6 最古の認知システムとしての免疫
第5章 免疫の形而上学
1 「科学の形而上学化」という試み
2 スピノザの哲学から免疫を考える
3 カンギレムの「生の規範性」から免疫を考える
4 生命の本質に免疫があり、免疫の本質には規範性を伴う心的性質が包摂される
5 免疫の形而上学が呼び込むもの、あるいは汎心論的世界
第6章 新しい生の哲学に向けて
おわりに
謝辞
図版クレジット
注
索引