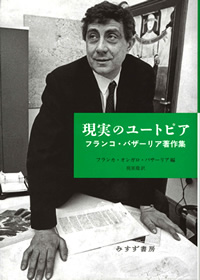
2019.08.26
イタリア精神病院廃絶の中心となった医師の思想。編者による「緒言」を転載
『現実のユートピア――フランコ・バザーリア著作集』 F・O・バザーリア編 梶原徹訳
原田光子『真実なる女性 クララ・シューマン』
2019.08.26
昭和16年秋。第一書房から出版された『眞実なる女性 クララ・シュウマン』の初版5000部は、2週間で完売となった。多くの人から出版社に増刷の希望が寄せられたが、用紙制限、出版許可制がすでに始まっていた当時、第二刷の5000部がようやく出たのは翌年になってからのことで、発売即日で店頭から消えたという。戦争へと向かう時代の空気とは別世界のように感じられる19世紀ドイツの女性ピアニストの一生を描いたこの評伝が、それほどまでに当時の日本人に待ち望まれ、読む者の心を打ったのはなぜだったのか。
音楽の著述で身を立てたい、クララ・シューマンの生涯を書いてみたい、との希望をいだく原田光子に引き合わされた音楽評論家、野村光一氏はこう記している。
初対面の彼女は、すべて輪郭のはっきりした印象を起こさせる人だった。背も高く、そして身体もがっちりしていたし、顔の造作なども、目鼻立ちが大作りで、きりりとしていた。(……)ピアノを弾いたり、音楽の話をしたりして、時の過ぎるのも忘れたが、この一日の会見で、わたしは彼女がピアノ音楽に底知れぬ情熱と、計り知れぬ知識を持っているのにすっかり度肝を抜かれてしまったのである。
(原田光子訳編『大ピアニストは語る』解説より)
19世紀初めに生まれたクララ・シューマンの一生は、最初は彼女の父の手で、長じてからは自身によって書き続けられた日記のなかに、つぶさに見ることができる。クララのピアノの師であり、演奏活動のマネジメントとプロモーションを一手に引き受けていた、父のフリードリッヒ・ヴィークは、幼い娘がまだ文字も書けないころから、「私は」とクララの一人称で、その日その日の娘のピアノの練習と上達、演奏会の様子を記していた。その父に師事するために9歳年上のシューマンがヴィーク家に下宿するようになった少女の日々、初めての外国への演奏旅行、少女から娘へと成長し、父との闘いを経て、シューマン夫人となる日々が、クララの日記に書きとどめられる。
高い身分であったとしても、家系図のなかにその名前と誕生、結婚、死没の記録だけがわずかにのこり、彼女の生きた道のり、心に抱いた想いなど後世に伝わることもなかった女性がほとんどだった時代である。妻となってからはシューマンと交替で「家族の日記」を書く一方、結婚生活をとおして、また、シューマンの死ののちも、あれだけの多忙な毎日のなかで書きつづけられた日記、それに劣らず膨大な量の往復書簡……それらによって、クララの一生のほぼすべてとともに、シューマンやブラームス、ショパン、メンデルスゾーン、リスト、ワグナーといった人びとの言葉や、彼らの音楽、なにげない日常もまた、いきいきと現代の私たちに伝えられているのだ。
筆を持つこともまれになった現代の私たちにくらべて、200年前の人びとが、何倍もの速さで簡単に書いたわけではない。ことに、自分の心だけでなく、相手との心のやりとりが加わる手紙ならなおのこと、時間はかかった。それでも、人は書き、受け取った手紙を大切に保管し、増えてゆく日記帳を死ぬまで手元に置いた。
気が遠くなるほど膨大な、貴重な材料からどう取捨し、どのように配して、編者・著者が自分のことばで組み立てて、評伝、書簡集、回想録に編むか。数かぎりない可能性が存在する。だからこそ、「底知れぬ情熱」「計り知れぬ知識」をもった編者、著者、訳者を得てはじめて、肉付けられて、著作となることができる。
著者は『眞実なる女性 クララ・シュウマン』に続いて、ショパン、リストの生涯に着手した。もともと強くない体をおして脱稿するや、さらに『コジマ・ワグナー』の出版に向けて意欲を燃やした。しかし、第一書房の長谷川巳之吉より、出版統制の強化はとうていこの本の出版を許可しないだろう、と伝えられて、彼女はふたたびクララへと戻ってゆく。クララとブラームスの『友情の書簡』の翻訳に打ち込み、最後のページまで訳しおわった原稿をのこして、昭和十九年春より病床に伏し、空襲の激しくなるなか、二年後の死まで湘南の病院で療養生活を送った。野村氏は、最後のときまで「その名の示すように明るくて、あでやかで、はっきりしていた」彼女の死は、「咲ききった大輪の牡丹の花が一時に飛び散ったようなものであった」と伝えている。

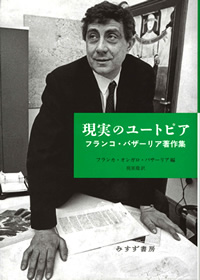
2019.08.26
『現実のユートピア――フランコ・バザーリア著作集』 F・O・バザーリア編 梶原徹訳

2019.08.08
S・ブルサッテ『恐竜の世界史――負け犬が覇者となり、絶滅するまで』黒川耕大訳 土屋健日本語版監修