トピックス
多田隆治『気候変動を理学する』
古気候学が変える地球環境観
新刊の『気候変動を理学する』では、地球の複雑な営みをできるだけ明快につかむためのコツ、ポイントがいくつか強調されている。そのうちの二つだけ、ちらっと紹介しておこう。それを知るだけでもちょっと勉強になる。
■地球の見方のポイントその1──【タイムスケール】
- 「よくある大きな誤解は、……多くの人が長いタイムスケールでのプロセスと短いスケールのプロセスをごちゃ混ぜにして考えていることです。情報の多くはタイムスケールのことを意識せずに流布されているのです。」(本書 p. 128)
 (図をクリックして拡大)
(図をクリックして拡大)『気候変動を理学する』図2-1(p. 55)
たとえば右の図を見てみる。この図の左半分は地球の歴史年表で、横に飛び出た棒で氷河時代が示されている。氷河時代とは、極域に氷床(広い領域を覆う氷塊)がある時代のこと。この年表から、「億年」ぐらいの間隔でときどき氷河時代がやってくることがわかる。一方、右半分にあるグラフはいちばん最近の氷河時代(「新生代氷河時代」)のあいだに、寒い時期(氷床の体積が大きい「氷期」)と暖かい時期(氷床の体積が小さい「間氷期」)が交互に繰り返していることを示すグラフだ。ギザギザの「山」が100年間に30回ぐらいあるから、氷期-間氷期の変動は「数万年」スケールの現象だとわかる。億年単位で地球を見るか、万年単位で地球を見るかによって、相手にしなければならない現象がまったく違ってくることがよくわかる。
さらに右下の図は、もっとびっくりするほど短い期間に急激に起こった気候変動の証拠。たった3年のあいだに地球の平均気温が10度も変わるような変動だって、過去には起こっていたらしい。もちろん、上の場合とは変動のメカニズムも違う。
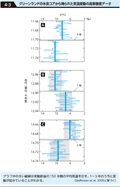 (図をクリックして拡大)
(図をクリックして拡大)『気候変動を理学する』図4-3(p. 159)
だからタイムスケールに応じて「見方」を変えないと、背景にあるダイナミクスもうまく理解できない。たとえば炭素が地球環境をどう巡っているか(炭素循環)を追う場合、「数十万年あるいはそれ以上の長いタイムスケールの炭素循環を考えるときには、基本的に大気と海洋は一つのボックスとして考えます。」一方、数万年以下のタイムスケールの炭素循環を考えるときには、「大気と海洋を別個の貯蔵庫と見たてて、その両者の間のやりとりに注目」するという。
■地球の見方のポイントその2──【スイートスポット】と【フィードバック】
- 「地球には、気候変動のツボとでもいうべきスポットがあって、外からの信号がそこをうまく刺激すると、変動が増幅されて地球全体に伝わるのです。」(本書 p. 54)
そういうツボ(「スイートスポット」)の例が本書にはいろいろ出てくるが、最初に語られているのは、上にも出てきた氷期―間氷期を繰り返す変動に関係するツボだ。じつは、日光を地表に受ける量(日照量)の分布のわずかな変化が、地球の極域にある氷床の増減を通じて増幅されて、それが地球全体に伝わり、氷期─間氷期のサイクルというグローバルな気候変動を作り出している。だからこの場合は氷床の大きさが「スイートスポット」ということになるだろうか。
そして、弱い信号を大きな信号へと増幅するのは「フィードバック」のメカニズムだ。たとえば「アイス・アルベド・フィードバック」は、「雪が積もるとその場所の反射率が高くなる。だから太陽光が当たってもみな反射して返してしまうから暖まらないのです。そうすると余計そこが寒くなり、もっと雪の領域が広がるという、そういう正のフィードバックです。」
スイートスポットとフィードバックの組み合わせがつくりだすのは非線形の系だから、そこで何がどこまで起こるかを予想するのはとても難しそうだ。しかも、その課題は想像以上に厄介にもなりうるという。なぜなら、
- 「こうしたスイートスポットの位置は、地球の歴史を通じてずっと同じ場所にあったというわけではなく、時代とともに地球上のどこか違う場所に移動する可能性があるということです。それこそ温暖化が進んで、たとえば地球の平均気温があるしきい値を超えると、北半球で氷床がもう二度と拡大しなくなるということもありうる。そうしたときにはスイートスポットが今度は別の場所に移って、別のシグナルに応答して気候システムが変動しだす可能性もあるということです。これは一般論ですけれども、地球の過去の環境変動の記録を見ていると、そういうスイートスポットの移動は十分に起こりうることなのです。」(本書 p. 92)
■さて、連繋された無数のシステム、サブシステムを抱え、いろんなところにスイートスポットをはらんだ精妙な地球像が見えてきたところで、あらためて、われわれ人類が地球にいかに乱暴をしているかに目を向けておきたい。上に出てきた“氷期から間氷期にかけての変動”によって大気中のCO2濃度は(自然に)上昇するのだが、その場合の変化速度は自然界が生みだしうるCO2濃度の変化としては一番速いと考えられているそうだ。ところが、人為的なCO2放出の規模をそれと比較してみると……。
- 「氷期から間氷期にかけての大気中CO2総量の増加速度というのは、簡単な計算で27×1015(g/千年)ぐらいです。……一方、火山ガスの放出速度も大ざっぱですが推定されていて、これがだいたい2桁低い30×1013(g/千年)という速度なのです。……
人類によるCO2の放出速度はさらにそれ〔氷期から間氷期にかけての大気中CO2の増加速度〕よりも3桁大きいのです。だから、火山活動の放出速度と比べたら、5桁違うわけですよね。このことからも、われわれ人類が今やっていることがいかに本来の地球の営みからかけ離れているかということがわかると思います。じつは今の地球温暖化の問題というのは、出すCO2の総量の問題もありますが、それよりも出すスピードの問題のほうが大きいのです。放出のスピードが非常に速いということがいちばん大きな問題だと思います。」(本書 p. 103-105)
- S・R・ワート『温暖化の〈発見〉とは何か』増田耕一・熊井ひろ美訳はこちら
- ヴァンダーミーア/ペルフェクト『生物多様性〈喪失〉の真実』新島義昭訳・阿部健一解説はこちら
- T・ヘイガー『大気を変える錬金術』渡会圭子訳・白川英樹解説はこちら
- J・ザラシーヴィッチ『小石、地球の来歴を語る』の詳しい書誌情報はこちら
- ニック・レーン『ミトコンドリアが進化を決めた』斉藤隆央訳はこちら
- ニック・レーン『生命の跳躍』斉藤隆央訳はこちら
- G・ゴオー『地質学の歴史』菅谷暁訳はこちら

