鞄に入れた本の話
私の美術書散策
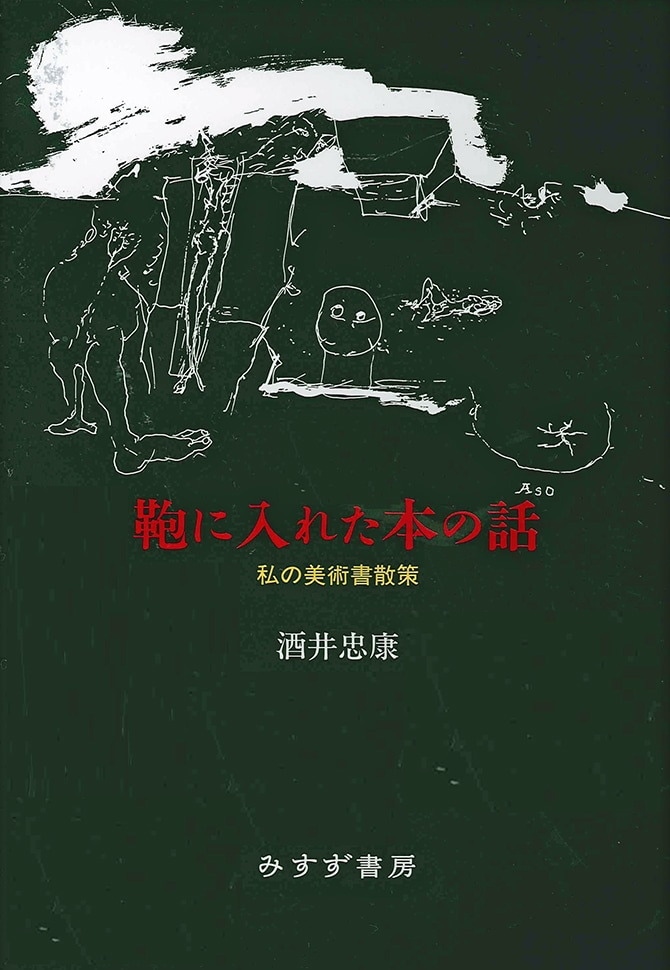
| 判型 | 四六判 |
|---|---|
| 頁数 | 296頁 |
| 定価 | 3,740円 (本体:3,400円) |
| ISBN | 978-4-622-07555-4 |
| Cコード | C0070 |
| 発行日 | 2010年9月24日 |
| 備考 | 現在品切 |
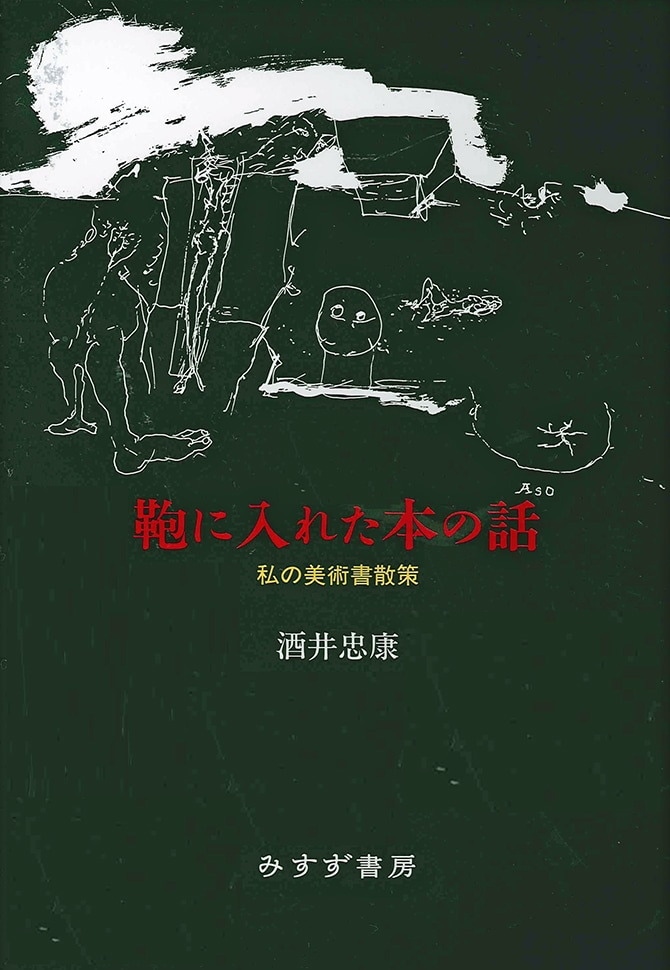
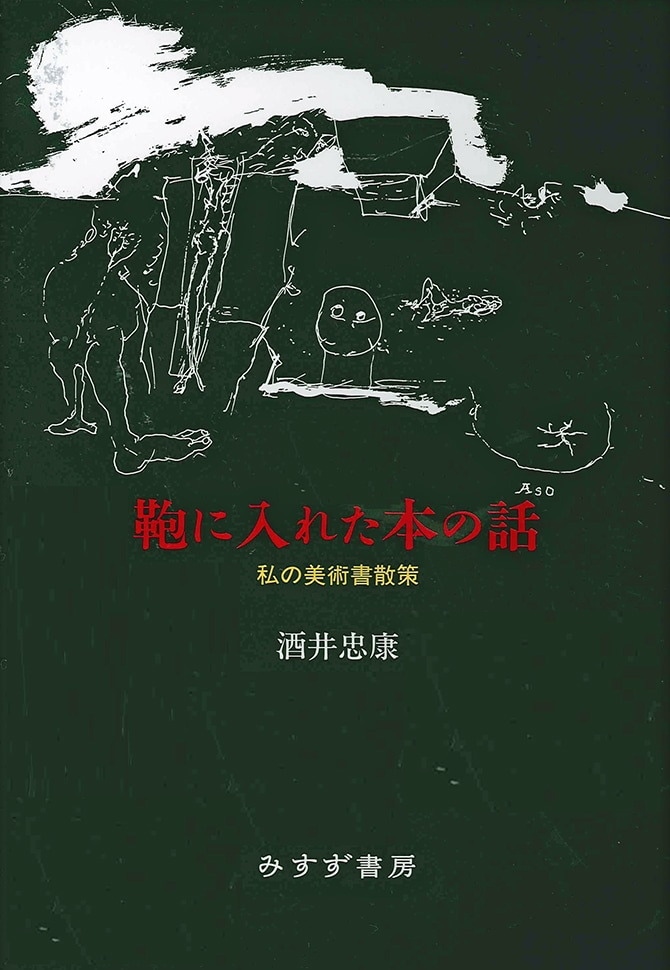
| 判型 | 四六判 |
|---|---|
| 頁数 | 296頁 |
| 定価 | 3,740円 (本体:3,400円) |
| ISBN | 978-4-622-07555-4 |
| Cコード | C0070 |
| 発行日 | 2010年9月24日 |
| 備考 | 現在品切 |
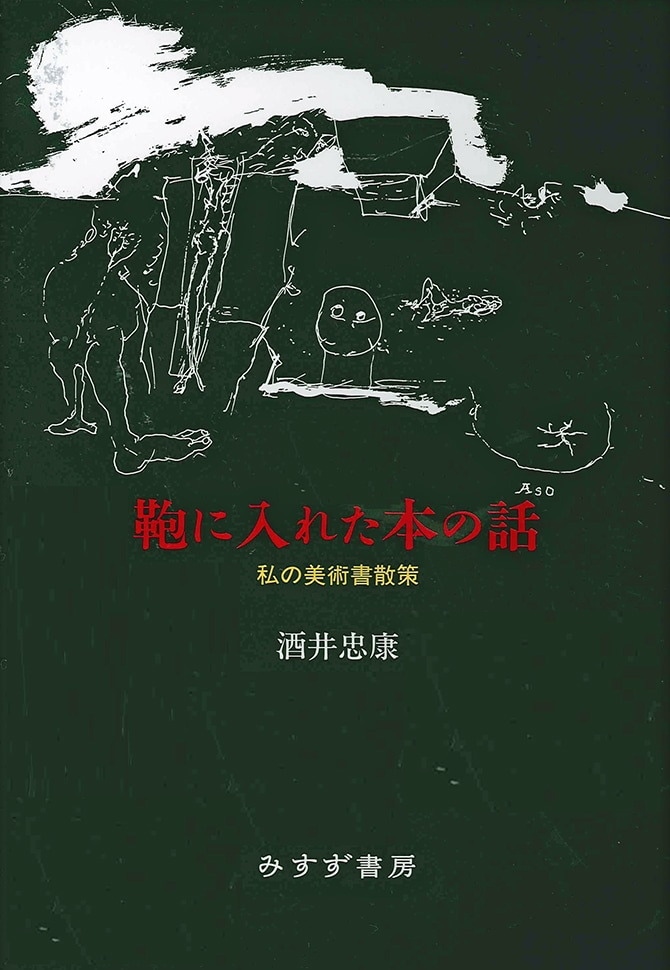
永く勤務した鎌倉の美術館を離れて都内の美術館に着任したのを機に、著者は通勤時間を利用して古今東西の美術書の味読・再読を始めた。本書は、そのような思い入れのある美術書について書き綴った味わい深いエッセイ集である。
愛用する大きめの肩懸け鞄に数冊の本を忍ばせ、館長という職務との往復でのひそかな愉しみとしたのだが、一方で美術館をめぐる情勢は混迷を深めていた。
「さて、これからの美術館は何をすべきか、と考えて車窓の外に目をやる。妙案はもとより浮かばない」
美術館のあり方をつねに思案し、また後進の育成に心をくばりながらも、これまで出会ってきた多彩な美術書を手にとり、著者は自身の歩みを追想するかのように、そこにたち現れる“美”の記憶を丁寧に読み解いていく。
時には私的な回想を交え、美術書とのつきない対話を楽しむその筆致は、書物を通じて美と向き合うことの冥利を誰よりも知っている著者ならではである。ページを繰るほどに、美を解することの示唆を与えてくれる本書は、百花繚乱のごとき美術書のガイドブックとしても楽しめるだろう。
I
父と娘の距離 岸田麗子『父 岸田劉生』
すべて親掛かり 高村光太郎『芸術論集 緑色の太陽』
巨匠の一番弟子 アンドレ・ヴォジャンスキー『ル・コルビュジエの手』
厠が画想の蔵と化して 棟方志功『板極道』
手ごろな入門書 ハーバート・リード『芸術の意味』
二人の仄々としたやりとり 岡本太郎『青春ピカソ』
いつまでも谺となって 飯田善國『彫刻家 創造への出発』
「作り手」への興味 東野芳明『現代美術 ポロック以降』
言葉を耕して リルケ『ロダン』
展覧会の一隅 青山二郎『青山二郎全文集』
高く生きた人 辻晉堂『泥古庵雑記』
本当の価値のある遺産 フェリックス・クレー『パウル・クレー』
美しき誤解 草野心平『村山槐多』
新旧の変遷、小気味よく 高村光雲『幕末維新懐古談』
芸術の領域に包み込まれて ヴァルター・ベンヤミン『図説 写真小史』
深い詩想と「生の道」を説く 岡倉天心『茶の本』
自然との深い交響 ヘルマン・ヘッセ『色彩の魔術』
画家の思索の運動示す 麻生三郎『絵そして人、時』
最良の案内人は最高の鑑賞者 エウヘーニオ・ドールス『プラド美術館の三時間』
「内なる声」を聞いた 中原悌二郎『彫刻の生命』
軽妙な愉しいエスプリ 芳賀徹編『小出楢重随筆集』
対象を凝視すること ジェイムズ・ロード『ジャコメッティの肖像』
本当のもとは遥か遠く 野見山暁治『四百字のデッサン』
縁起の妙 土門拳『写真と人生』
ものづくりの原点 佐藤忠良『つぶれた帽子』
耐え難い日々の幻影 バーナード・リーチ『東と西を超えて——自伝的回想』
大観をかりた「天心伝」 近藤啓太郎『大観伝』
謎の見え隠れ フランク・ウイン『私はフェルメール』
浸透する感性の役割 岡田隆彦『ラファエル前派』
史観と解釈 土方定一『日本の近代美術』
身近な人たちの証言 ニック・スタング『評伝 エドワルド・ムンク』
信望篤い論客、熱っぽく デイヴィッド・シルヴェスター『肉への慈悲——フランシス・ベイコン・インタヴュー』
人生の妙薬飲まされて 濱田庄司『無盡蔵』
「もの」見抜く鋭い感覚 平野雅章編『魯山人書論』
詩人の思索の運動通し ポール・ヴァレリー『ドガに就いて』
精神の水位を落さない感動の伝達 井上靖『忘れ得ぬ芸術家たち』
絵にまつわる人間的出会い 洲之内徹『帰りたい風景——気まぐれ美術館』
孤独な人間の対決と死 柳原義達『孤独なる彫刻』
再読・出会い・薄桃色の虹 マルク・シャガール『シャガール わが回想』
創造の秘密に共感 ジョアン・ミロ/ジョルジュ・ライヤール『ミロとの対話』
味わい深い評伝 ドナルド・キーン『渡辺崋山』
彫刻の究極的フォルム 中原佑介『ブランクーシ』
美的体験を物語る「美学」 ルドルフ・シュタイナー『芸術の贈りもの』
創造的源泉にふれて ジョン・ラッセル『ヘンリー・ムア』
垣根を越えて親しむ 吉田秀和『調和の幻想』
「詩と真実」が語る個人的体験 宮崎進『鳥のように』
先駆者の構想 井上太郎『大原總一郎』
秘密を搾りとられたら エミル・ベルナール『回想のセザンヌ』
闘いの場に共感して ドーレ・アシュトン『評伝イサム・ノグチ』
「画家の神話」を打ち砕き ジャンヌ・モディリアニ『モディリアニ』
時代の赤裸々な姿を刻んで 張望編『魯迅美術論集』
体験踏まえた「絵解き」 ケネス・クラーク『絵画の見かた』
辺境に属するものを享受 鶴見俊輔『限界芸術論』
色の不思議に誘われて 志村ふくみ『一色一生』
実証の細部をおさえて 『夏目漱石・美術批評』
実験的試みのつづき 石山修武『笑う住宅』
広い視野から舌鋒鋭く 岩村透『芸苑雑稿 他』
精神と物質の出会う場所 駒井哲郎『白と黒の造形』
新しい美術学・美術批評の方法 高階秀爾『美の思索者たち』
省察に富む暗示 李禹煥『余白の芸術』
II
『画学生の頃』を再読して
回想の美術雑誌
批評眼と史的解釈 高階秀爾『日本近代美術史論』
想像を喚起する都市 芳賀徹編『絵のなかの東京』
都市の探索者の作業 海野弘『新版 都市風景の発見』
変幻自在の「美術談義」 『吉田秀和全集17——調和の幻想 トゥールーズ=ロートレック』
セザンヌの絵の謎をめぐって 吉田秀和『セザンヌ物語』
遠くを見る眼差し 中村真一郎『眼の快楽』
中山公男『私たちは、私たちの世代の歌を持てなかった。』
井関正昭『未来派——イタリア・ロシア・日本』
桁外れのコレクターたち 宮下夏生/ジェラルディーン・ノーマン『世界のトップ・コレクター』
辻川一徳『われらが時代のビッグ・アーティスト』
『矢口國夫美術論集 美術の内と外』
『麻原雄芸術論集 イーゼンハイムの火』
座右の本、あるいは 土方定一『日本の近代美術』
一途な詩人・版画家 川上澄生『明治少年懐古』
あとがき
初出一覧
“美術書”というジャンルは、残念な存在である。
出版社のカタログでは傍流扱いされ、書店でも店舗の奥また奥に小さなスペースが割かれるに過ぎず、新聞書評で取り上げられることは滅多になく、読者の皆さんからは「なぜこんなに高いのか」と嘆かれる始末だ。
しかしその美術書が、哲学書、歴史書、文芸書など人文書の一端を担い、日本人の文化活動を啓発してきた功績は疑う余地がない。特に高度成長期は、西洋美術に対する国民の関心が高まり、高価な美術書・画集が多く読まれるようになり(小社も『現代美術』全25巻の販売で糊口をしのいだという)、一方で泰西名画を集めた展覧会が開催されるなど、美術に対する理解が醸成された。本書は、まさしくそうした時期に、美術館学芸員として数々の展覧会を企画した酒井忠康氏(現・世田谷美術館館長)の、美術書遍歴ともいえるエッセイ集である。
美術評論の第一人者、土方定一(1904-1980)が館長を務める神奈川県立近代美術館に勤務し、師ととともに美術の来し方行く末を見つめてきた著者は、書をひもとくことを第二のフィールドワークとしながら独自の姿勢を形成してきた。本書は、そうした氏の嗜好が強く働いたところでセレクトされた美術書ガイドである。“雑食主義”と著者自ら言うところの縦横な読書癖も相まって、ここに取り上げられるのはいわばガチガチの美術書ではなく、美とかかわる人々のユニークな心性が伝わる味わい深い美術書が中心となっている。本書のもとになっている新聞連載「美術本の一隅」のタイトルそのままに、美術の片隅をそっと照らす、著者の優しいまなざしが感じられる一冊である。
美術書はどこへ向かうのであろうか。愛惜したり懐古したりする対象だけではつまらない。美術“本体”とともに同時代を鋭く描き、抉出する存在として、まだまだ本領を発揮してもらわねばならない。さまざまな美術書を座右に置くことで、美術をより深く洞察できることを本書は教えてくれる。
この秋も、全国の美術館やデパートで多彩な展覧会が開催される。皆さんご愛用の鞄に本書を携えて、お近くの美術展に足を運んでみてはいかがだろうか。(八)