磁力と重力の発見 1
古代・中世
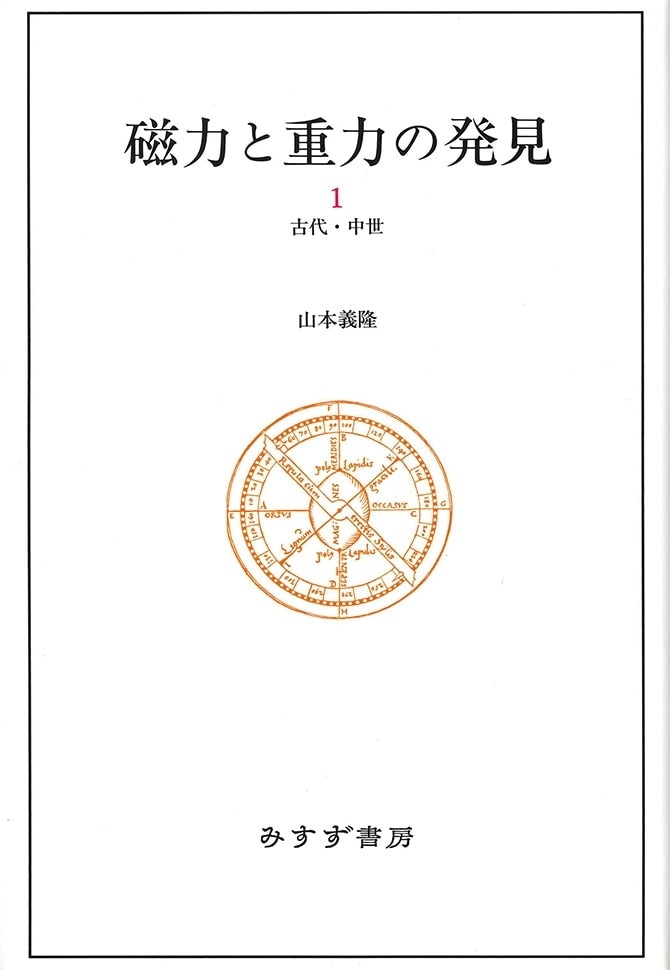
| 判型 | 四六判 |
|---|---|
| 頁数 | 336頁 |
| 定価 | 3,740円 (本体:3,400円) |
| ISBN | 978-4-622-08031-2 |
| Cコード | C1340 |
| 発行日 | 2003年5月22日 |
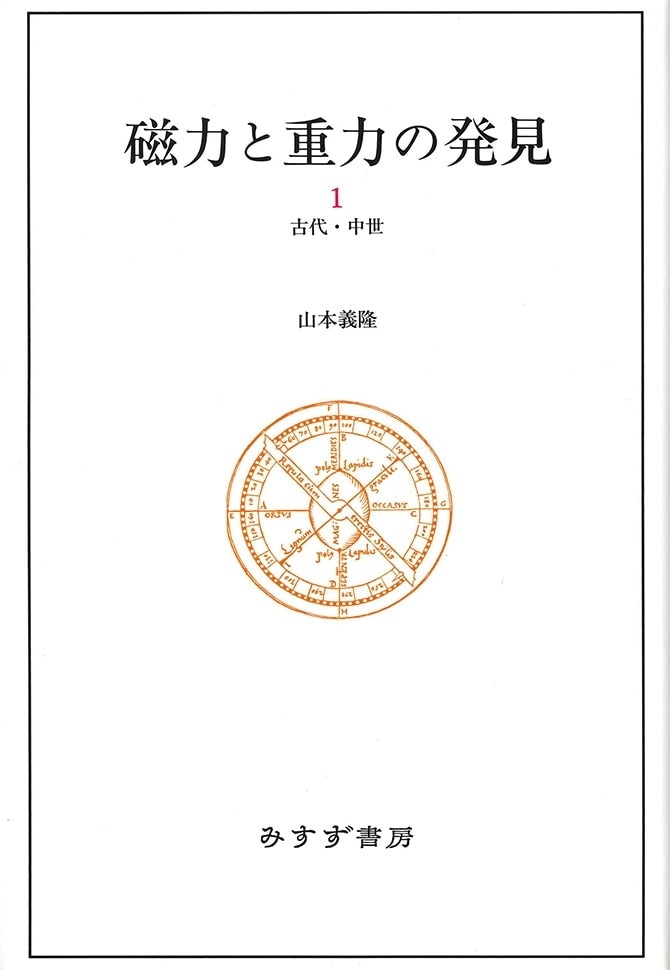
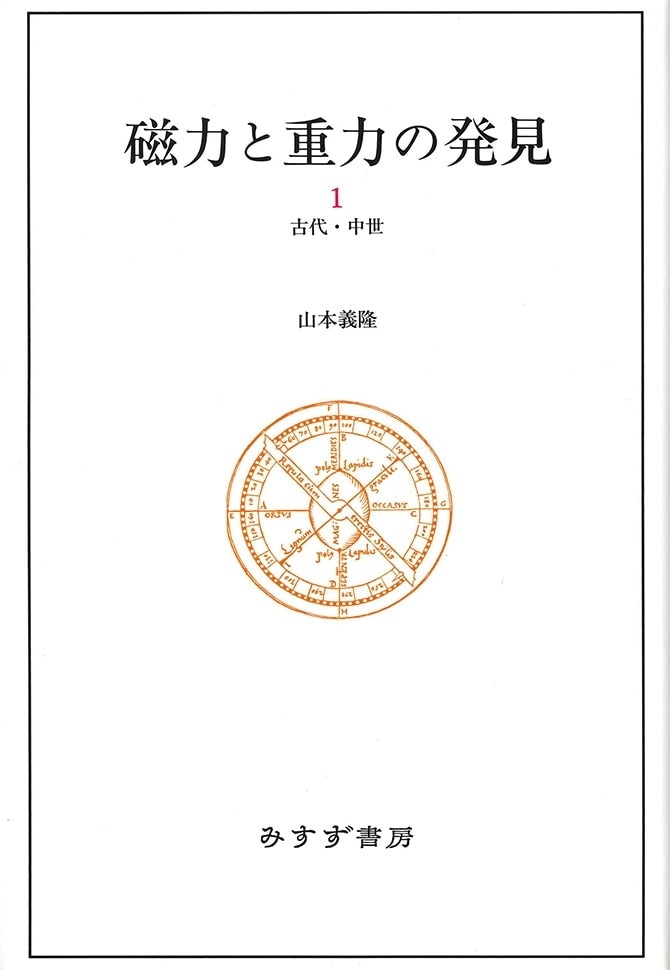
| 判型 | 四六判 |
|---|---|
| 頁数 | 336頁 |
| 定価 | 3,740円 (本体:3,400円) |
| ISBN | 978-4-622-08031-2 |
| Cコード | C1340 |
| 発行日 | 2003年5月22日 |
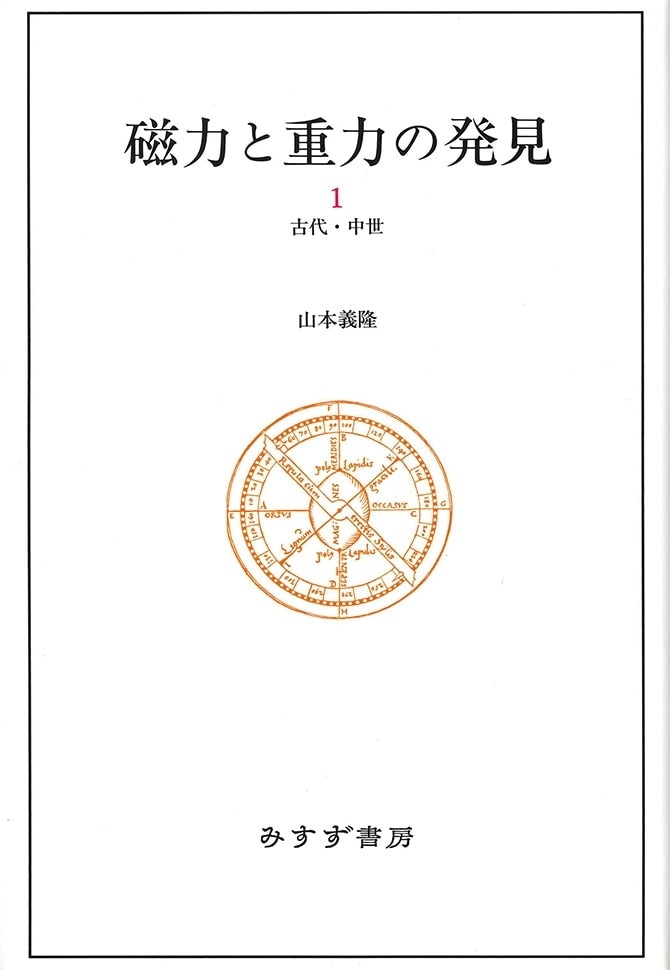
近代物理学成立のキー概念は力、とりわけ万有引力だろう。天体間にはたらく重力を太陽系に組み込むことで、近代物理学は勝利の進軍の第一歩を踏み出した。
ところが、人が直接ものを押し引きするような擬人的な力の表象とちがって、遠隔作用する力は〈発見〉され説明されなくてはならなかった。遠隔力としての重力は実感として認めにくく、ニュートンの当時にも科学のリーダーたちからは厳しく排斥された。むしろ占星術・魔術的思考のほうになじみやすいものだったのである。そして、古来ほとんど唯一顕著な遠隔力の例となってきたのが磁力である。
こうして本書の追跡がはじまる。従来の科学史で見落とされてきた一千年余の、さまざまな言説の競合と技術的実践をたどり、ニュートンとクーロンの登場でこの心躍る前=科学史にひとまず幕がおりるとき、近代自然科学はどうして近代ヨーロッパに生まれたのか、その秘密に手の届く至近距離にまで来ているのに気づくにちがいない。
6年前の著書『古典力学の形成』のあとがきで遠回しに予告されていた大テーマ、西洋近代科学技術誕生の謎に、真っ向からとりくんだ渾身の書き下ろし、全3巻。
序文
第一章 磁気学の始まり——古代ギリシャ
1 磁力のはじめての「説明」
2 プラトンと『ティマイオス』
3 プラトンとプルタルコスによる磁力の「説明」
4 アリストテレスの自然学
5 テオプラストスとその後のアリストテレス主義
第二章 ヘレニズムの時代
1 エピクロスと原子論
2 ルクレティウスと原子論
3 ルクレティウスによる磁力の「説明」
4 ガレノスと「自然の諸機能」
5 磁力の原因をめぐる論争
6 アプロディシアスのアレクサンドロス
第三章 ローマ帝国の時代
1 アイリアノスとローマの科学
2 ディオスコリデスの『薬物誌』
3 プリニウスの『博物誌』
4 磁力の生物態的理解
5 自然界の「共感」と「反感」
6 クラウディアヌスとアイリアノス
第四章 中世キリスト教世界
1 アウグスティヌスと『神の国』
2 自然物にそなわる「力」
3 キリスト教における医学理論の不在
4 マルボドゥスの『石について』
5 ビンゲンのヒルデガルト
6 大アルベルトゥスの『鉱物の書』
第五章 中世社会の転換と磁石の指向性の発見
1 中世社会の転換
2 古代哲学の発見と翻訳
3 航海用コンパスの使用のはじまり
4 磁石の指向性の発見
5 マイケル・スコットとフリードリヒ二世
第六章 トマス・アクィナスの磁力理解
1 キリスト教社会における知の構造
2 アリストテレスと自然の発見
3 聖トマス・アクィナス
4 アリストテレスの因果性の図式
5 トマス・アクィナスと磁力
6 磁石に対する天の影響
第七章 ロジャー・ベーコンと磁力の伝播
1 ロジャー・ベーコンの基本的スタンス
2 ベーコンにおける数学と経験
3 ロバート・グロステスト
4 ベーコンにおける「形象の増殖」
5 近接作用としての磁力の伝播
第八章 ペトロス・ペレグリヌスと『磁気書簡』
1 磁石の極性の発見
2 磁力をめぐる考察
3 ペレグリヌスの方法と目的
4 『磁気書簡』登場の社会的背景
5 サンタマンのジャン
注
Yoshitaka Yamamoto, THE PULL OF HISTORY: Human Understanding of Magnetism and Gravity through the Ages (World Scientific, 2018).
http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/10540
2018年2月刊行です。
『磁力と重力の発見』全3巻は2003年度、〈制度としてのアカデミズムの外で達成された学問的業績、あるいは科学技術ジャーナリストの仕事のように学問と社会をつなぐ役割を果たした業績〉を顕彰するために創設された第1回パピルス賞(財団法人 関科学技術振興記念財団)、および第57回毎日出版文化賞(毎日新聞社)、第30回大佛次郎賞(朝日新聞社)を受賞しました。
『磁力と重力の発見』では、古代ギリシャ・ローマにはじまり17世紀にいたる「科学革命前史」が解き明かされます。
この執筆の過程で、17世紀科学革命を準備した「16世紀文化革命」という仮説が、しだいにはっきりと形をとっていきます。この課題に挑んだ次著が『一六世紀文化革命』(全2巻、2007年)。さらに書き継がれた『世界の見方の発見』(全3巻、2017年)をもって、近代科学の誕生の謎を追う三部作が完結します。