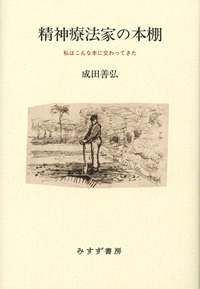
2014.04.28
成田善弘『精神療法家の本棚』
私はこんな本に交わってきた
1 天文学の復興と天地学の提唱 2 地動説の提唱と宇宙論の相克 3 世界の一元化と天文学の改革 [2014年3月20日刊]
2014.03.31
[『数学文化』では新連載スタート 山本義隆「小数と対数の発見」]
すでに古典たる評価を得ている『磁力と重力の発見』『一六世紀文化革命』に続き、「なぜ、どのように西欧近代において科学が生まれたのか」を解き明かす。近代科学誕生史〈三部作〉を締めくくる待望の書き下ろし。2014年3月20日刊行。
プトレマイオス理論の復元にはじまり、コペルニクス地動説をへてケプラーにいたる15-16世紀天文学の展開は、観測にもとづく天文学を言葉の学問であった宇宙論の上位に置くという学問的序列の一大変革をなしとげ、「まったく新しい自然研究のあり方を生みだした」。それは、「認識の内容、真理性の規準、研究の方法、そして学問の目的、そのすべてを刷新する過程、端的に〈世界の見方と学問のあり方の転換〉であり、こうして17世紀の新科学を準備することになる」(「まえがき」より)。
なお本書は、じつは古代以来の天文学の発展にともなう数学の歩みについて、当初の原稿では触れていたのですが、全体があまりにも膨大になりすぎたので、削除しました。この部分については、雑誌『数学文化』の編集部から寄稿を依頼されたので、連載として掲載していただくことになりました。(「あとがき」より)
『世界の見方の転換』の「あとがき」にこのように予告された新連載が、『数学文化』第21号(2014年3月31日発行)からスタートします。
『数学文化』第21号(日本数学協会 編集/日本評論社 発行) http://www.nippyo.co.jp/book/6498.html
[全3巻]
〈遠隔力〉の概念が、近代科学の扉を開いた。古代ギリシャからニュートンとクーロンにいたる力概念の形成を追い、科学史の空白の一千年余を解き明かす。(2003年5月刊)
〈制度としてのアカデミズムの外で達成された学問的業績、あるいは科学技術ジャーナリストの仕事のように学問と社会をつなぐ役割を果たした業績〉を顕彰するために創設された2003年度第1回パピルス賞(財団法人 関科学技術振興記念財団)、および第57回毎日出版文化賞(毎日新聞社)、第30回大佛次郎賞(朝日新聞社)受賞。
大佛次郎賞という賞をいただいて、正直いうと私はどういう賞かよく知らなかったのですが、ただ大佛次郎という作家は、好きです。『鞍馬天狗』は読んでいませんけれども、一連のフランスものといわれるノンフィクション、とくにパリ・コミューンを扱った『パリ燃ゆ』は感激しました。
(……)私は物理学史をやっていますが、物理学史というものは一方では科学史のプロの批判に耐えなければいけないし、同時に物理屋が読んでも面白くて意味のあるものでなければならないというふうに思っているのです。まさしく大佛次郎の『パリ燃ゆ』は、学者でなく小説家の大佛次郎が、なおかつ歴史学者の批判に耐えるものを書いて、それによって学者の書くものを超えたのだなあとつくづく思っていますので、その名を冠した賞を受けたことを私自身も励みにして今後も勉強を続けていきたいと思っています。どうもありがとうございました。
…続きを読む »
(2004年1月28日の同賞贈呈式でのスピーチをもとに、月刊『みすず』2004年3月号、著者の同意を得て抜粋・転載)
本書は固有の意味での「物理学史」が成立する以前が主要なテーマになっている。したがって最近流行のサッカー用語でいうならば、これまでの仕事はある程度ホームでのゲームであったが、今回はまったくアウェーでの勝負ということになる。なお、本書、とくに第2巻を読んでいただければわかるように、本書を書く過程で、1500年代ルネサンスと言われている時期の西洋に「16世紀文化革命」とも言うべき知の世界の地殻変動があったのではないかということに思い当たった。この点をさらに明確にする課題については、今後の宿題にしておきたい。
(著者の同意を得て抜粋・転載)
正解にたどりついておしまいの出来レースではない、ダイナミックな観念の歴史を、本書は各時代の世界観との関わりで入念に描き出す。
本書の世界観へのこだわりを、ぼくは懐かしい思いで読んだ。それはかつて著者に予備校で教わったものだったからだ。
本書の著者名を聞いて、書評委員会は一瞬どよめき、自分の知らない時代のできごとが、三十年たっても深い刻印を残していることにぼくは改めて驚いた。それは多くの点でマイナスの刻印だっただろう。全共闘騒動の最大の損失は、山本義隆が研究者の道を外れ、後進の指導にもあたれなかったことだ、という人さえいた。でもプラスの刻印もあった。その事件のおかげで、ぼくをはじめ無数の受験生が予備校でこの人に物理を教われたのだもの。かれが教えてくれたのはただの受験テクニックじゃなかった。物理は一つの世界観で、各種の数式はその世界での因果律の表現だということを、かれは(たかが受験勉強で!)みっちりたたき込んでくれたのだった。
本書はその物理的な世界観を思い出させてくれた。同時に本書は、磁力や重力という常識化した概念/現象の不思議さに、改めて読者の目を開かせてくれるだろう。さらに本書を読むことで、世界はちょっとちがって見えるだろう。無味乾燥な科学が支配していたこの世界に魔法が戻ってきたのをあなたは感じるだろう。さあ、ハリー・ポッターに夢中になっている子供に、いつか本書を見せて教えてやろう。魔法の世界は、いま、きみの目の前にあるんだよ、と。
* 別の書評を読む » 山形浩生「マグル科学の魔術的起源と魔術界の衰退に関する一考察。」(『CUT』2003年7月号)http://cruel.org/cut/cut200305.html
…続きを読む »
(朝日新聞2003年7月20日、著者の同意を得て抜粋・転載)
全三巻、総計一千頁に及ぶ大著である。ようやく読了し、主人公の「磁力」が時を経て「重力」へと成長して行く壮大な大河小説を読み終えたような心躍りと充実感を味わった。
本書を手にし、タイトルと目次を眺めていささか奇異の念を覚えたことは否めない。山本義隆氏といえば、『重力と力学的世界』や『古典力学の形成』などの労作、そしてカッシーラーやボーアの翻訳で知られる科学史家であり、そのフィールドは近代以降の物理学のはずだったからである。実際、山本氏も「これまでの仕事はある程度ホームでのゲームであったが、今回はまったくアウェーでの勝負ということになる」(あとがき)と述べているように、本書の舞台は古典古代から近代初期にいたる「科学以前」の世界であり、扱う資料もギリシア語やラテン語の文献であってみれば、その困難と労苦は想像に余りある。
ところが、ハンディのあるアウェーでのゲームとは思えないほど、氏のフットワークは自在闊達であり、次々と枠を捉えて的確なシュートを決めていくさまには、思わず手に汗を握り、ときに歓声を上げたくなるほどである。そのような試合運びを可能にしているのは、近代科学の核心を万有引力に象徴される遠隔作用としての「力の概念」の獲得に見定め、その源流を古代中世以来の魔術的伝統、とりわけ「磁力」をめぐる考察の中に探ろうとする著者の一貫した問題意識だと言ってよい。(……)
本書を通読してまっさきに思い浮かんだのは、かつて下村寅太郎が科学史は「『科学の歴史』ではなく『科学への歴史』でなければならぬ」と説いてやまなかったことである。しかし、下村は早くから魔術の重要性に着目しつつも、「科学への歴史」を完成させるには至らなかった。この下村が企図しつつなしえなかった「科学への歴史」を、山本氏は本書において見事なまでに実現したと言うことができる。しかも本書は、科学史の本道からは無視され、埋もれてきた思想家たちの著作を丹念に発掘してその意義を宣揚し、従来の科学史の通説・俗説に書き直しを迫らずにはおかない、数々の創見に満ちた力作である。
このような質・量ともに群を抜いた科学史書が、資料収集の面でも大きなハンディを背負ったアカデミズムの外部で書かれたことに心からの敬意を表するとともに、著者が構想しつつある「一六世紀文化革命論」の今後の展開を刮目して待ち望みたい。
…続きを読む »
(週刊読書人2003年9月12日、著者の同意を得て抜粋・転載)
議論の焦点は、書名にも現れているように、磁力、重力の語に共通に伴っている「力」という概念そのものに向けられていく。「力」というのはいったい何なのか。明らかに遠隔的に働くが、それ自体は変化し、さまざまな形態を取る。後に力の変化のさなかに量的な保存が見出されたとき、それが力の保存則、すなわちエネルギー保存則となる。力は近代の自然学のなかでさまざまな発見をもたらした稀有な概念であった。
本書は、こうした力の概念に引き継がれていく前史までをギリシャから丹念に掘り起こしている。文句のない力作である。
本書のように斬新な問題設定で一貫した議論を展開した著作は、実にさまざまなことに気づかせてくれる。遠隔作用というとき、すでに広がりを示す空間が前提になっている。空間をどう考え、空間とさまざまな作用との関係をどう考えるかは現在なお大問題である。個人的には、私の研究テーマであるシステム論でも、個々のシステムの位相空間の形成は、要となる大問題の1つである。また眼で物を見るさいも離れたものが、離れたところに見えるのだから、視覚でさえ光を介した遠隔作用だと見ることもできる。この光学と生態心理にかかわる事態を精確に定式化しようとすれば、ただちに難題が噴出する。多様で根源的な問題群の根っこに、おそらく本書は触れているのである。
…続きを読む »
(『科学』2003年10月号、著者の同意を得て抜粋・転載)
接触による普通の力と違って、磁石は距離を隔てて鉄片を引くように見える。古代ギリシャの哲学者たちは、この磁力を目に見えない粒子を介した近接作用とみるか、霊的な遠隔作用とみるかの二通りの思想を生み出した。
本書は、ここから説き起こし、磁力が魔術とみなされた中世から、イスラム社会(そこに伝えられていたギリシャ科学)との接触による十三世紀の転換、十五世紀の思弁的魔術から十六世紀の経験的・数学的・実践的な魔術への脱皮(自然界は諸事物とそれらの相互作用からなり人は観察によりその力を知ることができる)を経て、ケプラーが惑星の運動を太陽の磁力に帰しつつも観測データに助けられて彼の三法則を発見し、やがてニュートンが「私は仮説を立てません」といって重力の機構の追究を放棄し惑星の運動の三法則を解析して重力を厳密な数学的法則に従わせることにより魔術的な遠隔作用をひとまず合理化するまでを、原典に直接あたりながら精細に跡づけたものである。それだけに、新事実の発掘、通説の誤りの指摘も多い。たとえば、近代電磁気学の出発点とされてきたギルバートの『磁力論』(1600)が無視した先行者デッラ・ポルタの存在(『自然魔術』、1558)。さらに時代時代の思潮の社会的・技術的背景にも細かい目配りを忘れていない。
…続きを読む »
(『日本物理学会誌』第59巻5号、2004年、著者の同意を得て抜粋・転載)
本書の著者山本義隆は、アインシュタインとは異なった方法で力の本質について深く考えた人である。万有引力の発見によって近代物理学が成立し得たと言っても過言ではない。では、万有引力の発見において、力は接触によって作用するという考えを超越して、いかに遠隔作用という魔術的な力の概念が生まれ出たのだろうか。
遠隔作用といえば磁石の力も同じである。離れた所に空間を越えて伝わるからだ。ならば、まず磁石の歴史を辿ることによって、遠隔作用の概念がどのように生まれてきたかを探ることが第一である。遠く古代ギリシャ以来、磁石の力について考察が重ねられてきたからだ。そして、それがどのように遠隔作用としての万有引力に収斂していったのか。その過程において、魔術と技術がどのような役割を果たしたかを明らかにしたい。それが著者の問題意識であり方法であった。
それ故に、本書では古代から中世のさまざまな人物の磁力の理解がどうであったかが克明に追われ、ルネサンス期の魔術思想とのせめぎ合いにも多くの章が割かれている。さらに、一七世紀の機械論を挟みながら、ガリレオの静力学(力の概念を用いない)からケプラーやフックやニュートンの動力学へと転換する過程で、魔術的要素がむしろ功を奏して万有引力の発見に至ったことが活写されている。
従来の科学史は、科学の諸概念の萌芽を古代ギリシャ時代の自然哲学に求めつつも、その後一挙に千年以上も飛んで、ルネサンスから近代初頭におけるアリストテレス哲学との格闘を通じて近代科学が成立したという筋書きになっている。著者は、むしろ近代以前の占星術や魔術思想に遠隔力の源泉を求め、近代においても機械論の限界をはっきりと認識すべきとして、新しい科学史を書き上げたのだ(書き直したのではない)。
(……)本書を読みつつ、さらに中国における磁石(慈石というべきか)の歴史があれば、と思ったものである。中国では原理を追い求めるよりは実用価値に重きをおく傾向が強く、近代科学に直接影響を及ぼすことがなかったから多くを書いていないとは思うのだが、その限界を示すためにも章を割いて欲しかったのだ。どの段階まで理解や応用が進んでいたのか、なぜそこで磁力の理解が止まってしまったのか、そんな考察を聞きたかった。
ともあれ、これまでの科学史の定説を覆す内容が多く、蒙を啓かれたことが多くあった。著者の執念と勉強ぶりに脱帽した。
…続きを読む »
(『文學界』2004年6月号、著者の同意を得て抜粋・転載)
[全2巻]
大学や人文主義者を中心としたルネサンス像に抗し、16 世紀ヨーロッパの知の地殻変動を綿密に追う。『磁力と重力の発見』と『世界の見方の転換』の結節点。(2007年4月刊)
私が今回『一六世紀文化革命』でもって描いた事実の多くは、個別にはこれまでに知られていた。(……)しかし、これらがおりからの印刷書籍の登場(印刷革命)と国民国家形成の主要な要素としての国語の形成(言語革命)を背景に、さらには大航海の経験による古代の権威の失墜を追い風にして、軌を一にして全面展開された事態は、巨大なひとつの「文化革命」と捉えることによってはじめて、科学史のなかにしかるべく位置づけられるように思われる。(……)このようなあつかましい主張が、無免許運転者の暴走なのか、それともビギナーズ・ラックで鉱脈の末端を掘りあてたのか、その点の判断は読者の評価に委ねたいと思う。
(月刊「みすず」2007年5月号、著者の同意を得て抜粋・転載)
もっと話を遡れば、ちょうど10年前に日本評論社から上梓した『古典力学の形成』のやはり末尾に書いた「現在では全世界を制覇するまでになった近代の科学技術が、なぜ西洋近代にのみ誕生したのかは、科学史・技術史のつきせぬ謎である。というか、科学史とか技術史という学問は、要はこの問題の解決のためにこそ存在しているのであろう」という問題設定に始まる。現在は、この問題にたいして、前著『磁力と重力の発見』とあわせて、今回の著書で非力ながら自分なりの解答を与えることができたという気分でいる。
(……)知識人の観念が書斎で編み出したテクストだけを追いかけて、本当に機械論的世界像の発生が理解できるのだろうか、という疑問は許されるであろう。実験と観測を数学と論証に併合させた、17世紀における新しい科学の形成は、それまではアカデミズムの世界が一顧だにしなかった職人たちの手仕事・機械的技芸の評価のうえに可能となったのである。(……)ついでに少しばかり先走っておこう。(……)科学に裏付けられた技術という意味での「科学技術」という思想がやがて生み出されてゆく。16・17世紀には科学は先行していた技術から学んだのであるが、18世紀以降は、逆に、科学が技術を基礎づけるだけでなく、科学は技術を先導さえするようになる。(……)もともと近代自然科学とりわけ物理学や化学は法則の確立を目的としていたが、しかしその法則というのは、直接的な応用とは無関係な天文学をのぞいては、まわりの世界から切り離され純化された小世界、すなわち環境との相互作用を極小にするように制御された自然の小部分のみに着目し、そのなかで人為的・強制的に創出された現象によってはじめて認められるものである。自然科学はそのような法則の体系として存在し、実際にはかなり限られた問題にたいしてのみ答えてきたのであるが、そのような科学にもとづく技術が、生産の大規模化にむけて野放図に拡大されれば、実験室規模では無視することの許された効果や予測されなかった事態が顕在化するのは避けられない。…もっと読む »
…続きを読む »
(著者の同意を得て抜粋・転載)
西洋近代は十四、五世紀のルネサンスに始まるというのが、高校で習う「世界史」の定説であろう。それに対して、英国の歴史家バターフィールドは、十七世紀の「科学革命」に近代の真の始まりを見た。いわゆる科学革命論である。そのため、両者の間に位置する十六世紀は「谷間の時代」として、歴史家に顧みられることはなかった。山本義隆氏の新著は、この埋もれた時代に光を当て、十六世紀に胎動した「知の世界の地殻変動」をヨーロッパの知の布置を刷新した文化革命としてとらえ直す。
この大胆な問題提起を支えているのは、「歴史認識と歴史記述の座標軸を美術史や思想史から科学史と技術史に変換する」という視座の転換であり、文化革命を推進した職人、技術者、芸術家、外科医、商人らが書き残した膨大な文書の丹念きわまりない解読である。
(……)本書は従来の科学史像を一新するとともに、測定技術や実験技法を洗練させ、定量化を推し進めた職人たちの業績を掘り起こした文字通りの労作である。前著「磁力と重力の発見」からわずか四年で七百ページを超す大著を完成された著者の研鑽に敬意を表したい。
…続きを読む »
(山陽新聞2007年5月6日他、著者の同意を得て抜粋・転載)
『磁力と重力の発見』が、比較的伝統的な概念史的手法に貫かれているのに比べると、論じられる対象が自然界と多少とも直接的な交叉を示す中で練り上げられていく知識群だという意味で、概念史からは大きく横逸している。しかも、その話題は、まるであの下村寅太郎が、無限論から芸術や歴史学へとその視点を拡大していったのをなぞるかのような、言説領野の拡張的構成を伴う。ざっと枚挙しただけでも造形芸術、外科学、植物画、製鉄、鉱山採掘、代数学、機械学、軍事技術、天文学、地理学などというように、である。それらについての論述の仕方はいつも通り、明晰かつ簡明で淀むところがない。細かい史実の追跡は十分役に立ち、読んでいて面白い。
では、これら実に多様な分野の史実を渉猟しながら、氏が導き出そうとするテーゼは何なのか。それは、題名通り、主に一六世紀にヨーロッパで展開された知識についての或る重要な姿勢の変化を巡るものだ。それまで文献中心的で権威主義的な知識観を背景に、ラテン語という特殊言語で少数のエリート同士で作られてきた知識と、正規の高等教育を経ない職人や商人を中心的担い手としながら、直接に自然界と関わる手作業を介して経験的に蓄積され、しかも俗語で書かれた知識。その両者の対立の構図をまずは据える。そして伝統的に前者を重視してきた知識観が、新世界の発見や鉱山開発など、社会背景の変化と連動しながら徐々に実力を増していく後者の知識生産によって凌駕されていくという大枠の構図を浮き上がらせるのだ。(……)
いつもながらに情報量に富み、深い学識に裏打ちされた本、だが今回に限っては、歴史的視点としてはやや一面的な偏向を伴う本。この優れた著者に対する評言としては無礼に過ぎるかもしれないが、それが率直な感想だ。だが、本書は一つの通過点、次の作品が今から既に楽しみである。
…続きを読む »
(週刊読書人2007年6月8日、著者の同意を得て抜粋・転載)
第一級の物理学者として出発した著者が、大学紛争に出あって野に下り、欧米の各国語はもちろん、ラテン語などをも読みこなして四年前、『磁力と重力の発見』を書き上げた。本書はこれに続く、17世紀の科学革命を準備した、16世紀ヨーロッパにおける知識生産に関する構造変動を描いてみせた労作である。
(……)16世紀には何が起こっていたのか。この問題に対して本書は、神学を頂点とするスコラ文献の注釈学を至高のものと考える、大学アカデミズムの知識人とは別の、手作業に従事していたギルドに近い人たちが、複雑な表現には適さないとされていたドイツ語や英語などの俗語で、実証的な事実を集約して独自に出版し、知識を共有しようとしたことにある、とする骨太の構図を提示する。
そのための文献学的な跡付けは実に緻密である。(……)
いまや著者は、押しも押されもせぬ円熟した科学史家である。だがこれらは、大学アカデミズムから生まれてもよい研究成果である。日本の大学への批判が隠しようもなくにじみ出ている点が、また味わい深い陰影となっている。
…続きを読む »
(読売新聞2007年6月24日、著者の同意を得て抜粋・転載)
意表をつく着眼によって書かれた、「コロンブスの卵」のような本である。
西洋の一六世紀が偉大な造形の時代であって、レオナルドやデューラーが活躍したことは有名である。グーテンベルクの活版印刷が普及し、ルターが民衆に聖書を読むことを奨めたせいもあって、この頃からラテン語ではなく、国語による読み書きが広まったことも知られている。自然科学の先駆者として、パラケルススやチコ・ブラーエといった人たちが現れたことも、世界史の年表にある。
だが著者の洞察がこの三つの話題を結びつけると、一六世紀はたちまち一つの文化革命の時代となり、中世から近代への転換の軸となったようである。着眼の新しさは、この時代を知的な職人の台頭期として捉え、手を使う人が仕事を広げるとともに、その技能を活字で表現し始めた時代と見た点にあった。
(……)職人と活字の関係を重視し、画家から医師にいたる人物群を「手を使う人」としてまとめた文明観は、著者独自の功績だろう。博引旁証、博覧強記の二巻、七四〇ページの大著は、とくにその細部に神が宿っている。「あとがき」に付言された現代科学批判には議論もあろうが、一般に現代文明があまりにも頭だけの営みにかたより、手の働きを忘れると同時に、どの分野でも専門家のたこつぼに埋没しつつあるという、憂慮には共感できる。
…続きを読む »
(毎日新聞2007年7月29日、著者の同意を得て抜粋・転載)
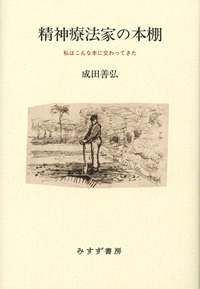
2014.04.28
私はこんな本に交わってきた

2014.03.28
姜信子編