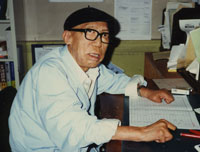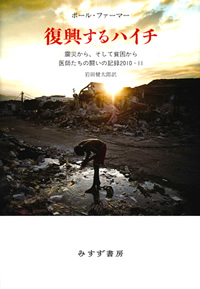電子書籍もできました!
電子書籍もできました!
honto電子書籍ストアから2014年3月20日発売。同店では4月13日(日)までポイント20倍キャンペーン実施。
honto電子書籍ストア http://honto.jp/cp/ebook/2014/animal-orchestra
 本書の音風景
本書の音風景
本書で語られている音風景の一部は、専用のウェブサイトで聴くことができます。
- ◆ 65種の音風景が聴ける音声再生用ウェブサイトはこちら
- orchestra.msz.co.jp
《音声の例》
- 以下、5つの音声をここでお聴きになれます。
- * ご使用の環境によっては、再生ボタンを押してから再生が始まるまで数秒かかる場合があります
- * Mac Safariをご利用の方で、うまく再生されない場合には、Google Chromeなどのブラウザをご利用下さい
- [音声no. 6] 夜に吠えるオオカミ
- 経験を積んだ聞き手としてわたしが特に好きなのは、露が地面や木々の枝葉を濡らす夜に鳴くように進化した動物たちの声だ。夜は美しいエコーのかかった劇場のような効果がある……コヨーテやオオカミが夜に吠えるのは、自分たちの声の特徴がよく響き、遠くまで届くからである。(本書p. 32)
- [音声no. 19] ハゲワシの雛の叫び声(エクアドル)
- エクアドルの森に棲むハゲワシの雛は人間の手のひらにすっぽりと収まるぐらい小さいが、その叫び声は大きくて激しく、ホラー映画に採用されてもおかしくないほどだ。(本書p. 64)
- [音声no. 26] 濃密で健康な状態のサンゴ礁の音(フィジー)
- (本書p. 79)
- [音声no. 27] no. 26と同じサンゴ礁だがほぼ活動をやめ、ひどくストレスを受けている部分を録音したサウンドスケープ(フィジー)
- ほとんどすべての魚がいなくなって、海洋バイオフォニーの一部としては数匹のテッポウエビが残っているだけだ。海水温度の上昇、pH値の変化、汚染などにより、世界中でたくさんのサンゴ礁が死滅し、ここと同様の音響上の損失が起きている。(本書p. 79-80)
- [音声no. 50] バイオフォニーと調和するバヤカ族の歌唱(中央アフリカ共和国)
- バヤカ族の女性は濃密なザンガ・サンガの森のいたるところに散らばって、……嵐が去った後に戻って来ていた鳥や昆虫の歌に耳を傾けながら、ほとばしる音のなかで歌う。(本書p. 147)
 バーニー・クラウスのTED講演「自然界からの声」
バーニー・クラウスのTED講演「自然界からの声」
(字幕付き)
生物がつくる音響が、自然環境の状態を知る重要な手がかりになるという話題を中心に語っています(2013年6月)。
- * 映像が表示されないときには下記のリンクをご利用下さい
- TEDウェブサイト www.ted.com/talks/lang/ja/bernie_krause_the_voice_of_the_natural_world.html
- * 日本語字幕を表示するには、Flash Playerがインストールされていることが必要です。Flash Playerをお持ちでない方は、以下のサイトからダウンロードできます(無料)
- Adobe Flash Playerを入手する get.adobe.com/jp/flashplayer/
 ハーバード大学で行われたパフォーマンス・イベント
ハーバード大学で行われたパフォーマンス・イベント
2012年9月27日にハーバード大学のボイルストン・ホールで行われた、バーニー・クラウスと詩人のジョナサン・スキナーによるパフォーマンスの映像です。クラウスが自然のサウンドスケープを音と映像で提示、スキナーがそれに呼応する詩を吟ずるという興味深い試みです(字幕はありません)。
- * 映像が表示されないときには下記のリンクをご利用下さい
- YouTube動画 youtu.be/tsEgbo1o70g
 リンク集
リンク集
- ● WIRED.jpに、本書の原著 The Great Animal Orchestra(2012, Back Bay/Little Brown/Profile)が音声ファイル付きで詳しく紹介されています。
- サウンドスケープ:音による自然学(by Brandon Keim) wired.jp/2012/04/01/great-animal-orchestral/
- ● 著者の現在の活動母体であるWILD SANCTUARYのWebサイト
- www.wildsanctuary.com
 推薦評からの抜粋
推薦評からの抜粋
- ◆ジェーン・グドール(動物行動学博士、ジェーン・グドール研究所所長、国連平和大使)
- この本は、普段わたしたちが聞き逃している太古より奏でられてきた音楽についての物語である。さすがにバーニー・クラウスはアーティストだ。わたしはチンパンジーの鳴き声や昆虫や鳥の歌を録音する彼の姿を見てきたし、彼が自然のハーモニーを深く愛している様子も目の当りにしてきた。彼は本書を通じて、普段は見落とされがちな音楽家たちの歌を新しい方法でわたしたちが耳にし、正しく評価する手助けをしてくれる。しかし彼は、こうした歌、つまり人類が平穏に暮らすうえでも欠かすことのできない自然界に特有の一面が、わたしたちの活動によって日に日に減少し、消滅に向かっていると警告する。本書を読んだら、そのことをお友達にも伝えてほしい。バーニーが強く主張しているように、脈々と受け継がれてきた自然の音が失われてしまう前に、みんながそれぞれできることをしましょう。
…続きを読む »
- ◆ウォルター・マーチ(映画音響エンジニア/音響デザイナー)
- 読者は、自然の音の質感(テクスチャー)に満ちた世界を解明しようと40年以上にわたって旅を続けるクラウスの個人的な物語を楽しみながら、古代の音も現代の音も含めて、そうした音を追体験しているように感じるだろう。この素晴らしい本を読んだ後は世界が変わって見えるはずだ。
- ◆ノーマン・レブレヒト(『だれがクラシックをだめにしたか』著者)
- バーニー・クラウスには、音楽についてわたしたちが知っていることの大半を考え直させられる。最初の仕事としてカンサスの畑でトウモロコシが成長する音を録音したという彼は、プロとしての目的意識を持って、わたしたちが音を聞いたこともないようなものに40年にわたって耳を澄ませてきた。蟻の歌やクジラの唸り声を調査してきた。……クラウスは、映像を伴わずオーケストラも従えないデイヴィッド・アッテンボローといったところだ。クラウスは音楽の起源の付近にまでわたしたちを導き、ノイズのなかに埋もれることなく、立ち止まって耳を澄ませることの重要性に気づかせてくれる。本書はそういう類まれな一冊である――と同時に、控えめながらも重要な一冊である。素晴らしい。
…続きを読む »
- ◆ジョージ・マーティン(音楽プロデューサー)
- クラウスは、わたしたちを取り巻く自然環境の音楽と音の持つ意味に関して、驚くべき物語を暴き続ける。動物や昆虫の繊細な音を対象にした彼の研究は他に類を見ず、この惑星で現実に起きている劇的な変化に関する彼の記述を読むと、しばし立ち止まって驚愕せずにはいられない……じっと耳を澄ませてみてほしい。耳に届く音が今までとは違って聞こえるはずだ。
- ◆パブリッシャーズ・ウィークリー誌
- クラウスは音楽業界での経験を活かして、各バイオフォニー内のさまざまな動物たちによるオーケストラのような層を聞き取っている。それは集団での発声を、目的を持って一斉に発せられるノイズとしてではなく、進化的生存の構造とする観点である。
- ◆ポール・ミチンソン(ワシントンポスト紙)
- クラウスは世界でも最も歯に衣を着せない、類まれな環境学者になった。人類学者であり、専門技術者であり、音楽家でもある彼は、急速な変化の只中にあるこの地球で消えゆくサウンドスケープをとらえようとしている……本書は人類の発するノイズが自然界に課してきた目に見えない代償に対するクラウスの怒りと、それが重大なことである理由を伝え、読む者の心を揺さぶる。
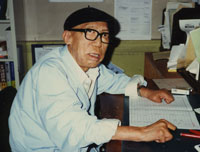
 電子書籍もできました!
電子書籍もできました!
 本書の音風景
本書の音風景 バーニー・クラウスのTED講演「自然界からの声」
バーニー・クラウスのTED講演「自然界からの声」 ハーバード大学で行われたパフォーマンス・イベント
ハーバード大学で行われたパフォーマンス・イベント リンク集
リンク集 推薦評からの抜粋
推薦評からの抜粋