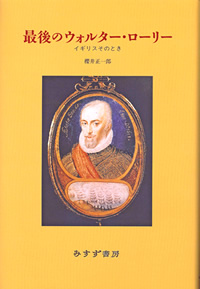トピックス
櫻井正一郎『最後のウォルター・ローリー』
イギリスそのとき
本書にも引用されている、歴史家トンプソンによる『ローリー伝』のエピグラフには、こう書かれている。
「サー・ウォルター・ローリー。歴史家、詩人、哲学者、海戦記の作家、宮廷人、政治家、兵士、軍将、海賊、船主、愛国者、化学者、植民地企画者、コンワル選出の議員、同時にジャージー島総督、行政官、文人のパトロン、科学者でありながら不可知論者、策士でありながら殉教者だった」。
ひとりの人物にこれだけの肩書きが付くのは驚くべきことである。万能の天才を多く生んだルネサンス時代のなかでも、傑出しているだろう。そんなローリーの生涯が面白くないはずがない。英米ではすでに40冊をこえる伝記が書かれている。櫻井正一郎氏の前著『サー・ウォルター・ローリー――植民と黄金』(人文書院)もまた、波瀾万丈の生涯を描いた伝記だった。代わって本書は、ローリー最期の時に絞って、断首台から放たれたスピーチの真意と、スピーチがもたらした反響を検証する。
スピーチにみられる修辞と仕掛けを読み解きながら著者は、ニュー・ヒストリシズムの歴史家グリーンブラットの「自己成型(self-fashioning)」という用語を用いて、つぎのように述べる。
「ローリーは断首台の上でキリスト者としての〈自己〉を〈成型〉したが、それとは別に、国王に反抗する〈自己〉をも〈成型〉した。(…)国王への反抗は、国家のためを思った公共心の産物よりも、利己心の産物という要素がより強かった。(…)利己心こそ、ローリーが脱出できなかった〈深淵〉であった」。
キリスト者の〈自己〉は演技、国王に反抗する〈自己〉は実質である。つまりローリーは、実際にはキリスト者でも愛国者でもなく、ひとりの利己的な「個人」にすぎなかったわけだ。ここに「現代人」の遠い雛型をみるのは、穿ちすぎだろうか。
それにしても、現代人がローリーのように多彩な肩書きをもつことは、もはや不可能である。そのあたりの時代背景をめぐって、前述のグリーンブラットは『ルネサンスの自己成型』の序文でこう問いかけていた。
「ローリーはその生を舞台の上で役割を演じているかのように生きた。(…)ローリーにとって、そしてルネサンス期イングランドの何人にとっても、自分のアイデンティティを創作され形づくられ展示されうるものとして経験することがいかにして可能だったのか、自己とは与えられる――両親や職業や信仰によって、あるいは単に運命によって、決定される――ものではなく、創作されるものである、と感じることがいかにして可能だったのか(…)」。
ローリーも、そしてルネサンス人も、役者が役を演じるようにさまざまな仮面を付け替えて生きたからこそ、あのような八面六臂の大活躍ができたということだろう。それでは、その仮面の下にあるほんとうの素顔は……そう問いかけることはもはや、「現代人」に特有の野暮というものだ。堅実な実証と活劇のスリルが凝縮された歴史物語である。
- (S・グリーンブラット『ルネサンスの自己成型』〔高田茂樹訳、みすず書房、1992年〕はおそれいりますが現在品切です。)