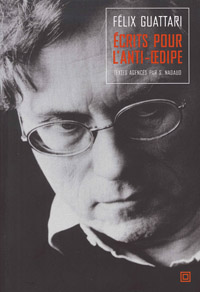トピックス
F・ガタリ『アンチ・オイディプス草稿』
S・ナドー編 國分功一郎・千葉雅也訳
フェリックス・ガタリとジル・ドゥルーズが出会ったのは1969年6月のことである。フランソワ・ドス『ドゥルーズとガタリ 交差的評伝』(杉村昌昭訳、河出書房新社、2009年)によれば、その翌月、ドゥルーズはガタリ宛にこのような手紙を認めている。
「精神病の形態は、とにかく必ずしも、一般に言われているような仕方で、オイディプス的な三角的構造化を経て生じるものではありませんね。ここがまずいちばん重要な点だと、私には思われます……ただ、精神分析の〈家族主義〉、パパ‐ママ図式から脱出するのはむずかしいですね(あなたが読んだ私のテクストはまるっきりそれに従属したものです)……ですから、たとえば精神病において、社会=経済的なシステムが、どのようにして〈じかに〉作用することができるのかを明らかにしなければなりません。もちろん、このメカニズムが〈そのまま〉作用する(たとえば剰余価値や利潤率などのように)と言いたいわけではありません。これは、もっと複雑な問題でしょう。あなたが、かつて、狂人は単に宇宙論をやっているのではなくて、政治経済学もやっているんだと言ったとき、この問題にアプローチしていたのです」
おおまかにではあれ、ふたりの共同作業の進むべき方向が示されている。とはいえ定期的な会合、あるいはそこで「ドゥルーズがフェリックスの言ったことをメモして、つじつまを合わせ、批判し、哲学の歴史に照らし合わせる」のではけっして十分ではなかった。論文こそあれ著書がまだ1冊もなかったガタリに対して、ドゥルーズは毎朝考えを書きとめ、読み直すことなく送るようにと提案する。それが本書を構成するテクスト群である。
そしてこのテクスト群がまさに『アンチ・オイディプス草稿』であるのは、エクリチュールの運動が「どんなものでも引きずっていく分裂症の流れ」であるうえに、横断的思考を発生させつつ、独自の、またさまざまの分野からの新たな諸概念(ガタリによるドゥルーズの概念の転用も含む)をすでに作動させているからだ。オイディプスではない何か、コギトや去勢された主体ではない何か、シニフィアン(の連鎖と専制)ではない何か……。舞台から工場へ。構造(主体)から機械へ。無意識が生産の場へと変貌をとげるなか、ラカン理論の核心的テーゼが掘り崩される。「無意識はそれなりのやり方で働き、冗談を言い、あれこれやって組み立てる。無意識は何も気にしない! 無意識は〈言語のように構造化〉されてなどいない」
さて『アンチ・オイディプス』(以下AO)をひもといてみよう。「オイディプスの首枷を吹き飛ばし、いたるところで欲望的生産の力を再び見いだすために、無意識の領野も歴史的領野も分裂症化すること。分析機械と欲望と生産の間の絆を、〈現実的なもの〉にじかに接して結び直すことが問題ではないのか。なぜなら、無意識そのものは、構造的でも人称的でもなく、想像することも形象化することもしないし、象徴することもしないからである。無意識は、想像的でもなく象徴的でもなく、それ自体〈現実的なもの〉である。つまり、〈不可能なる現実的なもの〉であり、またこれの生産なのである」(上巻、宇野邦一訳、河出文庫)。ラカンさん安らかに、とあたかも生前の師に向かって弔辞を読むかのごとく!
むろん、最終的に背景に押しやられた概念やダイアグラムもあり、逆にこれらテクスト群に姿を見せていない展開もAO本体にはみてとれるだろう。テクストを仕上げることは、もっぱらドゥルーズに委ねられていた。1971年夏、ふたりで長期合宿を行った後、AOが完成にいたるのはその年末(刊行は翌年3月)である。
しかし、ドゥルーズによって目覚めさせられたガタリ‐エクリチュール機械はとどまるところを知らない。本書には、完成後もなおドゥルーズ宛に書き続けられたテクストが収録されている。『カフカ』『千のプラトー』の予備的考察となるものや、後に『分子革命』の一部として公刊されたテクストである。
『アンチ・オイディプス草稿』を読むことは、希有な遭遇から生まれたある思考の発露と運動に立ち会うことである。訳者あとがきに記されているように、読者ひとりひとりが自身のAOを作成していただきたいと思う。そのとき、開かれるのは「明かしえぬ共同体」への扉……?
- J・デリダ『ならず者たち』(鵜飼哲・高橋哲哉訳)はこちら
- J・デリダ『留まれ、アテネ』(矢橋透訳)はこちら
- 『ロラン・バルト 喪の日記』(石川美子訳)はこちら
- S・ソンタグ『書くこと、ロラン・バルトについて』(富山太佳夫訳)はこちら
- 宇野邦一『映像身体論』はこちら