
2015.01.14
相互性の歴史的展開 押村高・谷澤正嗣・近藤和貴・宮崎文典訳
2015.01.09
本書は、いわゆるプラトン、アリストテレスから自由主義、功利主義、カント主義を経て、ロールズへと至る正義の古典的系譜の紹介を第一義の目的とはしていない。また、懐疑論や現実主義、相対主義の批判をも意図してはしない。むしろ、それらのみで構成されている通史を批判しつつ、新しい正義の観念と系譜を掘り起こし、グローバル化時代におけるその意義を強調することを狙っている。
従来の系譜に対するジョンストンの不満の第一は、それが近代以降の帰結主義とカント主義の対立に過度の力点を置き、また社会正義や「公正としての正義」に必要以上の注目を与え、逆に古代、西洋やその周辺で時空を横断してみられた、人間関係に焦点を定めた正義論もしくは「相互性」を軽視していることにある。
ジョンストンのみるところ、正義論を上の二つの流れに限定する思想史は、正しきものについての多産な思考の成果を矮小化し、相互に抱き合う本能的な感覚から人間が正義を捉えてきたという事実を忘却している。とくに現代の社会正義の理論は、交換より「配分」に重きを置きすぎて、能力に差がある人間同士がどうやってその差を克服しつつ相互的関係を取り結ぶかという本質的な問題をないがしろにしてきた。
近代の社会正義の理論は、ジョンストンの分析によると、D・ヒュームが正義の由来をその利点としての有用性に求めてから徐々に頭角を現し、A・スミスが分業の社会的な役割を強調してそれを所有と結びつけたとき、正義論の新しい流れとなって定着した。これにより、相互性は背後に退き、かわって個々人の相互尊重には重きを置くことのない、生産物を共同体成員にどう分配するかを論ずる正義論が主流になったのである。
倫理的個人主義者のロールズは社会内の分配の問題に対して、「公正としての正義」で応えようとした。しかしジョンストンによると、ロールズの解法は平等な個々人の織り成す閉じた社会を前提とし、また個人を同等な自己決定能力を持つ主体と想定したため、価値において平等だが能力においては必ずしも平等ではないという人間関係の本質を捉えそこない、それぞれの能力に見合った相互性をどう築くかという問題から遠ざかってしまった。
さらに、より長い社会正義論の系譜からいうと、フィヒテからロールズまで、同質的な人間により構成される共同体の内部で、必要性や生産への貢献に応じて富や財をいかに配分するかを主題としていた社会正義論の主流は、配分に与かる資格者を、ともに分業に加わる成員、生産に貢献した成員に限定したため、国境を越えたステージへとそれを適用することができないのである。
(中略)
四十余年前にはJ・ロールズ、近年ではM・サンデルによって世界的ブームに火が付いた正義論争だが、過去五年に限っても和書、翻訳を含め夥しい数の正義に関する書物が日本で公刊されている。帰結主義やカント主義の正義論についてそれなりの見取り図を得ている日本の読者に対し、本書が正義論の理解に広がりを与え、西洋の軸に捕われない正義の論争を活発にしてくれることを、訳者たちはひそかに期待している。
copyright Oshimura Takashi 2015
(執筆者のご許諾を得て抜粋掲載しています)
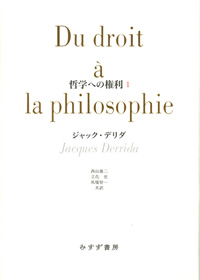



2015.01.14
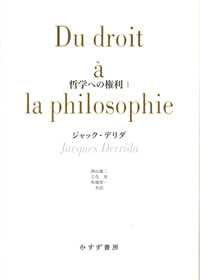
2014.12.26
西山雄二・立花史・馬場智一訳 [全2巻]