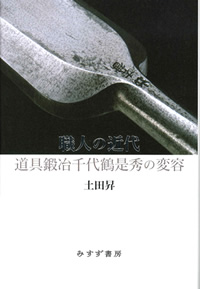
2017.02.10
『職人の近代――道具鍛冶千代鶴是秀の変容』
土田昇
武井彩佳『〈和解〉のリアルポリティクス――ドイツ人とユダヤ人』
2017.01.27
「リアルポリティクス」とは直訳すれば「現実政治」であるが、弱肉強食の権力政治(パワーポリティクス)とほとんど同義で用いられることが多い。しかしリアルポリティクスの源流は19世紀ドイツの自由主義者ロッハウが1853年に著した『レアルポリティークの諸原則』で、何が望ましいかということより、何が達成可能かを問い、そのための政策を求めるという意味での現実主義であった。そこにパワーポリティクスのニュアンスはない。
ドイツの戦後処理は、本書の洞察によれば、本来の意味でのリアルポリティクスに基づいている。ナチ政権の崩壊後、ドイツの人々は戦争の惨禍から立ち直るのに精いっぱいで、加害者意識は希薄、むしろ被害者意識が強かったが、ドイツ連邦共和国として再生したドイツには、過去の過ちを清算した国として国際社会に受け入れられる必要があった。一方、ホロコースト生存者を含むユダヤ人安住の地として建国されたイスラエルは物質的・金銭的援助を必要としており、そこへ手を差し伸べたのがドイツである。反ユダヤ感情の残る世論を背景に自らを加害者と位置づけ贖罪に舵を切る覚悟と、仇敵からの援助を利用する決断。本書は加害者と被害者双方のリアルポリティクスを、実証的に描き出している。
ドイツの贖罪は、最初から全面的に展開されてきたわけではない。その歴史を眺めると、外圧を受けておずおずと始め、時々の状況に応じて可能なことを継ぎはぎしてきたという印象を受ける。その過程で、公共の場でのホロコースト否定は法律で禁じられるようになった。今では欧州の他の国にも同様の法律がある。もちろん、歴史修正主義の問題はあった。よく知られているのはイギリスのアーヴィング裁判だろう。これは、ホロコースト遂行におけるヒトラーの役割は大きくなかった主張する作家デーヴィッド・アーヴィングが、彼を歴史修正主義者として批判する歴史家デボラ・リップシュタットを名誉棄損で訴えた裁判(1996-2000)であるが、証人として錚々たるホロコースト研究者らが膨大な報告書を提出し、ホロコーストの事実認定が司法の場でなされることによってアーヴィングの主張が退けられた。これが昨年、レイチェル・ワイス主演で映画化された(タイトルはDenial)。そのポスターにはこうある。「世界中が知っている。ホロコーストは事実だ。しかし、彼女はそれを証明しなくてはならない」。ドイツ国内の興味深い事例は本書で紹介されているが、歴史修正主義の問題が決定的に深刻になることはなかったようだ。償いと軌を一に形成されてきた歴史認識が「アウシュヴィッツはなかった」「ガス室はなかった」という言説への法的包囲網をせばめ、大手を振って歩くことを容認しない空気を生んだ。
本書が刊行された頃、日本の某ホテルが南京虐殺否定本を客室に置いているとして中国政府から非難されるという事件が起き、日本国内からは中国への反発が沸き上がった。ネットで検索してみると、上位に上がってくるのは「南京虐殺はなかった」という言説ばかりで、まさに大手を振っている。全く慰めにはならないが、これは最近の諸外国でも加速している傾向のようだ。世界最大の英語辞書であるオックスフォード英語辞典は、2016年を象徴する「今年の単語」にPost-truthを選んだ。世論形成において、客観的事実(Truth)が、感情や個人的信念に訴えるものより影響力を持たない状況、つまり、真実は重要でない、ということを言い表した語だそうだ。先週はトランプ大統領就任式をめぐってひと悶着あった。大統領報道官が就任式に集まった群集の数を「過去最大」と言ったが、これが嘘と分かり、さらに大統領顧問が「彼はオルタナティブ・ファクト(代替真実)を言っただけ」と擁護して非難を浴びた。真実に代替などない。それは「嘘」、または「誤り」である。
真実が格下げされる世界では、歴史はデマと同格になるのか。リアルポリティクスの実践からはほど遠い地点に我々は立っているような気がするが、600万の死屍累々を間に挟んだドイツ人とユダヤ人が和解するなど、終戦直後には誰も想像しなかっただろう。和解からほど遠いところに、当時の両者は立っていた。その後の長い道のりは、どのように歩まれたのか。そして、和解の代償としてのパレスチナ問題とドイツ国内の労働移民の統合問題は、これからどうなるのか。近い将来に当事者がゼロになるなか、世界中の非当事者が記念碑や収容所跡を見学したり、映画を観たり小説を読むことでますます増大してゆくホロコーストの記憶とは、一体なんなのか。本書の力強く、射程の広い論考から見えてくることは多い。
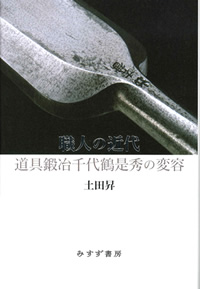
2017.02.10
土田昇

2017.01.26
G・アガンベン『哲学とはなにか』 上村忠男訳